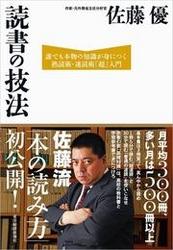
総合評価
(410件)| 90 | ||
| 157 | ||
| 103 | ||
| 17 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログKindle版を購入。1575円→1143円 この本は想像以上に私をモチベートしてくれた。 ただ単に、この本を読んで終わりではなく、ここ本から派生して学びたいこと、そして学び方がはっきり見えてくる。そんな本。 私の場合は、理系の高校だったため知識の偏りが激しいことを改善したかったのだが、基礎知識を学び直す動機付けとその方針を与えてくれた。 普段読んでいる本の他に、月3,4冊の熟読本を選びじっくりと身になる読書を行っていきたいと思う。
1投稿日: 2012.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優の知識量には圧倒されっぱなし。 良い意味で病気なんじゃないかと思うぐらい。 (多分、普通の人が持っていない病的な部分は何かしらあると思う。) 本の内容は速読や、熟読(書籍の深い理解)をするための具体的な方法が書いてある。 あとは、教養に関するものも後半実際に引用されながら紹介されてた。 経済・歴史・数学・国語・外国語etc... (特に数学や国語の部分の分析は考えさせられる・新しい視点をもらえたものが多かった。) また、そこから派生させてコネの作り方なんかも紹介されてる。 (同著者の本の内容と多少被るところも多々あったので良い復習にもなった。) 印象に残った一節は 「テーマを決める事の重要性(p171)」の部分。 今まで自分が学んでいる教養(読書も含む)にテーマを設定するという視点が抜けてたので、この部分は耳が痛かった。 「教養のための外国語とか歴史というような、動機が曖昧なままだらだら学習することは時間と機会費用の無駄なのでやめたほうがいい。」 今は、読書のリズムをつかめてる時期なので、著者の視点・技法も上手く取り入れながら良い習慣を続けていきたい。
0投稿日: 2012.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログスイスイと読めるが、内容は非常に厚みがあります。 筆者が書いている通り、読書の技法だけでなく、どのようにすれば体型的な知識を得られるのかを、論理的にかつ明確に書いている。
1投稿日: 2012.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログどんなふうに本を読んだらいいのか知りたくて手に取りました。 いわゆる速読などには興味がないので、そのような内容だったらどうしようと思っていました。 内容は、速読術のような部分もありますが、さまざまな本を引用しながら、その本の読み方を解説してくれる部分が多かったです。 最後のほうにある小説や漫画の読み方も、こういう風に読んだらよいのか、と参考になりました。 そろそろ仕事に役立つ本を読んでいきたいと思っていたので、そのためにはどのような本をどういう風に読んでいけばよいのか、小説とはどのように向き合ったらよいのか教えてくれました。 また、著者の書き方が面白かったので苦なく読めました。 著者の考え方、書き方とあわないとイマイチかもしれませんが…
0投稿日: 2012.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ"知の怪物"と呼ばれる著者の読書法が紹介されている。佐藤優氏の著書は初めて読んだけれど、称号通りの博学にぶりには驚くばかり。単純なノウハウではなく、真の教養を身につける為の方法が書かれている
1投稿日: 2012.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて電子書籍で読みました。 ハイライトなどあとで読み返す時に便利な機能がある上に、今すぐ安く読めることに感動しました。 内容は、著者の職業や経歴が少し特殊すぎて、一般人の自分にはどこを活用できるかとややがっくり。 でも自分がやってきた読書法に加えることで、また読み方が広がりそうな部分がありました。
0投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ立ち読み、もしくは図書館でOK。 この人は本気で言ってるのか読者を食ってるのかわからないことを言うときがある。なんのために、誰に向かってこの発言をしているのか、わからないということだ。
0投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優著「読書の技法」東洋経済(2012) * 本当に言いたいことを何度も繰り返すと、読者に飽きられてしまい、一番伝えたい内容が印象に残らなくなってしまう。同時に、伝えたい内容の格子を一回書いただけでは読書の印象に残らない。したがって反復が不可欠になる。多くの作家は、一番伝えたい内容について、自分の言葉で一回だけ述べ、それ以外は他人の口を借りてその内容を読者に印象付ける。だから引用はとても重要な意味を持つ。 * 速読の技法で小説を取り上げなかったのも、必要な情報を拾い上げる速読と楽しんで読む小説とは、基本的に相容れないものだからだ。
0投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすいです。 読書についてというよりも、勉強の方法について書かれた本。 よって、一般の速読法のような効率を重視した内容ではありません。 本を読んで得た知識を出来るだけ効率的に身に付けるのか、そのための読書法。具体的に書かれていて勉強になりました。 勉強しなければ。
1投稿日: 2012.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログインテリジェンスだった著者の読書について書いた一冊。 改めて、教養・知識の重要さを思い知った。 そして、単に知識があるだけではなく、それを運用できる状態にしておくことが肝心。 正直月300冊とか言われてもピンとこないけど、しっかりと読書を体系だてて説明していたのでわかりやすかった。 限られた人生の中で有意義な読書生活を送りたい。これを機会に高校の時の参考書なんかも見直してみたいと思う。 読む本と読まない本を分けることをしていなかったので、これからはしっかりしていきたい。
0投稿日: 2012.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の読み方に関する著者のアイデアが多数紹介されていてたいへん参考になる本。また、たいへん多岐にわたる参考図書が紹介されていて役立つ。
0投稿日: 2012.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読には、その分野の基礎知識と目標意識が必要。 それに加えて、読解力のレベル、多様な知識、論理的思考力が土台として欠かせない。 それらがなければ、本の選別はもちろん、書かれていることの選別もできず、早く読むことは不可能。 そういうレベルまで多読を続け、自分なりの速読手段を考えていくのが早いと感じる。
0投稿日: 2012.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読了。月平均300冊、多い月で500冊読むというこの作者スゲー!!本を読み始めて5年になるけど、読めば読むほど感じる事があった。それは学問の基礎が無い、基礎知識などのベースが無い状態で経済学や社会の本を読んでも頭の中に体系が出来てないから理解するのに時間がかかる事。高校の教科書を勉強し直そうと決めました。もう一回読もうっと。
0投稿日: 2012.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読とは熟読するための本を選ぶためにすること。基礎知識がない分野は速読することはできない。基礎知識をつけるために高校レベルの教科書と参考書を利用すること。熟読とは3回は通読することであり、重要なところはノートに書き写すこと。これが本当の知識を身につける方法と腹落ちした。
3投稿日: 2012.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
佐藤優の読書術を記載した本。本をどのように読むべきか、何を読むべきか、いつ読むべきかを述べている。どのように読むべきかは、超速読、速読、熟読の3つの読み方を提唱しており、どのような本が各読み方に適しているかを述べている。何を読むべきかは、基礎的理解としての高校レベルの学習参考書の有用性を説いており、社会で起こっていることを参考書の記述を引用しつつ説明している。いつ読むべきかに関しては「時間の圧縮」というキーワードを用いて記述を進めており、本をどこでどのような環境下で読むかでインプットの変わってくるということを述べている。 読書を娯楽というより知識を得るための手段として捉えている印象を強く受けた。字面を追っているだけで満足している自分の読書生活を考えなおさせてくれる1冊だったかもしれない。
0投稿日: 2012.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間は有限であり希少財である 歴史小説で歴史を学ぼうという安直な考えは捨てるべき シグマベスト 理解しやすい政治経済改訂版 文英堂 1648 ドイツ30年戦争の終戦処理のためにウエストファリア条約 NEW青木世界史B講義実況中継 全5巻 語学春秋社 詳説世界史書き込み教科書 世界史 改訂版 ナビゲータ世界史B NEW出口現代文講義実況中継 全3巻 語学春秋社 存在の耐えられない軽さ 夜は悪魔の支配する時間なので夜中に原稿を書いてはいけない。夜中に原稿を書く子をと余儀なくされた場合、翌日太陽の光の下でもう一度その原稿を読みなおして見ること カシオ電子辞書 Ex word XD-SF7700
0投稿日: 2012.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ【P54】 基本書は、3冊・5冊と奇数にすること 【P62~】 熟読の要諦は、基本書を3回読むこと 第1回目 シャーペンで線引き&印付けながらの通読 第2回目 ノートに重要箇所の抜き書き&コメント 第3回目 再度通読 【P258】 一日1~2時間の読書を、休日を含め継続を怠らなこと 時間を効率的に用いるために、「終わりから考える」 学習計画を立てること
0投稿日: 2012.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログフォトリーディング。高速リーディング。かなり面白いと感じた。 以後は高速リーディングを交えてもう一度読む事にする。 自分の速読を反省させられた。著者は速読を熟読する本を選り分けるために使っている。月に熟読する本はせいぜい10冊とのこと。 基本は5分で超速読し、どのように読むかを判断。それで終わりの本もあれば、そのあと30分で速読と読書ノートを付ける本もある。(超速読もノートは付けるようだ。) この本で自分の読書が記憶に残らないザルのような読書であると自覚させられた。ノートを取ろうと思う。ノートといっても氏は特別なものを要求していない。現在ある手帳やメモの中に記すことを述べている。そうすることによっていつでも持ち歩くノートが一冊ですみ、情報を一元化できるとのこと。読書ノートは長くとも30分で書き終えるようにすると、情報の取捨選択も強制的にできるらしい。 小説の読み方の章では「1Q84」を例に解説をしている。この小説を国際政治やビジネスシーンに照らし合わせて理解できる著者にはほとほと感心させられた。こういう本の読み方をしたいものだ。 最後のあとがきに少しだけ、著者の周りの読書階級の人々の話(インテリジェンス系の人々)の読書談話が載っていて興味深い。こんな知的な人々の仲間に入りたいと思った。 後半は速読と情報抜き書きの例が豊富。高速リーディングを交えて飛ばす。
0投稿日: 2012.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ・読者が知りたいと思う分野の基本書は、3冊、もしくは5冊購入するべきである。1冊の基本書だけに頼ると、学説が偏っていた場合、後でそれに気づいて知識を矯正するには時間と手間がかかる。 ・経済的に許す範囲で、書籍、雑誌に関しては「迷ったら買う」の姿勢を原則にしたほうが得である。もっとも人間は本来、ケチな動物なので、カネを払って得た雑誌の内容のほうが、ただでコピーをとったものよりも記憶に定着する。 ・熟読法の要諦は、同じ本を3回読む。基本書は、最低3回読む。第1回目は線を引きながらの通読、第2回目はノートに重要箇所の抜きかき、そして最後に再度通読する。
0投稿日: 2012.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ月平均300冊、多い月は500冊以上の「書籍」に目を通されるという、 元外務省情報分析官・佐藤優さんが、ご自身の読書術についてまとめられた一冊です。 - 筆者は、本書を通じ、読者に、読書の有用性について訴えたかった。 貧乏性な私はどうしても、一通り目を通したくなってしまう傾向があるので、 "超速読"、"速読"、"熟読"の区分がとても興味深く、いい刺激になりました。 といっても、全てを同じ枠組みにはめて"読む"というわけではなく、 まずは、自分にとって有益かどうかの区分けをしてはどうか、と仰っているのだと思います。 - 大雑把に理解・記憶し、「インデックス」をつけて整理する まずは「自分にとっての位置付けを判別するための"超速読"」、 店頭での立ち読みと同じ感覚でしょうか、、ふむふむ。 その上で「概要だけ抑えればいいとの判断であれば"速読"」、 問題提起と結論を抑えれば十分な書籍は、こんな感じで。。 さらに、「自分にとっての「基本書」になるであろう一冊を読み込む際には"熟読"」、 これはかなりコッテリとした読み方を示唆されていました、、ノート必須。 ちょうど今年は、学術系の本を読む環境にもあり、とても参考になりました。 全てをコッテリと読んでいたら、とてもではないですが終わらないので。。 なお興味深かったのは、そうやってインフォメーションした"情報"について、 - テーマを決め、週に1回書評の会合を行う との形でエクスフォーメーションする事を推奨している点でしょうか。 これは、同じ一冊の「本」に対する解釈を比較してもいいでしょうし、 同じテーマ対するアプローチを、様々な「本」を題材に比較しても面白いでしょう。 また、日々の生活の中で面白いと感じた「本」をただアウトプットするのも楽しいかと。 いずれにせよ、自分の頭の中でもやっとしているコトなども、 他者に伝えようと意識することで、整理されていくのだと思います。 もう一つ印象的であったのが、次の一片にまつわるトピック。 - 歴史書や哲学書、さらに小説など、意外な本を挙げないとならない。 なんでも、優れた情報専門家はすべからく読書好きとの事で、雑談していると、 専門分野とは別の、歴史書や哲学書、小説などの意外な本に興味を持つことが多いそうで。 さらにはこの意外な本がどこかで仕事につながることもあるとか。。 本棚で人柄も推し量れたりもするので、そうやって判断材料にしてるんだろうなぁ、、と。 確かに「座右の書」というものは、その人の心根を投影している気もします。 今後機会があったら、人間観察の手法の一つにしてみよう。。 なんにせよ、教養はどこの世界でも大事なんだなぁ、と改めて実感です。 そんなこんなで読みたくなった本がさらに増えてしまいました。。 『古典ギリシャ語初歩』 『想像の共同体』 『ネイションとエスニシティ』 『高校世界史B(教科書)』 リベラル・アーツをきっちりと修めるには、ギリシャ語の素養が無いとダメなのでしょうか。 ん、英語でさえ四苦八苦している自分にとってはなかなかに高いハードルです、、なんて。
7投稿日: 2012.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の「残り寿命から逆算して取得できる知識」を意識する考え方はとても好き。本書にある読書法の使い分けを実践できるようになりたい。それにはまず基礎知識の習得が不可欠!しっかり頑張ろう。
0投稿日: 2012.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ多読、速読の必要性をひしひしと感じていた時に本屋で出会って購入。その辺の速読本と違い、熟読の仕方も記載があり、◎ 本著の読書方法を実践中なので、長い目でどれくらい読書量、スピードが伸びるかに期待。
0投稿日: 2012.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読は、読むべき本とそうでない本を選別する為という考え方は新鮮だった。読書への動機が高まるというより、あらためて高校までの勉強をしたくなる本でした。高校生、大学受験生の動機付けにぴったりの本だと思います。
0投稿日: 2012.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の経験談を交え、本の読み方が書かれていて、とてもためになった。熟読の技法はぜひ取り入れたい。第二部の「何を読めばいいか」は、面白かった。高校の歴史の教科書について、興味深かった。世界史や日本史の勉強が意味がないと思う人には、ぜひ読んでほしい。
0投稿日: 2012.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の読み方。 読まなくてもよい本をはじきだす事も大事。 小説や漫画はリラックスする娯楽として。または動機づけとして。漫画から得た情報を知識としない。
0投稿日: 2012.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ元外務省分析官の著者が自身の諜報経験をもとに読書のあり方についてまとめた本。 熟読術、速読術とあるがテクニックというよりも考え方について語られている部分が大きい。さらに、読書とは何のためにするのかという観点から大いに学ぶ部分がある。 個人的には、読書から知り得た知識をつなぎ合わせ、現実を自身の言葉で解釈できなければ読書の意味がないとの件に共感。自身の読書スタイルを見直すきっかけしたい。
0投稿日: 2012.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ元外務省主任分析官、現在は作家である著者の「本の読み方」を紹介した本。 月平均300冊、多い月は500冊以上読むという大変な読書家である著者が、どのように熟読し、またどのように速読するのか、その方法が丁寧に書かれている。 2012/10/30 読了
0投稿日: 2012.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ本は図書館で借りることが多いので、書き込みやページを折ることはできない… でも、じっくり読む本、さらりと読む本、自分なりの判断基準をもう少し明確にしようと思った。 時間は無限ではないから、大切にしていい本と出会うチャンスを増やしたい!
0投稿日: 2012.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤さんの読書量には驚かされます。速読、熟読を身につけられた佐藤さんの「読書の仕方」は信頼できますし、納得がいきます。分かりやすいです。本を使ってどんなジャンルでも基礎から知識をつけたい方は、是非一読をされるべきです。
0投稿日: 2012.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の読み方に関してはこれまで読んだ本の中では一番詳しかったように思います。 フォローのノートの取り方も詳しい。
0投稿日: 2012.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、読書に時間が割けず、ペースが落ちていたこともあり、速読、熟読、普通読、参考になりました。著者の書評や解説も紹介されており、充実の内容でした。
0投稿日: 2012.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2012/9/30 ノート作りめんどくさそうだが、知識を定着させるにはそこまでやらなければならないのは納得。 今まで読んできた本のうち、何割が自分の中に残っているのだろうか…
0投稿日: 2012.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこの手の読書法の本を読むたびに、自分がいかに目的の定まらないダラダラ読書をしているか、思い知らされる。多読、熟読、速読、読書ノートなどそれぞれの技法を実践してみようと思う。特に「教科書、学習参考書を使いこなす」の章は、参考になる。でも、本はきたなく読め!というのは貧乏性の私にはハードルが高いかも。。。
1投稿日: 2012.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優氏の「読書の技法」を読んだ。彼は、月平均300冊に目を通すという。彼は神学部出身で、学部時代から難解な哲学書を原文で熟読し、外務省情報官となってから膨大な資料をいかに短時間で読み込むかに格闘し、実践してきた体験から身につけた正しい読書術を公開している。 読む本によって読み方を変える。熟読、超速読、普通の速読。速度は読む必要のない本を排除するために必要だと説く。 この本で参考になったのは、次の点だ。 1.基本書をどう読みこなすのかという点。同じテーマなら三冊(または五冊)の異なる基本書を読み比べよ、との教え。その理由は異なった定義や見解が異なる場合、多数決を取れば良いからだという。 2.もう一つは、基礎知識の欠損は、高校レベルの教科書と参考書(受験用で良い)を活用することだ、と。 「学校秀才だったビジネスパーソンに限って、自分に高校レベルでの学力に欠損があることを認めたがらない。それは数学にも、英語においてもだ。数学も英語も、基礎学力がついていないと、どれだけ努力を費やしても能力が向上しない。現実を虚心坦懐に認め、自らの欠損を早く埋めた者が最終的に得をする。」「文科系出身者であっても、経済学の理解に数学が必要だ。」と指摘する。
0投稿日: 2012.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者いわく、本には4つのカテゴリーがある。 1.熟読する必要があるもの。 2.普通に速読して読書ノートを作成するもの。 3.普通に速読するが、読書ノートを作成するの及ばないもの。 4.超速読に留めるもの。 自分では、このようなわけ方をしていなかった。 満遍なく、最初から最後まで漠然と読んでいた。 時間は有限なので、無駄にはしない著者の考えには賛成。 『本は買って汚しながら読む。』 この発想も面白い。 著者のように読書に一日の大半を割くことはできないが、 最低1日1時間は勉強するようにしたい。
1投稿日: 2012.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ一日に何十冊、一年で何万冊と本を読む著者が送る、実践的な読書術。(細かい数字忘れました) 速読と勘違いしそうだけど、どちらかと言うと本を読む姿勢だったり、読む時に気を付ける事などを具体的に説明してあり、非常に実践的。 他の速読系の本に無い、本を読む必要性と重要性に重きを置いて書いてる事に感心します。 一部無駄と思われるページ(章)もあるが、全体を通して非常にタメになる一冊。 これからの読書への向き合い方を良い方向に進めてくれる。是非おすすめしたい。
0投稿日: 2012.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読む目的】 速読、熟読のノウハウを知りたくて。 【内容とコメント】 •著者が先生の膨大な読書量から学んだのは、その見た目の読書量ではなく、圧倒的な基礎知識と熟読法だ。 →基礎知識を身につけること、それば1番重要だと理解しつつ優先度さげている、そこを今年中に改めなくていけないと思いました。 •最大月10冊読んだとしても、1年で120冊、30年で3600冊にすぎない。 →優先順位を決めたいと思いました。 下記3つを均等に時間配分したいと思います。 1.仕事で必要、且つリラックスするために読む本 →流行の本、小説 2.基礎知識を身につける本 →ビジネス書(入門編) 3.視野を広げる本 →専門書(入門編) 3.完璧主義を捨て、目的意識を持つ →さっそく実践したいと思います。 4.5分の制約も設け、最初と最後、目次以外はひたすら読み飛ばす。 →さっそく実践したいと思います。
0投稿日: 2012.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間は有限。多読、熟読、速読。基本書は熟読してきっちりインストール。超速読(試し読み)で本を仕分ける。普通の速読では、目的意識を明確にし頭の中にインデックスを作る。 本は、最初から最後まで順に全ページ全文字に目を通さないと読んだ気にならない、見たら読んだつもり、でした。 基礎知識は足りないし、忘れてしまって、実質、読んでないのと同じ、というのも多数。全ページ読んだはずだというのに。 読んでる最中、それで楽しめればよい、なんて自己正当化してみたりして。
0投稿日: 2012.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ大変,参考になりました。40歳を過ぎて,私も,「捨てるもの」,「やるべきもの」の仕訳をしていく必要があるのかもしれない。
1投稿日: 2012.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は今まで本とは熟読・精読するものだと思ってきましたが、超速読(5分!)の定義を読んでなるほどねと思いました。読まなくて言い本を決めるための超速読。納得です。 勝間和代さんの奨める速読やフォトリーディングについて、全く理解できていませんでしたが、実用書に関して行う、基礎知識のないものについては速読できない、などとてもストンと腹に落ちる説明でした。再読始めています。私には滅多にないことです。
0投稿日: 2012.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ月平均300冊、多い月は500冊以上の読書量を誇る筆者による、読書の方法論と読書の意義に関する一冊。 歴史社会学やナショナリズム等のイデオロギーに関するものからロシア文学、高校で使用する教科書に至るまでジャンルの壁を超えた書評は読み応え充分ですが、面白かったのは漫画の読み方。漫画の指向性から、その漫画を好む人間のタイプを推して行く。巨人の星好きはヤバい、と。 脳が高機能のディスティラリーとすれば、多様な書籍と触れ合うことで得た知識を発酵させるよう心得て、味わい深い至高の一滴を蒸留したいものです。
0投稿日: 2012.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の読書技法とおすすめの本、本の選び方などの紹介がメイン。合間合間に著者の経験を加えたエッセイ的な要素があるのが特徴。「本は汚く読む」というのは今後の読書で参考になるもので、試しに専門書を線を引きつつ読んでみると俄然集中力に歴然とした差が出た。
0投稿日: 2012.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書を一言で要約するなら「大学受験の勉強をやり直せ」という事だろう。という点で読書の技法というよりは知の技法というか勉強の技法になっており、読書家向けの本ではなく、読書を仕事に生かしたいサラリーマン向けの本になっている。特に現代文の受験問題を解くこと重要性については日頃から感じていた事なので、著者がこの点を強調しているのはとても納得。歴史や政治・経済の勉強も受験参考書が最適だろう。 1~4章は所謂読書法の紹介だが、特に目新しいものはない。多読の必要性については同意するものの、1冊5分の超速読の有用性には疑問があるし、そのために本を購入はしないだろう。速読の毎日3~4冊が限界としても、仮に毎月100冊購入するには15~20万円程度が必要であり、これでは家賃並かそれ以上になってしまい、非現実的である。著者は否定的なようだが、図書館利用を前提とした方法を提示すべきだ。6章の小説の読み方についての記述が少ないのが残念。代理体験の重要性についてもっと論じてほしかった。また全体的に引用が多く、やや冗長なのは難点。著者の読書量の多さに圧倒され溜息が出ると共に、人生は有限である、何を読むか?は非常に重要な問題であるというのを再認識した。
0投稿日: 2012.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【内容の備忘録】 ・速読の目的は、読まなくてよい本をはじき出すこと。一生で読める本の数は限られている。 ・基本書は必ず奇数冊読む。一冊目のノートで、最重要事項の暗記は完了しておく。 ・熟読法。基本書は最低3回詠む。1回目は線を引きながら、2回目はノート等に書き写す。最後に再度通読する。 ・速読。以下の4つにカテゴリー分けする。(1)熟読する必要があるもの。(2)普通に速読し、ノートを作成。(3)普通の速度を行うが、ノートを作成するには及ばないもの。(4)超速読。読み飛ばす。 ・超速読→5分の制約を設け、目次と最初と最後の結論ページ以外、ひたすら読み飛ばす。気になるワード等はポストイット、ラインマーカーでチェック。 ・普通の速読。完璧主義を捨て、目的意識を明確にする。定規を当てながら1P15秒で読む。本の重要部分を15秒、それ以外は超速読。大雑把に理解しインデックスを付ける。後でどこに何が書いてあったか思い出せる程度に記憶する。 ・レーニンの読書ノート。書き抜き→自分のコメント ・基礎知識の欠損部分を補う。大学入試程度。高校参考書。超基礎入門書→問題集→参考書、問題集で重複させながら徹底的に演習。 ・日本語読解能力はすべての基礎。出口現代文講義の実況中継で基礎を抑える。 ・論理を無視した知識は、すぐに記憶から消える。 ・数学や外国語は、頭でなく体で覚える。 ・一日の重要部分は、昼までの6時間に圧縮する。 ・能率が落ちてきたら、仮眠をとるか、数学等の単純練習問題を解く。 ・夜中に読むのは、何度でも読み返す基本書や過去に読んだ本。過去に読んだ本を読み返すことで新たな着想を得ることもある。 ・毎日、最低数十ページは外国語の読書を行う。 短時間睡眠のコツは、二度寝しないこと。ハッと目が覚めたら、その時点で起き上がる。 ・時間を効率的に使うためには、「終わりから考える」詳細計画を立て、効率よく知識を身につける。
0投稿日: 2012.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログハウツー本とは一線を画した、内容に重みのある本。著者の読書にまつわる5W1Hすべてをこの一冊にこめています。
0投稿日: 2012.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者である佐藤優は、月平均300冊の本を読むという.読み方は、超速読、速読、熟読など本の内容や質によって使い分けている。独自のフォトリーディングも備えているようだ.異色の経歴や歴史に造詣が深いことに興味を覚えた.本の中で紹介された本を何冊か読みたいと思った.
0投稿日: 2012.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者からの読書論は、これまでに幾つか出されていたが、これだけ内容濃くかつ具体的な読書法伝授は初めてである。速読法も、熟読法もこれまで世に出たものとは一線を画す画期的内容である。また、ターゲットをビジネスパーソンに絞っており、時間の無い人にはこうしろ。というアドバイスもありがたい。 特筆は基礎的教養を学ぶにあたって、高校教科書・大学受験の参考書を挙げている点である。また、さらに一般的生活レベルでは中学教科書でも十分に通用すると教示している。 なかでも、日本近代史については、本書のハイライト部分を読むだけで、復習になるほどである。あらためて著者の「本物の教養」とは何かを痛感させられた次第である。
0投稿日: 2012.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者がいかに物すごい読書活動をしているのかを記した本。 高校レベルの知識を幅広く身につけることが速読につながるというのは、深く納得するところがありました。 「知識のない分野の書物は速読できない」という非常に当たり前のことを、説得力のある著者が言ってくれるのは、速読のできない一個人としては、助かったというような感じです。 ただ、自分の知識のこれみよがしなひけらかしの部分もちょっと多かったかなあと思い、残念。エッセンスだけ抽出すれば、本の厚さはこの半分になったのではないかと思います。 ただ、読んで無駄になる本ではない。ぜひご一読を。
0投稿日: 2012.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は月300冊以上に目を通すそうです。それをどうやってこなすか、という本。 読むとはいっても、熟読する場合もあれば、速読するための超速読もある。書き込み方とか、読書ノートのつけかた、なんて記述もあるのだけど、本書は多読のための技術というよりも、本を読み抜くための力や、読むのを放棄する判断力、そのベースになる基礎力をつけるべし、時間は有限である、というメッセージが主題なのかな。 熟読と速読は表裏の技術であること、そしてその本を読むのはそれで最後だ、という覚悟を持って読む、みたいなあたりが好き。
0投稿日: 2012.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の知識の深さに脱帽。「基礎知識」をどれだけ積み重ねることができるか。積み本を「超速読」してみようかな。
0投稿日: 2012.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ本をあまり汚したくない派だったので、この本と同時にシャーペンと消しゴムも買ってきた。今までも読書術の本はいくつか読んだことがあるが、それらも本に傍線やら書き込みをすることは述べられていたが、実践してこなかった。 別に読んだ本を古本屋に売ることも無いので、汚く読んでもかまわないのだが、読書に対する目的意識が希薄というか、割りきりが足りなかったと思う。 本を何冊読んでも記憶に残っていないという悩みは自分だけかと思っていたが、結構他の人もそうなんだ、と思った。また記憶に残らない、知識を習得できないのは高校レベルの基礎知識に欠損があるからというのは、その通りかも知れない。今すぐ学参を引っ張り出す気にはなれないが、もう一度学習の必要性は感じる。
0投稿日: 2012.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ単なる速読スキル本とは一線を画するものでした。 まず速読は読まなくて良い本を排除する方法と定義。そして読書を「熟読」「速読(30分)」「超速読(5分)」に分類。この超速読で読むに値しない本を選別し読書候補から排除する。 また本書は熟読の方法から始まる。本書が読書の速さより如何に知識を吸収するかに重きが置かれていることが分かる。どのようなジャンルの本を読むにしても、まずはその分野の正しい基礎知識を習得していることが必要であるといを言い方を変え反復されている。
0投稿日: 2012.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の読み方と教養をつけるための本のリストが半々くらいの構成。 ・定規を当てながら1ページ15秒で読む。 ・歴史小説で歴史を勉強してはいけない。 ・シグマベスト 理解しやすい政治・経済 ・出口現代文実況中継 ・野矢 新版 論理トレーニング
0投稿日: 2012.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読法やらの類ではなく、効率的な読書方法を説いた本書。参考になる点は多々あるのでぜひ取り入れていきたい。ざっくりしているので、これをどう生かすか。
0投稿日: 2012.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の技法、本の読み方・選び方、速読術など、読書に纏わる書籍は枚挙に暇がない。 自分らしいの読書スタイルの確立がしにくいのであろうか。他人の読書スタイルにヒントを探したいのであろうか、それとも冊数をこなし、より多くの知識を短時間で習得したい、という分かり易い欲求に応えるヒントを得たい、というものなのであろうか。 浅田次郎氏のエッセイにもあったが、ボールペンで印を付ける、読書ノートを作る等、読中、読後の読書スタイルの形成に入る前に、どう読書をする時間を確保するか、自分の中でどう確保する決意が取れるか、が最初のポイントであると感じた。 読む時間がない、という決まり文句をまず無くし(解決し)、次のステップに進むことが、自分らしい読書のスタイル展開を楽しみにさせる。 本書を読んだ、僕なりの箇条書き項目は、 ①まずは自分なりの読書時間の確保(ルール化、決意) ②読書というインプットだけでなく、内容を振り返ることができるアウトプットもポイント 。 読むことが仕事の人は、書くことも仕事になっている。その逆もあり。 これらを仕事としていないそれ以外の人は、読書をして学ぶこと、感じることが仕事であろう。
0投稿日: 2012.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強熱、読書熱が高まる一冊。 佐藤優、流石だった。 3つの読み方を使い分ける。 ・超速読(1冊5分) ・普通の速読(1冊30分) ・熟読 その分野の基礎知識があれば、本はほとんど読まずに読み終わる。 (そのためにはまず知識の欠損部分を確認すること) どこまで真似するかは置いといて(さすがに一冊5分は真似できない…?)、 知ってると思ったらガンガン飛ばして読む、ということを覚えた。 世界史、日本史、政治、経済、国語、数学…各教科の勉強法が紹介されているので、試してみようと思う。 佐藤優は線を引きながら読み、熟読後は読書ノートをつけるらしい。 --- MEMO p123 教科書とは、教師がいる環境を想定しているので、説明不足が許されるのである。 これに対して、学習参考書は、それだけを読んでわかるような自己完結した構成になっている。 p212 リラックスするための読書は無駄ではない p226 村上春樹『1Q84』をどう読むか ベストセラーはどんな作品であっても、その時代の雰囲気をつかんでいる。(中略)それに村上春樹氏は、時代とともに歩いていくことができる数少ない作家である。
0投稿日: 2012.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ学術書や専門書などの知識を多く取り込むときには有効な読み方だなぁ、と思います。 個人的に普段の読書は娯楽の小説に偏りがちなので、普段はさほど使わない方式ですが。 速読などで本を評価するには基礎知識が必要不可欠というのは確かにそうだなぁ、と思います。 仕事上、基礎知識を再確認しようという気持ちになりました。
0投稿日: 2012.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
確かに熟読や速読のことも書かれていますが、 自分が重要だと思ったことは、 まずは高校レベルの内容をしっかり理解して それから大学レベルの勉強をする。 昔から読書は続けていて 最近でもビジネス書とか読み続けている自分ですが、 本の内容は理解できるが なんか読んでも頭に入っていかないな~と思っていたので やっぱり基本的なことがわかっていないとダメ! ということを知ってすごく納得できました。 自分もまずは数学の復習から始めて 次に国語、政治経済、世界史・日本史と 徐々に大学レベルの勉強をいていこうと思いました。 読書法も大事ですが、 今までの自分の読書を振り返りたいという方にオススメです!
0投稿日: 2012.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書を読書術のハウツー本というくくりに分類するのは正しくない。読書の捉え方や、読書の周りを取り巻く環境(勉強、人生、時間など)と読書の関連性を、俗にエリートと分類される外交官時代の経験から得た知恵をもとに解説したものである。 個人的な感想としては、今年読んだ本の中で断トツで面白かった。単なるハウツー本ではない。それ以上の人生をより良いものにするための様々な叡智が詰まっていると言っても過言ではない。今回佐藤優の本を初めて読んだが、正直ここまで面白いとは思わなかった。とても知的で論理的で説得力がある本であった。
0投稿日: 2012.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤氏の読書量には驚いた。氏の実際に行っている読書の技法(方法)を紹介しながら,基礎知識の重要性,その習得方法について教えて下さっている。今すぐにでも実践できることだったので,これからの読書に活かしていきたい。
0投稿日: 2012.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優氏の読書法が実例を交えながら紹介されている。熟読、速読、超速読の進め方や読書ノートの作成方法は具体的な解説があり、すぐにでも試せるもので、とても参考になった。その点で、第Ⅰ部「本はどう読むか」は非常に価値があったが、第Ⅱ部「何を読めばいいか」は佐藤氏による教養講座といった内容で、個人的には興味は持てなかった。ただし、高校レベルの知識が重要であることは納得できる。第Ⅲ部「本はいつ、どこで読むか」は佐藤氏のライフスタイルが紹介されているが、とても真似のできるものではない。
0投稿日: 2012.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優氏による読書や勉強方法の紹介。氏が実践している読書の方法や勉強方法についてかなり詳細に紹介がなされている。特に高校の勉強の重要性を力説している部分については支持できた。それ以外の読書の技法についても実践してみたいと思う。 読書をなんとなくしてしまっている人、読書で成果を出したい人、大学受験に向けて準備する高校生に加え、大学生、大学院生まですべてにお勧めしたい。
0投稿日: 2012.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ元外務省官僚の佐藤さんの読書術が書かれている。この本は自分の読書法のバイブルになりうる本だった。著者は作家活動を生活の軸に置いているので100%同じ方法はとれないが参考にすべき部分は多い。もう一度世界史も勉強したくなるという副産物つき。
1投稿日: 2012.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の読書系の本は1回共著の新書を読んだことがあるのですが、それ以前の基礎的なことも書いてありました。買って損はなかったです。 高校の教科書レベルをマスターすることは、社会系科目で言うとでいうと大学院で論文が書けるレベル。 ビジネスパーソンにとってはその能力を飛躍的に向上させるものである、と。 社会についてはあんだけ膨大な量があればそのとおりかもしれないよね。 現代文のおすすめ書籍はとてもおもしろそう。読んでみよう。 「論理的思考を問う」意味で現代文と数学はとても似ているものである。そのとおりだね。 数学は「テクネー」が必要なので、問題を解いて自分のものにしないとと意味がない。 簿記もそうだなぁ。最近ぜんぜんやってないけど。。。 教科書引っ張り返してみたくなる。 小説から学ぶって部分もおもしろかった。 3の法則ってのは間違いないよね。 重要な人脈は3週間経つ前に会う。 みんながそうかもしれないと思ってることを言葉にして切り取れる人は偉大だなぁとつくづく思います。
1投稿日: 2012.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書に対する完璧主義を払しょくする必要性を感じさせられる一冊だった。目的意識をもって読書をすることを,いっそう強く念頭に置くようにしたい。
0投稿日: 2012.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟読、速読をするためには、基礎知識が必要ということ。基礎がなっていないと、読んでも読んだ気になるだけ。わたしは高校のお勉強をやり直さないとダメなようです(T_T)
0投稿日: 2012.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初はとっつきにくく読みにくいと思いながら読んだ。それは著者の独特の読書、勉強法に特異性が感じられたから。自分とはレベルの違う難しい勉強をされてきたのだ。だから、読み進めるのが途中できつくなって・・自分のレベルで理解できそうな部分をつまんで読んでいる(笑)しかし、この部分(読書ノートのつくりかた)などはとても参考になったので、実践するようにした。
0投稿日: 2012.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書系の本の中でも、特に参考になったポイントは「高校の教科書や学習参考書に戻れ」という部分だ。同じことを言っている本はあるが、世界史、日本史、現代文、数学、政治・経済と幅広く具体的な本まであげているものは少ないのではないか?早速、amazonで注文すると関連書籍で、この本で上げられていた本が次々とあがってくるのは、影響力を思い知らされた。 「時間が人間にとって最大の制約である」という価値観に基づいて、いかに読むかを論じた本。著者のライフスタイルや熟読法、速読法を述べている。繰り返し、基礎知識の大切さを唱えているのは、納得できる。量のない質はあり得ない。基礎があるからこそ、質の高い速読ができる。今後はいかに基礎知識を蓄える「基本書」を見定めるかが必要な視点だ
0投稿日: 2012.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ月に平均300百冊読むという佐藤優氏の読書論。「速読は当該分野の基礎知識がないと出来ない」、「基礎知識は高校の教科書をマスターすれば身に付く」「歴史小説で日本史、世界史を勉強してはいけない」など、中々興味深い内容となっている。分からないことがあったらそのままにせず、当該分野の基礎内容や原典にあたるという姿勢が大切だと実感。学習意欲が湧く1冊。
3投稿日: 2012.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的好奇心を刺激しまくられる一冊。一生のなかで読むことのできる本の数に限界があるため、プライオリティをつけることが必要、とのこと。なるほど。
0投稿日: 2012.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者がどのように大量の書籍に目を通し、血肉にしているかがわかる。 単純な速読法ではなく、読書ノートも使用する熟読があってこその、本当に必要かどうかを見極めるための速読・超速読。 ノートに書き起こし血肉にするのが主眼だが、基礎知識がないと昇華することはできないため、高校の参考書から政治経済、近現代史、国語、数学等をどのように習得するかを説明している。 読書=知の技法としての良書かと思う。
0投稿日: 2012.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んで、日々増えていくばかりだった積読本を消化するヒントが得られた。 ・熟読術を身につけないで速読術を体得することは不可能。 ・「超速読」は読むべき本どうかの仕分け作業。 ・基礎知識が身についていない状況で消化できない専門書を読んでも時間の無駄。誤読するだけ。 ・漫画や娯楽小説は「動機づけ」に使える。 毎日webから大量に流れてくる情報を処理しているのと同じように、本も消化していけばいいのかもしれない。そう考えるとブクログは本のソーシャルブックマークサービス。ブクログが読書ノートとして使えるともっと便利なのに。
1投稿日: 2012.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ後半部分の「何を読むか」については、これまでの著書や連載等で触れられて来たことなので、前半部分の「どう読むか」に重点を置いて読了。 「超速読」「普通の速読」「熟読」に分け、かつ読書ノートをとることを進めている。 特に読書ノートのくだりは、読書をしても知識の定着が薄かった自分には、良い指針となった。
0投稿日: 2012.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読書その100】記念すべき2012年の100冊目。1か月間読書から離れ、ずいぶん時間がかかってしまった。本書は、元外務省主任分析官の佐藤優氏による熟読術、速読術。子供がまだ小さく、子育てにも追われる自分にとっては、月平均300冊を読む佐藤氏の速読術は本当に有益。熟読できる本の数は限られているため、熟読する本を絞り込むためにも速読術をマスターするという指摘は本当にはっとした。今日から実践したい。ポイントはいかに得た情報を自分の知識として身に着けるかどうか。また、読書の基礎体力を高校の教科書と学習参考書で身につけるというのは勉強になり、実家の本棚から引っ張り出そうと思った。
0投稿日: 2012.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書を知識をためるための作業として考えた場合の、効率的かつ実践的な手法を提案している。 全ての本を読む際に通じる手法ではなく、【読書】=【勉強】の場合に役立つ手法。 本書を読んだあと、その手法はすぐに実践している。
0投稿日: 2012.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読してその本の内容を理解するためにはその分野についてのある程度の知識が必要、ということには大いに納得でした。 正直なことを言うと速読というものは、何かテクニックが必要でそのテクニックについてが書かれているのか、と勝手に想像していたのですが、やはりそんな楽なものではなさそうですね(苦笑) なかでも取り組んでみたいな、と思ったのが熟読法の話。これもテクニックの理論ではなく、読書ノートの作り方などのことなのですがぜひとも取り組んでみたいな、と思います。新書なんかたまに読んでもすぐに内容があやふやになって身につかないことが多いので…… 初めのうちはこの本を読んで小説だけでなく勉強関連の本や、新書をたくさん読んでやろう、と浅はかな思いを抱いていたのですが、読み終えた後はまずは読んだ本の内容をしっかり理解できるよう「量より質」の読書をしようと思い直していました。速読についてはいつかはやってみたいですがまだ当分先のことかなあ。
0投稿日: 2012.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
どのように知識を得たらいいのか。月平均300冊読むという著者の情報の整理術を記した本。各教科の勉強法や、現在の社会問題についてどのように考えているかまで幅広く書かれており、他の速読本とは一線を画す。学生から社会人まで是非おすすめしたい一冊だ。 著者は、読むべき本を速読で嗅ぎ分けている。本屋で自己啓発やハウツー本をパラパラ一冊数分で見てエッセンスを拾って帰ることを趣味としている私だが、著者はきっとこのような読み方で結構難易度の高い本もある程度理解してしまうのだろう。 著者は気になった本は全て購入して、読むべき本と読むに値しない本を分けているらしいが、私は本屋で立ち読みして、買うべき本と買うに値しない本を分けている(ちなみに著者は本は全て購入することを奨励している)。本書も立ち読みで済ませようと思ったが、詳しく読みたくなって購入してしまった、私的には「読むに値する本」である。 本書を読んで、読書のこと以外で気付いたこと。何か成功していると言われている人を近くで観察したり、こうやって本から生活スタイルを見てみると、彼らに共通しているのは体力があることだ。勉強も仕事も遊びも人生は体力がある人の方が、普通の人に比べて数倍の力を発揮できる。著者も凄まじい体力を持った1人。そんな著者の頭の中を覗くことができる、新しい本を引き続き心待ちにしたい。
4投稿日: 2012.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書本の中では、他と一線を画す内容だった。 速読は、読まない本をはじき出すためにある。熟読できる本は限られている。1ヶ月に6-10冊として、30年で3600冊しかない。速読とは、本の精査のためにある。 紹介されている本は、政治、経済、歴史など社会学が中心だが、読んでみたいという本が多かった。自分の本を選ぶ基準を、見直そうと感じた。
0投稿日: 2012.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ毎月300冊以上の本を読む元外交官佐藤優さんの読書の読み方。 本には「簡単に読むことができる本」「そこそこ時間がかかる本」「ものすごく時間がかかる本」がある。 ものすごく〜は語学や教科書である。 なにを読むかを判断するために速読を用いる。なにを読んだらいいかは専門家に聞く。いなかったら本屋さんの店員に聞く。 基本書は奇数にする。多数決で答えを求めるためである。 熟読するには 1:本の真ん中から読む。本の真ん中は一番弱いところだから善し悪しが分かる。 2:一番最初の基礎の本は3回読む。 1回目:線を引きながら通読。時間をかけてゆっくり熟読する。 2回目:1回目でよんだ特に重要な所を四角で囲む。その四角をノートに重要箇所を抜き書きする。 3回目:結論部分を3回読む。目次を頭に叩き込んでから通読する。内容は1回目よりわかっているはず。 3:2冊目以降はスピードアップ。通読は1冊目よりも早く。気になるところは付箋を貼る。特に重要な所を書き写す。1冊目と違うところなんかは重要。 熟読しなくていい本。(教科書とか言語の本以外) 5分で読む「超速読」 30分で読む「普通の速読」 超速読でその本をどう読むかを決める。 熟読必要・普通の速読でノートを作る・普通の速読でノートを作らない・超速読でとどめる。 超速読:5分でかならず終える。はじめの1ページと目次をしっかりよんでからぱらぱらめくる。大きい字やタイトルぐらいでOK。 超速読でこの本は有益かどうか?を見極める。 この本のどこをよめばいいのか?を当たりをつける。 普通の速読:ほかの速読本のやり方でいいと思う。ここでは書かない。 読書後の30分でノートを作る。記憶に残すために必要な作業。四角で囲んだところを書き写す。そしてコメントを書いておく。自分の意見を書く。わかる/わからない程度ではじめはOK。 マンガ、小説はきっかけでいい。学ぶためのきっかけ。 夜の読書は楽なもの。眠気と戦っても頭には入らない。再読したいもの。 勉強は1日一時間出来ればいい。期間を決めて目的、予定を考える。
1投稿日: 2012.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読は自分には難しいな。読書ノートの作り方は参考になった。やはり記憶を定着させないと意味ないし。高校の教科書と学習参考書を知識の基礎レベルにおく、というところも参考になった。「1Q84」をどう読むか、について記載があったのでBook1-3も買ってみた。
0投稿日: 2012.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ何となくこの著者を毛嫌いしていたけれど、平積みになっていたからパラパラとめくった後、買ってみた。 要点は、 ・速読には基礎が必要。 ・基本書で基礎を身につける。基本書は熟読。メモを取りながら3回読む。 ・その上で、速読で読むべき本かどうか判断する。 ・速読の目的は、大雑把に内容をつかむこと。インデックスをつけること。 書いてみたら、当たり前やなあ。 てゆうか、速読の本も含めて「読んだ」ことにしていいのか?という素朴な疑問がわいてくる。
0投稿日: 2012.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書を通じた実用的な知識の得方について。基礎が大切ということについては異論はないけど、こういうのは人それぞれのやり方があるからなぁ。
0投稿日: 2012.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書本のハウツー本ではなく、著者の思想や経験を通した読書についての考え方の本であると感じた。 そもそも速読ができない自分にとって、著者の提唱する方法は実践できないものであるが、それぞれの分野における読書の重要性というものを改めて認識することができた。 しかし、マンガや小説についての読書法については、著者の思想的な練りが薄いのか、非常に中途半端で説得力にかける記載であった。
0投稿日: 2012.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読み終えてしばらく経つと、何が書いてあったかというかとの記憶が薄れてしまう。この点を改善するには、読書後30分かけて補強作業をするとよい。線で囲んだ部分をノートに書き写し、その下に簡単なコメントを走り書きするのだ。これだけで記憶への定着がまったく変わってくる。という。早速実績したい。何となく理解をしたつもりでは、役に立たない。
1投稿日: 2012.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「真理は具体的だ」 と言う言葉が印象的だった。 読書に関して、ともかく具体的。 読書の仕方、本の推薦、たとえばの具体例など・・・ 本の読み方はいろんな著者の本があるが、 共通しているのは ・本を書き込みながら読むのと書き込まず読む本が2種類ある ・1冊を熟読することの大切さ ということ。 他の読書本には書かれていないのは、基礎知識、つまり高校生レベルの知識の大切さ。 この本では高校の教科書や学習本もたくさん出てあり、まずは土台作りの大切さが強調されている。 (日本の高校授業の難易度は大学レベルのものもあり、中学レベルから急に難しくなりすぎているらしい) 読書好きというより、読書で知識を物にしたい人向け。
0投稿日: 2012.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会人の読書基盤として、高校の教科書を活用して知識ギャップを埋めるという方法。今の勉強に疑問を感じている高校生に読んでもらいたい。
0投稿日: 2012.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【出会い】 東洋経済の特集に新刊が出たとあったので。 【概要】 読書に充てられる時間は限られているので、熟読・速読・超速読の使い分けが重要。 基礎体力を身につけることが第一であり、それがなければ速読はできない。 【感想】 ただ量をこなせというはなしではなく、熟読と対になった速読という方法には説得力がある。 しばらく試してみたい。 基本的にアナログなやり方だが、これが今後のデジタル化時代にどう応用できるか。
0投稿日: 2012.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読して本の選別をして熟読しながらノートをとれ、という本の読み方の次に、なんの本を読むか、という話になる。 高校段階の知識の欠損部分を把握するために、高校の教科書と参考書を読むことをすすめる。高校の世界史や政治経済の知識、国語や数学の論理的思考を土台にしてはじめて熟読も速読もできるようになるというのである。 この本自体が「教養」を必要とされるエリートビジネスマンに向けて書かれているため、読書する意義めいたものは「当然だろ?」と言わんばかりに飛ばされる。また、「忙しいビジネスマンはそんな地道にやる時間が取れないだろう」といった論旨が散見されるが、これは「学生はこういうところを泥臭くやれ」と受け取った。 つまり、本書は「楽しい読書」「趣味は読書です」という人向けの本ではない。勉強のために本を読み、その休憩に本を読む、というような、本当に知識を身につけるための読書スタイルをする人用の読書法が書かれているのである。 佐藤さんは「知の巨人」と言われるだけあって、「楽しく本が読めたらいいなぁ」という読書ではそこまで辿りつけないのである。
0投稿日: 2012.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読法だけ学んでも時間の無駄!と言い切るのが良い。基礎がなければ速読しても身につかない。だから基礎となる本は熟読し、その上で速読しろと。 知識を身につけるという視点からだと、一番効率の良い読書方法が書いてあると思う。
0投稿日: 2012.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ■読書の3つの技法 1.超速読 ・5分の制約を設け、最初と最後、目次以外はひたすらページをめくる。 ・超速読の目的は、本の仕分け作業と、全体の中であたりをつける。 2.普通の速読 ・完璧主義を捨て、目的意識を明確にする。 ・雑誌の場合は、著者が誰かで判断する。 ・定期を当てながら1ページ15秒で読む。 ・重要箇所はシャーペンで印をつけ、ポストイットを貼る。 ・本の重要部分を1ページ15秒、残りを超速読する。 ・大雑把に理解・記憶し、インデックスをつけて整理する。 3.熟読 ・まず本の真ん中くらいのページを読んでみる。 ・シャーペン、消しゴム、ノートを用意する。 ・シャーペンで印をつけながら読む。 ・本に囲みを作る。 ・囲み部分をノートに写す ・結論部分を3回読み、もう一回通読する。
4投稿日: 2012.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、本を読んでも頭に入らないことや覚えていないことが多くなり、実用に繋げられないことに少し焦っていたので、読書のあり方を見直したいと思っていたときに出合った本。 「基礎知識は熟読によってしか身につけることはできない。しかし、熟読できる本の数は限られている。そのため、熟読する本を絞り込む、時間を確保するための本の精査として、速読が必要になるのである。」 限りある時間の中で、良い(正しい)読書法を身につける方法を体系的に書かれている。 筆者の専門分野での事例ではあるが、具体的で丁寧に説明してあり、改めて読書の有用性を認識させられた。 若いころの習得方法が通用しなくなったと気づいてはいたが、この本で書かれていた手法を読んでいて、今が改める時なのだと感じた。 これまで読んだ本を含めて仕分けし、改めて自分の知識にしていけるように読み返そうと思う。
0投稿日: 2012.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学の学習に関する記載、「存在の耐えられない軽さ」に対する評価などうなずける意見がたくさんあった。 速読の技法に関しては、やはり個人差があるのではないかなあという感想。そもそも技法の解説書については、すべてを同じようにたどろうとすると破綻することは必至と考えているので、著者の読書法について知ることができたことで十分であると思っている。
0投稿日: 2012.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人生で読める本は限られている」という根本的な所から真剣に考えて、自分なりの方法を確立させはったんやなぁ、と感じた。具体的&独特、骨太な読書方法で、こんなこと言っちゃアレだが読み物として面白かったです。 しかし骨太過ぎて並の人間にゃ無理です。 著者もその辺はやっぱりご承知なようで、対象をビジネスパーソンとかエリートとか、割とふわっと言ってますよね…。部分的に、大いに参考にさせて頂きますです。
0投稿日: 2012.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨今の効率重視のハック型読書の逆を行くようだが、知識の吸収・定着の確実さから見れば実は効率性の高い読書技法である。読書方法の紹介に加え、知識を身に付けるためには、基礎知識の欠損部分を客観的に把握し、欠落部分があった場合は高校教科書・参考書を活用し基礎知識をつけることを薦めている。(「現実を虚心坦懐に認め、自らの欠損を早く埋めた者が最終的に得をする。」p114)
0投稿日: 2012.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「千招有るを怖れず、一招熟するを怖れよ」という言葉がある。 佐藤氏が高校レベルの学力の再確認を薦めるのも、それに通ずるものがある。 多読速読の要が基礎学力の強化にあるという、明快な論旨が実に同意できる。
1投稿日: 2012.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直言ってこの本に書かれていることをそのまま実行するのは自分にはとても無理って感じです。 ただ、正しい知識を身につけるために高校の教科書を再学習することがとても重要という点には思わず納得。 そして国語の現代文は数学と同じで論理的思考力を身に付けるための教科だというのはまさに目から鱗という感じです。今の今まで現代文というのはフィーリングで解くものだと思ってましたから。 筆者が外務省時代に行っていたブックレビューで、詐欺師の本からヒントを得るくだりや筆者逮捕時にブックレビュー仲間が徹底的に事情聴取されたくだりなど中々興味深い内容でした。
0投稿日: 2012.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書術と名の付く本は玉石混淆あるが、読書以外のところでも実用的な内容があるケースが多い。 まして外務省のラスプーチン著なら、とりあえず手に取らざるを得ぬ。 のっけからの常人離れした読書遍歴。おいおい、いきなり凡人を置いてきぼりにするつもりか!と思いきや、意外にも高校の学習参考書を挙げて、読書基礎力をどうやって補うかに結構なページ割いてたりする。 中でも現代文と数学はオモロー。鳩山由紀夫のイミフな行動も微分的な要素で説明出来るかもみたいなところ、ぜひ一冊の本として仕上げてもらいたい。
0投稿日: 2012.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ元外務省職員、むねお事件で逮捕された佐藤優氏の読書術。 月平均300冊読書しているんだとか。 俺と比べたらよほど知識が豊富で論理力に富んだ人なんだろうなぁ。 時間は有限だから、速読は大事なんだろうな〜 やけに高校の基礎知識獲得を説いているのが少し斬新。
0投稿日: 2012.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優氏の作品は好きなんでほとんど読む。どうしてあんなに本が読めるのだろう?という興味からこちらも読了。◆熟読、速読、超速読の手法は読むだけでなくあらゆる事に応用できそう。◆超速読するには、基礎知識がなければできない、というのが前提。◆大学受験レベルの知識は持っておきたい。◆積み上げ式の知識を重要視するジャンルは、中学・高校年代から戻ってしっかり復習する。◆佐藤さんが哲学書のどういう順番で読んだらいいのか?というアドバイスに、大宮の押田謙文堂さんが出てきたのは感動した。◆読書とは、寿命という有限の中で、何を読み何を読まないか?の格闘に思えてきた。
0投稿日: 2012.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近仕事をしていて、メモをすること、ノートを取ることの重要性をようやく実感として感じられるようになってきた。これまでも様々な方からメモをとることの重要性を教わってきたし、また自分自身でも「メモを取ることは大切だ」と思っていたが、それは偏にそのように指導されてきたからであって、自分の実感に基づくものではなかったように思う。 社会人になると学生の時ほど時間に余裕がないし、またすぐに頭を(論点などを)切り替えなければならない場面が頻繁に出てくる。そのような経験を積み重ねる中で、自分の思考もある種の非連続的な側面があると感じるようになった。昨日の自分と今の自分は違うものだし、極端なことを言えばさっきの自分と今の自分もやはり完全に同じ存在ではない。であるとすれば、必要なものについては、今と異なる”自分”に対して何かしらの痕跡を残しておかなければならない。 また最近は、一つ一つのアクションに対して、学生の時とは比較にならないほどコミットしていることに気付く。つまり、意味のないことはしない、それぞれのアクションには、それ相応の覚悟を持っているということだ。 メモにしても、以前は漫然とメモを取っていたが、今は一つ一つのメモに「なぜその記述をするのか」という自覚を伴っているケースが多くなっている。 読書も同じようなものかもしれない。これまでは漫然と知的好奇心に基づいて読むことが多かったが、娯楽としての読書は別としても、目的を持った読書であれば、やはりもっとテクニカルに、多量に読みこなしていく必要があると感じた(精読すべき著書とのバランス、見極めも重要)。 著書を通して感じたことは、速読とは①前提となる基礎的知識を有した上での②高度な情報の取捨選択であるということである。決してごく一部の人間のみが有することのできる特殊な技能ではない(相応の努力は必要だけど)。速読をしている人はそもそも「本を読む」ということに対しての考え方が異なるのだと感じる。自分もこれまでの読書の仕方を少し見直してみたい。
2投稿日: 2012.08.07
