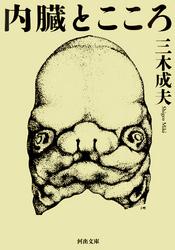
内臓とこころ
三木成夫
河出文庫
はらわたを熱く語る
保育園での講演を元にしていて、ほとんど語ったままの形を本にしてあるようで、「はらわたの復権」とか熱のこもった語りがその様子を髣髴とさせます。この三木先生はたいへんに人気のあった方みたいで、それが何となく分かるかんじです。ただ数十年を隔てて本を読むだけで接すると、伝わってくるものと、伝わってこないものとが、それぞれあるのかもしれません。 いくつか「へえ」と思ったところはあるのですが、次のような考え方って、最近の研究者が唱えているようなことを先取りしているのでは。 -感覚が原因で運動が結果だという考えは間違い。「犬も歩けば棒にあたる」など、動いたから新しい感覚が起こることも。両者を、原因-結果として結びつけるのは人間のわがままで、どちらが後先ということはなく連関している。 -感覚の「互換」(共感覚)が人間の言語のベースではないか。
0投稿日: 2014.07.05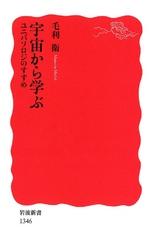
宇宙から学ぶ ユニバソロジのすすめ
毛利衛
岩波新書
宇宙からの地球観
「生き延びる」や「生命をつなぐ」をキーワードに、著者がユニバソロジと名づけた世界観について語る本です。しばしば聞きますが、宇宙から帰ってくると人生観が変わる、というやつでしょうか。ただ、この「ユニバソロジ」からは、すごく新奇だとか神がかったようなところはない、ある意味オーソドックスな印象を受けました。 次の一節にあるように、宇宙にいった結果、宇宙よりも地球に目が向いたそうです。 ”アポロ計画や国際宇宙ステーションをはじめ、アメリカやヨーロッパの宇宙開発計画では、その最終目的として、「地球を離れて宇宙に人類が進出すること」が謳われています。はたしてそうなのでしょうか。私は宇宙開発の最終目的は、私たちの住む地球をよりよく知るためではないか、と思っています。”
1投稿日: 2014.07.05
空飛ぶ納豆菌 黄砂に乗る微生物たち
岩坂泰信
PHPサイエンス・ワールド新書
大気中にはいろいろな微粒子があるのが当たり前だそうで
著者はエアロゾル(大気中に浮遊する微粒子の総称)を研究していて、この本のタイトルにあるように、近年は大気中の微生物=バイオエアロゾルにとりくんでいます。まだまだバイオエアロゾルはこれからの分野のようで、じつは本書でも主に研究の過程や問題意識が中心となります。 前半部分は、著者がバイオエアロゾルを研究する前にやっていたオゾンホールだとか黄砂の話が占めていて、1テーマにしぼった新書ではなく研究者の半生記に近いです。個人的にはこういうのは好きですね。 面白かった箇所をひとつ引用します。エアロゾルのなかには、なぜか2つの粒子がくっついているものが見かけられるというのに続いて、 -そんなに珍しいことではないのだが、「どうしてくっついたのか」を調べようとするとなかなか難しい。なかなか難しい理由のうちで、最も大きな理由は「そんなことが重要そうな問題に見えない」ということであろう。- 世の中ではいろんな人がいろんな研究をしているのだろうな、と思わせられる一節です。
1投稿日: 2014.07.05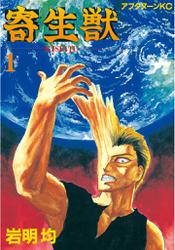
寄生獣(1)
岩明均
アフタヌーン
理屈抜きにおもしろい
これまで1巻しか読んだことがなかったのですが、その1巻が無料だったので再読しました。また、それから数ヶ月ほっぽいておいたのですが、2巻からはもう一気読みでした。なぜ、これまで読んでいなかったのか!というくらい。 人間に取りついて見分けがつかなくなる異星人っていうのは古典的ネタですが、しっかり料理してあるので陳腐さは感じません。環境問題的なこととか、「なぜ寄生生物は生まれてきたのか?」などのテーマも散りばめられているのですが、あまりそっち方向に深入りしすぎずに語るべきでないことは語らず、作品全体のバランスがとても優れています。 特にマンガについては、電子書籍がなければ読んでいなかったであろう作品と多く出会えてうれしいです。
1投稿日: 2014.05.04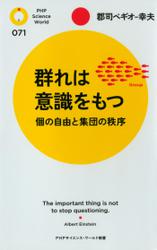
群れは意識をもつ
郡司ペギオ-幸夫
PHPサイエンス・ワールド新書
たまにはこんな本も
群れがまるでひとつの生き物みたいに動くメカニズムを、実際の動物の群れを観察したり、コンピューター上でシミュレーションしたりして研究するわけですが、そんな研究をする問題意識の根底では「個体-群れ」の関係を「脳細胞-意識」になぞらえているのです。 群れをシミュレートしたモデルとして、バード・アンドロイドを縮めた「ボイド」というやつがあります。各個体は、周囲の個体の動きを観察して①衝突回避②速度(方向含む)平均化③群れ誘引といった原則で群れとして動きます。この「ボイド」が著者にとってはつまらなく感じられ、「ダチョウ倶楽部」モデルを考え出します。これは、みんなが行こうとしているところに行きたがる、というちょっと複雑なモデル。個体に群れへの同調性みたいなロジックを仕込まないところがミソだとのこと。たしかに、ちょっと生き物っぽくなる気がします。 さらにはカニの群れを使って時計や計算機を作ろうとしたりするのですが、読んでいるほうとしては段々と何をやっているのか訳が分からなくなってくる所も。すごく大事で難しいことをやっている気もしますが、たいしたことないものを殊更むずかしく研究している気すらしてきました。いやまあ難しいです。 毎日新聞の養老孟司書評によると「わかりにくい本を書く著者だったが、今回の著作はみごとにわかりやすくなっている。」とのコトですが、これまでの著作はホントに難しかったのでしょうね。
2投稿日: 2014.05.04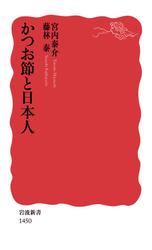
かつお節と日本人
宮内泰介,藤林泰
岩波新書
けっこう鰹節のイメージが変わりました
かつお節に漠然と抱いていたイメージを改めさせてくれた好著です。 伝統食品と言われつつも、庶民の食卓にはいってきたのは割と最近で(こういう食材は他にもいろいろあるかもしれません)、パック入り削り節や風味調味料の登場もあって今日に至るまで消費量は右肩上がりに伸びています。また日本の南洋進出とかつお節の歴史にも注目です。ミクロネシアの島々に沖縄漁民が移住してかつお節を作っていたとは知りませんでした。
1投稿日: 2014.05.04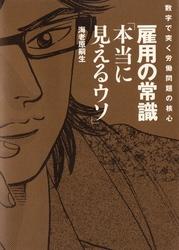
雇用の常識「本当に見えるウソ」 数字で突く労働問題の核心
海老原嗣生
プレジデント社
データによる雇用論
文庫版(紙)で読みました。内容に改定が入っているそうなので少し違うかもしれませんが。 データを使っての議論が売りみたいですが、全般的にデータを使った部分に少しあやしいところが散見され、人材業界の体験に根ざす部分のほうが面白いと感じました。ただ「あやしい」と思えるのもデータをベースに議論すればこそですからね。 産業構造の変化によって、昔はヒト相手の仕事をしなくて済んでいた人も対人業務に引っ張り出されているなど、興味深い指摘は数多いです。
0投稿日: 2014.05.01
統計学が最強の学問である
西内啓
ダイヤモンド社
なんにでも応用できちゃう統計学
タイトルにふさわしく本文も煽り気味な統計に関する読み物です。実践寄りの話が多く、特に後半戦の統計学を使う分野によっての使い方の違い(ぜんぜん違う!)は面白く読めました。また、一般化線形モデルのまとめ表も秀逸。
7投稿日: 2014.05.01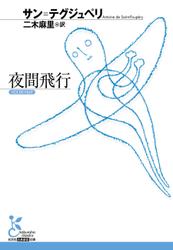
夜間飛行
サン=テグジュペリ,二木麻里
光文社古典新訳文庫
舞台は南米。黎明期の夜間郵便飛行。
とにかく直球勝負なのがよろしい。無駄をそぎ落としたような文体で、危険をおかしてでも目標に向けて働く気高さをうたっています。 21世紀日本視点から、リヴィエール社長のマネジメントに「それ違うんじゃないか」と思ってみたり、主人公たちに「そこ無理しないで飛ぶのやめたら」と突っ込みたくなったりもしますが、そういうことが問題なのではありません。ひとつの寓話として読めば、いま自分が失ないかけているものの価値について考えさせられます。 読んでいて気になった、飛行機のスピードがどうも速すぎだよね、という点は解説で確認。『星の王子様』ならともかく、ここはリアリズムで行くべきじゃないかと思うのですが。。。
1投稿日: 2014.05.01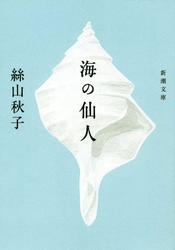
海の仙人
絲山秋子
新潮社
薄いけれどギュッと詰まっています
あらすじだけ要約したら「なんじゃこれは」と言いたくなるような話ですが、それでいて読ませます。前半で、ともすると細部のウマさだけを読まされているような気がしてくると、家族とか会社の同期とか人の死とか、人生の時間の経過を感じさせるようなフレームが後半に向けて待っています。 終盤は時間があれよあれよと流れていくのですが、あるシーンでの、主人公の友人のたった一行のセリフで時間の経過がグッと感じられます。目立つ所ではないのですが、これには感心しました。
1投稿日: 2014.05.01
bookkeeperさんのレビュー
いいね!された数185
