
化石の分子生物学 生命進化の謎を解く
更科功
講談社現代新書
ネアンデルタール人も、恐竜も、歴史上の人物も
ネアンデルタール人やら恐竜やら歴史上の人物やらのDNAをしらべる話。いまホットな分野と思われる。『ネアンデルタール人は私たちと交配した』を読む準備として手にとった。 分子生物学の技術的なところでの難しさが丁寧に解説されてる。なぜミトコンドリアのDNAをしらべることが多いのか?時の経過や保存状態がDNAにどう影響するのか?などなど 個人的にあたらしく知ったのは、ミトコンドリアのパラドックス、すなわちミトコンドリア・イブにかならずたどりつく理由である。ある時点では多様なミトコンドリアがいる。でも子供を産まない女性がいたり、産んでも男だったりするとそのミトコンドリアは子孫に受け継がれない。ミトコンドリアはそうして減る一方なのでそのうち生き残りは単一になる。それを遡ればイブになる。それでも現時点でミトコンドリアの多様性があるのは変異のため。むずかしい? さらにいえば分子進化の中立説はほんとうにムズカシかった。
1投稿日: 2016.10.09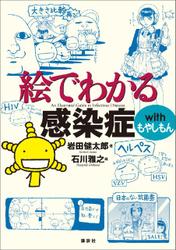
絵でわかる感染症 with もやしもん
岩田健太郎,石川雅之
KS絵でわかるシリーズ
どうして僕はこんな本を
岩田健太郎×「もやしもん」ということで思わず手にとる。しかし、僕はなんで感染症について薬や症状や微生物やと詳しく淡々と総説したこんな本を読んでいるのだろうか。ただ、ひとつ言えるのは、その道の達人が道について説くのを聞くのは、だいたいそれがどんな道であっても面白いということだ。かわいい菌のイラストがいっしょなら尚更である。
0投稿日: 2016.10.09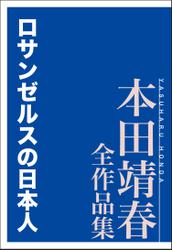
ロサンゼルスの日本人 本田靖春全作品集
本田靖春
講談社
先人たちの足跡
この本が刊行されたのが30年前、ロス疑惑のころである。なつかしい。さらに数十年前の初期日系移民を多く題材にしている。時代ともに変わったことも多い。著者の問題意識は日米貿易摩擦にあるのだから(もっともトランプなんかいまだにそんな感覚のようだが)。『ニューヨークの日本人』とセットとして無理矢理取材して書いた感がなきにしもあらず。ただ、わたくしなどは仮住まいの身であるものの、日本からアメリカにやってきた先人の足跡を学ばせてもらった。日系人と在米日本人が新聞の意見広告で言い争った事件など知らなかった。また、アメリカ、特にカリフォルニアのオープンさ加減をあらためて認識した(だから反動としてトランプみたいなのが支持されもするのだろうが)。 最後のほうにカリフォルニアを第二の満洲国にするなんて気宇壮大なことを言う元伊藤忠の人が登場するが、今の米国での日本人のプレゼンスを思うと隔世の感がある。もっとも今では中国人が増えているので、皮肉だが第二の満洲国という感じがしないでもない。
1投稿日: 2016.10.09
空港は誰が動かしているのか
轟木一博
日本経済新聞出版
空港経営の実体験談
関西国際空港の経営権売却(コンセッション)に運営会社に出向してかかわった元官僚による本。最初の3章で空港経営の要点、日本の空港や関空が抱えている問題を総説し、後半の3章で関空伊丹経営統合からコンセッションまでの体験を語る。前半の、空港や民間「風」経営の問題点にかかわる総説は的確ながら他でも読めるようなものかもしれないが、実際のコンセッションまでのプロセスについては(あまり具体的な話は書けない部分もあるだろうが)「中の人」が書いただけにたいへん臨場感のあるエピソードが多く、いろんな人がいろんなことを言う現場の雰囲気が伝わっておもしろい。また、空港という単なる民間企業ではない公共的な性格の強い施設の運営は、民間企業で働いている身からは新鮮である。むしろ民間の企業経営の性質を違う立場から照らし出しているようにも読める。
1投稿日: 2016.10.09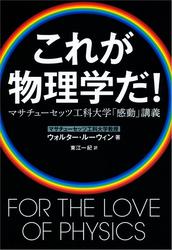
これが物理学だ! マサチューセッツ工科大学「感動」講義
ウォルター・ルーウィン,東江一紀
文藝春秋
実験物理学者の名講義
MITで一般教養の物理をやっている先生による本。講義の様子はMITのサイトで動画が公開されており、本書中にリンクもふくまれています。前半はその授業に準じていて、後半は専門であるX線天文学の歴史をみずからの体験で語っています。その後半はちょっと難しいといえば難しいですが、十分に理解できなくても読み物としてたのしめるので心配いらないでしょう。 ヒッグス粒子がノーベル賞の対象になったとき、理論物理学者と実験物理学者のどちらに賞が送られるべきか(実際は「理論」のほうでした)議論されているのを見かけて、両者がけっこう分業のようなかんじになっていることを知ったのですが、著者は実験物理学者のほうです。だからか、虹とかワイングラスの共鳴とか長縄跳びとか身近な現象に根ざした話がおおくて素人にもしたしみやすいです。とにかく測定の精度の大事さを強調するところも実験屋さんならでは。 たとえば年周視差で恒星との距離をはかるのですが、もっともご近所のプロキシマ・ケンタウリ(4.3光年)でも年周視差は0.76秒角しかないのです。ちなみに1秒角=月を1,800枚にスライスしたときの角度。いかに物理学者たちが観測精度を向上させるのに苦心しているかがよくイメージできます。そんなふうに物理学の現場の感じがわかる事例がたくさんあげられている本です。
4投稿日: 2014.07.20
日本軍のインテリジェンス なぜ情報が活かされないのか
小谷賢
講談社選書メチエ
インテリジェンスなのだ
日本軍の暗号読解能力は言われるほどヘボではなかったが、英米に比べて情報を共有、分析、活用する仕組みが弱かったそうです。結局、正確な情報よりも内部の政治的調整が重視されていたとの指摘、他人事とおもえないのはなぜでしょう。防諜の意識がぜんぜんなかったのでミッドウェーの敗北や山本五十六撃墜事件につながったとして、著者の評価は特に海軍にたいして辛いです。 個人的には、「インテリジェンス」という用語をもったいぶって使うところが鼻につき、意見・主張にわたる部分(とくに将来へ向けて)には首肯しかねる部分もありました。
0投稿日: 2014.07.05
Self-Reference ENGINE
円城塔
ハヤカワ文庫JA
正直なところ、ついていききれず
時間とは何か、言語とは何か、有限と無限、自己同一性などなど、テーマは思い切り直球勝負。けれど直球勝負のテーマの数々をてんこ盛りに盛りすぎているのと、奇をてらった構成や語り口や小道具のせいで、ふざけているようにしか見えません。ストーリーをこわすギャグが多すぎて、体をなさなくなった芝居みたいなものでしょうか。 あまりに韜晦が過ぎて物語の持ち味を殺しているような気がするんですよね。しかし、こんなお話をまじめな顔でされても困ってしまうかもしれません。粋みたいなものを感じつつ読むのが良いでしょう。
4投稿日: 2014.07.05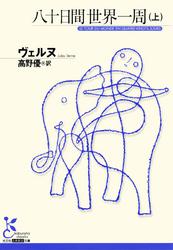
八十日間世界一周(上)
ヴェルヌ,高野優
光文社古典新訳文庫
なつかしいっす
この新訳のおかげで何十年かぶりにヴェルヌを読みました。いま読むとチャチに感じる部分も多分にありますが、十九世紀の時代の熱さが伝わってくるような気がします。すくなくとも子供のころに持っていた冒険への憧れを思いだしました。ストーリーテリングは軽快そのもの。無邪気ですらある進歩主義も心地よいです。
0投稿日: 2014.07.05
新訂 孫子
孫子,金谷治
岩波文庫
2000年前の現実主義
漢文の鑑賞を兼ねて読みました。古典ですが、注釈はありますし、要は箴言集なのでそう読みにくいものではありません。 古いだけあって異本が多く存在するのですが、あの三国志の曹操が入れた注釈が定番になっているそうです。自国で戦うのを不利としているあたりは、いまの感覚とちがっていて面白いですね。
0投稿日: 2014.07.05
「世間」とは何か
阿部謹也
講談社現代新書
ヨーロッパ史研究者による「世間」研究
日本歴代の文学・思想から「世間」とはなにかを探る本です。おもしろいのは、ヨーロッパ史研究者である著者が日本の「世間」をテーマにすること。たとえば漱石や荷風のように、一旦海外での生活をして日本文化の相対化をしたのでしょうか。 挙げられた事例の中では、真宗の一種の合理主義が興味深いです。他は特殊な一個人の思想ともいえますが、真宗はまさにある文化の層を形成しているからです。
2投稿日: 2014.07.05
bookkeeperさんのレビュー
いいね!された数185
