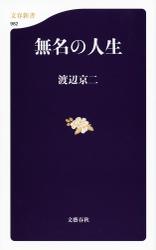
無名の人生
渡辺京二
文春新書
無名の人生たち
軽い語り口と思えば、インタビューを書き起こしたものらしい。もうお年だから、そういう本があって自分の来歴を語ってもらえるのも良い。既に渡辺京二は無名の人とは言えまい。ただ、かなりの年になるまでは、そういう気概でやってこられたのだろう。
1投稿日: 2016.10.09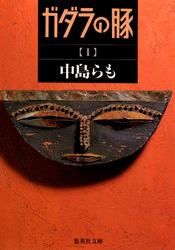
ガダラの豚 I
中島らも
集英社文庫
中島らもって小説も書いていたのか
中島らもってテレビで見たイメージくらいしかないが、こんなものを書いていたのか。この第1巻は「そこそこおもしろい」レベルだが、第2巻のアフリカ編で急に様相が変わって一気読みさせる。先を読ませぬまさかの技巧派ストーリーテラーぶり。
1投稿日: 2016.10.09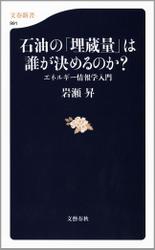
石油の「埋蔵量」は誰が決めるのか? エネルギー情報学入門
岩瀬昇
文春新書
実践的エネルギー論
元商社マンによるエネルギー論。なんといっても現代社会の基幹であるエネルギーについて手ごろな見取り図を与えてくれる。石油・ガスの話がおおむね中心。ブローカーの存在意義など「あれっ?」と思う記述があったり、電力会社の原油生焚きのようなわたくしのごとき浅学にとっては説明不足だった箇所もあるがご愛嬌レベル。 ガス田/油田開発の経済、なぜ日本の買う天然ガスは高いのか、パイプライン大国アメリカの市場、原油先物取引市場の成立史など
1投稿日: 2016.10.09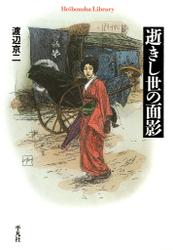
逝きし世の面影
渡辺京二
平凡社ライブラリー
西洋人の目から見た開国前後の日本
幕末・明治初期に日本を訪れた西洋人の観察記から近代以前の日本のすがたを探る。読み方について議論があるのもうなずけるが、渡辺は日本の話がしたいのではなく近代以前の話がしたいのである。ここに描かれる日本の姿は「逝きし世」であり今には残っていないのだ。他の著作と十分に一貫していると思う。 いろいろ読みどころの多い本だが、興味深かった点をひとつだけ。西洋文明の衝撃に直面して、幕末思想家の何人かは東洋の精神的道徳と西洋の物質的技術の統合、すなわち和魂洋才を夢見たが、当の西洋人は日本の特長は物質的生活にあり、それに反して西洋の特長は精神のダイナミクスにあると考えていたという。 しかしベストセラーのはずなのにこれが初レビューとは
3投稿日: 2016.10.09
神秘日本
岡本太郎
角川ソフィア文庫
爆発してるだけじゃないのですね太郎さん
岡本太郎はこういう本も書いていたのか。意外にと言っては失礼だが文章もなかなか読ませる。最初の4篇は中央公論連載の旅行記、後ろ2篇は芸術新潮連載でもうすこし形式張った芸術論らしきものでやや読みづらい。しかし、こうトーンをはっきり書き分けるあたりもけっこう器用よね。 いくつか本文中より引用: 呪術には矛盾がある。効果、力があらわれるという前提がなければ成り立たない。少なくともそれが示現する、した、と人々に思われることがなければならぬ。しかし同時にそれが必ずあらわれるのでは、やはりいけないのである。カクすれば、必ずカクなる、というんだったら、それは実用的約束であって、呪術でも何でもないからだ。(p.18) 夜の火は虚飾の奢りである。華やかに燃えて、目に鮮やかだ。だが昼の炎、そのエネルギーは不可視だ。思わずふれて、傷つく。人間はそういう経験をつみ重ねている。その危険感は不吉な力だ。だからいっそう神聖なのである。(p.167)
1投稿日: 2016.10.09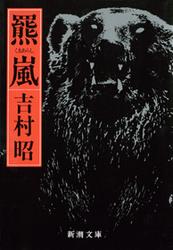
羆嵐
吉村昭
新潮社
100年前の北海道
ヒグマの恐怖もさることながら、たかだか100年前の北海道農民の貧しさが印象的でせつない。自然の一部でしかない「ヒト」なのである。 しかし素人が鉄砲を持っていてもダメなんですなあ。
1投稿日: 2016.10.09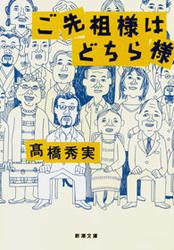
ご先祖様はどちら様(新潮文庫)
高橋秀実
新潮文庫
ご先祖様をたずねる旅
著者がおのれのルーツをたどる顛末記だが、家系というものについてのなかなか深い考察を含む。たいていの人にとっては、何代かさかのぼれば過去を生きた人々の痕跡は儚く消えうせており杳としてつかめない。しかし、ルーツを求める気持ちやみがたく、家系をみずから作り出すことこそ当たり前という、まるで逆立ちしたような結論に至る。それも先祖の数は代をさかのぼるごとに2倍になる(とりあえず重複を考えなければ)ので20代さかのぼると100万人、27代前には1億人を越えてしまうことからすれば、大体誰の先祖にも立派な人、有名な人がいておかしくない道理でもある。だいたい武士として系図を引けば、清和天皇か桓武天皇につながってしまうわけで。また著者が、戦時下であった自分の父母の子供時代や、子供3人に先立たれた先祖について思いを馳せるところはしみじみする。
1投稿日: 2016.10.09
損したくないニッポン人
高橋秀実
講談社現代新書
ヒデミネ節も空回り気味
季刊誌『セオリー』への連載を再構成したもの。貨幣愛だとか行動経済学だとかに興味があって読んだ。ヒデミネ節は楽しめるが議論が深まっていかない感じ。 「損失回避の原則」に疑問を呈しているが、この本はほぼ全編その話をしているような。ただ、二者択一問題に対する、設問の裏をムダに読むような勘ぐりはおもしろい。 東京リスクマネージャー懇談会によるリスクの定義の矛盾はその通りと思う。リスクとは、本来的には「不測の」要素があると思うのだが、金融工学では事例の数が多ければ予測可能なものという概念になっていると思う。オッズも読めないものは不確実性として別に整理しないといけないことに。
2投稿日: 2016.10.09
地球の履歴書(新潮選書)
大河内直彦
新潮選書
ロマンあふれる読み物
文章といい、トピックの選定といい、引用のワザといい、物書きとして玄人はだしである。うますぎて鼻につくくらい。福岡伸一にライバル登場という感じ。 しかし地学ってやつにはそもそもロマンがあるし、これはよい読み物。数多のギヨーがプレートに乗っかって太平洋の端から端へ横切りながら沈みこんでいく様を想像した。ほかにも巨大噴火、頁岩から作る燃料、干上がった地中海、ニオス湖の湖水爆発などなど。
1投稿日: 2016.10.09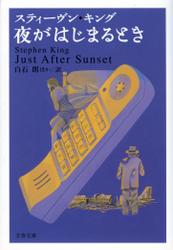
夜がはじまるとき
スティーヴン・キング,白石朗・他・訳
文春文庫
さすがのお手並み
短編集。アメリカでは1冊のものを2分冊にしている。あいかわらずうまい。 複数の手記を組合わせる形式をとったクトゥルー神話風の「N」。解説によるとキングには直接にクトゥルー神話に題材をとったものは少ないそうだが、前にも短編で1つ読んだことがあったな。あれはなんだったか。 超自然的なものは何ひとつ出てこないが身の毛もよだつ描写の「どんづまりの窮地」などなど
1投稿日: 2016.10.09
bookkeeperさんのレビュー
いいね!された数185
