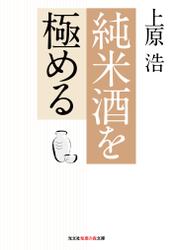
純米酒を極める
上原浩
光文社知恵の森文庫
ここまで日本酒が衰退したのは…。
日本人が日常的に日本酒を飲まなくなって久しいですが、もし日本人として(自衛隊海外派兵よりも)日本の文化を海外に伝えたいなら、この本を読んで、純米酒を楽しむべきです。ちなみに私は(この本には載ってませんが)秋田の天の戸(生酛)が好きです。
4投稿日: 2015.06.16
あ・うん
向田邦子
文春文庫
生身の人と人が付き合い、生きていくって、やっぱりこういうことかな。
門倉と仙吉、そして、たみ。この3人だけではなく、登場する人たちがその日その日を地に足つけて生きている昭和の一コマ。この平成のドライでスマートな生き方ではない、かなり泥臭く、でもエネルギッシュで、人情の薫る素敵なエピソードが流れるように語られます。あの戦争の後で、失った何か大きなものを感じさせてくれます。大正から昭和初期にかけて、我々は今にはない別のものを確かに持っていたのかも。著者が生きていたらこの先の話も読めたかもしれないと考えるとちょっと別の意味で切ないです。
6投稿日: 2015.05.05
新訂 妖怪談義
柳田国男,小松和彦
角川ソフィア文庫
遠野物語を読んでもわからなかった、柳田がここにいます。
この本の位置づけを書いておきます。遠野物語は遠野で語られていた伝承をまとめてありますが、この本は今や妖怪(彼は別の言い方もしてますが)と言われているモノたちの呼び名、中身を全国の伝承を通してまとめてある書です。我々は水木しげるたちによって描き出された「妖怪」に慣れ親しんでいますが、ここで描かれているそのものはその原初のデータです。こうしてまとめられていることは、正直奇跡です。妖怪ファンの方、是非ご一読を。
6投稿日: 2015.03.15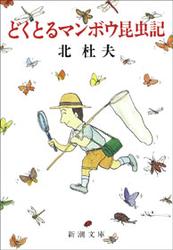
どくとるマンボウ昆虫記
北杜夫
新潮社
今改めて読んでも、これは昆虫記どころではありません…。
まず、今の読者に北杜夫の「面白さ」をわかっていない人がいたら(いるに違いない)、まず読んでみてください。どこからどう進んだら彼のような人間が出来上がるのか、当時もわかりませんでしたが、今読んでも、やっぱりわかりません。とにかく愉快で、楽しめます。この2015年前後のちょっとぎすぎすした世の中が変だな、窮屈だなと思った方は是非手に取って、この規格外の破天荒さをお楽しみください。
5投稿日: 2015.03.15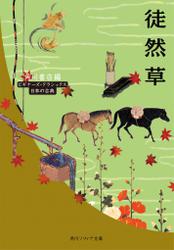
徒然草 ビギナーズ・クラシックス 日本の古典
角川書店
角川ソフィア文庫
この徒然草は読みやすい。こんな感触初めてかも…。
はじめ出会ったときはかなりソフトな感じで、きっと軽い感じな内容だろうと勝手に想像していたこの本。侮れませんでした。かなり編集にこだわりを感じますし、とにかく読みやすい。この種の古典はとかく原文、訳文が忠実に並び、定型化されているとの印象ですが、アレンジが見事です。こんな読み手にやさしい「徒然草」は初めてです。最後までするっと行けます。特に今までつれづれに最後まで行けなかった方にお奨めです。
3投稿日: 2014.10.30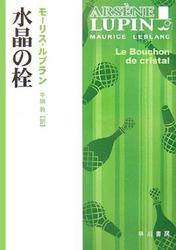
水晶の栓
モーリス・ルブラン,平岡敦
ハヤカワ・ミステリ文庫
今読んでも、まったく新鮮!どうして?
子供の頃、新潮文庫版や、児童書系の書籍でも何度も読んだお話。しかし、今回新訳で再挑戦。何と、まったく感動。面白さが変わらず。どういうことでしょうか?一体ルパンって何者だ。最後のラストシーンまでホントに素敵なストーリーです。まだの方、うらやましい限りですが、是非お楽しみください。そしてルパンに振り回されてください。
4投稿日: 2014.10.20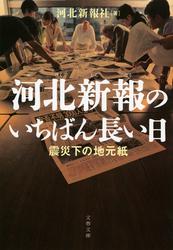
河北新報のいちばん長い日 震災下の地元紙
河北新報社
文春文庫
新聞の役割って…、ホント普段気づきませんが…。
最近、大手新聞社の歴史的記事責任についての事案がありましたが、この本を通して新聞の役割を改めて認識させられました。この新聞社およびその関係者が出会い、経験した事柄は、もう2度と起こってほしくはないですが、これによって彼らが得た教訓と後世への知恵は何事にも代えがたいです。今改めてあの震災の直後、またしばらく後に起こったあの地方を基盤とする新聞社が体験した人との交わりとつながりを追体験しました。
4投稿日: 2014.10.20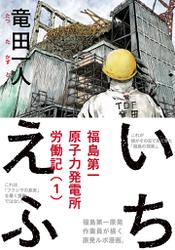
いちえふ 福島第一原子力発電所労働記(1)
竜田一人
モーニング
こんな視点があったか…。ちょっと不思議な読了感
まさに淡々とした日常として福島原発内での「ある仕事」のシーンが、別に何かに向かって力むでもなく描かれています。この読了感は、正直かなり「さわやか」です。 福島原発での過酷な作業にはこんな種類の、また、いろいろなレベルでの仕事があるんだと認識させられながらも、それとはまったく関係のない、非常に懐かしい感覚「仕事をするってこんな感じ」だよなあ、というどこかうらやましい思いが強く想起させられました。読後、「福島って…」という悲壮感ではなく(それは、それで考えさせられますが)、それを前向きに受け止め、巧みに咀嚼してしまった後に、いわば「爽快感」みたいなとても素敵で気持ち良い感覚を残します。続きがもっと読みたいです。
6投稿日: 2014.06.29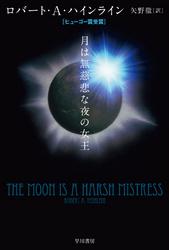
月は無慈悲な夜の女王
ロバート・A・ハインライン,矢野徹
ハヤカワ文庫SF
翻訳SFモノの宿命か、時は残酷だ…。
名作といわれ続けて、読んでいなかったこのの一つ。ついに手に取ってみました。しかし、残念な問題点が2つ。 一つ目は翻訳上の言葉遣いの古臭さがどうしても鼻についてしまいスムーズに読めません。当時は矢野徹の名訳が光っていたのでしょうが、21世紀も10年以上過ぎて今使われている日本語にはあっていません。つまり、もっと早く読んでいればよかった、という話でしょうね(すみません) 二つ目は表現されている科学技術について。ハインラインの書かれた当時の既存技術からの類推と、未来への見通しの鋭さは脱帽ですが、さすがにここまでネット活用が進み、科学技術が発展した今ではちょいつらいです。これほど翻訳SFものの悲哀を感じてしまった作品も珍しいです。せめて「エンダーのゲーム」のように(映画化が伴ったからですが)新訳が待たれます。
1投稿日: 2014.06.29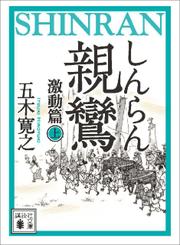
親鸞(しんらん) 激動篇(上) 【五木寛之ノベリスク】
五木寛之
講談社文庫
同様な読者を念頭に書かれているのか?何が書きたいのか?
激動編に入って、ちょっと話が妙になってきました。話はリズム感もあり悪くないですが、もともと自伝的にほとんど何も残していない人物の話とはいえ、フィクションとしても作者の意図がよく伝わってきません。私の勝手な期待とはずれているだけなら良いですが、ここで描かれている「親鸞」という人物に対してまったく感情移入もできず戸惑っています。敢えて言うなら「親鸞」という人物設定を使った、まったく別の人物のお話、というところでしょうか。言いすぎですか?ちなみに下巻まで読んだ後の感想です。
3投稿日: 2014.06.13
Shuttle0131さんのレビュー
いいね!された数214
