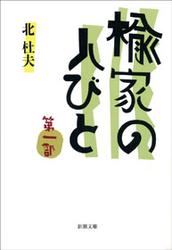
楡家の人びと 第一部
北杜夫
新潮社
美しい文章に彩られた、あるファミリーの年代記、群像小説です
この小説のすさまじいところは、北杜夫自身の祖父から始まるほぼ実在したと思われる人々の話を見てきたように生き生きと描き切っているところです。一体どんな想像力を働かせればこんなことができるのか。いわゆる他の私小説がかなたに霞みます。昭和を生きた家族のそれぞれの視点の、立場の、境遇の深い洞察と、美しい文章。北杜夫の腹を抱えて笑える小説しか読んだことがなかったので(それはそれで傑作ですが、特に「船乗りクプクプの冒険」とか)この小説は結構衝撃でした。
6投稿日: 2016.02.10
大炊介始末
山本周五郎
新潮社
また、見事なストーリーテラーぶりで、言葉もありません。
私が理解していないだけなのか、もの知らずなのか、この作家はなぜここまでこの時代の庶民の様子を描けるのだろうかとにかく。もう何冊読んだか忘れましたが自分がタイムスリップして江戸の町にいるようで、とても心地よいです。まだ周五郎を読んだことがない方はこの短編集を是非。そしてその後で「樅の木は残った」で号泣してください。
5投稿日: 2016.01.02
反知性主義―アメリカが生んだ「熱病」の正体―(新潮選書)
森本あんり
新潮選書
これが本場の反知性主義? 日本のは確かに違う
私には本当にわからないキリスト教からの道徳規範形成。でもこの本によりマックス・ヴェーバーの比較宗教社会学から見た宗教倫理からの資本主義の産出と同じくらい納得感ありました。かの国と我が国はどのように「親密な同盟国」なのか?この目線から正直わかりません。わが国の反知性主義はどうやらこれとは違うようなので別考察が必要かも。とはいえ、この本は目を通しておいて損はないと思います。
5投稿日: 2016.01.02
「文藝春秋」で読む戦後70年 第一巻 終戦から高度成長期まで
文藝春秋・編
文藝春秋
今読むとちょっとびっくりな記事が…。
もちろん「文藝春秋」ですから、その時代の空気をうまく伝える記事が多くまとめられていますが、 その中に「ベトナム最前線の日本兵」という記事が入っていました。「昭和41年」に「19歳」でベトナムで戦死する日本兵の話です。どんな話を想像されますか?タイトルを見て、私も一体どういうこと?と思いました。しかし、中身は、今の沖縄の辺野古問題に通じる重要な問題提起でした。沖縄には住んでいない、住んだことがない「日本人」がまるで意識していない、想像もできない現実が付きつけられていて言葉がでません。この問題を70年もほったらかしにしている我々って、何だろう?
6投稿日: 2015.11.11
幼年期の終わり
クラーク,池田真紀子
光文社古典新訳文庫
不朽の名作、旧訳よりは読みやすかったです。が。。。
もちろん、訳の差分の問題もありますが、むしろ2015年という今、この物語をどう読むか?SFの古典として読むか、はたまた今の社会情勢や文化背景を思い浮かべながら読むか、の立ち位置が問題となるくらい古典になっています。今やこの物語が最初に語られてから社会状況は大きく変わり、予想もつかなかった社会的、政治的パワー不均衡が存在してます。私としては残念ながら旧訳を読んだ時の恐ろしく感動的な感覚は戻ってきませんでした。むしろ人間至上主義的なちょっと鼻につく感じが後味として残ってしまったことが意外でした。まあもっとも新訳「ソラリス」を読んだ後だったので、特にその感覚が強調されたのかもしれません。逆に「ソラリス」の普遍的な問題提起が改めて評価したくなりました。ん?何の読後感想書いてるんだっけ?
8投稿日: 2015.09.05
それから
夏目漱石
岩波文庫
すさまじい…。夏目漱石恐るべし。
現在、改めて朝日新聞に連載中ですが、むかし最初の方だけを読みかじっていただけだったので、ちゃんと最後まで読んでみました。夏目漱石の「それから」はこんな話とは知りませんでした。迂闊でした。最後の方はもうノンストップ。これが当時新聞に連載された時はおそらくとんでもない反響だったんでしょうね。今、読んでもこの文章から感じる迫力は、まったく色あせていないですね。驚きです。(とはいえ、この感触は、いろいろ様々経験して、この歳になって読んだからかなあ…)
8投稿日: 2015.08.22
ソラリス
スタニスワフ レム,沼野 充義
ハヤカワ文庫SF
どのようにも読める不思議な物語です。私の読み方は…
旧訳は読んだことはなかったのですが、今回ポーランド版原典から全訳がされたと聞いて手に取ってみました。もちろん、SFに(ハードSF)に分類されるのでしょう。おそらく私はコンタクトものとして読んだと思います。というのも、読んでいる最中では自分がどのように感じて、理解して味わっているのかわからず、読了してようやく自分がどのように読んだかが分かったからです。蛇足ながら書かせてもらうと、物語とは全く関係なく、そんな話も出てきませんが、「ひも理論」を思い出しました。つまり、ひもはまだ理論的にも実証的にも完成していない考え方ですが、もし人間の理解を超えた宇宙の仕組みを直接的に理解してしまう何かが存在し、それと接触した人類はどのような行動を取り、何を考えることになるのだろうか?という妄想です。そもそも「人間の理解を超える」というのはどういう意味なのか。そんなことを考えさせられた作品でした。お奨めします。
8投稿日: 2015.08.22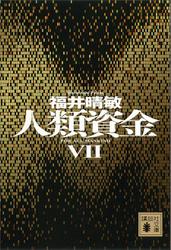
人類資金VII
福井晴敏
講談社文庫
長い間待たされましたが…。
これから1巻から読まれる方は、ちょっと大変ですね。でも(途中でもいろいろありますが)面白いコンゲームが待っていますので楽しみに読み進めてください。よくもまあこれだけの身体能力と頭脳を持った人間たちを多層的に描けるものだと感心しきりです。それに文章もうまい!福井風文章が日常の会話の中でも移ってしまいそうです。電子版で読みましたが、本屋で7巻の厚さを見てびっくりこんな厚さだったんだ…。電子版万歳!2015年現在の国際・社会情勢を頭の片隅に置きながら、今読む本として非常に興味深かったです。
10投稿日: 2015.08.10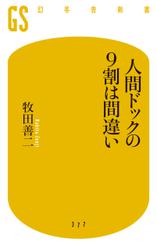
人間ドックの9割は間違い
牧田善二
幻冬舎新書
言いたいことはよくわかります、が…。
自分にとっての人間ドックの位置づけを改めて考えさせられる本でした。確かに著者が指摘するように惰性で受けているだけだし、本気で何かが見つかるとも思っていないけど、だからと言って、今の時点の技術で、もれなく、できることを、徹底的に検査しておくというのは、正直ちょっとしんどいです。それとも著者がいうような検査が今後標準になるのだろうか?変な話ですが、この本を読んでいる間、気分が悪く、病気になりそうな感じがしました。
6投稿日: 2015.07.04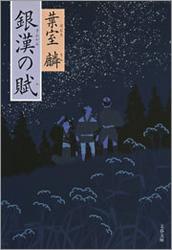
銀漢の賦
葉室麟
文春文庫
幼馴染のあうんの呼吸、あるいは男の生き様
ありきたりの付き合いではこうは行かない。確かにこれは幼馴染の強みかも。ただ、この話を単なる友情の物語と読んでしまうより、ひとりひとりの男の生き様と理解した方が泣けます。事実、最後に向かって盛り上がります。同じ年代の男としてラストもグッド!
5投稿日: 2015.07.04
Shuttle0131さんのレビュー
いいね!された数214
