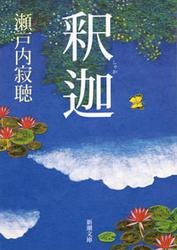
釈迦(新潮文庫)
瀬戸内寂聴
新潮文庫
釈迦の「入滅の旅」の物語である。
寂聴さんには「ブッダと女の物語」という昭和58年出版の作品があるが、それに入滅の時を書き加え感動のエンディングに持っていった感じである。教団の修行僧であっても嫉妬や渇愛から騒動が起きる。人々は風に吹かれ散り落ちる葉のように愚かである。釈迦の旅はどこか目的地を目指すものではなく出会う人々に煩悩の火を消す方法を教えさとす旅であった。ひとつひとつのエピソードはアラビアンナイトのように魅惑的。仏教の教えとして疑問を持つ部分も少々あるが本書はあくまでも小説として楽しむものだと思う。
0投稿日: 2018.05.21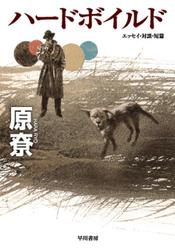
ハードボイルド
原 りょう
ハヤカワ文庫JA
盛り沢山の読み応えある1冊だった。
原さんのエッセイと対談、小説以外の沢崎シリーズ、文庫・単行本未収録短編と盛り沢山の読み応えある1冊だった。 前半はロバート・B・パーカーの来日の際の思いを語り、チャンドラーや結城昌治さんへの敬愛の深さを語り、ドストエフスキーを解説する。 船戸与一さんとの対談では「ハードボイルドとは何か」を掘りさげる。本来の事件解決以外のプラスα部分、それはセンスであり美学であり結局は定義できないものなのかもしれない。 さらに沢山のミステリ小説の解説をされているので読書案内の意味合いも強い。後半は雰囲気が変わり短編集となる。パートナー渡辺の失踪事件の詳細が明らかになる「番号が間違っている」は三人称で書かれていて他作品と作風が違うが面白かった。 本書を読むと原さんは大変な読書家でありジャズを愛する音楽家でもあり博識な方なのだということが伝わってくる。今まで出版された本すべて題名が7文字であることは全く気付いていなかったので驚いた。 もしかしたら、こういう小さなコダワリだったり受賞後はやく普通の生活に戻りたいと熱望したりする姿こそがハードボイルドなのかもしれない。
0投稿日: 2018.05.17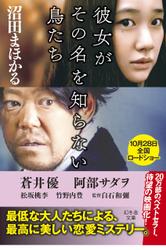
彼女がその名を知らない鳥たち
沼田まほかる
幻冬舎文庫
私の中では陣治は最後まで火野正平さんだった
このところ暗く重い本を読み続けてきたがそのトドメの一冊に相応しい作品だった。 嫌悪なのか愛なのか十和子と陣治の奇妙な生活。どこか懐かしい昭和を思い起こさせる作風、寂聴さんが瀬戸内晴美さん名義で書いていた小説に似ている。Wikiで沼田さんのことを調べてみると70歳、女性、離婚、得度という文言があり納得した。お二人とも人間の醜さや心の闇から逃げず受け留めながら書いている点が共通している。 私はいつも日本文学よりも海外作品のほうが良くも悪しくも女性が活き活き描かれていると感じていた。しかし本書の十和子は見事である。 優しさなのか残虐なのか正直なのか狂気なのか、とにかくすべてが詰まった作品。なんとなく展開は途中でわかってしまうがミステリ要素を凌ぐ心理描写である。
0投稿日: 2018.05.15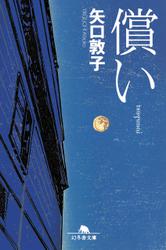
償い
矢口敦子
幻冬舎文庫
償いというより自分の弱さとの闘いである
脳外科医の日高は妻子と死別し、大学病院の派閥闘争に巻き込まれ、背負ってしまった荷物を降ろすため全てを捨てホームレスになった。償いというより自分の弱さとの闘いである。ミステリ仕立てにする意味があるのだろうかと感じるほど日高の自己愛の吐露である。ところがそれはそれで面白いのだから不思議だ。日高が天才医師ではなく愚かな凡人であることに共鳴するからだろうかと考えながら読んだ。本筋からは逸れるが日高と15歳の少年との会話が面白かった。私も「現代の猿はなぜ人間に進化しないのか」などと考える子供だったことを思い出した。
0投稿日: 2018.05.07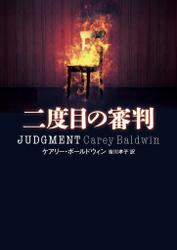
二度目の審判
ケアリー・ボールドウィン,皆川孝子
ハーパーBOOKS
邪悪とは一体何なのだろうと考えさせられる良書
学習障害を克服してFBIのプロファイラーになったスペンスと法精神科医ケイティが連続猟奇殺人に挑む。18歳で父の処刑に立ち会った少女は父の無実を信じ、人を犯罪行為に駆り立てる仕組みを解明したいと願い続けた。念願かなって法精神科医になったケイティだが愛という概念が欠落したまま虚しい日々を送っていた。 かなりハードなミステリと言っていい内容なのだが、ケイティの愛を得ようとするスペンスのアタックがロマンス小説の雰囲気を作り出して何とも不思議な作風になっている。グロテスクな内容が緩和されて読みやすいのは事実なのだが・・・ハーパーBOOKを何冊か読んだがロマンスを絡めた作品が多いので私は勝手にハーレクインミステリと名づけている。 慣れてくるとこの作風も面白いので、実は結構気に入っている。 司法取引がアメリカではわりと好意的に受け入れられていること、FBIの犯罪調査分析の仕事内容、復習と正義の違いなどはしっかりと書かれている。 「恐怖は抑えられない。それは住処をもたず、大地をさまようこともしないが、われわれの心の奥底に存在する」邪悪とは一体何なのだろうと考えさせられる良書である。 途中で犯人が分かったと思っていたが半分当たって半分外れていた。
0投稿日: 2018.05.01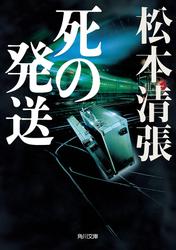
死の発送 新装版
松本清張
角川文庫
突っ込みどころ満載のまさに隠れた名作である
清張さんの隠れた名作と言われているが何故「隠れた」なのかは読んでみると納得の作品である。 3流新聞社の記者が5億円の公金横領犯人を張込むシーンが続き展開が非常に遅い。半分過ぎてやっと動いたかと思ってからは結構面白かった。自ら発送したトランクの中から死体となって発見された新聞社編集長の謎を追う部分は面白い。記者は退屈な張込みから一転、東北までの列車トリックに挑むのである。 本作品は1961年の週刊公論連載だが急展開しすぎて話が繋がらない場面がある。何故か急に犯人が捕まっていて「供述によると」という文言がでてくる。ページを飛ばしてしまったかと思い数ページ戻って読み直してもやはり繋がらない。どういう経緯で逮捕されたかも分からないままである。 連載の残回数が少なくなり焦ったか、それとも売れっ子すぎて仕事掛け持ちで混乱していたのか。前半のスローペースは何だったのか。文庫になるときに加筆しなかったことも不思議。トリック自体は面白いが突っ込みどころ満載のまさに隠れた名作である。
0投稿日: 2018.05.01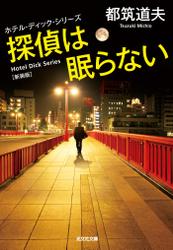
探偵は眠らない 新装版~ホテル・ディック・シリーズ~
都筑道夫
光文社文庫
ハードボイルドっていったい何だ?
ハードボイルドというキーワードだけで検索したら何故かこの作品がヒットした。 懐かしいと今さらと両方の思いで試し読みしたところ見事に嵌った。これは読むしかないと購入した次第。 元警視庁刑事だった田辺は浅草の高層ホテルの警備員になった。よく海外ミステリに出てくるホテル専属探偵は格好良いが、田辺は妻が亡くなり娘が嫁ぎ一人暮らしが面倒なのでホテルに住み込んだのだった。 ホテルは小さな街のようなもので様々な飲食店やSHOPや24時間体制で働く従業員がいる。警察と違ってその街では何かが起きる前に防ぐことが出来る。大切なのは事件の真相ではなくホテルへの影響である。その辺りは完全に割り切っていてホテルから一歩外に出たならば殺し合いをしたってかまわないのだった。外のことに関わるつもりはないという割り切りかたが何故か格好良かったりする。平気で証拠隠滅もする。 久々の都筑さんの世界を堪能したが少々時代が古いことは否めない。トラヴァーユという言葉も懐かしい。それを補うポイントは浅草の歴史や骨董品の薀蓄など披露される知識の広さである。
1投稿日: 2018.04.19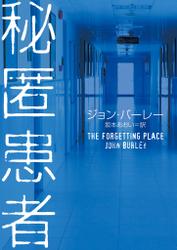
秘匿患者
ジョン・バーレー,坂本あおい
ハーパーBOOKS
難しいテーマ、不思議な雰囲気・・・でも★5つ。
こんなに感想の書きづらい小説を読んだのは初めてだ。舞台はアメリカの公立病院。患者は心神喪失により司法の場から移送されてくる。難しい立場の患者と医師の話からスタート。雰囲気はカフカの変身に似ているようでもありロシア文学のようでもあり。妄想は自分の偏見を写す鏡、誰もが陥る危険を秘めている。決して明るくはないが何故か離れられない魅力がある。前半が単調なので挫折する人も多いのではないかと考えていたが、この雰囲気がこの小説の生命線だということが最後にわかる、こんな感じにしか表現できないのだ。
0投稿日: 2018.04.17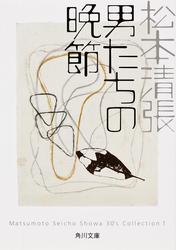
男たちの晩節
松本清張
角川文庫
松本清張の隠れた名作
短編7作品。大手企業を次長以上で退職したOBの集まる「社人会」の一幕、哲学者と口述筆記の速記者との悲しい恋などは「静かな名作」という雰囲気で志賀直哉を思い起こさせる。5作目「空白の意匠」では新聞社広告部と広告代理店の息詰まるようなかけひきを描いている。編集や記者などの花形部署と広告部との軋轢も読んでいていつの間にか引き込まれていく。派手さはないが日常の小さなエピソードを丁寧に書いた作品である。最後のミステリは流石は清張という面白さだった。
0投稿日: 2018.04.16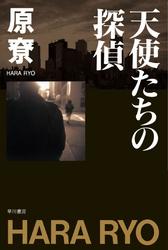
天使たちの探偵
原りょう
早川書房
全て子供中心のストーリー
沢崎シリーズの短編集。 今まで長編を4冊読んで原さんが書きたいのはミステリではなく屈折した少年(青年)と親子の関係ではないかと感じていた。これは読者にとっても興味深いテーマである。しかしスペンサーシリーズの初秋や森村誠一さんの人間の証明などを思い浮かべると難しいテーマと言わざるを得ない。 本書の短編6作品は全て子供中心のストーリーとなっている。読み始めてすぐにやはりこういうテーマで書きたかったのだなと感じた。 私は特に2作品目の「子供を失った男」が気に入っている。一輪の白い薔薇を車道の真ん中にそっと投げる男、そんな芝居がかったシーンで始まる短編だが芸術家を目指す若者の危うさが良い味を出している。 「自分の恐怖を自分ひとりで始末できなければ、いくつ年を重ねても大人とは言えない」・・・沢崎の心の声が響く。これは長編で読みたかった。 デビュー作の直後に書かれたということなのでセリフがまだまだチャンドラー色がありその点もポイントである。さらに「あとがきに代えて」で探偵になる前の沢崎の過去が語られていることも、もう一つのポイントである。 さて、次はいよいよ新刊へ。
0投稿日: 2018.04.06
shohjiさんのレビュー
いいね!された数34
