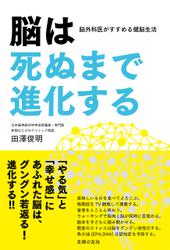
脳は死ぬまで進化する
田澤俊明
主婦の友社
どれくらい長生きするかによって違うのではないか
著者の説明によると細胞数より神経ネットワークのほうが大事なので年齢に関係なく脳は進化するとのこと。さらに通常は脳の1割しか活用していないので10万個の細胞が減っても開拓すれば良いという理屈である。 ではどうすれば良いのか、100項目のコツが載っている。 全てを実行するのは無理なので私の勝手な好みで選ぶと音読、計算、旅行、日曜大工、落語、感動した映画をもう一度見る、である。 特に落語は話を聞きながら登場人物を把握し展開を想像しオチを理解して笑う→脳の活性化プラス笑いがストレス解消に繋がるためベストである。素晴らしい。
0投稿日: 2018.08.15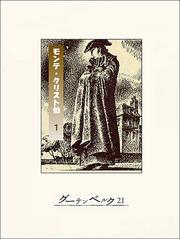
モンテ・クリスト伯(1)
アレクサンドル・デュマ,泉田武二
グーテンベルク21
長年、読むキッカケを掴めずにいたが・・・
ついに電子書籍のセールで背中を押され5冊セット購入。 無実の罪で投獄されたダンテスが脱獄して復讐を遂げる物語である。有名な小説なのでおおまかなストーリーは理解していたが、予想以上に深いボナパルティズムや王制復古の話に興味を持てず前半は長く感じた。 嫉妬と謀略、投獄、善人だが単純で無学な19歳のダンテスが獄中で神父と出会い目覚めていく。絶望を乗り越え脱獄を計画し始めたあたりから面白くなった。単純な復讐劇なんかじゃないというワクワク感が出てきた。 宝島に上陸したダンテス、2巻へ続く。
0投稿日: 2018.08.01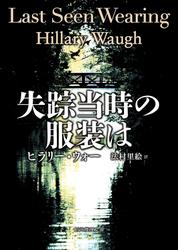
失踪当時の服装は
ヒラリー・ウォー,法村里絵
東京創元社
学生寮から姿を消した女子大生を探せ!
美人でしっかりした娘に何が起きたのか・・・あらゆる可能性を調べ篩にかけ消去法で方向を見出していく。 新作と間違って購入したが1952年に発表された作品の新訳本である(1991年海外ミステリベスト100で20位になっている)学生寮での生活は古き良き時代を彷彿とさせる内容だが地道な捜査過程は等身大の警察小説といった感じで面白い。 警察組織の闇を暴くような現代小説にかなり飽きているので新鮮な面白さだった。 抜群の推理力をもった個性的な探偵などまったく出てこないが渋い警察署長が魅力的。
0投稿日: 2018.07.23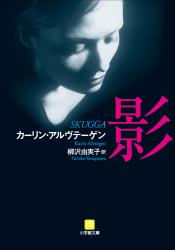
影
カーリン・アルヴテーゲン,柳沢由実子
小学館
これはミステリでありながら純文学である
「影」というよりは「裏」という感じだった。高名なノーベル文学賞作家だってもしかしたら最低最悪の偽善者かもしれない。物語は野外博物館で3歳くらいの男の子が保護されるシーンから始まる。一人の老女の孤独死、寝たきりの作家とその家族、作家を志す若者たち、それぞれのシーンが交互に描かれそれぞれに面白いのだがなかなか繋がってこない。書くことの「喜び」と書けない「苦悩」と書くためなら何でもしてしまう「狂気」と「罪悪感」と「嫉妬」が凝縮されている。久々にこの類の作品を読んだ。これはミステリでありながら純文学である。凄い。
0投稿日: 2018.07.17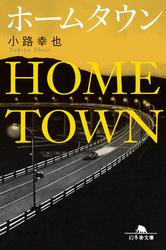
ホームタウン
小路幸也
幻冬舎文庫
他のシリーズとは作風が違っているが面白かった。
どちらかというとデビュー作に近い雰囲気で些細な出来事をきっかけに平凡な人生が変わっていく不思議さを描いている。 幸せな家族だったはずなのにある日、父と母が互いに傷つけあい亡くなってしまう。その場を目撃した兄妹。自分たちには殺人者の血が流れている。それぞれの方法で辛い日々をやっと乗り越えた2人だったが突然の妹の失踪。 大人になるってことはドアを閉めることを覚えることだ。責任ある立場の社会人として、時として嘘を突き通さなくてはならない時もある。それぞれの揺れ動く思い。 主人公の征人が百貨店内部監察の仕事をしてることも関係し軽いミステリ仕立になっているが全体を通して優しさがにじみ出る流れである。 嫌なこと、辛いことは溜め込まずに少しずつ吐き出しておきなさい、年寄りはそれを聞くのが役目、そしてぜんぶ墓場までもって行ってあげるよ。ばあちゃんの言葉が暖かい。 私たち世代はもしかしたら歳のとりかたを少し勘違いしてるかもしれない。いつまでも元気で若くいることも良いけれど上手に枯れていくことを学ばなければと感じた。
1投稿日: 2018.07.13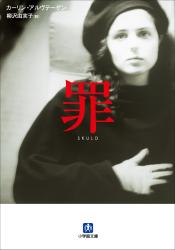
罪
カーリン・アルヴテーゲン,柳沢由実子
小学館
主人公の怯えが常に独特の暗さを醸し出している。
主人公ペーターは社員の横領で負債を抱えパニック障害を起こす。そんな混乱の最中に見知らぬ女から届け物を頼まれ奇妙な事件に次々と巻き込まれていく。ミステリとして展開は面白いが劣等感を抱えたペーターの怯えが常に独特の暗さを醸し出している。事件を通して孤独な一人暮らしの男性ルンドベリと出会い共に過ごすうちにどうして自分はこんなに孤独だったのか謎が解けていく。少年時代の親との関わり、若さ故の人間関係の苦しみ、回想シーンと現在進行形の事件が交差する。事件そのものよりペーターの崖っぷち感のほうが気になって仕方なかった。
0投稿日: 2018.07.09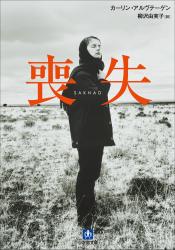
喪失
カーリン・アルヴテーゲン,柳沢由実子
小学館
冷たい重圧と過干渉で支配するという暴力なき虐待
地方都市の富豪の一人娘シビラの不幸は母親がシビラの心を全く理解しなかったことから始まる。常に冷たい重圧と過干渉で支配するという暴力なき虐待を繰り返す母親だったのだ。 ただただ自由を追い求め18歳で家出してホームレスとなった。ところが32歳になったシビラは殺人犯に仕立て上げられてしまう。 物語は少女時代の追憶と現実の逃避行が交互に繰り返されながら進む。ミステリとしてのワクワク感は少ない作品だが心理描写が素晴らしい。 育児放棄や暴力と違い周囲に理解してもらうことが難しいが故に深みにはまる絶望感を見事に表現している。 著者カーリン・アルヴテーゲンは大叔母が「長靴下のピッピ」の作者という文学家族の中で育った。家族の死や離婚など様々な問題を抱えご自身も深い鬱状態になり死を考える毎日だった。 そんななかで自分の心を見つめるために小説を書いた。自由を求めるだけでは社会に適応できないと悩む姿は多くの人が思春期に経験する葛藤でもある。猟奇殺人から始まる暗い作品だが読了後はなぜか癒しを感じるのだった。
0投稿日: 2018.07.03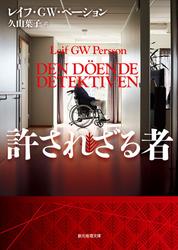
許されざる者
レイフ・GW・ペーション,久山葉子
東京創元社
やんちゃ坊主そのままの退職警官2人が時効を過ぎた事件に挑む。
片方は現役時代「角の向こうを見通せる男」と言われた切れ者だが脳梗塞で倒れ入院。2人の会話は熱く正義感に溢れ着々と事件の核心へと迫っていくが同時に高カロリー食への追憶も繰り広げられる。 北欧ミステリー、9歳の少女、暴行、死体遺棄、時効、などから想像したのは暗く重い作風だったが意外なほどテンションが高いので戸惑った。 ところが第2部に入ると加速度的に面白くなった。それにしても犯人を捜してどうするのかと心配したが謎が解けてからが本当の物語りの始まりだった・・・創造していた雰囲気と違っていたうえに謎解きの楽しみもなかったが面白い作品だった。
1投稿日: 2018.06.25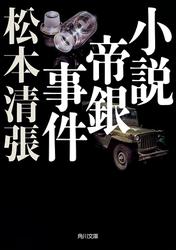
小説帝銀事件 新装版
松本清張
角川文庫
読んでいて何故か冤罪と思えなかった
昭和23年、戦後の混乱期に起きた帝銀事件を詳細に描いた作品。小説の形になっているがほぼ九割方が裁判記録のような体裁で巻頭と最後の各10ページ程度が清張さんらしさが光るフィクション部分である。 もっと冤罪を強調しているかと思ったが予想外の展開だった。コルサコフ症という脳の機能障害で日頃から嘘が多かった平沢は自白が二転三転し確実な物証も乏しく難しい事件であるのは事実。 当初から軍関係者の関与が疑われていた。特務機関の復員者は既に戸籍から抹消されていた場合が多く帰国後も警察の戸口調査に引っかからなかったとのこと。毒薬や細菌兵器の知識をもった人物がすぐ近くに生活していても分からない時代だったのだ。 そのうえ警察の捜査にGHQが介入してきて思い通りの捜査ができなかった。憲法は成立していてもまだ人権擁護という意識が希薄だった。様々な不運が重なった誤認逮捕の可能性も否定できないが、読んでいて何故か冤罪と思えなかったのはコルサコフ症という病気のせいなのだろうか。 どちらにしても現代ならばいきなり死刑判決とはならないであろう。筆跡鑑定や物証の科学検証を今の技術でやり直したらどんな結果がでるのだろう。
0投稿日: 2018.06.14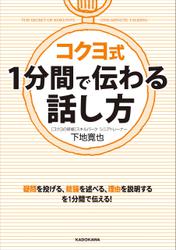
コクヨ式 1分間で伝わる話し方
下地寛也
中経の文庫
流石に1分は短いのではと思いながら読んだ・・・
文房具が好きでコクヨさんも大好きなので興味をもった。さらに私が社会人になったばかりの頃は3分間スピーチだったが、ついに1分になったかという感慨もあり読んでみた。しかし3分は思った以上に長かった記憶があるが流石に1分は短いのではと思いながら読んだのであった。結論から言うと驚く内容ではないが実践的な方法がしっかり書かれていた。早口を改善するにはスピードを遅くするのではなく間を入れること、声の出し方、朗読、シャドーイングなど、社内の共通認識とするのは難しいことだがしっかり研修に取り入れているのは凄いと感じた。
0投稿日: 2018.05.30
shohjiさんのレビュー
いいね!された数34
