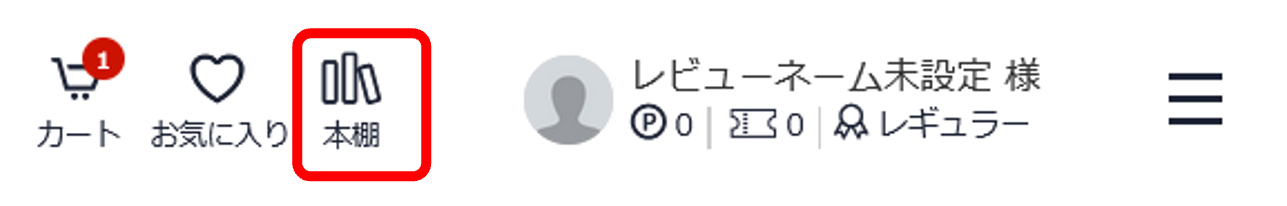![]()
shohjiさんのレビュー
参考にされた数
35
このユーザーのレビュー
-
神様の裏の顔
藤崎翔 / 角川文庫
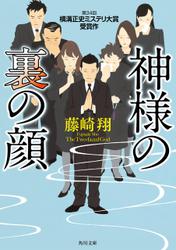
重くならない文体と語り手が次々と変わっていく構成の面白さは素晴らしい
3
元教師、誰からも慕われた神様のような男、坪井誠造の通夜での出来事。参列者同士の会話の中から故人には裏の顔があったのでないかという疑惑が浮上する。人間とは温厚すぎることも周囲の人を追い詰めてしまうものな…のだ。としみじみ感じた。その対極にある嫌われ者のスパルタ体育教師が所々で不思議と魅力的に見えてくるのも事実。後半の通夜ぶるまいの席での議論は空気に飲まれ二転三転する人間の弱さが丸見え状態。教師であるが故の子育ての難しさも露見する。それでも重くならない文体と語り手が次々と変わっていく構成の面白さは素晴らしい。 続きを読む
投稿日:2017.01.29
-
毒見師イレーナ
マリア・V・スナイダー, 渡辺由佳里 / ハーパーBOOKS
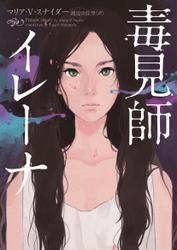
物語っていいなと実感できる
2
NHK-FM青春アドベンチャーのラジオドラマを聴いて面白かったので電子書籍を購入。
サバイバル・ファンタジーというジャンルは馴染みがないので私はもしかしたら最高齢読者なのではないかと変な心配をしなが…ら読んだ。
異世界にあるイクシアという国家が舞台。19歳の死刑囚イレーナは死刑執行日に絞首台に行くか毒見役になるか選択を迫られる。毒見師という職業も面白いが逃走防止用に猛毒を飲まされ解毒剤を毎日呑まなければ死んでしまうという設定が凄い。
いつも一人で苦しみを背負い逃げ出す準備をしながら生きてきた少女、孤児のイレーナ。自分の未来には希望も夢もないと考えながら迷路に迷い込んでいたが毒見役になったことで強く成長していく。
考えてみれば誰もが日々選択を迫られ今日を生き延びても明日のことなどわからないのだ。魔術師や幽霊も出てくる異世界の話なのだが生死のかかった緊迫感ゆえなのか結構面白かった。本来はリアリティあふれる小説が好きだがこういう作品を読むと物語っていいなと実感できる。 続きを読む投稿日:2018.02.07
-
世界のエリートがやっている 最高の休息法
久賀谷亮 / ダイヤモンド社
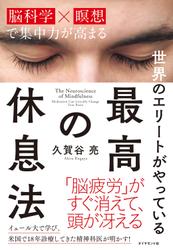
残念ながらストーリが洗練されているとは言い難いがそれ故の親しみ易さもある。
2
雑念が集中力を低下させ負の連鎖を作る。競争に負けたくないという気持ちが脳を疲弊させる。仕事のON/OFFの切り替えが難しい。何もしないでいるのが実に難しい。休もうとすることでかえって疲れてしまう。全て…は「心ここにあらず」過去を反芻し未来を心配するからである。全く笑えない内容である。私も堂々巡りの中で苦し紛れに瞑想や呼吸法などに興味を持った時期があった。その結果少しずつ、いつの間にか怒らなくなり焦らなくなったのも事実である。しかしこの一歩を踏み出すのは難しい。宗教を連想するため瞑想を嫌う人も多いと思う。
それならば何とかしてきっかけをみつければいいのである。そのきっかけ作りとしてこの本は脳科学の立場から書かれているので最適と言える。主人公が東洋思想や仏教にアレルギーを持っている設定なので入り易いと思う。残念ながらストーリが洗練されているとは言い難いがそれ故の親しみ易さもある。とにかく多くの人が推奨するのであればやってみようかという柔軟性を持ったならその瞬間にほとんどの問題を乗り越えているのだと思う。 続きを読む投稿日:2017.01.25
-
仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方
宇都出雅巳 / クロスメディア・パブリッシング(インプレス)

まさに王道テクニック
2
人間の脳は良く言えばエコ装置、悪く言えば怠け者で忘れっぽい。いくら能力を鍛えても脳のメカニズムを知らずに頑張っていたら効果はない。著者自身が「この本は画期的な技術本ではない」と書いているとおり王道テク…ニックを脳科学的に説明し納得するための本である。まずミスを4つの種類に分けて考えていく。さらに基本対策とマスターへの道と続く。NLPやメモ術、ワーキングメモリ、フレームワーク、ゾーンやアンカリング効果など説明は多岐に渡っている。結局「ミスはなくせない」という事実を受け入れることがミスをなくす唯一の道でもある。
業務に熟練していればミスがなくなるわけではない。自信過剰の罠や見栄やプライドや義務感なども判断ミスに繋がって行くのだ。著者はこれらの罠から抜け出すために大切なことを2つあげている。1つは思い切り痛い目にあって現実を知る。2つ目は脳の特性を知ることである。取り上げられている実務的対策はTO DOリストやチェックリスト、ルーチンを決めるなどまさに王道テクニックというべきものでる。こういう当たり前のことを書いてある本は良書であると最近思うようになった。そして当たり前のことを当たり前にこなしている人は賢人である。 続きを読む投稿日:2017.01.22
-
沈黙
遠藤周作 / 新潮社
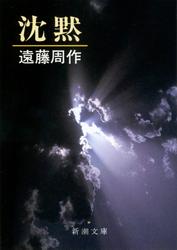
「信」とは何か
2
遠藤周作さんの棺には遺言により『沈黙』と『深い河』の2冊を入れたといわれている。この2冊に共通しているテーマは「信」とは何かということ。
そもそも信じるには勇気が必要だ。確固たる証拠があるならそれは…「信」ではなく「理解」である。司祭がキチジローに対し苦しんだのはこの「信」が揺らいだからである。
「信仰」とは人間の叡智を超えた存在を仰ぎみるというイメージがある。それは生きるためのものであり信が信仰を生み、信仰が信をさらに強くさせていく。だが不思議なことに時として最も賢明な行いは何もしないことである。
踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏んだとて心底の信仰がどうなるものでもない。
また、弱きものキチジローが居なければこの小説は成り立たない。強いものより苦しまなかったと誰が断言できよう。神は人それぞれの心に中にいるもの、ということか。
日本人は神仏をも日本文化に取り込み独自のものにしてきた。仏教も原始仏教とは違う「信心」を生み出している。
目的地が同じならどの道をたどろうとかまわない。というマハトマ・ガンジーの言葉を思い出した。 続きを読む投稿日:2017.01.25
-
犯罪者【上下 合本版】
太田愛 / 角川文庫
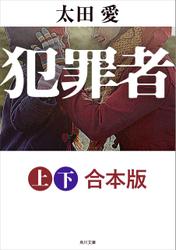
警察の闇を描くだけで終わっていない点が素晴らしい。
2
【上巻】
通り魔事件でただひとり生き残った修司は何故か再度命を狙われる。
警察官の相馬とその友人の鑓水が修司を助け共に謎に迫っていく。
シリーズ2作目の「幻夏」を先に読んでしまったため相馬の左遷…の理由は何だったのか気になっていた。その問題も1作目の本書を読んで無事解決。
相馬の一本気すぎる性格に苦笑する場面もあるが警察の闇を描くだけで終わっていない点が素晴らしい。
食の安全、産業廃棄物の問題点、子供の病気、政治家と大手企業の癒着など沢山のテーマが入り込んでいる。しかしその割に雰囲気が明るく、修司・相馬・鑓水の強い個性が光っている。
構成が上手で、話が何度も前後したり場面が急に変わったりするが読みづらさは余り感じない。
新事実が次々と出てくるので謎解きというよりは良い具合に予測しながら読み進められる楽しさでありスリルだと感じた。
だが、まだまだ事件は解決していない・・とにかく先に進まなければ・・・
【下巻】
そもそもの発端は通り魔だった。
下巻に入って舞台は高知県に飛び次々犯罪が上乗せされていく。高知での出来事だけでも一冊の小説に値する面白さ。若い男女の悲しい恋物語に一時通り魔のことを忘れてしまいそうになった。
相馬・鑓水とその仲間たちは自分と直接関係のない出来事に命がけで飛び込んで行くわけで、なぜこんなにも読者はこの展開に共感するのか・・・冷静に考えると不思議だが止まらない面白さだった。
大企業の傲慢さ、政治家の尊大な態度、成功には犠牲は付き物という自分勝手な解釈に対する反感が共感を呼ぶという一面もあるのだろう。
読み終わってみるとやはり3人のキャラが、とくに鑓水が強烈に印象に残りすぐ次を読まなければと前のめりになっている。
ただ事件決着後の後日談が余りに長すぎたのではないかという感じもしている。派手な演出のあとの謎解きはお金の行方だけわかれば疑問が残る程度が丁度良いのではないだろうか。
次作を読む前に冷静に一つだけ不満を考えだしてみた。 続きを読む投稿日:2017.10.23