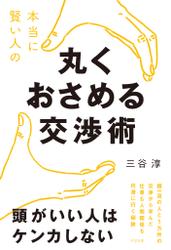
本当に賢い人の 丸くおさめる交渉術
三谷淳
すばる舎
日常に活用できるノウハウ本
著者は弁護士さんで若い時は裁判で勝利を続け悦に入っていたという。しかし報復合戦になることも多かった。そんな時に京セラの稲盛氏と出会い人生が大きく変わった。今では「日本一裁判をしない弁護士」と呼ばれているとか。長い目で見て得をすればいいと考えて相手の話を良く聞き落としどころをみつける。本書は日常に活用できるノウハウ本になっていてとても読みやすいが弁護士さんならではの経験談を期待して読むとがっかりする感じもある。弁護士さんでも相手に出来ないほど話の通じない人がいることを知ったのが一番の収穫であった。
1投稿日: 2017.01.22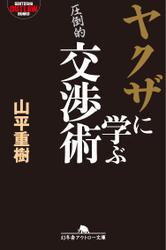
ヤクザに学ぶ交渉術
山平重樹
幻冬舎アウトロー文庫
ここだけの話ではあるが…
現代社会を生きて行くには様々な交渉事を乗り越えなくてはいけない。ビジネスマンと同じくらい交渉を必要とされるのがヤクザの社会だという。いかに本物の抗争に持ち込まずに勝利を収めるか。この交渉は真剣勝負である。決め手になるのは腹の括り方と聞き上手になること。相手にいかに喋らせるか、要は相手と同じ土俵にあがらないこと。普段から口数の多いヤクザは言質をとられやすい。逃げ道を塞ぐ形で相手を追い込んではいけない。今まで読んだコミュニケーションの本は30冊を超えているがその中でもこの本は面白い
0投稿日: 2017.01.22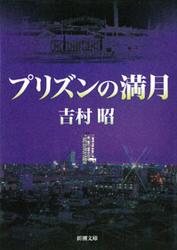
プリズンの満月
吉村昭
新潮社
平和とは何なのだろ
戦犯を収容していた「巣鴨プリズン」の元刑務官の回想録という形で話は進んでいく。GHQの支配下にあり絶対服従のプリズンの中で収容者の待遇改善に奔走した日本人が居た。その一人「巣鴨プリズン」初代日本人所長の鈴木英三郎(実在・実名)、この所長は「破獄」に出てくる府中刑務所長と同一人物である。途中まで私はA級戦犯の待遇改善に違和感を感じていた。国民は戦争が始まってしまえば戦わざるを得ない。戦争の計画に関わった人間の罪は重くて当然と思っていた。米国側が戦犯を英雄視する日本人がいることを警戒するのも理解できた。 しかし戦争裁判は戦勝国が一方的に裁くという前例のない異常なもので、別人と間違われたまま処刑された人も居たほど杜撰であったという。刑務官も全国から電報一本で召集されたが断ったら戦犯として投獄されるという絶対服従のものであった。またプリズンに関わった米兵も上官に逆らうことのできない悲しい立場であった。悲惨な戦争体験を語り継ぐだけではなく様々な立場から検証し記録を残していくことは大きな意味があると感じた。平和とは何なのだろう「これは絶対やらない」という選択肢を持ち自ら行動できる環境ではないかと考えながら読んだ。
0投稿日: 2017.01.22
仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方
宇都出雅巳
クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
まさに王道テクニック
人間の脳は良く言えばエコ装置、悪く言えば怠け者で忘れっぽい。いくら能力を鍛えても脳のメカニズムを知らずに頑張っていたら効果はない。著者自身が「この本は画期的な技術本ではない」と書いているとおり王道テクニックを脳科学的に説明し納得するための本である。まずミスを4つの種類に分けて考えていく。さらに基本対策とマスターへの道と続く。NLPやメモ術、ワーキングメモリ、フレームワーク、ゾーンやアンカリング効果など説明は多岐に渡っている。結局「ミスはなくせない」という事実を受け入れることがミスをなくす唯一の道でもある。 業務に熟練していればミスがなくなるわけではない。自信過剰の罠や見栄やプライドや義務感なども判断ミスに繋がって行くのだ。著者はこれらの罠から抜け出すために大切なことを2つあげている。1つは思い切り痛い目にあって現実を知る。2つ目は脳の特性を知ることである。取り上げられている実務的対策はTO DOリストやチェックリスト、ルーチンを決めるなどまさに王道テクニックというべきものでる。こういう当たり前のことを書いてある本は良書であると最近思うようになった。そして当たり前のことを当たり前にこなしている人は賢人である。
2投稿日: 2017.01.22
人生論ノート
三木清
新潮社
決して古さを感じない
昭和初期の大哲学者といわれている三木清氏。親鸞の関連本や歎異抄を読み漁っていた頃に何度も引用に遭遇していたが著書を読むには初めてである。この「人生論ノート」は【死について】から始まり、幸福、懐疑、習慣、虚栄、名誉心など23の項目について語っている。昭和13年から16年まで文学界に掲載された論文をまとめたものである。わずか175ページであるが一文一文が気を抜いて読むことなどできない文章であると感じた。脳科学の立場から語られることが増えてきた現代でも決して古さを感じない内容であることに驚きながら読み終えた。
0投稿日: 2017.01.22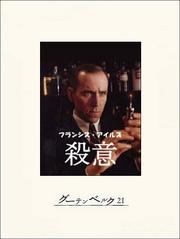
殺意
フランシス・アイルズ,宮西豊逸
グーテンベルク21
他人には言えない心の闇を描いた感じの暗さ
再読。この作品は犯行に至る心理や追い詰められる過程を犯人側から叙述する倒叙といわれる手法で書かれている。主人公ビグリー博士は田舎の開業医で地域の人々に愛されているが強い劣等感から妻に憎しみを募らせる。次第に殺意に変わり裁判へと場面は移っていく。はっきり言ってこのビグリー博士は非常に嫌な性格であるが妻も気位の高い冷たい性格である。普通は他人には言えない心の闇を描いた感じの暗さであり、ついにパンドラの箱を開けてしまいましたねと著者が嘲笑っているようだ。怖い、でも何故か繰返し読みたくなる。きっとまた読むだろう。
0投稿日: 2017.01.22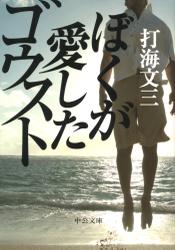
ぼくが愛したゴウスト
打海文三
中公文庫
不思議な世界
◆コンサートから帰る途中11歳の翔太は駅で人身事故の現場に遭遇する。 この時を境に周囲の人間と微妙なズレを感じるようになる。 やがて翔太は自分以外の人間は心を持っていないことに気がつく。心がなくても人に優しくすることは出来る。要するに言葉と振る舞いでコミュニケーションが取れれば良いという考え方で廻っている世界なのだ。 異次元に紛れ込んでしまったのか… 私は深く考えずに読み進んでいたが途中でとんでもない罠にハマったことに気付いた。心がない=感情がないということは憎しみや怒りもない世界なのだ。 ◆とにかく途中から興味のポイントが変わって読み方も慎重になった。 心がないとは、どんな状態なのか。 脳の思考中枢が笑えと命令するから笑う。泣けと命令するから泣く。出力は出来きるのでコミュニケーションは成立する。役者の演技と同じということなのか。 善人であるか悪人であるかに心の有無は関係しないのか。世の中の出来事はすべて幻想なのか。もともと他人の心の中を正確に知ることはできない。理解していると考えることも妄想に過ぎないのだ。 色々考えながら読み進んだ。 難しくややこしい問題が絡んでくるが脳とは心とは自分とは一体何か。11歳の少年を通して根本的な問題に迫っていく。 本当に文三さんの作品は独特の世界観である。 伊坂幸太郎さんは「派手さはないし大きな動きはないけれど、僕の好みにぴったりの小説だと興奮した」と解説に記している。まったく不思議な世界である。
0投稿日: 2017.01.22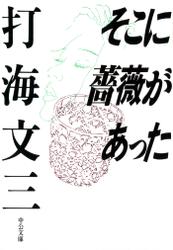
そこに薔薇があった
打海文三
中公文庫
何を書いてもネタバレになりそう。
ロマンス、猟奇殺人、ホラー、ミステリー、様々な要素を含んだ短編7編。読み始めはハッピーエンドも連想するラブストーリー。でも文三さんだからそんなはずないよね、という期待にしっかり応えてくれる。短編同士の不思議な接点と結末の面白さが暗く重い雰囲気を上手にカバーしているので読後感は悪くない。何を書いてもネタバレになりそう。どんなレビューを書いてみてもこの雰囲気は表現できない。敢えていうならば、伊坂幸太郎さんの「死神の精度」を読んでからこの作品を読むと両作品の構成の素晴らしさが良くわかるということだろうか。
0投稿日: 2017.01.22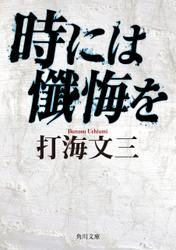
時には懺悔を
打海文三
角川文庫
凄い小説を読んだ!というのが正直な感想である。
凄い小説を読んだ!というのが正直な感想である。ベテラン探偵佐竹と見習い探偵聡子は殺された同業者の第一発見者となってしまう。なんとしても犯人を捜し出したい。動き出した2人はすぐに容疑者の男を探り出し盗聴を開始する。ところがその盗聴から伝わって来たのは重度障害児と父の感動すら覚える生活だった。父親が逮捕されたらこの子はどうなってしまうのか。さらに調査は進み未解決の誘拐事件が関わってくる。誘拐された子供も重度障害児であった。子供の解放を望んでいないような両親の態度、数時間後の通報。狂言説が飛び出すが証拠はない。 人はそれぞれに違う形、違う重さの荷物を背負って生きているのだ。他人の背負った荷物の重さを体感することは大変に難しい。善悪を決めることなどは人間の領域から逸脱しているとさえ感じてしまう。それでいながら自分だったらどうするだろうかと自問自答を繰り返さずにはいられない。重い課題が重なっていくが、この小説の凄さは何故か読んでいる途中も読後も清々しいことだ。探偵師弟コンビの出会いシーンから皮肉合戦であり微妙なギクシャク感が良い効果となっている。探偵稼業のモラルを皮肉り自ら落ちこぼれという佐竹だが心を打つ深さがある。
0投稿日: 2017.01.22
空を見上げる古い歌を口ずさむ
小路幸也
講談社文庫
不思議な満足感
「みんなの顔がのっぺらぼうに見える」と言う息子を救うため凌一は兄に救いを求める。兄も20年前「のっぺらぼう」を見てしまう少年だった。20年ぶりに再会した兄が自分の少年時代を語るシーンが8割という構成で非常に読みやすい。ところがサクサク読んでいると突然ドカンと重い言葉にぶつかりページを戻って読み直す。ということを何度か繰り返した。不思議な雰囲気を持った作品でどことなく恩田陸さんの「常野物語」に似ている。 私達は良くも悪くも何か突出しているところのある人に出会うと波長が合うとか合わないとか表現することがある。 感受性の強さ故に周囲に影響を与えてしまうこともある。「みんなの顔がのっぺらぼうに見える」というのも言わんとするところは良くわかる。ジャンルとしてはファンタジーということなのだろう。北海道旭川市出身で江別市在住の作家さんということで興味を持った。「東京バンドワゴン」という別の人気シリーズがあるそうだがデビュー作のこの作品だけ作風が違っているとのこと。天邪鬼な私はそれならこれから読みましょうと思った次第。読み終わってみるとなんと表現していいのか分からない不思議な満足感である。
0投稿日: 2017.01.22
shohjiさんのレビュー
いいね!された数34
