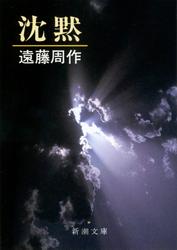
沈黙
遠藤周作
新潮社
「信」とは何か
遠藤周作さんの棺には遺言により『沈黙』と『深い河』の2冊を入れたといわれている。この2冊に共通しているテーマは「信」とは何かということ。 そもそも信じるには勇気が必要だ。確固たる証拠があるならそれは「信」ではなく「理解」である。司祭がキチジローに対し苦しんだのはこの「信」が揺らいだからである。 「信仰」とは人間の叡智を超えた存在を仰ぎみるというイメージがある。それは生きるためのものであり信が信仰を生み、信仰が信をさらに強くさせていく。だが不思議なことに時として最も賢明な行いは何もしないことである。 踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏んだとて心底の信仰がどうなるものでもない。 また、弱きものキチジローが居なければこの小説は成り立たない。強いものより苦しまなかったと誰が断言できよう。神は人それぞれの心に中にいるもの、ということか。 日本人は神仏をも日本文化に取り込み独自のものにしてきた。仏教も原始仏教とは違う「信心」を生み出している。 目的地が同じならどの道をたどろうとかまわない。というマハトマ・ガンジーの言葉を思い出した。
2投稿日: 2017.01.25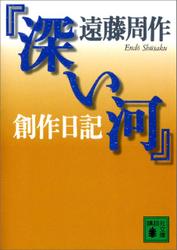
『深い河』創作日記
遠藤周作
講談社文庫
【とに角一枚でもよい。書き出せば始まるのだ】
日記の最初は中々書き出せない苦しみが続いていて辛くなった。しかし書き出してからは拘り書き直すの繰り返し。こんなにも作家さんとは一つのシーンを書き直すものなのかと驚く。10年程前に「深い河」を読んだ時にはサラリと読んでしまった場面、もう一度「深い河」も読み直さなければならない。平成4年夏【暑さ甚し 砂漠を歩く如く、小説を歩く。目的地まであとどのくらいか、ほとんどわからない】平成8年に亡くなられていることを考えると本当に最後の力をふりしぼった力作だったのだと感じる
0投稿日: 2017.01.25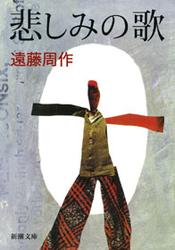
悲しみの歌(新潮文庫)
遠藤周作
新潮文庫
現代にも同じような虚無感が・・・
「海と毒薬」に引き続き読んでみた。日々の暗さ、希望のない生活、疲労、もうどうにでもなれという虚無感。単なる利己主義での追従と違うからこそ悔いも大きかったのだろうか。そもそも生体解剖事件の関係者すべてが無反省な人間だったならこの事件は闇に葬られたはずだ。過去の出来事から学んで来たはずなのに、豊かで平和である現代にも同じような虚無感があるように思う。後半で先輩記者の野口が語っている内容が深い・・・どんな正しい考えも限界を超えると悪になる。一人の人間が半生苦しんだことを半時間そこそこで話せるはずはない・・・
0投稿日: 2017.01.25
海と毒薬(新潮文庫)
遠藤周作
新潮文庫
追従してしまう弱さ・・・
「夜と霧」を読んだ時に戦争が人を狂わせてしまう怖さと同時に間違っていると感じながら権力者に追従してしまう弱さを色々考えてまたこの本に辿りついた。研究生の戸田の子供時代から良心の呵責を余り感じない人間だったことの告白が実際の手術シーンよりも強く印象に残った。他人からの罰を恐れることと良心の呵責とは違う。その違いが勝呂と戸田という2人の研究生のやり取りで上手く書かれている。
0投稿日: 2017.01.25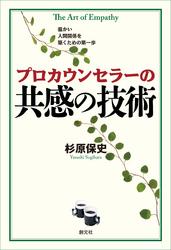
プロカウンセラーの共感の技術
杉原保史
創元社
人は人との関わりで傷つき、人との関わりで癒される・・・
リストラされた社員はリストラの現実よりも「その時の言われ方」にショックを受ける事が多い。無理矢理に共感を押し殺し厳しい内容を伝えている上司もリストラされなかった社員も皆が傷ついている。自分の淋しさや弱さ、人間としての限界をしっかり受け容れている人は共感する能力が高い。カウンセリングの現場での話しばかりでなく実際の身近な話題も多くわかり易い内容。共感を伴わないコミュニケーションは怖いと思った。まさに、人は人との関わりで傷つき、人との関わりで癒されるのです。 ===再読===前回、42の項目を一気に読んだことで矛盾を感じる点もあったので読み直した。しかし【人間の矛盾】についてもきちんと本書は解説していた。そもそも人間の欲求や願望には二面性がある。そして時間の経過と共に変化する。白黒つけようとしないで受容すれば良いのだ。多くの人は共感されたいのと同時に絶対共感されたくないと思っている。簡単に分かるわなどと言ってもらいたくないのだ。分からないという気持ちをありのままに感じて逃げ腰にならずに関り互いに影響しあうプロセスが共感なのだ。白黒つけようとして読んで矛盾したのであった。
0投稿日: 2017.01.25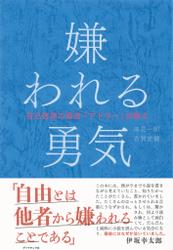
嫌われる勇気
岸見一郎,古賀史健
ダイヤモンド社
大切なものを見失わないようにしたい
もしも、人生が山頂にたどり着くための登山だとしたら人生の大半は「途上」となってしまう。大切なのは結果にこだわるだけではなく、その時その時の瞬間を生きること。バブル、勝ち組、負け組、などの言葉に踊らされヘリコプターで山頂を目指すような人生を夢見るのでは自己受容も他者貢献も有り得ないのだと思った。誰一人協力的でない状況でも誰かが始めなければならない。嫌われる勇気とは、その一歩を踏み出す勇気でもあるのかな。これからは自分を嫌っている人間に焦点をあてすぎて大切なものを見失わないようにしたい。
0投稿日: 2017.01.25
それでも人生にイエスと言う
ヴィクトール・エミール・フランクル(著),山田邦男(翻訳),松田美佳(翻訳)
春秋社
「夜と霧」のフランクル先生の講演記録と解説。
戦争の悲惨さを訴える内容ではなく「人は必ず死ぬと分かっているのに何故生きなければならないのか」を追求する内容。生きることはある意味で義務であり自分の活動範囲内で最善をつくすことで結果として喜びが湧いてくる。仕事をすること、愛すること、悩むこと、戦いに勝つことではなく戦いを放棄しないこと。人生が出す問いにその都度答えていくことで、しあわせへの扉は自然に外に向かって開くのである。難しいけれど取り敢えず今やっていることに真面目に取り組んでみよう。
0投稿日: 2017.01.25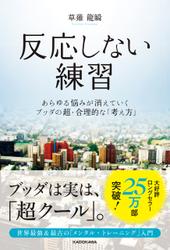
反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」
草薙龍瞬
KADOKAWA
優越感と劣等感、自信も全てが妄想。
スマナサーラ長老の本も何冊か読んでいるけれど、この本のほうが職場や学校、家庭内の問題に適応した内容で読みやすい。勝ち負け、優越感と劣等感、自信も全てが妄想。承認欲が満たされない悩み。しかし、全ての人が出家した僧侶のような生活が出来るわけがなく競争社会で生きているのです。では、そんな社会で本物の自信をつけるには?自信なんて考えなくて良いのです。先のことは分からない。それより今しておかなければいけないことがある。まず、やるべきことをやる。「自信家」も「自信がない人」も自分に都合の良い妄想にとらわれている…
0投稿日: 2017.01.25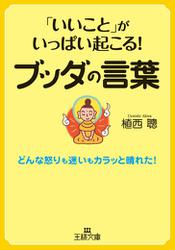
「いいこと」がいっぱい起こる!ブッダの言葉
植西聰
王様文庫
お釈迦様の「真理の言葉」の解説本です。
様々な宗派に分派した日本の仏教はそれぞれの開祖が残した書物がお経と共に重要視され小さな違いを強調しています。それはそれで日本の文化に根ざした素晴らしいものなのですが、原始仏教は驚くほど実用的で簡潔でそれでいながら全ての哲学に通じるような奥深さがあります。難しい言葉を使わずに日常の出来事を想定して書かれていますので、わかりやすく読みやすい。「よい行い」の見返りは少し遅れてやってきます。気長に気楽に努力するための応援メッセージがあふれています。
0投稿日: 2017.01.25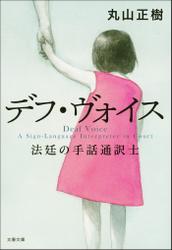
デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士
丸山正樹
文春文庫
涙、涙のラスト、久々の感動!!!
生活のため手話通訳士になったコーダ(聴こえない両親から生まれた聴こえる子ども)の荒井は、刑事事件に問われたデフ(ろう者)の法廷通訳を引き受けることに。 不自由なことがあれば、快適に過ごせるように工夫して、助け合えば良いはずである。これが上手く行かないのは無理解や偏見が原因であることが多い。ろう者の世界のみならず組織の中でも同じこと。警察内部の問題と絡めていく構成は上手い。ミステリー形式でこういう問題を扱って行くことで多くの人に知ってもらう。知ってもらうこと自体大きな意味があるのだと感じた。
0投稿日: 2017.01.24
shohjiさんのレビュー
いいね!された数34
