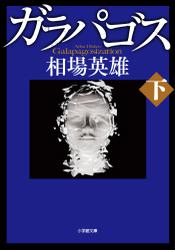
ガラパゴス 下
相場英雄
小学館文庫
ワンパターンな文章表現が目立つ
この作家さん、やたらと「耳に谺した」という表現が頻出する。 発せられた言葉が「耳に突き刺さった」とか「耳の奥で響いた」とか、もううんざりするほど。 編集段階で、ワンパターンになっていると指摘されなかったのだろうか。 『もしドラ』が高校野球の女子マネージャーがマネジメントを学ぶ話であるならば、こちらは刑事がいまの日本経済を学ぶ話であるわけで、ストーリーのドラマ部分は添え物といった感じ。 「なるほど知りませんでした、これまでの思い込みが覆りました」と無知を思い知り、「いまの日本、このままでいいのか?」と問いかける。
0投稿日: 2024.10.24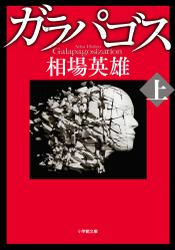
ガラパゴス 上
相場英雄
小学館文庫
「いままで甘えんなよって思ってました」
帯にも現代版「蟹工船」とあるし、捜査を通じて刑事が、若者の過酷な労働環境の実態を思い知るという展開なんだろうなとわかっていたが、そのまんまだった。 というか、そのまんま過ぎたと言うべきか。 元経済記者である著者が、各地を取材し集めたネタを、警察小説の体裁でフィクション仕立てにしてみたという感じに近い。 社会派ミステリというジャンルもあるのだが、代表的な作品で取り上げられる社会問題はあくまで事件の背景として描かれるのであって、本筋の事件捜査にリアリティが失われると一気に味気なくなってしまう。 例えば派遣社員の工藤が刑事の田川に「搾取され、部品のようにこき使われ、人間らしい生活の送れない世界」からやっと抜け出せますと述べる場面。 祝賀会の居酒屋の宴席は、工藤が田川に自身の給与明細を見せて悪どい派遣会社の手口を聞いてもらう学習会に変わるのだが、こういうのは読者を一気に白けさせる。 著者インタビューを読むと、この小説を書くため各地でいろいろと取材を進めたみたいだが、事件の背景に巧みに落とし込んでいるというより、わかったことをそのまま書いちゃったようだ。 刑事のお勉強パートが多すぎ、その都度メモしてる感じ。 ただ小説の導入はとても良かった。 半ばコールドケースと化そうとしていた身元不明者の再捜査で、現場の再鑑定や聞き込みに時間をとられ、昼飯を喰いそびれた刑事2人が、なじみのない土地では地元の腹を空かせた高校生の後をつければメシにありつけると裏路地に入ったところで、目にした看板の文字に惹かれて沖縄料理店に入り、そこで生前のガイシャの写真を目にするという展開はとても自然だし巧かった。 店主があまりにも歌声が素晴らしいからとたまたま撮影した仲野の動画。 そこで彼は『涙そうそう』のウチナーグチバージョンを歌っている。 名もない身元行方不明者が、読者の心にも一気に血肉化された瞬間だっただけに、ここからの転調があまりにも精彩を欠いていて残念だ。 「こんなこととは本官知りませんでした。いままでは甘えんなよって見下してました。驚きです」っていう感じでなんとも興が醒める。 それとNHKでドラマ化されたようだが、大柄でいかにも捜査一課という感じの木幡を女性が演じていて、イメージが違いすぎるだろ、と。 ちなみに、人材派遣会社の名前が単行本では「パーソネル」になっているのに、文庫本では「パーソネルズ」に変えられているのは、なぜなんだろうね。
0投稿日: 2024.10.19
やくざ映画入門(小学館新書)
春日太一
小学館新書
代表作でありながら終止符を打つ作品
1970年市ヶ谷で起きた三島由紀夫の割腹自殺の報に接した時、脚本家の笠原和夫は、衝撃とともにある種の安堵に包まれた。 手がけた任侠映画『総長賭博』に対する三島の熱烈な激賞以来、呪縛に苦しめられていたからだ。 大作家の目を意識するあまり、作品がどんどん観念的な内容に傾き、観客にそっぽを向かれ追いつめられていた。 そんな中での三島の突如の死は、笠原に解放感をもたらす。 深作と組んだ『仁義なき戦い』シリーズが始まるのが1973年。 古典的な様式美は跡形もなく、迸る情念と躍動する無秩序。 三島が生きていたらどう評しただろう。 笠原と深作は『仁義なき戦い』を通じて息の合ったコンビと思われるかもしれないが、実態は違う。 笠原は自身の脚本どおり丁寧にドラマを描き出したいのに、深作の激しいカメラワークで台無しにされたと怒り、深作は深作で笠原のいまだ軍国少年の情念を引きずった脚本に対し、若い観客は求めていないと突っぱねる。 その対立が際立っているのが『広島死闘篇』で、北大路扮する山中に仮託する笠原と、千葉扮する大友に仮託する深作という2人の戦後が作品内でぶつかりあう。 しかしラストの山中の自殺する場面をより悲劇的に描いたのは、深作の方だった。 やくざ映画というのは、任侠映画路線の流れを汲む、一つの型や様式をもったファンタジーであるはずなのに、いまやくざ映画の代表作として主に語られるのは根本となる特長をなす様式やファンタジーを悉く打ち破った『仁義なき戦い』だという皮肉。 その『仁義なき戦い』も、血みどろの抗争に明け暮れたやくざたちの最後にして最大の敵が「市民社会」であったという皮肉。 「秩序の破壊者である暴力団」を辛抱強く追いつめる「健全な秩序を求める市民たち」という構図を見せられた観客は、仮想と現実の境界線の薄さに気づき、それ以来このジャンルは退潮の一途と辿ることになる。 代表作でありながら終止符を打つ作品。 これもまた皮肉だ。
0投稿日: 2024.10.16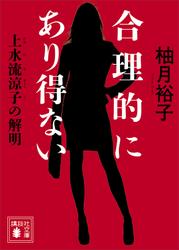
合理的にあり得ない 上水流涼子の解明
柚月裕子
講談社文庫
色々調べて売れそうな本書きました
アダム・ファウアーの『数学的にありえない』『心理学的にありえない』の題名に似せているが、恐ろしく低レベルな出来で"あり得ない"。 ヤクザや警察とのコネクションやトリックなど至る所にご都合主義や無理筋が頻出し論評にも値しない。 小説のキャラ設定の段階からスキルの割り振りを間違えたのかと思うほど、事件の活躍の手柄は主人公の女性探偵より、男性助手の貢献に負うところが大きい。 出来過ぎ君の男性助手にお茶汲みまでさせて、女性探偵が何をするかというと色仕掛けで罠にかけるというくだらなさ。 今年読んだ中のぶっちぎりのワースト。
0投稿日: 2024.10.15
運動の神話 下
ダニエル・E・リーバーマン,中里京子
早川書房
「若さの泉」には汗が流れている
二足歩行の起源を辿っていくと、チンパンジーの高コストな歩行にぶち当たる。 ナックル歩行のみじめな非効率性は、森の奥深くで生活する分には問題にならない。 だが、急激な気候変動で熱帯雨林が縮小し、飛び地の疎開林に分断されていくと、同じ量の食糧を得るため遠くまで遠征する必要に迫られることに。 木に登るメリットを損なわず、いかにして効率よく歩行するか。 その解決策が二足歩行だったというわけだ。 つまり、エネルギー的にコスパの悪いチンパンジーのナックル歩行が、あまりにもカロリーを大量に燃やす不経済な歩き方だったがゆえに、その代わりとしてよりエネルギー節約的な直立歩行が選ばれたということだ。 ウォーキングで減量できない理由として、ある仮説が立てられている。 それは人々の一日あたりの総エネルギー予算は決まっているため、努力して追加で余分に何時間もウォーキングしたとしても、体はそれを埋め合わせるように、安静時の代謝に使われるエネルギーを減らしてしまうため、結果として一日あたりの総カロリー消費量は変わらず、体重も減らないというもの。 身体活動が勝手に代謝を変化させて減量の努力を相殺してしまうといった説明は、まだ仮説の段階で未確定らしいが、とても腑に落ちる説明だった。 なぜウォーキングが必須の運動にならなかったのか? これほどコストのかからず、それでいて有益なものはないのに、なぜ人はほんの少しでも歩くのを嫌がるのだろう? 自然選択の結果なら、もっとウォーキング好きの人たちで溢れていないとおかしいではないか? その理由は、最近まで歩くことは運動ではなかったこと、さらには人はできるだけ歩かないように進化してきたため。 私たちの祖先は改めて一万歩のウォーキングをする必要はなかった。 なぜならそうする以上に日常生活でエネルギーを消費していたからだ。 限りあるエネルギー資源は生命維持と繁殖に回された。 今日では、有り余るエネルギー資源の使い道が見つからず、無理をして代替活動を探さねばならなくなった。 走行時に頭部を安定させる項靭帯の痕跡は、豚のような走らない動物だけでなく、ゴリラやチンパンジーや初期のヒト族にもなかった。 しかし人類の祖先であるホモ・エレクトスは、暑さの中でも長距離の狩りをするために、数百万年前に解剖学的構造を進化させた。 我々は「走るために生まれてきた」のだ。 「たとえ走るのが嫌いだとしても、あなたの体には、頭のてっぺんから足のつま先まで、長距離を効率的かつ効果的に走るための機能が備わっているのだ」 人間の脚にはアキレス腱のような長くて弾性のある腱が備わっているため、持久走に秀でている。 さらに他の動物の発汗よりも優れた身体の冷却システムを持っている。 体毛が薄くなり、体全体を巨大な濡れた舌に変えることで、大量の汗として蓄積した熱を素早く放出できるようになった。 また、馬は二足歩行の人間にはできないギャロップという高速走行が可能だが、短距離しか持続できない。 対して人間は、長距離を比較的速いスピードで走れるため、一般的な人間が馬を追い越すことも可能なのだ。 なんでそんな自然適応が働いたか? それはとりもなおさず肉が喰いたかったから。 弓や矢も発明されず、手元にめぼしい武器もないまま、獲物に近づくの自殺行為だ。 蹴られたり突かれたりすれば食事どころではなくなる。 それでもどうしても肉を手に入れたい。 ということで編み出されたのが、持久狩猟の戦法。 延々と追走してただ疲れさせるのではなく、獲物の体温を上げて、文字どおりオーバーヒートさせ立ち上がれなくさせるのだ。 それができければ危うく我々はベジタリアンになっているところだった。 「若さの泉」には汗が流れている。 さらに、その汗は年齢を重ねても流し続ける必要がある。 格言の通り「人は年を取るから遊ばなくなるのではない。人は遊ばなくなるから年を取るのだ」。 人間は運動するように進化してきたのではなく、必要に応じて体を動かすように進化してきた。 それでは、なぜそれほどまでに運動は有益なのだろうか。 運動が、徐々に進行する健康状態の悪化を遅らせたり、ときにはそれを押し戻したりする理由は何か? 結論としては身体活動が、老化を促進する悪材料を防いだり改善したりするから。 じゃあなぜ身体活動は、加齢に伴って蓄積される損傷の一部を修復する何十ものプロセスを活性化できるのか? それは運動が持つ回復力の素晴らしさにある。 運動はそれによって被ったダメージを修復するばかりか、運動していなかったときに蓄積されたダメージも修復してくれる。
0投稿日: 2024.10.12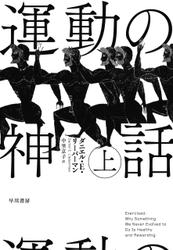
運動の神話 上
ダニエル・E・リーバーマン,中里京子
早川書房
ピッチャーができるのは人間だけ
「私たちは運動をしたがって当然だ」というのは思い込みであり、神話にすぎない。 我々の祖先を振り返っても、健康のために何キロも走ったり歩いたりするような者はいなかった。 私たちは運動するように進化してきたわけでもなければ、何だったら怠けるために生まれてきたのではと思えるほどの十分な証拠がある。 しかし今では、十分に運動しない人は怠け者とのレッテルが貼られてしまう。 だからといって著者は、運動にまつわるものは全て神話なんだから、体を動かす必要なんてないと言ってるわけではない。 運動は確かに健康を増進する。 著者が指摘しているのは、逆説的なのだが、運動というのは現代的なものでありながら健康的な行為であると言いたいのである。 昔の狩猟採集民たちはよく体を動かしていたが、現代人は十分運動していないという思い込みも人類学的視点に立てば、一日の身体運動を比較するとほとんど変わらないことがわかる。 また自然選択の観点に立てば、繁殖の成功を最大化するには必要のない身体活動にエネルギーを振り向けることは無駄以外の何ものでもなく、何だったら人間は極力体を動かさないように進化してきたとも言えるのだ。 古代の本能から言えば、不必要なエネルギーの浪費を避けるため体を極力動かさずいることは完全に理にかなった振る舞いである。 だがこれが、奇妙にも反転したのは現代になってからであり、健康のために自発的に体を動かすエクササイズが特権階級の特権となったのもここ最近のことなのだ。 それでも狩猟採集民は、現代のオフィスワーカーに比べれば活発だ。 面白いのは、現代人と同じくらい不活発なのは、我々のはるかな祖先である類人猿であるという事実。 それは大部分の哺乳類と比べても、これほど座りがちなのは例外的だと言えるほどなのだ。 なぜなら彼らは、森の中の移動に費やすエネルギーをできるだけ少なくして、可能な限り多くのエネルギーを、繁殖に充てられるように仕向けたためで、その意味で類人猿はカウチポテトになるように適応してきたのだ。 人間がこのカウチポテト族の類人猿から進化したにもかかわらず、それではなぜ狩猟採集民はあれほど活発なのか? 毎日8キロから16キロも歩き、食料や乳幼児を運び、何時間も掘り続け、ときには走るまでに進化した要因は、爆発的な繁殖の成功により、より大きなカロリーの消費とエネルギー生成といった正のスパイラルが働いたため。 それに応じてより脳は大きくなり、社会ネットワークも広がって、ますます繁殖成功度にプラスに働いた。 それでも長時間動かず座り続ける状態は異常。 これにほとんど運動しない状態が組み合わさるなに、さらに問題だ。 私たちの祖先は、腰を下ろす際にも、どっしりと座るより、しゃがんだり、膝をつくなど多様な座り方をしていた。 和式便所が駆逐され、しゃがむことができなかったり、蹲踞の姿勢を維持できない子供が増えていると聞くと、太ももやふくらはぎの筋肉は衰えていく一方に違いない。 人間はその祖先よりますます身体的に弱くなっているが、それは退化したためではなく進化したためだと著者は指摘する。 協調行動が増え平和になり戦わなくてもよいためか? 違う。 スポーツや武器など異なる形で戦うように進化してきたからだ。 まず人類史に起きた自己家畜化について。 この現象は二段階のプロセスで進行し、まず狩猟採集の開始に伴う協力関係の強化という選択圧によって、そしてホモ・サピエンスにおいて女性が攻撃性の少ない男性を選択したことによって生じた。 狩猟採集社会において、男女間の協力関係が増加すれば、女性の役割が増していく。 それに伴い、体格における性的二形性が減少していき、攻撃性が失われていく。 攻撃性は二種類あり、反応的攻撃性と能動的攻撃性がある。 我々は「反応的攻撃性が高く、能動的攻撃性が低い、強くて危険なサルのような動物から、反応的攻撃性が低く、能動的攻撃性が高い、弱くて協力的で遊び好きな人間」へと進化していった。 その裏にあったのは、人類が直立し二足歩行への移行が契機としてあった。 700万年前の運命の分岐点を境に、われわれは四本脚を手放したがために、ずっとのろまな動物として過ごす羽目に。 しかしそのトレードオフとして、直立して武器を使って戦うことができるようになった。 腕を盾として使ったり、棒を振り回すだけではない。 我々は肩を投石機のように使える初めての動物だ。 すなわち人間は、物を力を込めて正確に投げることに適応したのだ。 投擲武器の進化は、体が大きくて反応的攻撃性を持つことの優位性を減らし、自己家畜化を加速させた。
0投稿日: 2024.10.07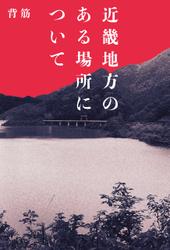
近畿地方のある場所について
背筋
KADOKAWA
怪異の語り方は面白いが...
ふつうはどんな怪異が起こっているのかが語られたら、その次は怪異の正体は何かに焦点が移るのだと思う。 あるいは、本書のタイトルのように、近畿地方の伏せ字にしてある地名やダムは具体的にどこなのかといったことに。 そんでもって最終的には何らかの解決を見て、主要因の呪いや祟りは一時的にも収まるのかを期待して読むのではないか。 そんな単純なことを頭に思い描きながら読んでいたので、ずいぶんと凝った体裁になっているとは後半に至るまで気づかなかった。 小沢君の「僕、ここまで来たら一度●●●●●に行ってみようと思います」というやり取りが数ページおきに何度も繰り返されるあたりから、「なんだこれ」と。 あらためて考察系のサイトを一通り見てみたが、わかったようなわからないような。 ただ、何かメタ小説を目指しているのかという印象はある。 アンソニー・ホロヴィッツの推理小説ホーソンシリーズは、著者自身が語り手となって物語にワトソン役として登場する。 本書でも背筋という作者が物語中に現れるわけではないが、この近畿地方に伝わる不可思議な怪異を広めるため、こうした体裁のものを発表したという感じになっているのではないか。 ただ、ちょっと詰め込み過ぎの感も否めない。 もともと発表されたのが小説という媒体ではなかったためか、無理矢理に整えられた印象も受ける。 様々な怪異を、よくあるインタビュー形式のものだけでなく、「学校のこわい話」や同人誌の短編小説、はてはネット収集情報として、パッチワークのようにちりばめて語っていくという手法は新鮮ではあった。 が、途中からそれも慣れてきて眠気を覚え始める。 怪異現象も複数あれば、正体も複数あるのだが、どれも弱いというか、実際の起きている現象に見合っていないというか、もう少し怨念の深さの方もそれなりに調整しなければ、納得感を得にくいのではないだろうか。 それにしても令和の時代になろうとも、怪異現象や正体がいまだ昔のままなのも、目新しさを感じなかった。 そりゃ古来から山は、日本人にとって神聖なところですけどね。
1投稿日: 2024.10.03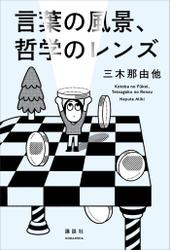
言葉の風景、哲学のレンズ
三木那由他
講談社
トランスジェンダー的言語哲学エッセイ
自身がトランスジェンダーであるからこそ、日常の何気ない会話で生じる違和感から、対話の本質がどこにあるかについて、常に考え続けているのだろう。 本書は言語哲学者の気取らないエッセイだが、著者のパーソナリティを色濃く反映したものになっている。 対話とは、単なる情報の伝達を通じた相互了解ではなく、ある種の約束事の構築と、それに伴うお互いの行動の擦り合わせや調整であると規定する。 言いかえれば、安易に理解しあうことよりも、お互いの立場を尊重し合うことを優先するということ。 トランスジェンダーである自分が婦人科に診察に行くことに対して、医師にセクハラしに行くに違いないと曲解する人たちとどう折り合えるか? 言葉を尽くして理解してもらえるとは到底思えない人たちに対して。 それより理解されなくて全然構わないから、この社会に身の置き場を作れるように、向き合い方を変えてもらえないか。 これはトランスジェンダーの人に対してはこのように振る舞うべしという知識の獲得ではなく、よくわからないけど一緒にやれるように配慮するよといった、某かの行動の変容を期待したもの。 それがコミュニケーションの本質ではないか。 しかしこの対話も実は、当事者同士だけによって形作られるのではなく、その対話を見ている周りの第三者によっても作られるというのが、「からかいのサークル」に属する第三者の証言の問題。 勝手に体を触ってくる人に対して「やめて」と言っているのに、「またまたあ」と冗談としか受け取らず、それを見ている周りの人たちも二人が戯れ合っているとか、あるいは「冗談を理解しない無粋な奴だ」というレッテルを貼ったりする。 両者間で約束事がなかなか構築されず、ズレまくってしまうのは、必ずしも当事者間の意思疎通の問題だけでなく、こうしたサークル内での暴力的な意味のねじ曲げが起きているから。 いじめの現場においてもたびたび見られる構図だが、必ずしも第三者の能天気な無理解ばかりではなく、上下関係といった社会的文脈を反映していることもあるのだろう。 「議論が尽くされていない」の前提にあるものも面白かった。 そもそも結婚の平等を求める議論が始まらないからこそ起こされた訴訟のはずなのに、判決で「議論が尽くされていない」と門前払いされた時には、なんで議論がなされていることが前提になっているのよと突っ込みたくなる。 さらに門外漢からすれば、「尽くされていない」とされることで、「議論はなされていたんだな」「それが熟す前に判決を求めるなんてずいぶん拙速だな」といった印象を抱きかねない。 意図してか知らずかわからないが、ずいぶん高等なテクニックだなと感心してしまった。 もう一つ「どういたしまして!」の正体は本書のなかで最も面白かったトピック。 ただこれは、「きれいにご利用いただきありがとうございます」というあのトイレの貼り紙のように、ある種の行動を期待し促すものという解釈には首肯しかねるが。 よくシットコムで、連れ合いを先に通すため、扉を開いたまま脇に立つ人が、会釈もなくさも当然といった顔つきで店内に入って行く様子を見て、「どういたしまて」と皮肉を込めて一人ごちるシーンが出てくる。 これなど感謝が適切なものになるよう期待しているわけではないと思うのだが、どうのなのだろう。 肝心のマーベル映画を見ていないのでよくわからないが、面白いなと思ったのはこんな遠回しの当てこすりめいたことまで、言語哲学で大真面目に取り上げられていること。 それとこの行為は、必ずしも発話相手を対象にしたものではなく、それを傍観している第三者に向けた、文脈調整の意味合いがあることの方が本筋ではないだろうか。 そう読みながら強く感じた。
0投稿日: 2024.10.02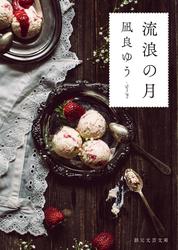
流浪の月
凪良ゆう
創元文芸文庫
持たずにいれば捨てずにすむ
「たっぷり豊か」 ひさしぶりの熟睡から目覚めた心地の表現として素敵な語感だなと感心した。 「文が淹れたコーヒーを静かに舌にのせた」というのも不思議な一文。 飲む表現として普通は「舌にのせる」なんて選ばない。 だけど読み進めていくと何かを秤に載せ、それぞれにその重みに耐えている登場人物が多い。 更紗は、周囲の人たちの善意や思いやりに押しつぶされ窒息寸前だ。 『過去のトラウマに苦しめられる犯罪被害者』という投影されたイメージは優しく温かいはずなのにどこか寒々しい。 思いが伝わらず一方的なレッテル貼りに困惑している。 体は外側から凍えるものだが、心は内側から凍えるものだ。 更紗の母親はその中では例外で、「重いことはそれだけで有罪ね」とあらゆる責務を遠ざけ、我が子も手放している。 いつも身軽に手をぶらぶらさせるためには、できるだけ持ち物は少ないに限る。 母親のように自分も、周りからの善意や、いつかわかってもらえるという希望を手放すことで楽になりたいと念じている。 文は文で、こちらも母親からの期待や理想の重みに苦しんでいる。 しかし更紗も文も、自分を苦しめるものから正面から対峙することを避け、一種の自己欺瞞と自己矛盾に陥っていく。 大人の女性を愛さないのは、愛せないからではなく、小さな子が好きだから。 いつのまにかレールを外れてしまったのでなく、自分から外れてやったのだ。 あるいは、とうに周りからはいつも作り笑いをしていることがバレているのに、心のなかでは「誰にもわかってもらえない」「私の言葉は誰の耳にも届かない」と諦念してみせているところ。 「事実と真実は違うのだ」という言葉が何度も繰り返し出てくる。 「トラウマのせいで犯人である小児性愛者を愛し、幸せを願う、おかしな、かわいそうな女性」というレッテルも大概だが、一方で不満を募らせるだけで子供のままでいつまでも自分の殻に閉じこもっている。相手に好かれたいと願っていながら別に構わないと嘯く。 「持たずにいれば捨てずにすむじゃない?」は名言だろうか。 うーん、やっぱりわからない。
0投稿日: 2024.09.29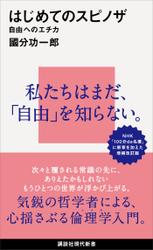
はじめてのスピノザ 自由へのエチカ
國分功一郎
講談社現代新書
これ読んで「スピノザ面白い」と思うだろうか?
いま脳科学研究においてスピノザの哲学があらためて見直され始めている。 そのことは本書でも指摘されている。 だけど、はじめて彼の思想に触れる入門書としてこれはどうなんだろうか。 一言で本当につまらない。 「組み合わせとしての善悪」とか「力の表現としての能動」といったキータームで概念を解説するだけのありがちなテキストになっている。 これだったらペパンの『フランスの高校生が学んでいる10人の哲学者』の方が数倍いい。 スピノザを幻想批判者として、何より受動を能動に変える、喜びの最上級を目指した哲学者だと簡潔に紹介している。
0投稿日: 2024.09.27
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
