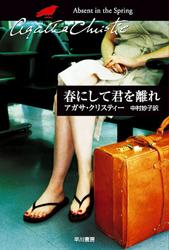
春にして君を離れ
アガサ・クリスティー,中村妙子
クリスティー文庫
戦間期のイギリスを体現する主人公
ここには確かに謎がある。 が、その謎は主人公であるジョーンの心のうちに突如沸き上がった疑念に端を発しており、異邦の地である中東で一人立ち往生しなければ生まれてこなかったものである。 さらに謎を謎たらしめているのは本人自身でもある。 周りの人には明白な事実を、認めることの恐怖から慎重に避け続けていた結果、見ないように蓋をしてきた真実。 息子のトニーが「ときどきお母さんって、誰のこともぜんぜんわかっちゃいないって気がするんだ」と語っている通り、あるいはかつての恩師が指摘した「物事に皮相的な判断を加える」きらいがあり、自分のことばかり考えたがるのを戒めよと指摘している通り、他人を都合良く自分勝手に解釈してしまう。 このようにジョーンという「信頼できない語り手」による一人称の回想小説として物語が進むため、ともすれば読者は「志村、うしろうしろ」とツッコミを入れつつ、なんなら本人よりも早く真相に辿り着いてしまう。 夫のロドニーは私が留守にして、ひどく淋しい思いをしているに違いない、いなくて喜んでる? 嘘よ、嘘に決まっている。 「もちろん、ロドニーはわたしの帰りを待ちかねているにきまっている!」 こんな調子だから、疑念の連鎖に陥っていく様は読んでいてハラハラさせられる。 実は自分は一人ぼっちなのではないか。 誰からも愛されていないのではないか。 夫や子供たちに尽くしてきたつもりが、実はひどく独りよがりの思い上がった一方通行で、彼らは実は深く傷つき、有り難迷惑に感じていたのではないか。 母親失格というだけではない。 心から愛していたからこそ、自分の振る舞いはより残酷さを際立てているのではあるまいか。 そこに少しでも無関心や嫌悪の情でもあれば、弁解の余地はあっただろうに。 多くの人は読み飛ばしているが、帰りの列車の友連れとなるサーシャは、物語の結末を見事に予知している。 ジョーンの天啓とも言うべき回心に至る経緯と帰国後にとる行動の決意を聞いた上で、サーシャはなんと言ったか? 「神の聖者たちにはそれができたのでしょうけれど(聖者でもないあなたには出来ますまい)」と。 クリスティほどの小説家が、最後のジョーンとロドニーの再会の場面の前にあえて、サーシャというコスモポリタンな貴族を登場させたのも理由があってのことだろう。 それがよりハッキリするのは、戦争が間近に迫っていると告げる場面。 ユダヤ人に向けられる敵意、ヒトラーが戦争を始めようとしていること、火の手は世界中に飛び火するであろうことを予言するサーシャ。 それに対してジョーンは、ヒトラーがそのような大それた野心を持つ人物とも思えず、いまにも戦争が起こるなんて寝耳に水だと答える。 本書の刊行は1944年、つまり終戦の前年に当たる。 とすればクリスティは、この物語に単なる一婦人の自己省察以上のものを込めているに違いない。 おそらくそれはジョーンという女性を、イギリスそのものと重ねあわせているのではないか。 サーシャがイギリスの特異な国民性を皮肉る場面が続くことも、その解釈を裏付けているように思える。 ドイツに対する宥和政策をとったイギリスの首相チェンバレンは最後までヒトラーに翻弄され続けたし、イギリスの上流階級になるほどヒトラーの政策に理解を示してひとかどの人物だと認めていたこと。 さらに先走ってしまえば、戦後のイギリスは次々と世界各国の植民地を手放して落ちぶれていく。 民主化や近代化に少なからぬ力を貸し、多少なりとも恩義を感じていると思っていたのに、次々と独立を宣言して袂を分かっていく植民地の人々。 「ご自分たちの長所については何か後ろめたげで間が悪そうな口ぶりをなさるのに — 短所は進んでお認めになるばかりか、むしろ自慢にしていらっしゃるようですのね」 サーシャの分析を読んでいると、ますますこの物語がロマンス小説以上の意味をもってくるように感じられる。 本書で最も面白い場面は、ジョーンとロドニーの再会の場面ではなく、ロドニーとエイブラルの対決の場面だろう。 妻のある年上の医師カーギルと駆け落ち同然で出奔の決意を固めるエイブラルを父親のロドニーがどう翻意させたか。 まるで法廷ドラマのような鬼気迫る弁舌の応酬。 父親の出方がわからないエイブラルは予測のたてやすい母親の同席を求めるが、そこでロドニーが漏らした一言 - 「なるほど、怖いんだな」。 ここから父の繰り出す論法が実に見事。 若さゆえの短慮や一時の恋慕と詰られるなら跳ね返せたろうが、義務の不履行という自身が最も信をおく暗黙の契約を持ち出されたため、手も足も出ない。 相手の弱みを的確に攻めるというのは一流の弁護士の所作。
0投稿日: 2024.11.25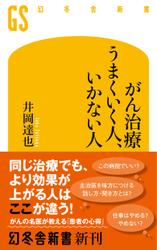
がん治療 うまくいく人、いかない人
井岡達也
幻冬舎新書
うまくいく・いかないの事例集
「うまくいかない人」とはつまり、医者の話を聞かない人。 主治医との信頼関係が築けないまま、長くてつらい闘病生活を続けることは、なんとも悲劇的だ。 複数の医療機関を受診するのもいいが、船頭多くではないが、責任の所在が曖昧になる危険性も。 何らかの効果がある治療は、必ずそれなりの副作用を伴うものであることを肝に銘じ、「副作用のない治療」などあり得ないと心得るべき。 がん治療においては、食べることがとりわけ重要。 抗がん剤治療は、常に赤血球や白血球を壊しながら続ける治療であるから、作り直すだけの栄養の供給は必須となる。 大事なのは食事量の維持であり、それで食べられるなら飲酒もOKだし、減塩も気にしなくていい。 がんにならないための食事とがんになってからの食事は、当たり前だが違ってくる。 吐き気や強い便秘で食事が喉を通らなくなることもある。 また、「がんが消える」などと民間の食事療法を信じて低栄養状態に陥った患者もいる。 独居の高齢患者が増えてきたため仕方がないのかもしれないが、治療に家族のサポートは欠かせない。 最初の告知の際には家族総出で面談に現れたのに、治療が始まるとだんだん付き添いが少なくなり、最後にはいなくなる患者も。 患者本人への愛情の問題ではなく、がんに対するある種の慣れや侮りが起因している。 しんどい抗がん剤治療で一番サポートのいるときに離れてしまうのは心細いし、医師も実はサポートする家族を当てにしている。 「不思議なもので、治療がうまくいっている患者さんに限って、もう付き添いなしで通院しても大丈夫と判断される段階になっても、家族が一緒に病院にやってくる例が多いように私は感じています」
0投稿日: 2024.11.22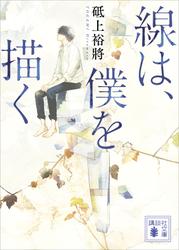
線は、僕を描く
砥上裕將
講談社文庫
線によって心が絵になる
たった一筆、サッと線を引いただけで、紙の上に蘭の葉がありありと立ち現れる。 透けて見えるほどの葉脈や、葉そのもの重みまで伝わってくる。 ただの一本の線が美しい絵となる様は、さぞや息をのむ瞬間だろう。 素人は筆の動かし方に目を奪われるが、穂先にどれほどの水分を含ませているかなんて想像にも及ぶまい。 そこに薄墨と濃墨がどのような割合で含まれているかなども。 線の太さや細さも、肘の上げ下ろしだけで繊細に調整されている。 主人公は過去の辛い体験からガラスに向かい思い出すということをずっとやっていた。 小さな狭いガラスの部屋で、記憶だけを眺めていた。 そのおかげで、師匠のたった一度の手本を何度も頭の中に再生できた。 腕や手の動き、その速度まで何度も執拗に繰り返し反復することで、水墨画初心者の腕前はいつしかプロも舌を巻くほど上達していく。 弟子の前で実演してみせる際、師匠はあらかじめ見るべきポイントなど伝えない。 あとから弟子が見るべき場所に注意を払い、練習でそれを再現できているかを黙って観察する。 「君はよく見ていた」という言葉は、最上の褒め言葉だろう。 主人公は重度の引き蘢りで拒食症気味。 少し話をするだけで疲れてしまうコミュ障の青年に、たまたま出会った水墨画の大家から目を掛けられ弟子としてマンツーマンの指導を受けるわ、見目麗しいその孫娘がわざわざ自宅までレッスンの送り向かいをしてくれ、最後はその彼女と賞をかけて対決するという、何とも少年漫画のようなシナリオ。 ただ、水墨画の面白さは十分に伝わってくる。 穂先で一本の線を引くことで、真っさらな平面の紙上に、空間が生まれ、時間が生まれる。 何かを始めることで、そこにあった可能性にはじめて気づくように、書き手の心は、線によって表われ絵になる。 何もない場所に突然、描き出され映しとられる人生そのもの。
0投稿日: 2024.11.21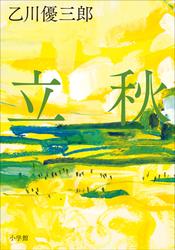
立秋
乙川優三郎
小学館
遅れてきた飛翔と離愁の狭間で
今作も期待を裏切らなかった。 何より会話がとてもいい。光岡と涼子だけでなく、"こしかけ"のママ寿美もそうだし、旅館の女中まで。口にする言葉の美しさもあるが、息のあったテンポが心地よい。 タイトルの「立秋」は暦の上では秋の始まりを意味するが、同時に極まった夏の暑さが徐々に弱まる残暑の始まりでもある。 いずれにしても豊穣の秋に向かう兆しとして、一方では異国の地での遅ればせの勇躍に胸はせる涼子の心模様と、急に近づいた離愁に戸惑いながら成りゆき任せの自らの人生帳簿を意識する光岡の覚悟を写した、見事なタイトルだと感じた。 輪島塗の工房を訪ねるシーンがあったり、テーマも奥深い漆工の世界だったので、時期も時期なのでてっきり能登半島地震も小説に出てくるのかと期待して読んだが、出てこなかった。 小説家といっても都内にいくつもマンションを所有し親の遺産で生活している光岡は、どこか『脊梁山脈』の主人公を連想させ、どうしてこの作家さんは高等遊民的人物を描くのが巧いんだろうとあらためて感心させられた。 「共感できることを期待して読み、共感できないことに失望する。そんな読書はなんの役にも立たない」という文中の言葉にひとりドキリとさせられた。
0投稿日: 2024.11.16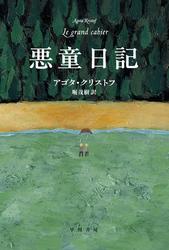
悪童日記
アゴタ・クリストフ,堀茂樹
ハヤカワepi文庫
脳味噌の詰まった心臓
数十年ぶりの再読で筋はとうに忘れてしまっている。 だが次の行で一気にこの不思議な世界観を思い出した。 「ぼくらはおばあちゃんを、おばあちゃんと呼ぶ。 人びとはおばあちゃんを、〈魔女〉と呼ぶ。 おばあちゃんはぼくらを、『牝犬の子』と呼ぶ」 本書は原題の「大きなノート」に綴られる双子たちの作文が元になっている。 その作文には彼ら独自の決まり事があって、主観的で曖昧な描写や、感情を想起させる言葉の使用を極力排し、起こった事実をありのまま客観的に記される。 奇妙なことに名前も一切排除されるため、地名はもとより、女中は女中と、将校・従卒も将校・従卒と属性だけで表記される。 肝心の双子の区別もまるでなく、「ぼくらのうちの一人」としか書かれない。 それにしてもこんなにエログロ満載だったかとあらためて驚く。 子供の視点とはいえ、小児性愛、マゾヒスト的な性的倒錯、おまけに獣姦まで、剥き出しのままたんたんと描写される。 最初は"どこが悪童だよ、いい子ちゃんじゃないか"と高をくくっているが、次第に様相が一変していき、最後には確かに悪童と呼ばわっても仕方がないかと思えてくる。 それにしてもやっぱりラストは衝撃的だ。 最後の一節がとにかく素晴らしい。 タイトルの「別離」が二重の意味でかかっていて、これ読んじゃうと誰かに薦めたくなるのもわかるなぁ。 フランスでも日本でも口コミでヒットした所以もここにある。 キャラクターの要素も大きい。 何かというと「悪魔」だの「牝犬の子」だのとわめき散らすおばあさんも、よくある吝嗇なイヤミばばあなのだが、双子が最後まで慕うほどの度量の深さを併せ持つ。 この双子らの設定がとにかく奇妙で、精神と肉体の鍛錬を怠らないストイックぶり。 "乞食の練習だ、盲と聾の練習だ、断食です、今は不動の時間です"と、やってることは忍者修行と変わらない。 訳者あとがきで堀茂樹氏が指摘している「ぼくら」の魅力を以下のように評している。 「非道な現実に衝撃を受けながらも『お祈り』を拒否し、涙を堪えて『ぼくたちは理解したいんです』と言い切るところに、この『個』の主体的な姿勢、すなわち外界に対して開かれていると同時にあくまで自律的でもある姿勢が如実に表れている。この両面性に注意を払っておきたい。なるほどこの『個』は、いわば心臓まで武装している。生き抜くために必要な残酷さとしたたかさを身につけている」 「心臓まで武装している」という表現にグッと来る。 と同時に思い出しのたが、デュ・デファン夫人が百科全書派を集めたサロンで、フォントゥネルの心臓の上に指を置いて語った「ここにも脳味噌がつまっている」という言葉。 そうそう、この子たちの心臓にも脳味噌がつまっている。 ひたすら合理的で、どこまでも冷静。 計算高いが決して私利私欲のためではない。 盗み見や万引きに人殺しと非道でありながら、彼らの行動基準にはどこか高潔なまでの高い倫理性を合わせ持っている。 司祭館の女中に対しては、おやつを食べさせてもらったり、風呂に入れてもらいつつ汚れた衣類の洗濯まで定期的にしてもらうという恩義を受けていた。 それにもかかわらず、連行されるユダヤ人に意地悪をしたという一点でもって爆殺を計る(死んではいないが顔に大けが)。 この双子の行動原理は容易に理解し難いものがある。 そこにはキリスト教的な博愛主義の倫理観からでは決してない、彼らなりの動機がある。 著者は「おばあちゃんの林檎」で女中とは正反対の行動(連行されるユダヤ人の行列にわざと林檎をばら撒く)を物語ることで、明確な対比の中から彼らの心模様を浮かび上がらせようとしている。 とにかくこの双子が自らの意志で人に危害を加えようとしたのは、この女中に対してだけだったような気がする。 その他は依頼殺人というか、頼まれてやったという形が多い。 この子らの中で他者との契約というか、"約束は絶対だ"という固い信念のようなものがあって、そこには恩義や情などといったウェットなものは一切見られない。 ただ、脳味噌の詰まった心臓があるだけだ。 牧師の双子に対する態度の変化も最初、奇妙に感じられた。 兎っ子家族への施しを目的として脅しとられていた金はいつかからか、この双子への援助基金に切り替わっていく。 聖書を諳んじられるほど教養高いのに、信仰心はまったく双子に対して不憫だと思ったのか、隠された疾しい性的な目的のためなのか。 実際はそのどちらでもなく、彼ら双子に神聖なものを感じたからかもしれない。 不条理で非情な世界に神に遣わされたかのような、どこにも染まらない岐立した何かを見出したのかもしれない。
0投稿日: 2024.11.14
心にとって時間とは何か
青山拓央
講談社現代新書
過去と未来が混じりあう「今」
ヒトは過去/今/未来の時間軸で生きている気になっているが、実はすべてが曖昧だ。 そこでの時間の流れも錯覚ではないか。 移り行く特定の時点としての「今」。 冒頭で示されるのは、過去と未来が混じりあう「今」である。 「人間は一瞬の物理的世界をスライスするようにして知覚するのではなく、ある程度の時間的幅をもった物理的世界の情報を脳で編集したうえで知覚しており、あくまでも主観的には、過去や未来が、すなわち、すでに体験した現象やまだ体験していない現象が混ざり込むようにして『今』は体験されている」 そうであるならば、「今」という語が含む同時性並びに時制は失われる。 なぜなら任意の時点における世界の認識が、その直前/直後の世界の情報を取り込むかたちで成立しているためだ。 つまり「今」とは、どの時点もそこから見れば「今」だという意味での「今」でしかなくなる。 「今」という捉えどころのなさは、自らの意思決定の時点の掴めなさを説明する形で有名なリベットの実験が紹介されている。 私たちが何かをしようと考えるより前に、脳はすでにその行動を開始しているを示した、あの実験である。 自由意志なんて幻想だとか、意識とは所詮あとづけの身体解釈ではないかとか、いやいやこれは神経伝達の速度の問題だろうなどと議論されてるアレである。 自由意志擁護派は、手首を動かすなんていう単純な行動では、意識するより前に準備が始まるだけで、もっと複雑な意思決定では自由意思が存在しているんだと主張している。 著者はまず意志決定の時点なんてもともと掴めないはずだと論じる。 意志をもつことに明らかに対応する心理現象などないのだと。 自らがそれを実行し始めているのを自覚することではじめて、自分がその意志決定を行なったことを確信できるのではないか。 何かを選ぶという行為についても同じことで、メレの批判を引用する形で、適当に手を動かすことは「自由な行為」の代表例とは見なしがたく、リベットの発見を「自由な行為」一般に当てはめることには無理があると指摘している。 魅力的な顔写真を選ぶ実験でも、被験者はすり替えられて渡された間違った写真でも、滔々と選んだ理由を説明する様を紹介して、何かを実行しはじめるのを自覚することでようやく、自身の選択を確信するに至るそんな後付け解釈の心理現象を説明する。 さらにこの選択と選択結果との不一致への盲目性からはもう一つ、「本気さ」についての視点も加えて議論している。 顔写真の実験は、適当に「評価」しただけで、本気で「選択」したわけではない。 責任や義務の発生しない選択と、日常生活における選択とは区別する必要がある。 リベットの実験同様、このことをもって人間の自由な行為についての一般的な知見を得たとは見なし難いと語っている。 ただ著者もリベットの実験がまったくの無価値だと見なしているのではないし、むしろ脳科学の世界では重要な知見が示されたと評価する声の方が多い。 そもそも意志決定の時点を正確に捉えることなど不可能だという考えに凝り固まっているのか、この実験成果から「本気度」の議論しか導き出せないとしたら、ちょっと寂しい気持ちがしないでもない。 『意識をめぐる冒険』でクリストフ・コッホは、意識感覚を「意図」と「自己主体感」と「所有者感覚」の3つのコンポーネントに区別している。 その上でコッホは、この実験からわかったのは、これら3つの感覚が通常は同時に感じられるが、常に同時に生じるというわけではないということであったと結論づけている。 私たちは、「意識が原因となって脳と行動に影響を与えている」と誤って捉えてしまうのも十分な理由があって、すべては自己主体感が生じるタイミングにあるのだと。 このことから、自由意志と行動、脳活動がどのように関係しているのかを次のようにわかりやすくまとめている。 「行動を起こそうというあなたの自由意志の感覚は、行動の直接の原因ではない。行動の直接の原因は、それを引き起こす運動皮質の脳活動であり、その行動に伴う自己主体感を引き起こす脳活動とは異なる。しかし、ここで忘れてはならないのは、両方の脳活動とも自分の脳が生み出しているという事実だ。前者の脳活動は意識にのぼらず、後者の活動は意識にのぼる、ということだ」
0投稿日: 2024.11.13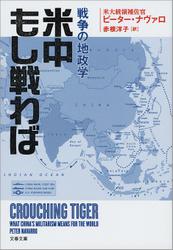
米中もし戦わば 戦争の地政学
ピーター・ナヴァロ,赤根洋子
文春文庫
米中戦争はもう始まっている
中国による軍事力の非対称性と接近阻止、領域拒否戦略によって、米軍のアジア駐留コストは激増している。 中国の狙いは、アメリカを軍事的に打ち負かしたり、アジアから完全に締め出すため防御壁を構築しようとしているのではない。 単に、アジア海域で作戦行動をおこなうアメリカ艦船のコストとリスクの負担感を上げようとしているだけなのだ。 孫子の兵法の「戦わずして勝つ」という戦法をお手本にした中国の意図は、アメリカに費用対効果という問題を突きつけて、コストとリスクの負担感からアジアへの介入を躊躇するように仕向けることにある。 その意味で太平洋の空と海を舞台に、東の孫子と西のクラウゼヴィッツが出会っているのである。 繰り返すが、中国の望みは戦わずして勝つこと、ホワイトハウスを躊躇わせ決定を先延ばしさせること、ゆっくりと自分主導で有利に事を進めるための時間を稼ぐことにある。 日本や台湾がいくらアメリカから最新のミサイル防衛システムを導入しても意味がない。 なぜなら、中国との更なる軍拡競争を引き起こすトリガーになるだけだし、もっと根本的なことは、中国が西側の最新で高価な兵器に対して大量の安価な兵器で対抗しようとしているからだ。 もともと戦闘員の命の重さも西と東で違っているのだから、ミサイル1発の価格も含め勝負にならない。 例えば機雷などその典型だろう。 日本が降伏を決意したのも実は原爆投下などではなく近海に大量にばらまれた機雷だったことからもわかる通り、台湾海域や南シナ海の海域を限定封鎖する目的で機雷を蒔かれたらどうなるか。 すでに中国海軍は十分な量を大量に保有していて、いつでも主要な海上交通路を封鎖することができる。 中国が仕掛けてくる戦い方は、「心理戦・メディア戦・法律戦」の三戦があるが、要は「嘘も繰り返せば真実になる」戦法である。 海洋法条約にそんな条文はないのに200海里の排他的経済水域内の航行の自由を制限したり、インチキ地図を持ち出して領有権を主張したり、レアアース輸出や日本の海洋産品の輸入を制限したりである。 日本への非難や不快感表明、経済的ボイコットなどの外交的心理戦はもはや日常茶飯事だが、嫌がらせも繰り返していくことでボディーブローのようにダメージを与えられると心得ている。 直接の軍事力は行使せず、非軍事的な手段で、搦め手搦め手で目論見を達成しようとしているのだ。 「まず曖昧な歴史に基づいて不当に領有権を主張する。これが法律戦である。次に、問題の海域に民間船を大量に送り込んだり経済的にボイコットするなど、あらゆる形態のノンキネティックな戦力を展開する。これが心理戦である。そして最後に、『中国は、屈辱の100年間に列強の帝国主義に踏みにじられた。平和を愛する中国は、歴史的な不正行為を正そうとしているだけなのだ』というストーリーを広め、国際世論をコントロールすることによって、メディア戦を制しようとする」 中国外交部は窓口でも交渉相手でもない。 外交政策の真の決定は党の中央対外連絡部が一元的に行なっている。 交渉相手を間違えると、いかなる取り決めも空手形に終わってしまう。 第一列島線上の要である台湾を失うことは、アメリカ軍の最前線を分断することとを意味し、中国海軍に自由に太平洋に出て行ける門を開いてやることと同じである。 アメリカは空母戦力ではなく、潜水艦戦力を強化して、非対称戦争を中国にやり返すべきだ。 潜水艦戦なら中国の弱みを突くことができる。 ただ空母には、アメリカの本気度を示す象徴的な意味合いもあり悩ましい。 中国のWTO加盟の承認は、米クリントン政権の致命的な失敗で、貿易赤字と失業者を増やしただけに終わった。 経済成長は中国の民主化にはつながらず、単に独裁国家の経済力向上をもたらしただけだった。 中国への経済的関与は平和をもたらすという理論も嘘っぱちで、中国との経済的関わりを削減することこそが、中国の軍事力増強を抑える唯一の手段になりうるのだ。 同様に、経済的相互依存を高めると戦争を防ぐことができるという理論も妄想に過ぎない。 現に、日中は貿易でも投資でも緊密に結びついた結果、どうなったか。 中国は相変わらず日本との衝突のリスクを高める行動を取り続けているではないか。 困ったことに中国軍は通常兵器も核兵器も総合的に一括管理されてしまっているため、中国本土の通常兵器への限定攻撃のはずが、図らずも相手の核兵器まで破壊してしまう可能性がある。
0投稿日: 2024.11.09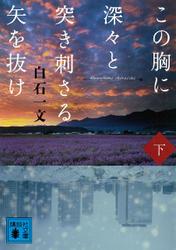
この胸に深々と突き刺さる矢を抜け 下
白石一文
講談社文庫
「必然に従って生きる」とは
なぜ疑惑の政治家をNと呼ぶのか、なぜ一部の登場人物の名前を漢字でなくカタカナで表記しているのか。 その疑問の答えというか仕掛けは、下巻で明かされる。 タイトルの突き刺さる矢もてっきり「外側からやってきて僕たちの内部に突き刺さる」と上巻で暗喩された理不尽な「死」であったり、「癌」なのだろうと思っていた。 それでもなぜ胃癌なのに胸なのかと釈然としないまま読み進めていって、矢の正体が「時間」だと明かされた時の衝撃、というか拍子抜け。 上巻で、無数の集合体としての意識を糸に通されたビーズ玉の連なりと表現したり、人生における隔絶とバラバラさ加減を闇に放たれた数十個のパチンコ玉に喩えたのは本当に良かったと思う。 それに時間の正体も下巻の最初でそうそうに答えが出ているのだ。 それは、過去から未来へと一直線に飛ぶ「矢」でもなければ、始まりも終わりもない「円環」でもない。 時間は「信じがたいほど複雑で奇妙奇天烈な運動を行う運動体」で、「繰り込み、巻き込み、重複や分裂といった多様な運動の合成物としか思えない」と結論づけられている。 まったく異論はなく、至極もっともな定義だと思うのに、なんでまたぞろ「時間という矢」が出てくるのか。 おそらく著者の信念である「いまを生きる」ことと「必然に従って生きる」ことを強調する意味合いもあるのだろう。 いたずらに過去に拘泥し、意味もなく未来に希望を寄せたり、反対に恐れたりする愚を犯さず、「現在という一瞬一瞬」を「食らい尽くす」。 そうやって「現在しかない人生を送るというのが、必然を生きるということでもある」と書いてあるから、抜くべき矢をそうした「時間や歴史の呪縛」という意味で表現しているんだろう。 それでも相当に変だ。 一方では「僕たちの幸福は自由と同じくらい束縛の中にも存在する」としながら、一方では「言葉だけが時間の魔術から僕たちを解き放ってくれる」ともしている。 どこからこの違和感が生じているかというと、やっぱりこの「必然性」にあるのだろうと思う。 行き当たりばったりや偶然に左右されるのではなく、「すでに決まっていることを自分で決めるんだ」と主人公は語る。 納得づくの確認作業のようでもあるし、何もしないことが「いまの自分の必然」ならそれでも構わないのだ、とも。 結局のところどこか運命論にも似た、どうとでも解釈づけ可能な自己肯定論のようでもある。
0投稿日: 2024.11.08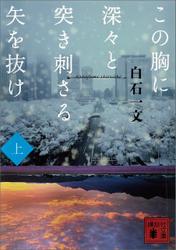
この胸に深々と突き刺さる矢を抜け 上
白石一文
講談社文庫
希望は絶望のために存在し、期待は諦めの球根に過ぎない
小説というものが、恋愛なりミステリなり、特定のジャンルの物語を紡ぐものであると思っている人には、本書のように、主人公の心のうちで展開される考えや意見表明と、それを補強する形で次々に挿話されるミルトン・フリードマンや立花隆のインタビューを見て、「これは何だ」と面食らうに違いない。 しかも語られる思念も、シニカルで身勝手な中年男性の独善的とも思える、明け透けな人生訓であるので、激しい拒絶反応を覚えるかもしれない。 ただ白石一文という小説家の作品はこういうものだと説明するなら、本書ほど適した作品はないだろう。 どこか徒然草風のスタイルは、文藝春秋に入社し週刊誌記者を務めていたという著者の略歴とも呼応している。 本書で山本周五郎賞を受賞し、翌年『ほかならぬ人』で直木賞を受賞するのだが、こちらで直木賞でも良かったんじゃないか、むしろ遥かに落ちる『ほかならぬ人』との合わせ技で評価されたのかしらんという気が、下巻未読の段階でしている。 傑作『神秘』で末期癌の主人公の身に起こる物語も、出会う人や見聞きした話がすべて一本の線で繋がるトゥルーストーリーで、人生とは「偶然をはるかにしのぐ必然によって形作られている」という感慨に支配されていたが、本書の主人公もこの必然性に囚われている。 人生半ばで胃癌の告知を受け、「自分の肉体が自分を裏切り、自分を殺そうと刃を向けて」くるという外側からやってくる死に怯え、「僕たちは死ぬのではなく、殺されるのだ」と悟る。 「死は常に僕たちの外側からやってきて僕たちの内部に突き刺さる」 その理不尽さを前に、我々にできるのはやってきた死の受容だけだと事実。 穏やかで納得のいく甘美な死などあり得ないのと同じように、「幸福になりたい」とか「誰かを愛したい」といった普段我々が行動の源泉として現実だと受け止めている意識自体もまやかしに過ぎない。 我々の意識は一瞬一瞬「幸福になりたい」と念じてなどいないし、「長く生きたい」とも「誰かに愛されたい」とも切望しつづけてはない。 集合体としての僕という意識は、時々刻々様々に変化し、相互に絡み合いつつ時に相反しながら、大ざっぱな形で自己意識を紡いでいるに過ぎない。 幸福や愛といった単純平明なお題目は、「グロテスクな自己意識の正体から目を逸らすために『大雑把な意味』が半ばでっち上げた自己慰安のためのトリック」である。 こうして辿り着いた人生の「真実」から主人公が導いた答えが「必然の中で生きる」というもので、自分自身の瞬間瞬間の意識を必然性の有無によって厳しく査定し、無駄を削ぎ落とすことで、偶然性や無駄と恐怖に支配された世界に抗おうと決意する。 見直しの対象は、現在の仕事や生活、妻や娘との関係、その他諸々にわたっていて、それを「引き算の人生」だと説明しているが、下巻で主人公の心境に変化はあるのかどうか、愉しみなところ。
0投稿日: 2024.11.07
完全シミュレーション 台湾侵攻戦争
山下裕貴
講談社+α新書
侵攻が成功するかどうか
台湾侵攻は必然的に日本侵攻となる。 なぜなら、台湾を南北に貫く山脈が天然の要害となるため、内陸からの東進が不可能なこと。 そのため東部侵攻には海上からの迂回路が選択されるが、日本の南西諸島とりわけ先島諸島があまりにも台湾に近接しているため、捨て置けなくなるからだ。 東部海岸に揚陸部隊を送るには、あらかじめ背後に当たる与那国島や石垣島に侵攻して占領しておかなくてはならない。 本書は米シンクタンクで実施されたシミュレーションを元に構成され、中国の目論みは失敗するだろうとの予測を立てている。 しかしこれはずいぶん虫のいい論拠を前提としていることは肝に銘じておく必要がある。 まずアメリカの参戦。 侵攻と同時に米軍が迅速かつ本格的に介入することを前提としているが、どうだろう。 さらに直接の戦争当事国である日本の参戦は言うに及ばず、オーストラリアやイギリスも戦闘地域に空母を派遣するわ、インドは中印国境付近で攪乱的な軍事行動を連動的に起こして戦争に協力するらしい。 もう一つ気になるのは、米中双方とも本土への直接攻撃は抑制し、核の使用を伴う全面戦争への進展を避けるとしている点。 これはウクライナと同様だとするが、果してそうか。 武器供与ではなく主体的に軍事活動に参加するなら、そもそも限定的だという境目自体が曖昧になる。 さらに、想定では習主席からの命令で、日本の自衛隊基地には攻撃していいが、在日米軍基地には攻撃を禁じるというのだから相当虫がいい。 一番の難点は、台湾海峡をめぐる攻防予測だ。侵攻開始後わずか140キロの海峡は、早々に中国の「内海」化されるはずである。 おまけに水深が浅く、潜水艦も航行しにくいこの海峡を、米軍は大量の水中ドローン艦隊を動員して中国の物資輸送を妨害するとしているが、そもそも封鎖海域に辿り着けるのだろうか。 本書を眼光紙背に徹して読めば、著者のシミュレーションとは異なる結論が得られるはずだ。 中国があらかじめ、台湾を東西に分断する形での占領をひとまずの目標として事に臨むなら、短期での決着はあり得ない話ではない。 「台湾市民を守るための限定的な特別軍事作戦で、他国は内政干渉するな」と釘をさせばいい。 当面はイスラエルによる占領みたいに一時的なものだと嘯いて既成事実化していけば、やがて全島占領への足がかりにはなるはず。 一方で、大量の台湾市民の避難の受け入れに謀殺され、日本や西側諸国の国内世論は分断すると予想される。
0投稿日: 2024.10.28
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
