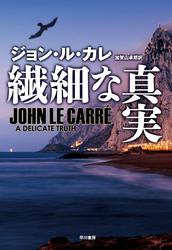
繊細な真実
ジョン・ル・カレ,加賀山卓朗
早川書房
両手の指先を合わせ、おもむろに語られる機知に富む会話が魅力
82歳の老作家が書いた本書を読んで、何の恥ずかしさも感じない作家はいないだろう。 とりわけ登場人物がどこで買い何を食べたかを事細かに書くことが人物描写だと思っている日本の小説家にとっては、ほんの一、二行ですべてを描写すると評されるほどのル・カレの筆力など顎がはずれて戻るまい。 壮大に練り上げられたプロットも、派手なドンパチも、甘美なベッドシーンもないが、両手の指先を合わせおもむろに語られる会話が本書の魅力。 特に外交官同士の会話は、丁寧で洗練された物言いの中で静かに弾を込め合ってるような迫力があってスリリング。 ル・カレの作品が近年も相次いで映画化され、あれだけの名優がこぞって出演するところを見ると、この魅力はあながち間違いではないのだろう。 ここに登場する政府による不都合な秘密の隠蔽や古き良きイギリス的妥協を読んでいると、とても彼の国だけの問題とは思えない。 不穏で唐突なラストからも、読者に少しでも事の切迫さを感じてもらいたい著者の思いが透けて見える。 授けられた勲章や年金の返上を辞さない母娘の真実の希求や、決して荒野に泣き言をこぼすような未熟さも思い上がりもない矜持と誇りには感心させられた。 世界中の外交官のあるべき姿も示される。 「相手をおだてて少しずつ攻略し、議論し、説得し、丸めこむ。だが期待はしない。万事において神聖なる基本外交政策にしたがい、あらゆる国の凶悪犯罪にそれを適用する、自国も含めてだ。会議室に入るときには、自分の感情は入口に置いてきて、特段の指示がないかぎり決して怒って退出することはない。何もかも中途半端で終わらせることを、むしろ誇りに思っている。ときには偉大な主人に注意深く進言することもある。けれども、決してウェストミンスター宮殿の国会を一日で再建しようなどとは思わない。思い上がったことをする危険も冒さない」
9投稿日: 2015.01.13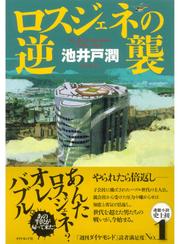
ロスジェネの逆襲
池井戸潤
ダイヤモンド社
形を変えたヤクザの組同士の抗争のようだ
おなじみの半沢の決め台詞もあり、ドラマで見知った展開ではあるのだが、読みだすとやめられなくなる。 登場人物に著者の会社論を語らせるところなんかは説教臭くて閉口させられるが、子会社が親会社に楯つき、その支援する企業とは敵対する企業に肩入れしていく成り行きには無理があるだろと思いつつも、大丈夫かとハラハラさせられるし、そもそも最初の買収案件の持ち込み先をめぐる謎が後の展開に大きく関わっていくところなど巧い。 形を変えたヤクザの組同士の抗争のようで、鉄砲玉よろしくダメ社員やダメ経営者が両者を飛び交う弾となっている。
2投稿日: 2014.12.28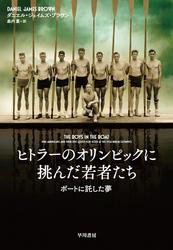
ヒトラーのオリンピックに挑んだ若者たち ボートに託した夢
ダニエル・ジェイムズ・ブラウン,森内薫
早川書房
「訳者あとがき」にもあるが、たしかに誰かに薦めたくなる本
ボートにまるで興味がなくても、読めばこの競技のもつ肉体的・精神的な過酷さがわかるし、その果てにある思いがけない神秘や美に出会える。 大著のノンフィクションに尻込みするかもしれないが、まるで青春小説を読んでいるようにグイグイと物語に引き込まれる。 綿密な取材を感じさせない著者の力量もあるのだろうが、幸福な両親の昔話に熱心に耳を傾けた娘の存在が大きい。 耳を澄ませば「エイト」の奏でるシンフォニーや観衆の喝采が聞こえてきそうで、読みながら何度も目頭が熱くなった。 本書を手に取る前にどれほどのアメリカ国民が、この物語の主人公であるジョーを知っていただろうか? 彼は幼くして母を失い、義母から嫌われ、父親から見放され、捨てられる。 地下で暮らし、「教会のネズミのように貧乏」だが、生活のため学業のためボートのために必死に働いた。 両親を恨むでも自身の不運を嘆くでもなく、ひたすらタブでポジティブな若者。 「他の人が見落としたり置き去りにしたりしたものの中」に価値を見いだし、樵夫として丸太を割りながら、ボートと相通ずる「心と筋肉を注意深く調和させること」のすばらしさに気づく。 「四つ葉が見つからないのは、探す努力をやめちゃったときだよ」 恋人はジョーがくれたクローバーを手元にラジオの実況に耳を傾けた。 口べたなポーカーフィスであり、記者から「この男の血管には、氷水が流れている」と評されるアル・ウルブリクソン・コーチも魅力的だが、イギリスから来たボート職人であるジョージ・ポーコックはそのさらに上をいく。 ボートを単に「つくる」のではなく、「造形していた」というほうが正しいと評されるほど、彼のシェル艇はもはや芸術の域に達するほどの職人なのに、ちっとも気難しくなく、誠実で謙虚。 そのくせボートの生き字引のような存在で、諸々のテクニックから勝敗の心理に至るまで深い洞察を持っている、ボート界の神のような男。 すでにアメリカでは評判を呼んで映画化も決定しているらしいが、ともすれば自由の国のアメリカの善良な若者たちが、自由の制限されたヒトラーのいる悪のドイツ帝国に挑むという安易な構図に陥ると、本書の魅力が半減する懸念を感じる。 その意味で、日本語訳のタイトルにもう少し配慮があれば良かったと思われ残念。
3投稿日: 2014.12.01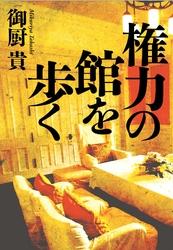
権力の館を歩く
御厨貴
毎日新聞出版
政治家の「居場所」をテーマとした優れた政治評論
*社会党の歴史 「社会党の歴史は、政権をとれぬ政党の歴史であった。 生まれ出ずる時と死に至る時の、そう、生と死を迎える二回だけしか政権党にならなかった「不幸」な歴史を持つ」 *宮澤喜一という政治家 「佐藤内閣の通産大臣として日米繊維交渉に臨むが失敗に終わる。 宮澤は性格上、法的にできない話は力ずくでやってはならず、できないものはできないとの信念が頭をもたげる時、硬直的になる。 今回も日米交渉ではしたたかに戦ったものの、日日交渉でのしなやかさに欠けた。 後任の田中角栄が日日交渉をカネの力で乗り切ったのは、余りにも有名な話である」 「おそらく宮澤が理想とする権力像は、池田総裁と前尾繁三郎幹事長との関係に現れていた。 前尾は池田に会わぬまま仕事をし、池田は前尾に来いとも言わず任せっきりである。 お互いに議論することなく相互信頼の中で、すべてが進んでいく・・・」
2投稿日: 2014.11.27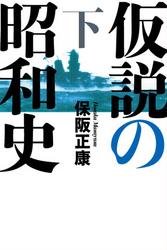
仮説の昭和史(下)―昭和史の大河を往く〈第13集〉
保阪正康
毎日新聞出版
戦局の悪化とともに「もし」の置き所が難しくなるが・・・
上巻では「もし」が確かにどちらに転がってもおかしくなかったポイントをすくい上げていたのに対し、下巻では軍部の組織原理を前提とすると明らかに無理だろうというような「もし」や無い物ねだりの「もし」が多く、雑誌連載の数合わせ的に感じられ残念。 特に「アッツ島やサイパン島の玉砕がなかったら」などは、亡くなった方や遺族を思うと読んでて不快な気持ちになった。 一方で、実現しなかったさまざまな講和交渉や、もしかしたらマッカーサーが戦死したかもしれないレイテ沖海戦など、あまり詳しく知らなかった話も多く勉強になった。
0投稿日: 2014.11.27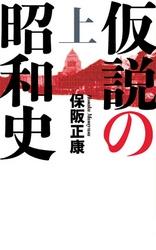
仮説の昭和史(上)―昭和史の大河を往く〈第12集〉
保阪正康
毎日新聞出版
井沢元彦が「逆説」なら、保阪正康は「仮説」で勝負
単なるIF物であれば、"有名な事件がもし起らなかったら"、ということを予想するだけだろうが、本書は長年にわたって昭和史をライフワークにしている著者だけに、「もし」の置きどころが絶妙だ。 例えば、張作霖爆殺前に日本人顧問が途中下車せず爆殺されていたらとか、駐華ドイツ大使による日中講和が実現していたらとか、宇垣一成が変心せずクーデターが実現していたら、などなど。 二・二六事件や日本軍によるタイ領の強行通過などは、史実とは異なる展開や結末が十分にありえたんだとわかる。 TV向きな内容でもある。 雑誌連載をまとめたもののため、写真が豊富なのはありがたいが、もう少し読みたいのにというのも少なくなかった。 それと、永田鉄山刺殺とか東条内閣成立後の「もし」は、私には非現実的であまり有益なIFとは思えなかった。 一少佐がルーズベルトからの親書を独断でおさえたり、酒気を帯びたまま上奏したり、大正から昭和に変わった途端に立て続けに重大な軍事行動を起こしたりと、まだ30歳を超えたばかりの昭和天皇を陸軍がどう見ていたのかよくわかるエピソードの数々には、考えさせられる。
2投稿日: 2014.11.27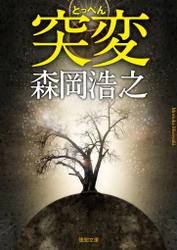
突変
森岡浩之
徳間文庫
本当に"解説不要の傑作"か?
300ページほど読んだとこでふと、貴志の『新世界より』であればもうとっくに小説の世界観にどっぷりはまって、ページをめくる手がもどかしくなるほどだったのに、こんなに淡々としたペースで大丈夫かと思ったが、心配が的中したようだ。 700ページを超えるボリュームを読んだのに、見事なほど何も残らない。 やたら管轄や権限がどうだとか、余計な話が長過ぎる。 極めつきは、巨大チェンジリングの説明の場面で、「ここは彼にまかせた」と話を振っているのに、「小学校の時にウサギを飼ってた」とかつまらない兄妹喧嘩が続くのだ。 唯一面白かったのは、"突変"発生時のスーパーで臨時休業を告げる店長に対して客たちが放つクレームで、 「どうせなら、十点限りじゃなくて、好きなだけ持っていかせてよ」 「これは移災なんでしょ。あたしら、裏返ったんでしょうっ!」 これは笑った。 このテーマで一番面白くなりそうのは、笑い飯の漫才のように、「人間の体と鶏の頭の境目」ならぬ「突然変移領域」、滝があり溝渠があり異形の生物がうごめく「生態系不連続線」だろうに、著者はこの部分に盛り上がりを持ってきていない。
5投稿日: 2014.10.31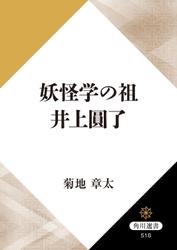
妖怪学の祖 井上圓了
菊地章太
角川選書
妖怪が「モノ」ではなく「コト」として感じられた時代の話
明治の時代に、狐憑きやコックリさんなんてのはタワゴトだと証明したくて、全国の怪現象を収集したために、後世の人から「妖怪学の祖」と奉られることになった男の生涯。 京極夏彦による小説の主人公「京極堂」との比較が分かりやすく、「この世に不思議などない」という点では共通だが、打倒否定されるべき前近代の迷信とまでは考えていない。 現在では妖怪というと、すでに「モノ」化した一個のキャラクターと考えるが、明治の頃には、それぞれの地方で形を変えて存在している「コト」としての怪異現象だった。 この点は重要で、それだけ不思議さと異様さが生々しく感じられたのだろう。 柳田も妖怪研究を行なっているけど、彼の書いたものは物悲しくて文学的すぎて、現代人には井上の方が私情もなくかえって都合が良かったのかもしれない。
6投稿日: 2014.10.23
フードトラップ 食品に仕掛けられた至福の罠
マイケル・モス,本間徳子
日経BP
自分や家族の食習慣をオーバーホールするためのヒント
読む前は、「食べてはいけない」のような単なる企業告発物を予想していたが、アメリカ食品メーカーの企業史や新製品開発秘話など、かなり読ませて面白い。 業界ではこれまで、糖分や塩分や脂肪分の配合量がある値にぴたりと一致していると消費者が大喜びするという「至福ポイント」を見つけ出すのにやっきになってきた。 ゆえにメーカーにとっては、塩・砂糖・脂肪は、栄養素というより兵器に近いのだが、あまりにもこれら三つの成分が便利でなくてはならい存在になったため、その罠にも容赦なく引きずり込まれることになったと著者は指摘する。 加工食品の原材料とその配合は、熟練の科学者や技術者たちが緻密な計算のもとで設計し、過食をそそのかすように計算し尽くされている。 われわれの脳は、糖分、脂肪分、塩分に目がない。 なら、これらが入った製品を作ればいい。 利幅を稼ぐために低コストの原料も使おう。 次に、『スーパーサイズ化』して販売量をさらに増やす。 そして『へビーユーザー』に照準を合わせて、広告とプロモーションを展開する。 加工食品業界には鉄則や基本ルールがいくつかあり、「迷ったときは糖を足せ」や奇抜な商品を戒める「80%の親しみ」などもその一つ。 また、体に良いとされるーつの成分を前面に出し、消費者が他の事実を見過ごしてくれるよう期待するなんていう姑息な方法も用いられる。 幹部が「われわれは、需要を作り出すのではありません。発掘するのです。試掘して、見つかるまで掘るのです」と語るほど、マーケティングは徹底している。 それによって、チップス類のように、いままでおやつとして間食で食べていたものを、朝昼晩の食事の常連アイテムに変えたり、贅沢品から成分になったチーズのように、いままで単品で食べられていたものを、原料化して消費を増やすことに成功している。 「糖分」 ・ドーナツはより大きく膨らみ、パンは日持ちが良くなる。 ・“かさ”を増し、色合いを良くする。 ・泣いてる子も泣き止むほどの「鎮痛薬」。 ・脳の興奮作用を持つ恐るべき存在。 ・素早く強力な作用を持つ覚醒剤のメタンフェクミンに似ている。 「脂肪」 ・目立たず、さりげなく作用するアヘンに似ている。 ・食品の口溶けや口当たりを良くし、食感を高める。 ・至福ポイントがない。 ・脂肪分は糖分と一緒になると、脳は脂肪分の存在をほとんど検知できなくなり、過食を防ぐブレーキがオフになる。 ・甘さは、好まれる限度があるが、脂肪分は多ければ多いほど好まれる。 ・多くても少なくても気づきにくく見えにくい。 「塩分」 ・「加工食品の偉大なフィクサー」 ・最初のひと口で味蕾に生じる刺激感を増大させる。 ・糖分の甘味を強めてくれる。 ・クラッカーやワッフルをさくさくに仕上げてくれる。 ・パンの膨らむスピードをゆっくりして、工場で大量生産できる。 ・腐敗を防いで賞味期限を伸ばしてくれる。 ・多くの加工食品につきまとう苦味や渋味といった不快な味を覆い隠してくれる。 ・肉の再加熱臭を手軽に解消できる。 「われわれは安い食品という鎖につながれている。安価なエネルギーに縛られているのと同じだ。ほんとうの問題は、われわれが値段に反応しやすいこと、そして、残念だが持つ者と持たざる者との格差が広がっていることにある。新鮮で健康的な食品を食べるほうがお金がかかる。肥満問題には大きな経済問題が関わっているのだ。そのしわ寄せは、社会的資源に最も乏しい人々、そしておそらく知識や理解が最も少ない人々にのしかかってくる」 本書は、自分や家族の食習慣をオーバーホールするための大きなヒントを与えてくれるが、問題は2つある。 1つは、「便利さの対価」をどう考えるか。 われわれは調理という「単調な繰り返し作業」を回避するために、便利さにお金を払ってもいいと考えている。 塩分への渇望は後天的であり、塩分摂取を減らそうとするなら早くから始めることが重要だとわかっていても、忙しい働き盛りの若い夫婦は、子供のために今日も塩分たっぷりの加工食品を買ってくるだろう。 もう1つは、当たり前のことだが「安全な食品を食べたければ金がかかる」ということ。 例えば、スープの滅塩に適した方法は、カーギルの提案する塩化カリウムではなく、新鮮なハーブやスパイスを使うことだが、コストは安価なナトリウムやそれより割高なカリウムよりもさらに上がる。 また食肉は、脂肪分が少ないほど価格が高くなる。影響を受けるのは、無知な人々だけでなく、貧しい地域の人々やその子どもたちなのだ。
9投稿日: 2014.10.15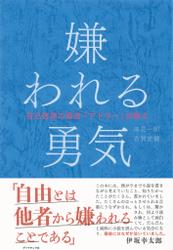
嫌われる勇気
岸見一郎,古賀史健
ダイヤモンド社
ジャッキー・ロビンソンも実践してた!?
本来は他者の課題であるはずのことまで、「自分の課題」だ思い込む。 こうした承認欲求に縛られた生き方を否定するアドラー心理学は、「課題の分離」という考えを呈示している。 「おまえの顔を気にしているのはおまえだけだよ」というお婆さんの言葉はその核心だ。 これを読んだ時、かつてジャッキー・ロビンソンがチームメイトに語った言葉を思い出した。 「ぼくが黒人であるのは自覚していますし、黒人であるというだけで僕を憎む人たちが出てくるのもわかっています。しかしですね、それは僕の問題ではなくて、そういう人たちの問題なのです」 初の黒人大リーガーである彼を周りはどう思うか。 これは他者の課題であって、自分にはどうすることもできない。 こんなことに悩み苦しんでいるとしたら、まずは「ここから先は自分の課題ではない」という境界線を引き、他者の課題は切り捨てて自分のプレーに集中すべきだ。 あらためて彼の偉大さを再確認した。
4投稿日: 2014.09.27
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
