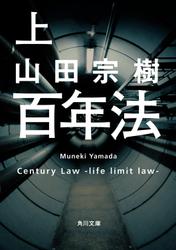
百年法 上
山田宗樹
角川文庫
大著だが、一気読み必至のエンタメ本
寿命を制限する法律をめぐって社会や人びとがどうなっていくかが描かれる。 奇抜な設定も最初のアイデア倒れに終わらず、その後の展開もしっかりと練り込まれていて、あぁなるほどと納得させられることもしばしば。 小説の中で流れる時間も長丁場だが、折々の時代の細かな変化を説明調にならず、流れの中で自然と語っているのうまいと思った。 ただ、映像系に近しい文体で、 「目を瞑る。サイレン。真下で鳴り止んだ。目をあける。背筋を伸ばす。夜空を見上げる」 など読むと、およそ文学書を読んだ気にはなれない。
2投稿日: 2015.03.26
ありふれた祈り
ウィリアム・ケント・クルーガー,宇佐川晶子
ハヤカワ・ミステリ
煮えたぎる怒りの果てに訪れる小さな奇跡
好きな小説やテレビドラマは決まって、登場する人物たちがたまらなくいとおしく思えてくるのだが、この作品も同じだった。 読み終わってなお、ニューブレーメンという小さな町とそこに住む住民たちが身近に感じられ、とても作者が創造した架空の町だとは思えない。 何度も家族(とりわけ兄弟がたまらなくいい)、町の人との何気ない会話のシーンで涙があふれそうになり、ページを繰る手が止まった。 全米4大ミステリ賞で最優秀長編賞を独占した本書だが、失礼な話むしろそれが余計に思えてしまうほど、ジャンルに囚われない新鮮な読後感と深い余韻をもたらしてくれる傑作だった。 とりわけ主人公たちがブラント家を訪問する最初のシーンは印象深い。 ポーチでは父親で教区の司祭を務めるネイサンと隠遁した盲目の天才ピアニスのエミールが籐椅子に座り談笑しながらブラインド・チェスをしている。 家の中では将来を嘱望された音楽家である姉のアリエルが、そのエミールの口述した回顧録をタイプしている。 庭では耳が聞こえず情緒不安定なリーゼを吃音症の弟のジェイクとその兄で主人公のフランクが手伝っている。 牧歌的で平穏な交流場面がやがて悲しみに変わるのだが、作者は単なる悲劇で終わらせず、最後には再生と許しを用意している。 「ありきたりの祈り」というタイトルの付け方も見事で、家族を救う小さな奇跡という込められた意味は明かされてなお胸に迫るものがあった。 気に入った箇所をいくつか。 「幸せとはなんだ、ネイサン? ぼくの経験では、幸せは長く困難な道のあちこちにある一瞬の間にすぎない。ずっと幸福でいられる人間などいないんだ」 「喪失は、いったん確実になれば、手につかんだ石と同じだ。重さがあり、大きさがあり、手触りがある」 「彼らはおれたちの近くにいるんだよ」 「彼らって?」 「死者だよ。違いはひと息分もない。最後の息を吐けばまた一緒になれる」
4投稿日: 2015.03.22
2050年の世界 英『エコノミスト』誌は予測する
英『エコノミスト』編集部,船橋洋一,東江一紀,峯村利哉
文春文庫
40年先を見据えるための最初のつかみどころを提供
英エコノミスト誌の選りすぐりの執筆陣が40年後の世界を幅広く分析する。 「40年前を振り返るのは、40階建ての建物の最上階から下を見るのと同じようなもので、めまいを起こしそうになる。非常に短い時間の中に、非常に多くの物事が詰め込まれているように思えるからだ。40年先を見据える場合、また違う感覚のめまいを覚える。むしろ、はるか彼方の青空をじっと眺めるのに似ている。視界は開け、果てしなく広がる一方で、これといった目標物はない。つかみどころがないのだ」 その意味で最初に取り上げられる人口動態は、ある程度確実な指標の一つと言える。 ・中国の人口は2025年に減少に転ずる。 ・2050年までの人口増加分の半分はアフリカ人が占める。 ・人口の増大は戦争に結びつくという仮説があるが、2050年にどれだけ人口が増加しようと、必ずしも暴力水準が上昇するとはかぎらない。 ・出生率は世界的に低下している。 ・出生率の変化が及ぼす世代間への影響には20年のタイムラグがある。すなわち、たとえ出生率が大幅かつ持続的に回復したとしても、高齢化のトレンドを逆転させるまでには、最低でも20年の時間が必要となる。 ・出生率の低下は、ある世代のみが突出して多いという現象を生み出し、その世代が年齢層のどこにいるかで、その国の経済が変わってくる。この出っ張り世代が子供から労働年齢に達したとき、その国は急成長する。これを「人口の配当」という。さらにその世代がリタイヤし、被扶養世代になると、その配当は負に変わる。 ・人口の配当が自動的に経済成長を創り出すわけではない。事の成否は、増大する労働力を国家が生産的に活用できるかどうかにかかっている。 ・これから人口の配当を受ける地域は、インドとアフリカと中東である。しかし、若年層の膨らみは政治的な不安定要困ともなる。若い労働者の増加は、成長の向上につながる場合もあるが、彼らが仕事にあぶれれば、社会の不安定性が進むこととなる。 ・ここから人口の負の配当を受けるのは、日本と欧州、そして中国である。ほかとは比較にならないほど人口動態の負の配当を受けるのは中国だ。安い労働力による世界の製造工場の役割を中国は終える。日本は世界史上未踏の高齢社会になる。 ・グローバル化と技術進歩によって、"物理的な距離の死"は起こったが、"文化的な距離の死"は起こっていない。人々の嗜好には地域色がいつまでも残り続ける。 ・無宗教者の出生率の低さとは対照的に、高い出生率による信者数の増加が、各宗派間のバランスを逆転させ、ひいては地域の宗教性を高めていくことになる。 ・二酸化炭素を増やす石炭も、そのすべてが天然ガスと置き換わってしまった場合、それまで硫化物の冷却効果によって受けていた恩恵が失われ、ひょっとすると2050年における気温上昇を大きくするかもしれない。 ・2050年までの間に最も大きな争いの種となるのは石油ではなく水であり、水不足と気候変動が、国際紛争や大規模な人口移動の引き金となるかもしれない。イエメンは、2015年までに水が枯渇する最初の国となる可能性があるとの指摘は、昨今の同国の状況を早くも予言しているようで興味深い。 ・2050年までの間に、中国では一党独裁国家ならではの脆弱性に直面し、インドでは複数政党制ならではの欠点と挫折に苦しめられるだろう。 ・防衛面では、中長期的に見ると、長距離以外の作戦行動の大部分は、さまざまな種類の無人機によって遂行される確率が高い。 「西側の政治制度は、内部でも二つの大きな危機に瀕している。パニックの危機と自己満足の危機だ。パニックは人々を臆病にさせる。彼らは強い指導者と手っ取り早い方法を望み、未来ではなく現在を懸念し、公益より私益を気にかける。パニックの原因として挙げられるのは、戦争や、テロや、あらゆる形の自然災害と経済危機。これらが発生したとき、政治制度は増強される代わりに、容赦なく弱点をさらけ出すこととなるだろう。 自己満足はもっと危険だ。自己満足が蔓延すれば、市民たちの積極行動主義は、自治体レベルでの雑事に呑み込まれていき、退屈な国政は優れた思索家たちを惹きつけられなくなる」
1投稿日: 2015.03.17
ぼくは物覚えが悪い 健忘症患者H・Mの生涯
スザンヌ・コーキン,鍛原多惠子
早川書房
人生を正常にしてくれると信じた医学に求められたのは、完璧な研究対象
重度のてんかん発作に苦しむ姿を見かねて、当時の最新脳外科手術を受けさせた両親に残されたのは、健忘症のわが子だった。確かに発作は激減したが、今日が何日か、朝食に何を食べたか、数分前に言ったことさえ思い出せない息子を背負うことになる両親。出会う人の顔も、訪れた場所も、日々のどんな経験もすぐに脳裏から消え失せ、亡くなるまで永遠の現在に閉じ込められることになった息子ヘンリー。彼はその後も人生を正常にしてくれる医学の進歩を待ち続けたが、ヒトの脳がもつ記憶のメカニズムを研究するための完璧な患者であり続けた男の物語。 不遇の生涯をひたすらウェットに追いかける感動ドラマを期待すると肩すかしに合うだろう。著者の視点はあくまでドライで科学者の視点なのだから。 「現在が刻々と過ぎ去っても、まるで足跡を残さないハイカーのようにヘンリーの記憶はなんの痕跡も残さない。そのような状態にある人は、どのようにして自分を自分と認識するのだろうか」。自分が何者であるかを示す豊かな感覚的、情動的な自伝的記憶に障害を持ち、ある出来事から別の出来事へ意識して時をさかのぼる能力に欠ける健忘症患者の自己認識は一体どんなものだろうか? 研究対象としてのへンリーの価値はますます上がっていった。「自分と同時代になされた科学的発見のなかで、へンリー研究と実は関連していることがわかったり、へンリーの研究によって裏づけが取れたりするものが実に多いことに、私たちは驚かされどおしで、ヘンリーの研究はわが研究室の名声にとってかけがえのない宝物だった」と著者は述べる。著者は、彼に対する研究や取材の窓口となり取捨選択も行なっていたため、「独り占めし、囲い込んでいる」と非難も受けた。 短期記憶のみで生きていくヘンリーは、意外なほど温厚で愛想が良かった。彼はつねにそのー瞬一瞬を生き、日常の出来事を満喫し、日々の多くのストレスと無縁でいられた。確かに長期記憶は生存に必要なものだが、時にそれがわれわれを苦しめ、重荷となっていることも気づかされる。これがあるばっかりに、心の痛みやトラウマ、問題をなかなか忘れさせてくれず、重い鎖で縛られる。ときに私たちは記憶に埋もれて生きるあまり、現在に生きることを忘れてしまう。 「日常生活で直面する不安や苦しみの多くが、長期記憶や、未来の心配や予期から生じるものであることを考えると、へンリーが人生の大半をほとんどストレスに煩わされずに生きた理由も見えてくる。彼は過去の思い出にも、未来への思い入れにも邪魔されずに生きた。長期記憶をもたずに生きるのは恐怖以外の何者でもないが、つねにいま現在を見据え、30秒という短く単純な世界に生きることがいかに開放感に満ちているか、私たちは心のどこかで知っている」 しかし記憶を奪われたへンリーは、人生で避けようのない別れを余人のように悲しんだり処理したりすることができなかった。大好きなおじの死を耳にするたび、彼は悲嘆に暮れ、やがて悲しみが薄れると、いつまたおじさんが訪ねてきてくれるかと母に尋ねるのだった。 「私たちの多くにとって、自分の個人史は自己を定義する根本的なものであり、私たちは過去の経験について思いをめぐらせたり、自分の物語が将来どのように進展するかを想像したりするのにかなりの時間を費やす」。ヘンリーは、過去を覚えられないのと同様に、未来を想像することもできなかった。彼は人生が前に進んでも自分史を構築することはできず、短期、長期の別を問わず心の中で時間を進めることができなかった。 「記憶を持つことで得られる大きな恩恵に、互いを知る能力、というものがある。私たちは共有された経験と会話をとおして関係を深めていく。そして記憶する能力がなければ、このような関係が紡がれていくのを見届けることはできないのだ。へンリーは生涯で多くの友人を得たものの、これらの関係の真の奥深さを感じ取ることはできなかった。彼は他者をよく知ることができず、悲しいことに、彼を知るすべての人 - そして全世界 - に自分が永遠に変わらない印象を与えたことを知らなかった」。
3投稿日: 2015.03.07
ザ・サークル
デイヴエガーズ,吉田恭子
早川書房
気鋭の作家が描くプライバシーが悪だとされる完璧な民主主義社会の姿
巨大インターネット企業「サークル」を舞台にした近未来小説。というより小説仕立ての予測シミュレーションと言った方が適切かも。きっかけはこれまで未整理で複雑だったユーザー情報を一つに統一したトゥルーユーの誕生と、お互いにシェアしあえば世界中の何百万のライブ映像にアクセスできる安価な個人用ライブカメラの登場にあるのだが、やがて社のトップは「秘密がなくなれば、人類は善になる」とか、「人類が経験しうるすべての経験への平等なアクセスは、基本的人権である」と宣言するまで至る。その過程に、なんら不自然な突飛さはない。 ただし同じような発想が日本でも生まれるだろうか?という問いは興味が尽きない。これはアメリカ、いやシリコンバレーという地でしか育まれない特有の思考形式だと思う。秘密は、「常軌を逸脱した行動様式の一部であり、反社会的で、非道徳的で、破壊的な行為を助長する」からなくすべきだし、すべての人のあらゆる経験にアクセスできることは必須で、自分の経験をオンライン上でシェアできないようにすることは、「知識の独占」で「わがまま」だという考えは、アジア人の間にも生まれまい。 透明性とオープンアクセスを信奉する会社で生き残るために、主人公のメイはキャンパス内で必死に努力する。 なにせこの会社は、ソーシャルであること、オンライン上のあらゆるアカウントで絶えず存在感を示しつづけることが、仕事の欠かすことのできない一部であるとする会社なのだ。一定レベル以上のコミュニティ参加が求められる職場というのは、まさに一昔前の社内運動会が盛んだった日本企業そのもののような気もするが。 ソーシャルネットワークとジャンクフードの類似性を指摘する箇所が面白い。社交的でないとなじられたマーサーが、問題は不自然に極端な社会的欲求を生み出す彼女の会社のツールにあると指摘し、他社との極度なコンタクトなんて誰も求めていないのになしで済ませられなくなるのは、科学的に塩分と油分が配合されたジャンクフードみたいなもので、「やめられない空疎なカロリーのソーシャルネットワーク版」だと言い返す。 マーサーはこの他にも、ソーシャルネットワークの進んだ状態を「誰にも強制されること」なく「自ら進んで自分を鎖に繋いで」しまう「社会的な自閉状態」と呼び、なるほど思わせる。 今年発売されるApple Watchがただのオモチャにしか思えないほどの究極なウェアラブル・デバイスが登場する。手首のモニターとつながるセンサーをドリンクと一緒に飲むことによって得られるデータは次の通り。心拍、血圧、コレステロール、体温の変化、摂取カロリー、睡眠時間、睡眠の質、消化効率、ストレス値、汗のPH値、血中酸素濃度、赤血球数、歩数、姿勢などなど。 しかし、自分についてのデータ収集が、やがてそれだけでは済まなくなり、他の人のデータまでも欲しくなり、それなしには足りないと感じてしまうような世界が、サークルが目指す完全化の達成した倒錯した世界なのだ。 何も持たず旅に出るなんてわがままで、非ソーシャルは自尊心の低さの現れだと主人公が詰られるシーンがあるが、新興宗教施設内での折檻や連合赤軍の総括を連想させ、なかなか恐ろしい。自分の趣味や興味を周りの人に知らせることは、自分の役割を果たすことにつながり、コミュニティの一部であることの不可欠な要素であるとする指摘は、一見まっとうに思えてなかなかに罪深い。 透明化したメイが自分は以前よりはるかに改善されたと感じる場面はなかなか興味深い。ついつい甘いものに手が伸びるダイエット志望の人にも、ついもう一杯と杯を重ねるアルコール依存症患者も、カメラによって常に見られて窮屈だという思いよりも、メイのようにカメラによって自分の振る舞いが矯正されたという感謝に変わるのだろうか?
2投稿日: 2015.03.07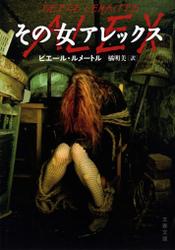
その女アレックス
ピエール・ルメートル,橘明美
文春文庫
やっぱり2014年度の1位はモートンの『秘密』だったと思う
例のごとく最初から疲れきった警部の登場でいつものあれかと嘆息したが予想は早々に裏切られる。 例えて言えば、玄関先に出てきた人が訪ねた先の家人かと思ったら実は泥棒で、さらにその家人まで犯罪に手を染めてるみたいな感じか。 前半で読者に植え付けられる、誘拐・監禁時の壮絶な暴力に耐える悲劇のヒロインのイメージが、後半になればなるほど効いてきて、明かされる真相の驚きを高めている。 タイトルの付け方も巧妙で、読者は読みはじめから警察が特定に難渋する被害女性がアレックスであるとわかっているのも、後半の謎の転換時に効果的だった。 ただしそれでもやっぱり、2014年度の"このミス"などの各賞の1位が軒並み本作で、ケイト・モートンの『秘密』を上回っていたのは納得しがたいものを感じてしまう。 読後感の悪さ云々ではなく、事件の真相に不自然なほど歪なあざとさが見られ、種明かしの後でどれほどの読書の楽しみがあったかを考えると、心もとなくなる。
2投稿日: 2015.03.06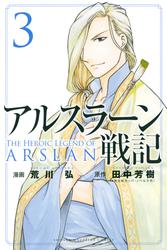
アルスラーン戦記(3)
荒川弘,田中芳樹
別冊少年マガジン
面白いのだが、描画で異和感も...
新作が出るのを楽しみにしている作品です。 荒川さんの漫画の特徴なのかどうかわからないですが、場面場面でセリフの文字の太さを適宜変えていて、とりわけ悲鳴や唸り声などは文字体すら変え、一層恐ろしげな印象を高めているのはさすがだと思いました。 ただいくつか描画の部分で気になった点もありました。 まず、馬の描写です。 アルスラーン王子がいる崖の上を目指して、カーラーン軍の騎馬隊が駆け上っていく戦闘シーンを見ていると、全体を俯瞰して多数の馬を描写する場面がより顕著なのですが、絵の拙さが目立たぬようにするためか、コマは小さく吹き出しの文字を大きめにしていて迫力に欠けます。 他にも、ファランギースとギーブの初対面のシーンでは、財宝の盗難の話になった時、ギーブがそれとなく自身の馬上の荷物を隠そうとする(と思われる)のですが、なんとも訳のわからない絵になっていて、脇に押そうとしているのかすら判然としません。
3投稿日: 2015.03.06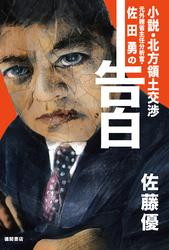
元外務省主任分析官・佐田勇の告白
佐藤優
徳間書店
小説としては青臭いが、日露の進むべき道は示される
1年前までの安倍・プーチン会談を含むこれまでの北方領土交渉の舞台裏が時系列で展開されるのかと期待したがそうではなかった。 著者自身が言う通り、本当の意味での情勢分析に必要な情報収集は外務省を辞めた2002年から更新されておらず、進んで表舞台に出ようとも思っていない。 これからの進むべき道は、東郷と元駐日ロシア大使の共同論文が示す方向で良いとし、自分はその障害になりそうな政治家や外務官僚を、自らの失職と裁判の報復がてら個人攻撃し、露払い役に徹している。 話は「〜か?」「そうだ」と問答形式で進み、小説としては青臭い。
2投稿日: 2015.02.12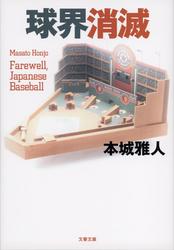
球界消滅
本城雅人
文春文庫
もしも大リーグが日本野球を吸収したら?
主人公にいま流行りのセイバーメトリクス的なデータ野球を得意とする若者を配し、もしも大リーグが日本野球を吸収したらという近未来小説、かと思ったらなかなかどうして。 通常この手のシミュレーション小説って、本筋とは別で起こるドラマ部分はありきたりでつまらないことが多いけど、なかなか読ませるし最後には見事に本筋と合流してる。 確かに本書の一番の読みどころは、牛島の仕掛けた合流構想の全貌とオーナー会議などで見せる巧みな説得、反対論の芽を摘み取る手札の数々にあるが、その過程でプロ野球界をとりまく状況も見事に映し出される。
1投稿日: 2015.02.05
イン・ザ・プール
奥田英朗
文春文庫
軽く読めるが印象も薄い
各話、一患者、一症状の連作短編集。 症例もありきたりで出てくる話題も少し古びた印象。 期待していた精神科医である伊良部と患者のやりとりは一方的で掛け合いが少なく、マイペースで自己中な伊良部のKY発言に患者が心の中で突っ込みを入れるスタイル。ここが笑い所なのだろうがちっとも面白くない。 共通する治療方針は患者の症状を押さえ込むのではなく、むしろ放置あるいは助長させ、患者自らに改善の糸口をつかませるものだが、この展開も予想を超える話は出てこない。 秀逸な表紙絵の方がよっぽど読者の想像をかき立てる。
0投稿日: 2015.01.21
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
