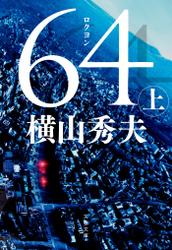
64(ロクヨン)(上)
横山秀夫
文春文庫
第3の道。それは選ぶものではなく、すでに踏みしめてるものなのかも。
警察内部での不穏な空気。先鋭化する刑事部と警務部の対立。 降って湧いた長官視察の真の目的は? 被害者遺族はなぜ慰問を謝絶するのか? それらの謎を繋ぎ解き明かす「幸田メモ」の存在。 主人公は自らをゲームの盤上の駒だと自覚する。 「警務部の犬でいい」と腹を括ったかと思えば、古巣の刑事部に矜持と未練を覗かせ揺れ動く。 その狭間で苦しんでいた三上にようやくジレンマを超える光がもたらされる。 平日に手を出したのがまずかった。これは明日が一日休みという時に、誰にも邪魔されず、時計の針も気にせず、没頭できる時に読むべき本だった。
2投稿日: 2015.05.21
スタンフォード大学で一番人気の経済学入門 ミクロ編
ティモシー・テイラー,池上彰,高橋璃子
かんき出版
すべてのトレードオフを考慮に入れようとする姿勢を学ぶ
これから経済学を学ぼうとする人たちだけでなく、ごく一部に過ぎないグループや個人にスポットを当てた毎日の経済ニュースに一喜一憂し、顔の見えない統計上の人びとにも想像を広げるセンスを欠いた人たちにとっても、貴重な気づきを与えてくれる本。 学問としての難しさよりも、その舵取りの慎重さや繊細さに思いが至る。 通底しているのは、 「ものごとにはトレードオフがある」こと、 「誰かを助けようとすれば、別の誰かが傷つく」こと、 「何かを選ぶことは、何かを捨てること」だという考えで、 「あらゆるものを完璧に満たす社会はない」のだから、より不断の判断や調整が求められていることがよくわかる。 「経済学は、貧しい人びとの敵ではありません。自由市場を絶対視して、あらゆる介入を否定するものでもありません。 どのような介入が望ましいかについては、経済学者のあいだでもさまざまな意見があります。しかし、意見の対立を超えて共通しているのは、あらゆる政策について、すべてのトレードオフを考慮に入れようとする姿勢です」 取り上げられるトピックは豊富な事例に富み、対立する論点を手際よく整理し、政策にかかるあらゆるコストを明示する。 セーフティネットの必要性の議論では、貧困対策につきまとう葛藤に触れ、求められるのは「入りにくく抜けだしにくい」ハンモックのようなネットではなく、空中ブランコのような「落下を広く受け止めてくれるけれど、すぐに跳ね上がれるような弾力性のある」安全ネットであると指摘している箇所が印象に残った。 レビュー時点(2015年4月)のニュースを見てると、フランスで見習い従業員に支払われる給料を国が1年間肩代わりすることを決定したという。 これまで見習いの数は年々減少していたが、中小の経営者は「タダなら雇う」と、増加に転じる見込みらしい。 直接の賃金対策ではなく、労働者の教育訓練に投資するというやり方は、悪影響の少ない支援のあり方ではないか? 本書を読みながらこれまでより深くニュースが理解できるようになった気がする。
6投稿日: 2015.04.23
半身
サラ・ウォーターズ,中村有希
東京創元社
"このミス1位(2004年)"の作品なのでとりあえずオチまでは、と歯を食いしばって読んだが...
ひたすらわがままで身勝手な主人公の行動にイライラさせられ、囚人シライナとの心の交流にも共感できないままだったので、何が多くの読者をこれほど引きつけたのか理解できなかった。 もしかしたら英国貴婦人のみだらな日記物としてではなくコン・ゲーム物として愉しんでいるのだろうか? この当時の降霊術の流行を知っていたのでその辺りは面白かったが、「お父さんは癌で亡くなった」との記述を読んで時代考証も中途半端だなと思った。
0投稿日: 2015.04.16
ビスマルク ドイツ帝国を築いた政治外交術
飯田洋介
中公新書
政治家の動機と結果について考えさせられる本
ドイツ帝国の創建という輝かしい政治的業績が実は、本来彼が目指してきた政治的スタンスと大きく異なっていたことが明らかになる。 また彼の外交手腕も、カリスマとして神聖視される割には状況に応じた「急場しのぎ」の連続で、絶体絶命のピンチも時々の外的状況の変化で運良く脱し、とりわけ内政面では必ずしも彼の思いを実現することは最後までできなかった。 プロイセン君主主義を奉じ、伝統的な権益に執着する田舎ユンカー政治家が、十九世紀最大のドイツの政治家になるまでの軌跡は、圧倒的に面白い。 もともとはドイツ帝国の樹立よりもプロイセンの大国化を目指していた。 伝統的なプロイセン主義者であるはずが、それと相反するドイツ・ナショナリズムの祖となるのだからなんとも不思議。 外野から見れば、明らかな矛盾や変節が、本人からすれば極めて自然な発展的融合であったりするのは、政治家や歴史を見ていく上で大切な視点であろう。 超保守主義者にして、ニューディールの辛辣な批判者だったマッカーサーが、日本では若いリベラルなニューディーラー・グルーブに熱心に頼り、戦後日本の形成に驚くばかりの自由を与えていたのも思い出された。 ビスマルクの「動機をめぐってはこれまでに幾度となく歴史家たちの頭を悩ませ、様々な解釈が登場して」いて、折に触れて著者は「的外れ」「一面的」だと批判するが、その割には出てきた新説は良いとこどりで目新しさに欠ける。 そもそも編集部から、初めてビスマルクを知るかもしれない読者に向けて書いてほしい、と注意を受けたにもかかわらず、現代にビスマルクの生涯を蘇らせることに失敗している。 紙数が限られているにも関わらず、各章こどにいちいち「先行研究」を紹介し、そのくせ最愛の妻にして、亡くなれば「パパもすっかりダメになってしまう」と言われたヨハナも、最期にさらりと触れる程度。 医者の通告も聞かずに暴飲暴食の限りを尽くしてきたとか、彼の声の「高さ」といった人間的な側面は本文に落とし込まず、あとがきまで待たねばならない。 辞任の一報は、イギリス首相をして悲痛の念を覚えさせ、国際社会に将来に対する不安感を感じさせたらしいが、同時代のビスマルク評をもっと読みたかった。
4投稿日: 2015.04.09
なぜ時代劇は滅びるのか(新潮新書)
春日太一
新潮新書
実名批判だけでない、「時代劇」再興に懸ける熱情の面白さ
時代劇とは「現在と異なる世界を描くファンタジー」である。 そこで大切なのは「ウソを本当に見せる技術」で、時代劇の芝居にはある程度の「作り込み」が必要だ。 役者が「昔の人っぽく見える」ことと同時に、「現代人が違和感なく受け止められる自然」な芝居でなければならない。 今後、問題になるのはこの「現代人」の部分だろう。 史実を改変しすぎてほとんど創作と化した大河ドラマの一定の支持を見ていると、著者などを筆頭に古き良きコアな時代劇ファンは、ますます眉をひそめることになりそうだ。
3投稿日: 2015.04.09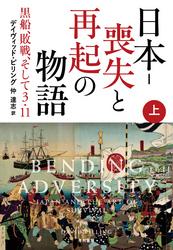
日本-喪失と再起の物語 黒船、敗戦、そして3・11(上)
デイヴィッド・ピリング,仲達志
早川書房
知日派経済記者の目に映る現在の日本の姿
著者は、3・11の震災直後に「日本の奇跡は終わっていない」と題する記事を全世界に配信した経済記者で、自然の破壊力とそれに応じた日本人のイメージを手がかりに、これまでに奇跡を生み出し続けてきた日本人が今回も「災い転じて福」となせるかに期待を寄せてきた。 本書では「将来の日本がどうあるべきかではなく、現在の日本が私の目にどう映っているか」が主題となっている。 あらゆる否定的な意味が込められた「日本化」など、海外で繰り返される悲観的な日本像には組せず、行き過ぎた誇張を否定し、見過ごされてきたものを提起している。 タイトルから受ける印象とは異なり、日本人を賞賛したり励ましたりする内容ではない。 第4章の論述には首肯しがたく、海外の日本像と、日本人の持つ自己像との乖離が感じられた。 ここでは、なぜ日本は戦争に向かったか、それは近代化の不徹底と、個人尊重や主権在民が顧みられず前近代的な天皇崇拝に回帰したためとし、明治維新を必敗自滅の始まりとしているが、著者の言う「奇跡」もここに端を発するのではなかったか?
2投稿日: 2015.04.09
任天堂“驚き”を生む方程式
井上理
日本経済新聞出版
DSやWiiが大ヒットし、快進撃を続けていた頃の話
Appleとの比較も随所に出てきて、存命であったジョブズとの対比は面白い。 意外なことに、カリスマ&ワンマン経営者の存在や業績の推移まで瓜二つだった。 任天堂は、山内という1人のカリスマから、岩田・宮本などの集団指導体制にうまく移行できたようだが、アップルも、ジョブズというカリスマから、数字のクックとデザインのアイブといった体制に変わってきている。 任天堂の山内やアップルのジョブズがそうであるように、成功するワンマン経営者の資質で重要なのは直感力だろう。 それは天賦の才というのもあるが、何度も会社を危うくするほどの失敗を重ねてきて身に付いた才でもある。 社員の顔色ばかりうかがっていては、盛大なちゃぶ台返しもできなかっただろう。 任天堂が今後も成功し続けるかはわからない。 終章で紹介されている電通との提携だとか、いろいろなサービスの提供とか、少し手を広げ過ぎではないかと不安にさせるものがあった。 本の題名については少しイチャモンを付けたくなる。 サブタイトルの「"驚き”を生む方程式」というのは、本の内容だけでなく任天堂の社是からも乖離している。 また、もともとベースが雑誌の記事が主体になっている為か、読みやすいけど、少し物足りなさも感じた。
1投稿日: 2015.04.09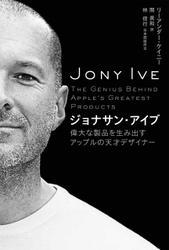
ジョナサン・アイブ 偉大な製品を生み出すアップルの天才デザイナー
リーアンダー・ケイニー,林信行,関美和
日経BP
「アップルにとってはスティーブの死よりジョニーが辞める方が深刻だ」
何という早熟だろう。 デザイン賞の授賞式のため大学の初日に出席できず、インターンとして働いた大手デザイン事務所では、給料取りのプロのデザイナー連中を押しのけ、すべての仕事を回される。 父親の薫陶やイギリスのデザイン教育の賜物もあるのだろうが、持って生まれた才能が最初から飛び抜けていた。 彼が卒業課題で作ったチューブ型電話を見てブルーナーは、「あれほどの美しい作品を製作し、その上すべてを計算しつくしている学生なんて、見たことがなかった」と舌を巻く。 ブルーナーはその後、三顧の礼ならぬ四顧の礼でもって彼を引き抜いた。 ヒトラーのお抱え建築家と言われたシュペーアも、ヒトラーと二人きりで何時間もベルリンの再開発について語り合い、周囲から「恋人同士」と揶揄されたが、ジョブズもしょっちゅうアイブのスタジオを訪れ、「一心同体」の関係にあった。 その後シュペーアは軍需大臣に抜擢され兵器製造の効率化に目を見張る貢献をすることになるが、アイブの今後はどうか? 営業には関心を示さず至高のデザインを追求する彼を、ハードウェアとソフトウェア両方の責任者に据えたのは吉と出るか凶と出るか? アップルに入社したアイブのリーダーとしての資質は際立っていた。 仕事に真摯に向き合い、真面目で優しく、部下思いの兄貴分的存在。 一見、物腰の柔らかな英国紳士だが、なわばり争いは容赦がなく、ルビンシュタイン、ファデル、フォーストールを次々と追い出す。 ジョブズの操縦法も心得たもので、プレゼンの仕方から情報操作まで、「ジョニーのほうがスティーブを動かしていることが少なくなかった」との証言もあるほど。 今後、懸念されるのは本書にもある通り、アイブを頂点とするデザインチームの極端な閉鎖性だろう。 結束が固く、家族ぐるみの付き合いだが、新陳代謝が少なく、新しい風を呼び込みにくい。 年代が比較的近かったため、若さが懸念される欠点を補ってきたが、今後は揃って年を取るため不安が残る。 また、年々膨れ上がる研究開発費の問題もある。 「デザイナーたちに費用なんて考えほしくない」という一語を目にして、ジョブズがクックをトップに据えた理由が納得できた気がした。
3投稿日: 2015.04.05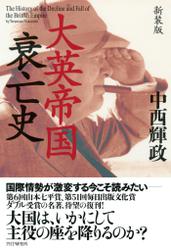
新装版 大英帝国衰亡史
中西輝政
PHP研究所
複雑で特異な「イギリス精神」から学ぶあるべき国家政策の行方
数ある大国興亡論の中で、本書はエリートの価値観や精神構造が及ぼす影響を重視している点が特長である。 「とりわけ国際社会における大国の盛衰に関して、従来重要視されてきた、国力や体制のあり方といった構造要因以外に、その国の指導者や国民の発想や思考様式といった精神的条件こそ、長期にわたる興隆と衰退の歴史の決定要因として今日、一層深く検討されるべき時代が到来しているように思う。少なくとも、力や体制による支配が大幅に抑制された、大英帝国という特異な支配・覇権のあり方を考えると、こうした精神的諸条件の重視はともかくも避けられないアプローチであるのである」 大英帝国とは「威信」のシステムであり、限られた資源によって効率的に支配するとための「威信」という精神的要素には、国内社会における貴族のリーダーシップが密接に関わっている。 「パクス・ブリタニカ」を支えたのは、優越した海軍力や経済力といった「イギリス自身の力」と、常に国内での革命に脅え続けた「他の欧米諸国の内在的弱さ」、「外交上手」の3つの柱があった。 とりわけ最後の「外交政策」が特徴的で、「自制」と「勢力均衡」を基本とした「宥和」による支配は、その背後にある複雑な特異さをもつ「イギリス精神」を解明しないかぎり理解しえないだろう。 イギリス外交文化はエリザベス時代に完成され、「イングランドの外堀」である「低地=ネーデルランド」へのフランスとスペインによる脅威に対して見せた、「正義の操作」と「決然たる日和見」を旨とする「エリザベス外交の精神」は、いまなお「模範」と讃えられるものであった。 「差し迫った脅威と、他方に横たわる潜在的脅威の双方に対して、意識と判断をともにオープンにしておく。このような、じっと事態の中で『自らを持する』ことの心理的・精神的制御は、外交指導者に第一に求められる心性として学びとられることになった」 最近の関連書としては、英国衰退の原因をつくったチャーチル見直し論につながるブキャナンの『不必要だった二つの大戦: チャーチルとヒトラー』、小説だが古き良きイギリス的妥協が学べるル・カレの『繊細な真実』、アングロサクソン人の変化に対する態度を分析したミードの『神と黄金 イギリス、アメリカはなぜ近現代世界を支配できたのか』がある。
2投稿日: 2015.03.27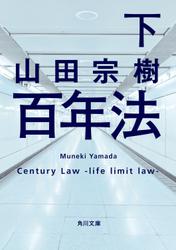
百年法 下
山田宗樹
角川文庫
不老化技術と寿命制限法によって成立する近未来の姿
下巻だけに限ってみれば、ある独裁国家と反体制派との間の闘争とその顛末が描かれ、上巻で精緻に練り上げられた、不老化技術と寿命制限法によって成立する近未来の社会構造や親子関係(120歳以上の母親が今生の別れに息子と床をともにし、自分の友人を恋人にしなよとアドバイスするシュールな展開)のドラマをもっと読みたかったな。 昨今の決められない政治に対する我々共通の不満をくみとる下巻のストーリーはそれはそれで楽しめるのだが、せっかく希有壮大な空間に足を踏み入れたのに最後になじみのドアから出てきたみたいで、残念この上ない。
0投稿日: 2015.03.26
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
