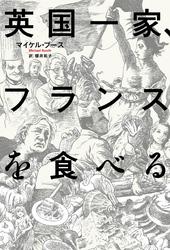
英国一家、フランスを食べる
マイケル・ブース,櫻井祐子
飛鳥新社
来日前に著者が、大切にしてた料理本を捨て、フランス料理の世界に飛び込んだ体当たりルポ
日本編では、イギリス人らしいユーモアとともに日本食を食べまくったフードライターが、今回はパリで名門の料理学校に入学してフランス料理を食べまくる。 おそらく落ちこぼれだろうと思ったら、意外に優秀な生徒で驚いた。 ただ、如何せん馴染みのないフランス料理なので、描写からすぐに連想ができず残念。 写真が豊富なら良かったし、もしこの映像ドキュメンタリーがあればそれも見てみたいが、彼の文体の醸す独特のゆるさが損なわれる気もする。 「料理は感性だ」と言う熱血教官や、オマール海老のトドメをさすのにオロオロする生徒たちの様子など、まるで教室内にいるみたいな気分にさせる。 鋭い観察眼は今回も健在で、気に入ったフランス(料理)評をいくつか。 「なんといってもフランス人は、自ら危機を生み出し、それをやりすごすという、とてつもない能力をもっている」 「フランス人は歴史を通じて、外から押しつけられたどんなルールも涼しい顔でくぐり抜けてきた」 「フランス料理が世界的優位を誇ることができたのは、フランスの王たちの大食いのおかげ」 「パリは年寄りのための街」 「パリはファッショナブルとはほど遠く、むしろ社会によって厳格に定められた"制服"がある」
2投稿日: 2015.11.21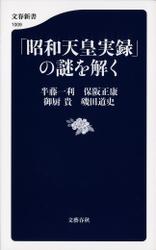
「昭和天皇実録」の謎を解く
半藤一利,保阪正康,御厨 貴,磯田道史
文春新書
まったく違う「顔」を見せる『昭和天皇実録』の読み解き
4氏揃っての対談ではなく、注目していた磯田氏は最初の2章のみで残念でした。 とはいえ実に示唆に富む指摘が続々となされています。 まず、軍部独走の起源は長州藩にあるという指摘にはハッとさせられました。 下が独走して上を従わせるというのは、長州とその派生体である陸軍に共通する構造でした。 また実録から、二・二六事件に便乗した石原莞爾の反革命構想や、近代的とは程遠い神的なものを強く内面化された昭和天皇の姿、さらには大東亜共栄圏の嘘まであぶり出しています。 これがもっとも驚いたところなのですが、実は天皇も、松岡のソ連を巻き込んだ四カ国同盟の大構想を承認していたという、これまでの「松岡悪人説」の見直しも迫っています。 とはいえ本書では、実録に「天皇の五感に触れる記述が少ない」という不満の表明もしっかりとなされています。 当然ながら天皇の立場から書かれているので、政治的配慮を要するものを巧みに避けながら、責任の追求に及びそうな都合の悪い部分は省かれているようです。 ただ、決して嘘が書かれているわけではないので、これからの歴史家には、底本となりこれまで幻とされていた資料の公開請求と合わせて、こうした書かれなかった部分の解読という作業が残されていると思いました。
0投稿日: 2015.11.20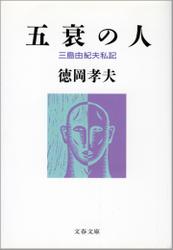
五衰の人 三島由紀夫私記
徳岡孝夫
文春文庫
なぜ彼は決起し、死なねばならなかったのか?
三島由紀夫が信頼し、最後の「檄」を託されたジャーナリストの手による評伝で、発表時ずいぶん各紙で取り上げられたが、いまなおその評価は揺るがない。 著者は、三島の自衛隊体験をこう解説している。 「一口でいえば、命令と規律によって行動が縛られる不自由な秩序の中に、三島さんはかえって自由を実感した。枠をはめられた制約によって曲げられることにより、それを跳ね返そうとするバネのたわみを、筋肉だけでなく胸の内に感じたのではないだろうか」 自衛隊の決起を呼びかけた後に割腹自殺をした事件の真相については、 「私は、三島さんと励まし励まされ合い、引きずり引きずられつつ、のっぴきならぬ結果に到達した原動力の一半は森田氏にあったという印象を、今も捨てきれない」 と、森田必勝氏の主導権を指摘し、当時おおいに驚かされた。
1投稿日: 2015.07.17
亜人(6)
桜井画門
good!アフタヌーン
「じゅわっ」と出てくる黒い幽霊の様のおもしろさ
佐藤による要人襲撃を待ち伏せるため、主人公たちは秘密キャンプで作戦を立て話し合う。 訓練や、オグラによる黒い幽霊(IBM)のレクチャーなどもあり、劇的に話は展開しない。 作者はここではむしろ、今後のクライマックスに向けて登場人物のキャラクターの肉付けやその後の伏線を展開することに注力している。 泉が戸崎の部下になるまでの過程と、刑務所で新キャラ琴吹が海斗に信頼を寄せ、脱獄の手伝いを約束するまでが描かれるているが、ドラマとしてはありきたりな流れで目新しさはない。 「ウザいよ、バカか、違う、超バカなんだ」という三段論法は、昨今よくある「中途半端ではなく極端なヤツこそスゴい」というテーゼにひたすら忠実。 逆に泉がどうしてそこまで戸崎に信頼を寄せるようになったかはよくわからない描かれ方。 1巻では、アゴで使われている感じだった関係性からするとちょっと軌道修正がかかった感じにも読めた。 それでもこの巻は前巻より面白い。 絵や構図もだんだんうまくなってきて、時に大友克洋チック。 (ただ戸崎の絵はなかなか安定せず、最初のシーンは情けないくらいカッコ悪い)。 一番に気になったのは、頻繁にキャラの目元にフォーカスを当てる所で、コマもそれを意識して効果的に演出されている。 全巻を通して、亜人で一番気に入っているのはIBMが出てくるところで、本巻でもオグラが「出してみろ」と挑発され圭が黒い幽霊を出すシーンはたまらない。 「じゅわっ」と恐ろしく登場しているのに、次のコマではオグラに無理な要求をされて首をかたむけて途方に暮れた様子はおかしくていい。 連続で何体も出すことができたり、IBM同士の衝突時の消失条件や、性格の反映など、今後のバトルに生かされるはずのゲームのルールが次々と出てくるので見逃せない。 最後にReader Storeに注文。 作者は最後のページで、アシスタントの方がどのページのどのコマの線画などを担当されたかを詳しく列記されている。 ただそれを読もうと思っても、字がつぶれて読めなくなっている。 容量の問題もあるので難しいとは思うが、大事な部分などでなんとか読みやすくなるよう工夫していただけるとありがたい。
3投稿日: 2015.07.15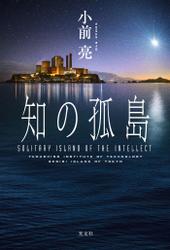
知の孤島
小前亮
光文社
最先端のエリート大学を舞台にした異色の学園ミステリ
著者が自身のブログで「ぱっとしない作家」の30冊目の作品とあるが、なかなかどうしてかなり読ませる。 各章すべてに「知」が含まれ、タイトルも「知の孤島」と、現在の大学をめぐる成果主義や学際性なども取り入れた時機にかなった作品。 知は金に変えてこそ価値があると考える大学側と、知は知だけで価値があると信じる学生側との闘い。 学園ミステリとしては思わぬ拾い物だと思う。 ただ、優秀な学生たちがそれぞれの得意分野を生かして戦う相手が少し役不足で、バランスが悪いような...。 冒頭でもう少し犯人の狡猾さを描いて、挑みがいのある肉付けをしてほしかったし、もっと言えば堅田の先輩を死に追いやった張本人という設定でも良かったような気がしてならない。
2投稿日: 2015.06.25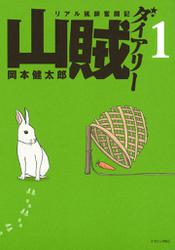
山賊ダイアリー(1)
岡本健太郎
イブニング
読むと狩猟に同行したくなる魅力的な物語
著者の描きたい狩猟の実態や解体・調理の知識が淡々とエッセイ風に綴られ、そこまでの前振りとなる導入部もなくいきなり物語の幕が開く。 基本的には、初心者である著者が狩猟免許や猟銃をはじめて手にし、狩猟生活をスタートさせる様子が描かれるが、もともと射撃の腕も良く、解体や調理もそつなくこなすので、いわゆる失敗や挫折の連続や、師匠の薫陶を受けるという展開には至らない。 主人公を含む主要登場人物も今後おいおい紹介されていくのだろうが、いかに猟師という職業が孤独なのかが1巻にしてよくわかる。 害獣の実態やその背景、外来種や絶命危惧種などにも目端のきいた物語となれば、物語世界はさらに厚みを増すが、このシンプルな朴訥さは失われるかもしれない。 今回は、99円セールであったため購入したが、120ページで正価500円以上というのは、なかなかいい値段だなと思った。
0投稿日: 2015.06.25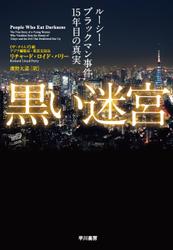
黒い迷宮 ルーシー・ブラックマン事件15年目の真実
リチャード ロイド パリー,濱野 大道
早川書房
外国人として日本で生きる独特の感覚を追体験する
一読すればいかにこの事件が、内に型通りの報道では収まりきらない「迷宮」を抱えているかがよくわかる。 「非常に入り組んだ」「異様で不合理な展開の連続」は、被害者の殺害を起点にも終点にもとらず、いまも解きほぐせぬ謎を残し、事件に関わった人たちの関係を分断する力となって伝播していった。 著者は、フィクションで用いられる物語の手法を駆使しながら、悲劇的な最期を迎えるまでのルーシーの人生を丹念に描く。 冒頭のカラスの鳴き声によって呼び起こされる「異邦感」が印象的で、読者は知らず知らず「ガイジン」の視点から事件を振り返る。 注目度の低くありふれた事件とならず、ルーシーが一人の不運な若い女性から、いかにしてある種の"被害者"の象徴となり得たか? そのキッカケの1つに、彼女の父親ティムの存在が大きかった。 記者や周りの人たちが求める役割を超越し、冷静で淀みなく悠然と受け答えする彼の挑戦は、イギリス人に自分たちの純真無垢な娘が被害に遭ったと感じさせることに成功し、やがて日英のみならず全世界の報道に影響を与えはじめる。 結果的に彼は、事件の構図のコントロールには成功したが、自身のイメージのコントロールには失敗している。 単なる事件ルポにとどまらず、日英の比較文化論とも読める本書は、犯罪報道に興味を持つ読者だけでなく心理学や社会学を専攻する読者にも必読の書。 ただ日本の警察に対するやや厳しすぎる見方には意見が分かれるかもしれない。 事件が起こる前に織原の蛮行を立件していれば彼女は死なずにすんだかもしれないという著者の見方に異議はないが、日本の犯罪率が低いのは、警察の能力が高いからではなく、日本人の遵法精神のおかげと見るのはいかにも一面的だ。 事件に至るまでのルーシーの行動は、著者の大胆な推理も加えて、ミステリー小説風に実に細部まで再現されているが、肝心の殺害から隠蔽までの経過は十分な裏付けが得られず、再現を断念している。 ひとつ疑問に思ったのは、織原の「征服プレイ」を映したビデオで、あれほどの汗かきでハンカチを手放させない彼が、覆面したまま何時間も休まず動き回わるというのは、何らかの注釈があっても良かったのではと感じた。
2投稿日: 2015.06.24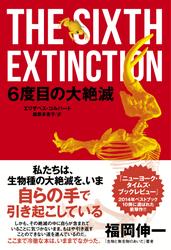
6度目の大絶滅
エリザベス・コルバート,鍛原多惠子
NHK出版
人がこの地上に出現した時「生存の条件」が変わった
「地球上の誰かがふと思った。『生命の未来を守らねば・・』」 漫画『寄生獣』の有名な冒頭シーンだが、本書でも「人類は最も成功をおさめた外来種」であり、人がこの地上に出現した時、地球上の全生命体の「生存の条件が変わった」のだと説く。 大海原を躊躇なく漕ぎ出す狂気の遺伝子を持つ現生人類は、はるかに大きく頑強な大型生物やネアンデルタール人などを絶滅させ、人間の移動がなければ維持された種の地理的分離を元に戻し、あげく海の酸性化や地上での大変動に影響を及ぼす。 いま、これまでとは質的に異なる、何か特別なことが進行している。 しかし事はそう単純でもなさそうだ。 理論と現実が食い違うことはままあるし、予測が観測と一致しないこともよくある。 人間のやること、観測の限界は避けられない。 いまも「何千何万という新種が人知れず成育していて、正式な分類を待っている」のだ。 しかも、絶滅には時間のかかるものもあるし、破壊で失われた生息地の再生も考慮に入れる必要がある。 そう、自然はしぶといのだ。 「現実はいつももっと複雑」という一文は思い上がりをくじき、謙虚にさせてくれる印象的なフレーズだ。 それにしても本書は生命を新しい視点から見るきっかけを与えてくれる。 18世紀の終わりまでは、絶滅というカテゴリーは存在せず、まったく自明の概念ではなかったというのも、あらためて考えると驚きだ。 その転換となったのがマンモスなどの奇妙な骨の発見なら、現代ならさしずめ1隻のスーパータンカーやジェット機の出現が引き起こす転換も凄まじい。 グローバル化が数百万年かけて進行した地理的分離の巻き戻し、「新パンゲア大陸」の形成過程にあるという指摘は強烈だった。
7投稿日: 2015.06.14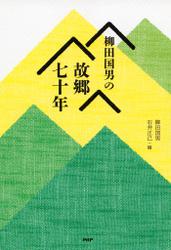
柳田国男の故郷七十年
柳田国男,石井正己
PHP研究所
読む人に不思議な感を与える書
本書の「ある神秘な暗示」は、講演「信ずることと考えること」で小林秀雄が紹介し、蝋石の珠を見た時の柳田の感受性に心打たれた場面だが、一読した印象では彼の異常心理の経験そのものより、祠の中がどうなっているか知りたいという飽くなき好奇心の方が、後の民族学につながったような気がしてならない。 他にも彼の抜群の記憶力、特に一度見た景色を決して手放さず、ガス灯のともる夜明けの東京や、西洋人が海水浴をしていた明石の海、利根川の白帆などの回想は瑞々しいほど新鮮だ。 法制局など道々で知った珍しい話をしゃべりたくてたまらない性質も彼の学問に欠かせなかったようで、仲間の小説家に数々のネタを提供したことを明かしている。 本書のタイトルから、語られるのは故郷の兵庫県を中心にしたものかと思っていたがそうではなかった。 柳田は小さい頃から転々としているので、故郷を離れて70年の節目に自身の生涯を回顧する体裁になっていて、神戸新聞に201回に分けて寄稿された聞き語りを編者が初学者向けに抜粋編纂している。 いままで敷居が高く敬遠していた読者にも手に取りやすく、大変読みやすくなっている。 ただ、思いのまま連想の赴くままに従った語り口は、時に主旨がよく飲み込めず、先に進むこともチラホラ。 あとがきもそうだが、特に序文が変わっていて、母の思い出から序文らしく本書全体の見通しが語られるのかと思いきや、自由という言葉の伝来で話が終わっている。 読む人にこれほど不思議な感を与える書も珍しい。
1投稿日: 2015.06.10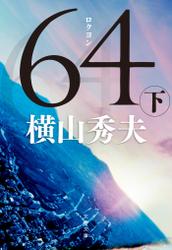
64(ロクヨン)(下)
横山秀夫
文春文庫
警察だけの問題ではない、情報の統制とあるべき未来の「安全」の形
物語の中心は、情報が一元的に集まる窓口でありながら、内部からもっとも切り離され「離島」と化した広報室。 実名公開をしぶり、情報をコントロールしたい警察上層部。 上から何も明かされないまま会見に臨み記者から集中砲火を浴びる担当者。 「匿名の壁の向こうでは、どれほど奇天烈な作り話も命を得られる」。 原発事故の東電会見も修羅場だった。 2号機タービン建屋でのありえないほど高い放射線測定値。 発表数値を取り消し、データ確認のためと、1日の会見回数を4回から2回に減らそうとする。 反発する記者たちとの押し問答。 共通するのは、役割の明確化と外部化。 生活圏から切り離し、つながりを細くし、幻想を抱かず「機能」のみを期待する。
3投稿日: 2015.05.21
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
