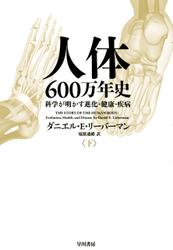
人体六〇〇万年史 下──科学が明かす進化・健康・疾病
ダニエル・E・リーバーマン,塩原通緒
早川書房
現代環境の変化に身体の適応が追いつかず起こる「ミスマッチ」病の深刻さ
農業や産業革命は、人類全体にとって大いなる恵みだったが、人体にとっては複雑な恵みだった。 確かに暮らしは豊かで便利で快適になったが、同時にすべての人間の身体に決定的な変化をもたらした。 健康に関するパラドックスとして、長生きできるようになったが、慢性病で長患いすることも多くなったと言われる。 つまり、食物の量は豊富になったが質は低下し、死亡率は下がったが罹患率を上昇させた、と。 著者は、こうした環境の変化が今日いかにわれわれを進化的なミスマッチによる病気にかかりやすくさせているかについて、読者の目を向けさせる。 エネルギーの摂り過ぎや、生理学的な負荷の不十分さなど、現代環境の新しい側面が原因で生じるさまざまなミスマッチ病。 単に目の前の病に対処するだけでなく、その予防の重要性を強調するが、同時にその裏で、人々の衝動や無知を食い物にする食品業界や、病人を生かしておける環境を作ることに腐心する製薬業界の存在も明かし、食習慣の継続的な改善と合わせて、問題の解決の困難さも指摘している。 しかしこうしたミスマッチ病の環境的な原因を放置することは、いつまでもその病を蔓延させ、悪化させることにもつながりかねない。 このあたりの、ミスマッチ病を誘発する環境条件が、文化を通じてそのまま子供に伝達されていく様は、技術的、経済的、科学的、社会的な変革の総体が、いかに人間の身体に大きな影響を及ぼしてきたか、改めて考えさせられた。
5投稿日: 2016.01.31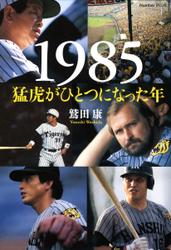
1985 猛虎がひとつになった年 (Sports Graphic Number PLUS(スポーツ・グラフィック ナンバー プラス))
鷲田康
文藝春秋
すべての野球ファンにとっての「1985」
虎党ではないので、何が特別なのか疑問だった。 1984ではなく86でもなく、なぜ1985なのか? しかし読み終わると腑に落ちる。 「あぁこれはすべての野球ファンにとっての1985なのだ」、と。 本書によれば、「伝説のバックスクリーン三連発」も正確には「二連発」らしい。 しかもこれが優勝の大きなポイントになったというわけではない。 (ただし、いつもスロースターターなバースが開幕早々から爆発するきっかけにはなったし、抑えの二本立てが確立した試合でもあった。) 監督の采配は「もう無茶苦茶で何が何だか分からない」とこぼされるほど我慢を知らない投手起用で、マウンドで交代を告げるときに明日の先発も託す吉田に、バースも「Oh、No」と天を仰ぐシーンは笑った。 ともすれば短気で兄貴肌の吉田が、ベンチ内での采配批判にも寛容に構える親父的存在に成長する様は面白い。 なかなか「優勝を目指せ」と口にしない吉田が、選手揃っての直訴を受け入れ、ミーティングでハッパをかけるシーンは感動的だ。 ただ中でもすごいのは、シーズンわずか5本しかヒットを打たなかった川籐をベンチに置き続けたことだ。 選手個々の実力は高いのに、あと1勝が勝てず、内紛に明け暮れ、やることが個々バラバラの阪神をひとつにする魔法の鍵は、首脳陣と選手をつなぐまとめ役を置くことだった。 「選手の気持ちをひとつに」、とはよく言われるフレーズだが、選手の顔を、喧しいファンや不実なフロントではなく、個々の成績でもなく、まずはチームに向かせること。 チームが勝つために、同じ方向を見る。 そのために、まとめ役は不可欠で、川藤ほどの適任者はいなかった。
2投稿日: 2016.01.17
驚きの皮膚
傳田光洋
講談社
システムにまきこまれていく人間が最後に求めるもの、それは皮膚感覚
前半では、人間の皮膚が単なる界面ではなく、「環境の情報を感知し、ある程度の情報処理を行い、さらにそれに基づいて、適切な指令を全身、そしてこころにまで及ぼしうる」機能を持った境界であると説く。 つまり、この境界には知能が存在しているのだ。 さらに後半では、皮膚感覚から得られる膨大な情報を、意識や無意識、システムと対比させながら、いかに私たちの全身や情動に多大な影響を及ぼしているかを解説し、現代社会が言語を中心とする視聴覚情報に偏りすぎており、システムから個を救い出す切り札としての皮膚感覚に期待を寄せている。
3投稿日: 2015.12.27
あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか
津田久資
ダイヤモンド社
意識的に狭く考え、バカの壁を少なくすれば、発想の範囲は広がっていく
著者のいう天才とは、勉強のできる知識豊富なエリートではない。 むしろ、佐藤優風に言えば「地アタマ」を持つ、養老孟司風に言えば「バカの壁」が入りづらい人であり、発想に制約がなくアイデアが豊富で、無意識の見落としも少ない人ということだ。 この"発想に制約がない"というのが重要で、著者は発想を広げるために、あえて「意識的に狭く考える」ことを提案している。 まさに逆転の"発想”で、いま自分が考えている範囲を明確化することで、的を絞り、除外した「外部」をも意識化する。 それによって”無意識の見落とし”も防いでいるのだ。 他にも有用なアプローチがいろいろと紹介されている。 「公園のハトが減った原因」の仮説を作っていく過程も面白い。 著者は「公園のハトが減っている」というのを「増加するハトの割合が減っている」と「減少するハトの割合が増えている」に分解できたかどうかで、バカの壁を回避できるかどうかが決まるという。 さらに、この分解はさらなる分解によって、発想の範囲は広がっていく。 論理学の援用のようなアプローチだが、ちょうど空海の言語の分節化の話を読んでいるところだったので、より腑に落ちる点が多かった。 さらに、情報収集についても新たな提案がある。 「まず情報」ではなく「まず思考」だという。 まずやるべきなのは「質の高い結論仮説」を作ることで、それを作ったうえで、その答え(仮説)を裏付ける材料を集めるために情報収集を行なうのだ。 ここにも"逆転の発想"があった。
0投稿日: 2015.12.23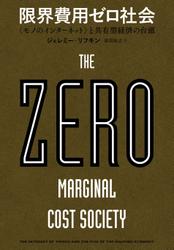
限界費用ゼロ社会 <モノのインターネット>と共有型経済の台頭
ジェレミー・リフキン,柴田裕之
NHK出版
「稀少性」から「潤沢さ」へ、「所有」から「アクセス」への緩やかな転換
単にあらゆるモノがインターネットにつながる、という話ではない。 読む者の遠くない将来の姿を暗示する本だ。 いまの職場や持ち家に別れを告げ、身の回りの自分のモノを手放し、これまでの人間関係や考え方さえ一変する未来の姿。 著者にとっては年来の予言した未来の到来であり、ドイツのメルケル首相とともに積極的にこの社会の実現にコミットしている。 どのような社会か? いまの成熟した資本主義経済がいよいよ最終段階を迎え、それこそ究極の勝利を手にしようとするまさにその時、体制の核心にある矛盾から主導権を失い、かわりに協働型コモンズの社会が表舞台に立つようになるという。 資本主義体制が崩壊するという一時期さかんに喧伝された話ではない。資本主義市場は縮小し、より狭いニッチへと後退するが、生き延び続ける。それが経済の辺縁部であろうとも。 「あらゆる人とモノを結びつけるグローバルなネットワークが形成され、生産性が極限まで高まれば、私たちは財とサービスがほぼ無料になる時代に向かってしだいに加速しながら突き進むことになる。そしてそれに伴い、次の半世紀の間に資本主義は縮小し、経済生活を構成する主要なモデルとして協働型コモンズが台頭してくる」 「遅くとも今世紀なかばまでには、世界の雇用者の半数以上が協働型コモンズの非営利部門に属し、ソーシャルエコノミーの推進に尽力する一方で、必要とする財やサービスの少なくとも一部を従来の市場で購入するといった状況になるのではなかろうか。そして伝統的な資本主義経済は、少数の専門職と技術職が管理するインテリジェント・テクノロジーによって運営されることになるだろう」 それにしてもなんとも皮肉な話である。「生産性を押し上げ、限界費用を押し下げるという、競争的市場に固有の起業家のダイナミズム」が、無駄を極限まで削ぎ落とすテクノロジーの導入を強い、それによって生産性は最適状態まで押し上げられ、最終的には生産にかかる費用がほぼゼロに近づく。生産コストが実質ゼロであるなら、その製品やサービスはほとんど無料になるということだ。「仮にそんな事態に至れば、資本主義の命脈とも言える利益が枯渇する」し、所有権は意味を失い、市場も不要になる。これは、旧来の経済学者の言葉を失わせる事態だ。 「ほとんどのモノがただ同然になれば、財やサービスの生産と流通を司るメカニズムとしての資本主義の稼働原理は何もかも無意味になる。というのも、資本主義のダイナミズムの源泉は稀少性にあるからだ。資源や財やサービスは、稀少であればこそ交換価値を持ち、市場に提供されるまでにかかったコスト以上の価格をつけられる。だが、財やサービスを生み出すための限界費用がゼロに近づき、価格がほぼ無料になれば、資本主義体制は稀少性をうまく活用して、他者に依存される状態から利益を得ることができなくなる」 稀少性ではなく、潤沢さやシェアを中心に経済生活を構成するという考え方は、従来の経済理論はとはあまりにもかけ離れているため、すぐに想像することはできないが、それこそが今まさに起こり始めていることなのだ。 限界費用がほぼゼロの社会は、一般の福祉を増進するにはこのうえなく効率がよい。 ・インターネット上での情報の大衆化 ・エネルギーインターネット上での電力の大衆化 ・オープンソースの3Dプリンティングを用いた製造の大衆化 ・MOOCを活用した高等教育の大衆化 ・ウェブ上での保健医療の大衆化 GDPの一貫した下落の原因も、著者によれば、資本主義体制の緩やかな凋落と協働型コモンズの台頭によって説明できるとする。 「財やサービスを生産する限界費用がさまざまな部門で次から次へとゼロに近づくなか、利益は縮小し、GDPは減少に転じ始めている。そして、しだいに多くの財やサービスがほぼ無料になるにつれ、市場での購入は減少し、これまたGDPにブレーキをかける。かつては購入していた財を、共有型経済の中で再流通させたりリサイクルしたりする人が増えたため、使用可能なライフサイクルが引き延ばされ、結果としてGDPの損失を招いているのだ。しだいに多くの消費者が、財の所有よりも財へのアクセスを選択し、自動車や自転車、玩具、道具といったものの使用時間に対してだけお金を払うことを好むようになりつつあり、これがまたGDPの減少につながっている。一方、自動化とロボット工学、人工知能(AI)のせいで、何千万もの労働者が職を失い、市場での消費者の購買力は縮小を続け、さらにGDPが減少する。それと並行してプロシューマーの数が増え、市場における交換経済から協働型コモンズにおける共有型経済へと経済活動が移るにつれ、GDPの伸び率はさらに縮まっている」
1投稿日: 2015.12.23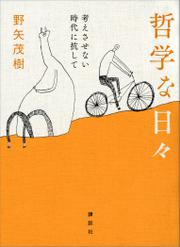
哲学な日々 考えさせない時代に抗して
野矢茂樹
講談社
"考える技術"とは"問う技術"であり、"待つ"ことこそ"考える"こと
哲学は、なにか固有の研究対象というのがあるわけではなく、あらゆる領域の前提というか、ゲームで言えばルールのような「メタ」を取り扱う。 自分がやっていることや、生きていくための「メタ」を問うのだから、生活などしていられない。 だから哲学者は、世捨て人か学生に適していると言われているが、立ち止まって問い直す余裕は誰にとっても価値がある。 しかし大変である。 教職者であれば、気持ちが教科や教え子に向かわず、「教育とは?」という一般論に向かうし、恋愛中の男女であれば「そもそも恋愛とは何ぞや?」と考えてしまうのだから。 哲学者はどのように考えるか? いきなり心とは何か? みたいにそのまま問うことはしない。 まずは、もっとずっと小さい、手頃な問題を設定する。 「考える技術とは、どうやって答えを閃かせるかではなく、いかに問いをうまく立てるかという、問う技術である」。 かつて小林秀雄が「考える」とは「迎える」ことだと語ったように、最後は「雨乞いの儀式」のごとく閃きを待つわけだが、そのまえに下準備として論理的に詰められるところはきちんと詰めておくというのが著者らしいところ。 「待つことこそ、考えること」に他ならぬのなら、現代はますます「考えさせない時代」となりつつあり、野崎まどの『know』のような脳内に電子葉を埋め込まれ、「知らない」と思うまもなく瞬時にわかってしまう世界が到来するとしたら、哲学者はおそらく失業だろうな。 「バラは暗闇でも赤いか?」という話がもっとも面白かった。 著者は街なかでこの話を考えつき、うれしさのあまり散々周りの人に語ったのだが「まちがっている」と否定されたり反応がいまいちらしい。 ただ著者としては異論は大いに結構で、全面同意される方が気色悪いかもしれない。 バラは暗闇では赤くない。 色は物の性質ではなく、われわれの主観に生じる感覚でしかない。 著者はここでもやもやを覚える。本当に色は感覚なのか? と。 本のタイトルを『赤いバラと雷鳴』に替えてほしいほど鮮やかに推論する。 いま新聞でも雑誌でも哲学者の書くエッセイはどこも引っ張りだこだが、著者の書く文章はどこか味気ない。 接続詞の重要性を強調したり、文章には一家言があるのだろうが、著者独自の匂い立つような味わいがないので、前半のように短文になればなるど、淡泊さが余計に極まるのが残念なところ。
2投稿日: 2015.12.05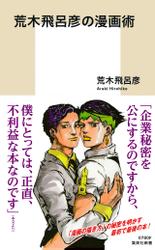
荒木飛呂彦の漫画術【帯カラーイラスト付】
荒木飛呂彦
集英社新書
「指に針を刺すと痛い」というサスペンスが描きたい
著者が漫画で描きたいと思った出発点は、何も「ジョジョ立ち」などの独特のポーズや「オラオラ」などの擬音語が描きたかったのではなく、「指に針を刺すと痛い」というサスペンスの部分だったという。 「傷み」という"見えないものを可視化する"というのは、漫画ひいては絵の本質的な役割で、大友克洋がエネルギーの破壊力を表現するために壊されたものを精緻に描写したように、氏はポージングやスタンドで見えないものを可視化している。 火を描くには風を、光は影をというように、傷みもその傷口からは一歩引いた全体の視点が必要なのだとわかる。 「重要なのはキャラクターであってストーリーではない」、むしろ"キャラが物語を決定する"であるとか、ストーリーも常に「プラス」を積み重ねなければならず、作者は「マイナス」に持って行きたいという誘惑とは徹底的に対峙する必要があると説く。 このあたりの現場の苦労も凄まじく、具体的には、第4部のラストの吉良との戦いで、あまりに主人公に不利な状態を作ってしまい、キャラクターと悪戦苦闘してピンチを乗り越えたと告白している。
4投稿日: 2015.11.27
聖地巡礼 ライジング 熊野紀行
内田樹,釈徹宗
東京書籍
訪れるだけで、ある精神状態へと導かれてしまう「巨大瞑想装置」としての熊野
旅から帰っても一向に収まらぬ、何か悶々とした気持ちを鎮めるために手にとった。 熊野とは「大きな困難と向き合う前に行っておくべき地」であり、典型的な神仏習合なんだけど、古層にあるむき出しの宗教性が、外来の神道も仏教も飲み込んで、「土地の信仰」として結実した異界であるので、昔から多くの人が「野生の霊気」を浴びる目的で熊野詣でを行ってきた。 "聖地"だ、"パワースポット"だと呑気に構えていると、本書にもある通り、いくつものトランス・スポットに絡め取られ、現実感が一瞬で希薄になり、たちまち気を違える危うさを秘めている。 神倉山とともに「よくできた瞑想装置」として紹介されているのが、那智の大滝で、筆者たちの興奮ぶりが伝わってくる。 内田 おお、この滝、すごいですよ。一粒の水滴に視点を合わせて、それがどこまで落ちていくか追っていくと、あっという間に瞑想状態に入りますね。訓練なんかいりません。誰でもすぐに瞑想状態になれます。 釈 あ、ほんとですね! ちょっと目で追うとすぐにクラクラします。いや、こういう滝が信仰の対象になるのがリアルにわかりますね。これは巨大瞑想装置です。 内田 何かが無尽蔵に湧き出してくる。 面白いのは、これだけ圧倒的な宗教装置であるがゆえに、その手前に軒を並べる土産物屋などが良い中和作用をはたしていると指摘するところだ。 内田 お土産物屋が軒を並べているような世俗的な舞台装置って、那智の滝の場合は、滝の宗教的なパワーを緩和するためのものだったんじゃないかな。あれがあるおかげで、人間たちが手頃な宗教的パワーを受け取れる。 釈 なるほど、そう見ますか。いくつか腑に落ちるところがあります。 内田 聖地のそばに世俗的なものが拡がるのって、ひとつはそういう人間の弱さを守るという働きがあってのことじゃないかな。「聖地はスラム化する」というのは、大瀧詠一さんの名言ですけれども、聖地の周りに世俗のものが拡がるのは、別に聖地を穢しているわけじゃなくて、聖地の発する人間的スケールを超えた力を制御して、宗教的に成熟していたい人間にでも「服用可能」な強度にまで抑制する。そういう働きをめざしてしていることじゃないんでしょうか。 "熊野=バリ説"も含めて、いくらかコジツケのような気がしないでもないが、とにかくある種の興奮状態を何か言葉にしないと収まらぬ心情は大いに共感できる。 結論としては、とにかく「熊野は大したものだった」ということに尽きるのだが。
1投稿日: 2015.11.25
「ドイツ帝国」が世界を破滅させる 日本人への警告
エマニュエル・トッド,堀茂樹・訳
文春新書
ヨーロッパやアメリカ、ひいては全世界が恐れるべきなのは、ロシアよりドイツだ!
パリでのテロを受け、これまで「ドイツ副首相」とまで揶揄され、埋没しがちだった指導力を急速に回復させつつあるオランド大統領。 本書で展開される主張もこの事件を受けて多少変更されるかもしれないが、著者の根強い「ドイツ嫌い」は揺るがないだろう。 ドイツは、権威主義的で不平等な文化の国であり、給与水準抑制策をたいした抵抗にも遭わず実施できる国であり、政権交代よりも好んで国民一致を実践する、途轍もない政治的非合理性のポテンシャルが潜んでいる国だとする。 普通の人であれば、たとえ隣国に不満があっても、その国の長所、たとえば規律の高さや優れた工業力などがあれば、それを渋々ながらも認めるものだが、著者にかかるとその長所の源泉が自国の文化と相容れないと激しい拒絶を示すのだから、まるで取り付く島がない。 ちなみに、著者の警戒すべき対象国には日本も含まれていて、この他にスウェーデンや、ユダヤ、バスク、カタロニアなどが、驚異的なエネルギーを生み出し得る社会文化として挙げられている。 著者とすれば、「EUの優等国 = ドイツ」という評価がまず我慢がならないのだろう。 ふつうヨーロッパの人々が恐れてるのは、ロシアの膨張主義の方だけど、著者はそれを「安定化」と肯定的に評価している。 クリミアやウクライナをめぐる紛争で擡頭してきているのは、ロシアではなく間違いなくドイツだと考える。 さらに昨今のドイツの、軍事的コストを負担せず、政治的な発言力を強め、裏切りととられるような反米的でアグレッシブな態度にも違和感を表明する。 アメリカが真に恐れるべきなのは、ウクライナでの勝利による、ドイツシステムの拡大とロシアの崩壊なのだ、と。 ドイツの民主主義に対する徹底した不和をどう評価するか意見が別れるところだが、ユーロ危機の実態やEU域内の各国の思惑とパワーバランスの変化など、傾聴に値する指摘も多い。
3投稿日: 2015.11.24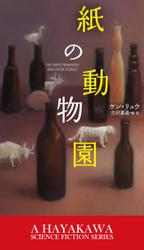
紙の動物園
ケン・リュウ,古沢嘉通
新☆ハヤカワ・SF・シリーズ
形容しがたい複雑な味わいと魅力を持った15篇の短編集
三種の異なる糸が撚り合わされてるよう。 通底に流れるのはノスタルジックで寓話的な愛の物語で、例えば「人々はいっしょに年を取らなくなった - いっしょに成長しようとしなくなった。結婚している夫婦はおたがいの誓いを変えた。もはやふたりをわかつのは死ではなく、退屈だった」と永遠に続く人生を送る夫婦を描写してみせる。 時に展開されるハードSFの片鱗、例えば哲学者サールの"AIは幻想で、思考も幻想だ"とする謎の問いかけに煙に巻かれ、どこか懐かしみを覚える東洋の文化的背景に支えられ、読者は過去と未来を往還する。
7投稿日: 2015.11.21
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
