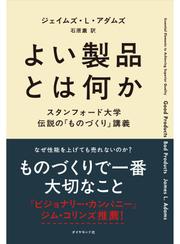
よい製品とは何か
ジェイムズ・L・アダムズ,石原薫
ダイヤモンド社
品質はディテールに依存し、ディテールはクラフツマンシップに依存する
著者はよくスタンフォード大の学生にある課題をやらせるのだが、これが面白い。 どこにでもある安価な製品を2つ買ってきて、片方だけを学生に改良させ、それが元の製品と比べどう変わったか議論させるのだ。 工学系の学生なので、たいていは機能に関係ない無駄な部分を省く生徒が多いが、なかに美術の心得のある生徒が、形に手を加えて製品を面白く見せることがある。 それを元のものと比べた時の学生の反応が特質モノで、「加えられた修正が技術的な機能とは何ら関係ないのに、変更後の商品が魅力的だと感じたときほど、学生たちは混乱した」という。 このことは、製品に対する感覚や感情の役割の大きさを現している。 成功した製品の中に、目や耳や鼻、場合によっては触覚にまで効果的に働きかける製品がいかに多いことか。 従来言われているように、感情は従うのではなく、先行するものなのだ。 感情は、理屈の二の次になることが多いが、アップルのように機能よりも感情が勝っていることを証明する製品が現れると、どれだけ製品品質を決定づけているか気づかせてくれる。 ここで著者は自分の妻の話を例にあげている。 彼女は、性能も信頼性も高いクルマを購入し、満足して乗っていたが、車庫でネズミがワイヤーハーネスを齧ったばっかり、評価がガタ落ちになったという。 著者は、奥さんがこのクルマを以前ほど品質がいいと思えなくなった理由を、知覚品質の低下にあると見ている。 メーカーの技術者たちは、とかくパフォーマンスを定量化したがる。 性能などを数字で表すことによって、製品を簡単に説明できたつもりになっている。 しかし性能を定量的に比べることなど本当にできるのだろうか? 品質が高いというには長持ちしなければならず、その製品寿命を通したパフォーマンスを考慮する必要がある。パフォーマンスには信頼性、耐久性、サービス性、メンテナンス性などの要素が含まれる。 なぜなら不具合が起きれば、直接生産者の落ち度によらなくても、製品性能に対してマイナスイメージとなるだからだ。 パフォーマンスを定量化する難しさをもう一つ挙げれば、「多ければいい」というものではない、ということだ。 技術が高度に進んだ今、我々は製品に「してほしいこと」だけでなく、「してほしくないこと」も考えなければならない。 著者は、高度化する農業機械にも目を向けている。 最新の農業機械は確かに性能は高いが、購入・使用・維持にかかるコストも高い。 メーカーの利益は大きく、農家にも利益はあるが、社会に対する利益はどうだろう? コストと価格も、パフォーマンスと同じように、製品寿命を通して考えるべきものだ。 また、「真実の原価」をめぐる議論のように、クルマにおける原油価格やスモッグ対策、原発における廃棄物や廃炉費用など、社会や環境へのコストは考慮されているのかを、製造者だけでなくユーザーも、いま一度立ち止まって考えてみる必要がある。
2投稿日: 2016.05.17
憲法の涙 リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください2
井上達夫
毎日新聞出版
9条削除・徴兵制導入を唱える「怖いオジサン」の論争的提言
『リベラルのことは嫌いでも〜』の続編だが、前著を未読でも大丈夫。 ロールズの正義論など法哲学の小難しい議論は省き、安保と9条により特化しているのでわかりやすい。 前著の読者にとっては多少重複も多いが、各方面からの異論や批判への回答、補論なども含まれているので読みごたえがある。 改憲派にも護憲派にも、その罪と欺瞞を具体的にあげてバッサバッサと切っていく様は痛快だが、やはりリベラルにより手厳しく容赦がない。 国会前でデモしてる若人には、叫ぶべきは「9条守れ!」じゃなくて「9条変えろ!」だろ?と疑問を投げ掛け、憲法を「うそ臭い空念仏」化させる護憲派の言説に呆れ、解釈改憲を「大人の知恵」とうそぶく修正主義派には、そもそも安倍政権の解釈改憲を非難する資格なしと断罪し、「違憲事態の固定化」を狙う原理主義派には、憲法が泣いていると憤る。 いったい9条が大事なのか? 憲法が大事なのか? 憲法がこれだけないがしろにされ、コケにされているのだから、国民はもっと怒らなければならない、というのが、著者の止むに止まれぬ義憤なのだろうが、その主張も本書で再三再四批判している、高みからのエリート主義的発想にも思えるし、むしろこれだけあやふやな状態の憲法で、曲がりなりにも戦後70年やってこれたことの方に感動を覚え、憲法をも超える国民の知恵に思いが至った。 日本列島自体、今後数十年以上は繰り返し地震や火山の噴火などの自然災害に見舞われることが予想され、そのたびに自衛隊員による献身的な救援が必要とされるであろう状況で、「戦力」とも認知されず憲法外に置かれた自衛隊の存在を思うと、本書の提言の広範なひろがりを待つまでもなく、『敗戦後論』でかつて加藤が主張していた「選び直し」や、政治的主体性を強めるという目的での改憲へのハードルは、ますます低くなりつつあるように思えるのだが、果たしてどうか? 「欺瞞にふける者は、その欺瞞を批判されると別の欺瞞的手段でそれを隠そうとする。嘘をついた者は、その嘘を指摘されると別の嘘でごまかそうとするのと同様に。護憲派も改憲派と同様『欺瞞の蟻地獄』に陥っている」 9条改廃により自衛隊をいったん「戦力」と認めた暁には、それを統制し濫用を防ぐ統制規範を憲法に盛り込むべきだという著者の主張だが、戦争に至るまでの歯止めだけでなく、戦争が始まった後の歯止めも盛り込むべきだろうと思った。 またぞろ「一億総玉砕」では、同じ轍を繰り返すことになるだろうから。
0投稿日: 2016.05.16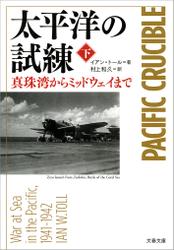
太平洋の試練 真珠湾からミッドウェイまで(下)
イアン・トール,村上和久・訳
文藝春秋
ミッドウェー海戦の敗戦の決定的な要因は、暗号解読ではなかった
この本を読むまで、日本にとってミッドウェー海戦は、事前に米側に暗号を完全に解読されていた時点で、負けるべくして負けた、振り返るのも気の重い戦いだと思っていた。 しかし本書によると、敗戦の決定的な要因は、必ずしも暗号解読ではなかったようだ。 もちろん作戦が筒抜けだったのだから、さすがに日本側の完勝はあり得ないが、少なくとも痛み分け、もしくは不戦敗ぐらいにはできたのかもしれない。 勝敗を分けたポイントは、一度は見失った日本空母を再び発見できたという幸運とヨークタウンのあり得ないほどの不沈ぶりと日本側の消火のまずさ。 これまで言われてきたように、ミッドウェー海戦は米側が、日本側の暗号をまるごと解読できたから負けたわけではない。 苦労しながら少しずつの成功だっため、現場では不確かで矛盾する情報に最初は信じられていなかった。 確かに、事前に日本軍の攻撃目標がわかり、さらにその日時までつかめたのは、「空母機動隊二個分に匹敵する価値」だった。 念のため、ひっかけをして再確認が取れた時も、その目標の戦略上の重要度の低さのため、日本側がかついでいるのではと疑ったくらい。 これを読んでわかったが、暗号解読者のその後は不遇で、きちんと評価されはじめたのは戦後しばらくたってから。 前もって攻撃目標と日時が分かっていたにもかかわらず、米側は勝利までに犠牲を出し過ぎ、その勝ちさえも幸運によってひろっている。 ただ、空母に群がる米軍機が悉く返り討ちにあったことで、それまで動揺していた日本側の油断を誘ったというプラスの面はあるかもしれないが、それは意図せざる結果だろう。 スプルーアンスは攻撃隊が全機揃って発艦する前に攻撃を命じているが、これは日本軍に比べて発艦にそもそも時間がかかりすぎていたことと、日本側にこちらの艦の所在を知られたためであるが、それによって第8雷撃飛行隊はすべてゼロ戦に撃ち落とされている。 むしろ、それだけ発艦に時間がかかるのに全機揃って編隊を組んで向かわさせようとしたので、著しく時間をロスしており、事実目的地に駆けつけた時には日本軍はおらず、ただ大海原が広がるだけだった。 探し回った末に、たまたま運良く見つけることが出来たのも、パイロットの勘がすぐれていたことと、南雲提督があろうことか米空母に接近するよう命じていたため。 第一撃でミッドウェー島の攻略に成功しなかったことと、ありえないほど早く敵空母が周辺海域に現れていることをもって、作戦を中止し撤退していれば良かったが、南雲艦長はむしろ敵艦に向けて前進したことが、一度は見失った敵パイロットに発見される不運を招いたようだ。 一度は大破させたはずのヨークタウンだが、実はまだ沈まず動いていて、日本側のパイロットが戻って再度二艦目の標的を探していたところまたも発見され、さらに致命的な打撃を受ける。 日本の潜水艦が魚雷を見舞うまで沈没しなかった。 珊瑚海海戦から数えて4回目の攻撃でやっと沈没すると言う不沈ぶりが凄い。 米側にとっては、 ・暗号解読によって日本側の奇襲をさけられ、ミッドウェー島の防備を固めることが出来たこと、 ・無敵の日本艦隊やゼロ戦に対して不安はあったものの、不思議と戦闘意欲は高かったこと、 ・ゼロ戦に対する必勝戦法を編み出しつつあったこと、 などがこの戦い前までの有利な点であったが、それでも、 ・暗号解読していたにもかかわらず不完全な奇襲になったこと、 ・米空軍パイロットの技量が極めて拙かったこと(命中率が悪く、弾を無駄にしすぎたり、発艦に時間がかかりすぎる) などによって、危うくこれほどの大勝を逃しかけていた。 日本側にとっては、 ・暗号解読により思わぬ奇襲にあったが、それまでが相手を呑んでかかっていたためか、さほどパニックにもならず冷静に対処できたこと、 ・零戦乗りの技量がずば抜けていて、稚拙なトップの失敗を何度も救ったこと、 など有利な面もあったのだが、最後には挽回しきれない不運とミスが重なった。
1投稿日: 2016.05.13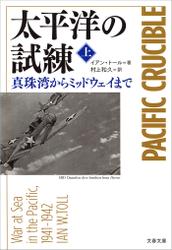
太平洋の試練 真珠湾からミッドウェイまで(上)
イアン・トール,村上和久・訳
文藝春秋
アメリカの学習曲線が急激に上昇する前の180日間
「日本が戦争に勝っていた180日間」は、アメリカの学習曲線が急激に上昇する前の180日間でもある。 「日本が戦争に勝っていた180日間」は、裏を返せばアメリカがその急激な学習曲線の一番下にいた期間といえる。 開戦時、すでに5年も前から中国大陸を舞台に実戦を積んでいた日本海軍は、パイロットの練度は高く、編隊は統率が取れ、魚雷の投下は精度が高いの対し、米海軍は戦時下でのすべての海上活動に不慣れで、潜水艦の探知に正確性を欠き、航行中の燃料補給にとまどい、あげくは「天然の魚に魚雷を使いすぎる」と身内からこぼされるほど練度が低かった。 実戦経験の乏しさはトップも同様で、参謀組織はにわか仕立てで統率がとれていなかった。 しかし彼らは戦闘意欲が旺盛で、実戦を貴重な糧として、何がまずかったかを議論しあう。 対して日本は、一部のトップは的確に相手の攻撃の意味を読み取るのだが、危機感を仲間同志で議論し共有しあわない。 真珠湾攻撃からミッドウェイ海戦までの間の過程が、細かいところまで丹念に描かれる。 真珠湾直後のウィーキ島救出をめぐる米首脳部の混乱や、前任者の解任という混乱にもかかわらず、ニミッツがわざわざ時間をかけ、大陸を列車で横断して太平洋艦隊司令長官に着任するまでの過程、これまで見過ごされてきたマーシャル諸島への奇襲攻撃の意義など、興味の尽きないエピソードに溢れている。
0投稿日: 2016.05.13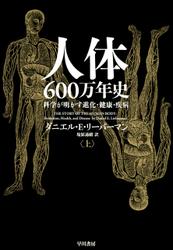
人体六〇〇万年史 上──科学が明かす進化・健康・疾病
ダニエル・E・リーバーマン,塩原通緒
早川書房
人間の身体は何に対して適応しているのか?
上巻の、そして本書の核心となる疑問は、人間の身体は何に対して適応しているのか? であり、もっと言えば、われわれの身体に適応的なライフスタイルとは何か? ということだ。 著者の答えは、人間が何に適応しているかなんて簡単に言えないということだろう。 確かにわれわれの体には何千もの適応的な特徴があるが、すべてが適応的なわけでもなく「多くの適応にはトレードオフが関わっていて、人体のさまざまな適応の寄せ集めは、時として互いの衝突を生む」。 ゆえに現代生活があまりに進化上逸脱しているわけでも、旧石器時代が健康的なわけでもない。
2投稿日: 2016.05.13
2100年の科学ライフ
ミチオ・カク,斉藤隆央
NHK出版
いくつか類似の予測本を読んだが、その中でもベスト
説明が抜群に分かりやすく、ギリシャ神話や馴染のある映画の印象的な場面から語り始めるのでとっつきやすい。 何が解明されていないかを示し、その説明がつけられたらノーベル賞が待っているぞと叱咤する。 実現を阻んでいるのは、物理法則や工学的な技術の問題ではなく、コストなどの経済的な要因によるものが多いようだ。 それでもおよそ100年というスパンで考えれば、やがて時が解決してくれる問題でもあるのだろうが、その成果は科学知識を一変させ、ひいては生活や生き方を一変させる。 どんな仕事が生き残るか? という第7章「富の未来」は、これから就職を控える学生や指導する学校関係者の方に是非読んでもらいたい。
0投稿日: 2016.05.12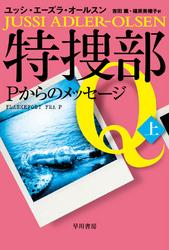
特捜部Q―Pからのメッセージ―(上)
ユッシ・エーズラ・オールスン,吉田薫,福原美穂子
ハヤカワ・ミステリ文庫
100ページほどで読むのをやめた
この辺りでも、いまだボトルメッセージがイタズラではないかと議論し合っていて、手がかりの端緒すら得られていない。 それもメッセージが暗号かなにかで、薄皮を一枚ずつ剥ぐように解明されているならまだ我慢ができるが、単に不手際で判読不能な紙を壁に貼り出して、その前でああだこうだと腕組んで睨んでるだけ。 こんな調子で進んでいくなら、時間の無駄たと思い本を閉じた。 シリーズ物の第一作からの読者ではないためはじめは手に取る予定になかったが、北上氏が絶賛していたのでそれではと読み始めたがガッカリ。
0投稿日: 2016.05.12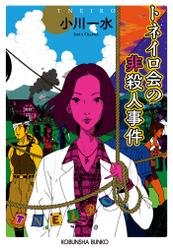
トネイロ会の非殺人事件
小川一水
光文社文庫
着想は凄いんだけど、果たして傑作かと言われると...。
「くばり神」みたいなネタはこんな展開じゃなくて、古い因習の残った地方都市舞台の長編で読みたかった。 「この中に殺してないヤツがいる」という犯人捜しの逆バージョンの表題作も新鮮だけど、短編で登場人物が11人って多すぎないか? ボトルをぶら下げる順番をより複雑化させたいだけのような気がしてならない。 ここまで書いてて、単にこの作者の長編が読んでみたいってことだと気がついた。 最後に、「トネイロ」って何?
0投稿日: 2016.05.12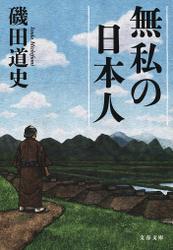
無私の日本人
磯田道史
文春文庫
一途な志は喋らなくても誰かが分かってくれる
いつもは年貢などむしり取られるだけの民草が、お上から金を取ろうという大それた考えも面白いが、出資者である仲間を募っていく過程もいい。 調子のいい男には理屈ではなく、酒席で情に訴えたりなどなかなかにしたたかだし、銭湯好きが一転して、水垢離をとり始めたことが思わぬ効果を生むところなどは、一途な志は喋らなくても誰かが分かってくれているんだなと感動する。 計画に一銭も出さずタダ乗りしようなんて欲得ずくの人間は、江戸時代には庶民に至るまで見られないし、たとえ思い通りならなくても恨み言を言わず、相手を気遣う質朴さは頭が下がる。 悪く言えば、仙台藩のイメージが変わった。 東北人特有のお上に対する従順さをいいことに、米を専売して利益をことごとく手中にするさまは醜悪この上ない。 震災復興の過程で宮城県政がこうした過去と重ね合わされることのないように望む。
8投稿日: 2016.05.12
天国でまた会おう 上
ピエール ルメートル,平岡 敦
ハヤカワ・ミステリ文庫
人生はいつも、なにかもの足りずにすぎていく
わけのわからぬ文体で、戦争の混乱ぶりを効果的に演出するためかと思って読みすすめたが、最後までこのスタイルが続き、さすがフランス文学と妙に感心した。 一人称なのかと思いきや、三人称に、果ては作者が弁士さながらに顔を出し、読者も観衆となって実に奇妙この上ない物語につきあうことになる。 この時期の異形の傷痍軍人たちを写した映像はつとに有名で、おそらく作者もこの映像と実際に起きた事件に着想を得たのだろうが、第一次世界大戦直後の混乱したフランス社会の世相がよくわかって面白い。 途中から荒木飛呂彦が漫画化したらと思いつき、最後まで勝手にキャラクタライズされた登場人物たちが頭から離れなくなった。 気に入った文をいくつか。 「単に死ぬのが怖いんじゃない。今になって死ぬのがやりきれないのだ。最後に死ぬなら、最初に死んだって同じことだ」 「これまでの行動から見てもわかるように、拳を握ったままにしておくほうが有利だと思えば、いつまでもそうしておく男なのだ、プラデルは」 「今のエドゥアールは、壊れた時計よりも役立たずだ。時計ならば壊れていても、1日に2度は正しい時間をさすのだから」 「どんなに大きな喜びにも、わずかな悔いが残る。人生はいつも、なにかもの足りずにすぎていく」
2投稿日: 2016.02.29
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
