
スティーブ・ジョブズ(4)
ウォルター・アイザックソン,ヤマザキマリ
Kiss
失意のどん底にいるジョブズをここまで淡泊に描いた初めての作品
Macの開発と発表、スカリーの登場、マイクロソフトの裏切り、社長解任とネクスト立ち上げと、原著では上巻の半分のボリュームを一気に一巻に凝縮させている。 次の巻からはピクサー時代とアップル復帰が描かれる予定らしいので、3巻までのペースから考えれば、あきらにスピードUPで、完結を急いでるのかな? 原著を読んだ作者が思い描いたジョブズ像を漫画という自らの土俵に引き寄せ思う存分描いたというより、ひたすら原著に忠実に骨格をなぞり、ドラマ部分とインタビューなどの証言部分を背景を変えながら物語に同居させているので、なんとも読みにくい。 「一生、砂糖水を売り続ける気かい?」という有名な口説き文句をスカリーに放つ場面や、ゲイツを呼びつけ罵倒する場面など、印象的なシーンの連続のはずが、貧弱な漫画表現で盛り上がりにも欠いている。
0投稿日: 2016.08.02
亜人(8)
桜井画門
good!アフタヌーン
「覚悟を持った者同士の戦闘」こそ、著者がこの漫画で本当に描きたいテーマ
なぜ佐藤らの要人暗殺リストに女性秘書の名があるのか?、その秘書・李と社長・甲斐の関係は?、また田中と李の浅からぬ因縁とは?…。 前巻から引き続く謎をますます深めながら、本巻は全編に渡ってシリーズ随一と言ってもいいほどの息つく暇を与えぬ戦闘シーンの連続で、とりわけ最後の38話は圧巻だ。 コマの使い方がとにかく上手いので、階段上で鉢合わせになる下村と田中、佐藤とその襲撃を防ぐ平沢を中心とした4人の黒幕の姿が、台詞ともどもとにかく印象に残る。 致命傷を負ったため、自分の武器を仲間に放り、「お先」と右手を軽く上げ、それに頷いて応えるシーンは、何度見てもカッコよすぎます。 「この国の”兵士”に相当する職種の人間は 戦闘に身を置く 覚悟がぬるい だが 君らは違う ちゃんと”殺し合いをしてきた”風情を感じる」 佐藤がいみじくも語る「覚悟を持った者同士の戦闘」こそ、著者がこの漫画で本当に描きたいテーマなんだろう。 「断続的な戦闘で 物質は削がれ 好調な戦況は 油断を生む 出口のない檻の深くまで 猛進してるとも知らずに」 高校生の主人公にこのような不敵な台詞を吐かせて、違和感のない漫画がかつてあっただろうか。 複数の亜人の動きを止め捕獲し、救難連絡を入れさせるためハッカーへの襲撃はわざと遅らせるといった見事な作戦を立案するほどの今孔明ぶり。 亜人という不死の者たちとの戦闘はますます深化していて、SPやSATなどの人間側が、"復活の暇を与えない連続殺傷"と"麻酔銃での無力化”を臨機応変に使い分けて拘束を目指せば、対する亜人たちは、戦闘中に深手を負った仲間を間髪入れず殺すことによって助け(なんと秀逸!)、ここぞという時に無敵の幽霊(IBM)を出して局面を打開する。 難点を言えば、プロ同士の銃を使った戦闘は早晩ネタがつき、佐藤の相手はグリーンベレーでも引っ張り出してこないと収まらないほどエスカレートしていることと、いわゆる幽霊同士の戦闘が、たとえ拳法の構えを見せても、どこまでいっても拳同士の殴り合いに終始し、ジョジョのような異なる能力同士の違いを見せる戦いに持っていけていないところ。
0投稿日: 2016.07.09
帰ってきたヒトラー 下
ティムール・ヴェルメシュ,森内薫
河出文庫
"ソウトー"は、最後まで全くブレ無し
下巻になっても批判の鋭さはとどまることを知らず、ドイツ国内の現役・元政治家を含め実名で次々と切り捨てる。 その矛先はついにはダックスフントまで及び「犬の世界のユダ」呼ばわり。 あげくは、カメラを連れて極右ネオナチ本部に乗り込み「恥を知れ」と説教を垂れる始末。 まさに、毒をもって毒を制す。 物語の展開上、第二の人生を送る彼も少しは現代と折り合いをつけて、主張を弱めたり反省の弁を口にするのかなと思いきや、最後まで全くブレ無し。 一人称で語られているため、気づかないと危うく共感を寄せてしまいそうになる怖さをはらんでいる。 この一人称もそうだし、結末も含め彼を洗いざらい現代に再現しきった、著者の徹底した手法は、この物語でしか味わえぬ相当に痛烈な現代風刺に満ちている。
2投稿日: 2016.06.11
帰ってきたヒトラー 上
ティムール・ヴェルメシュ,森内薫
河出文庫
ヨーロッパの優等生たる現代ドイツもこの男にかかれば形無し
風刺や批判の毒を盛り込みながら、歴史上の人物をまったくあり得ないシチュエーションに再現するパロディ小説の手本のような作品。 壁の落書きやテレビ(なんと総統はテレビに向かって、話の進展について文句を言いまたあとで必ず戻ると約束したりする!)にいちいち「なんということだ」と驚きながらも、ヨーロッパの優等生たる現代ドイツもこの男にかかれば形無しである。 散歩中に犬の糞を拾う行為はどう考えても彼にとって奇行だし、「現在のドイツ人は民族の分別に比べ、ゴミの分別はずっと正確に行っている」という嘆息は切実であるだけ滑稽だ。 意外にも現代の政党では『緑の党』に親近感を覚えており、小説とはいえいい迷惑だろうなと同情も。 「最高の人材ほど早く死ぬ」という彼の信念は、第二の人生においてその正しさが証明されたようだが、現代に生きてる我々はなんなんだ..。 まぁ、いい人ほど早く亡くなるのは彼だけの実感ではないが...。
4投稿日: 2016.06.11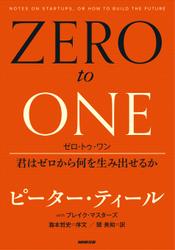
ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか
ピーター・ティール,ブレイク・マスターズ,瀧本哲史,関美和
NHK出版
正しく行なえば、「1999年のグーグルになることができる」
どの会社もまずははじめが一番肝心。 誰と組み、誰を雇うかなど、正しく創業すること。 社内の揉め事を回避するのに最適なのは、社員が受け持つ役割を明確化すること。 社内の競争だけでなく、社外の競争も厳禁。 大きな市場で壮絶な競争の末わずかな利益を追い求めるより、小さくニッチな市場で独占的利益を得ること。 ただし、自分の市場を極端に狭く限定するのは禁物で、周辺市場への拡大は常に念頭に置かねばならない。 破壊ではなく創造を、競争ではなくパイの拡大を。 不毛な競争から抜け出すためには、他社のできないことをやり、二番手よりも少なくとも10倍は優れていなければならない。 将来のリスクやチャンスを分散させることに意味はないし、成功が単なる運だと諦めている人はそもそも本書を手に取ることもしないだろう。 圧倒的なリターンは、”正規分布"ではなく”べき乗則"を知らねば決して得られない。 ともかく、いちばんはじめの創業時に正しく行なうこと、そして特定のニッチを支配すること、次に周辺市場に拡大していくこと。 そうすれば、「報酬や福利厚生では2014年のグーグルに勝つことはできないけれど、使命とチームについての正しい答えがあれば、1999年のグーグルになることができる」。
1投稿日: 2016.06.05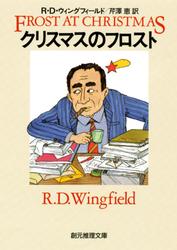
クリスマスのフロスト
R・D・ウィングフィールド,芹澤恵
創元推理文庫
イギリス人がどれだけユーモアを愛しているかよくわかる小説
10年ぶりに再読して改めて気づかされるのは、イギリス人のユーモアに対する寛容さ。 愛と言ってもいいが、むしろ性と呼ぶべきかも。 登場人物の多くが、フロスト警部のきわどいジョークにうまい合いの手を入れ、さらなる冗談を引き出している。 まるでエチケットのように。 社会の潤滑油として認知されているためか、冷たく無視されることもたまにあるものの、マレット署長のようにムッとされながらも大人の対応。 関係がギスギスし、事態が緊迫すればするほど、微妙なニュアンスをもったジョークで隙間が埋められるが、当のフロストに何の思惑もない。 今回も大いに笑わされたのは、フロストが最初にマレットの署長室に出頭する場面。 再三の呼び出しも無視し、あまつさえ署長の愛車に傷をつけ、苦虫を噛みつぶしたマレットは、入ってきたフロストに顔も上げず、そのまま沈黙の苦痛を感じさせようとするのだが、マッチの音ともに信じられない光景を目にする。 「ああ、スーパー、気遣いはご無用に。そっちの仕事が一段落してからでいいから・・・」 フロストの犯罪者に対する見方も終始一貫している。 前方不注意でお婆さんを撥ねて殺してしまった若者には「運が悪い」と言い、卑猥な本やポルノまがいの写真をトランクに隠していた司祭には「われわれとまったく同じような人間」と同情を示す。 「正義なんてものは、ただのことばだ」と宣言するように、警察だからといって、自らを市民とは切り離し、一段高いところにいる存在とは考えない。
0投稿日: 2016.05.31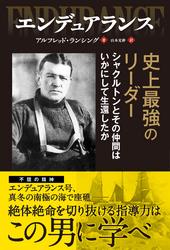
エンデュアランス ──史上最強のリーダー シャクルトンとその仲間はいかにして生還したか
アルフレッド・ランシング
パンローリング
冒険ノンフィクションの金字塔
「求む男子。至難の旅。僅かな報酬。極寒。暗黒の長い日々。絶えざる危険。生還の保証なし。 成功の暁には名誉と賞賛を得る。」 いまも語り継がれる、シャクルトンがロンドンの新聞に出した、有名な求人広告である。 これに5千人以上もの志願者が殺到したというのも凄いが、その中から稲妻のような早さで直感的に隊員を選んでいくシャクルトンもやはり凄い。 とにかくシャクルトンは規格外の男で、彼にとって南極は、名誉やお金を得るための場ではなく、彼の怪物のような自我となだめがだい衝動を投げ打つ舞台だった。 並外れた勇気や大胆さを発揮したい人間にとって、ロンドンでの生活はきっと牢獄だったことだろう。 ついに出航という時、シャクルトンの気持ちの高ぶりを、著者はこう表現している。 「長い準備の期間はとうとう終わった・・・頼み込んだり、おべっかをつかったり、小細工をしたり - もう、そんなことはしなくてもいい。失敗と挫折、空しさに満ちた世界には別れを告げた。ものの数時間を経ずして、無数の小さな問題がからみあった複雑極まりない人生は、ただ1つの目的を掲げた単純明快なひとすじの道になる - あとはひたすらにゴールを目指すだけだ」 氷上での生活は、さまざまな試練を隊員たちに与えたが、それは不便を通り越し、どこか豊かさを感じさせるものに変わり、彼らの心に自立心を育んだ。 ズボンの継ぎを当てることさえ、家では人任せにしていた男たちが、何時間もかけてそれを成し遂げ、「なんと恩知らずだったのだろう」「最高の一日だ…生きることの喜びを感じる」と日記にしたためる。 雪と氷しかない、苛酷で寂しい原初的生活の中で男たちは、限られたものの中に満足を見いだし、必要以上のものを望まなくなる。 陸では無敵のシャクルトンも、最期にボートの旅に不安を感じていた。 海では、別種の戦いを強いられるためだ。 海との格闘は、疲れを知らない敵との肉体的な格闘であり、困難を耐え抜く勇気や信念ではどうにもすることができず、人間に望めるのは、ただ打ち負かされないことだけだからだ。 生き残りをかけたシャクルトンの戦いが最期にどういう結末を迎えるかは、読んでもらうしかない。
0投稿日: 2016.05.21
モンスター 尼崎連続殺人事件の真実
一橋文哉
講談社+α文庫
導くべき真相は手口の詳細を集めても見えてこない
本書で明かされるのは、モンスター誕生の秘密や彼女を影で操った黒幕の存在、北九州一家監禁連続殺人事件との"驚くべき接点"などだが、最終章の「真相」を読み終えても、優れた事件ノンフィクションというよりは週刊誌の実録物の印象しか感じない。 入手した日記の内容がどれほど事件の真相に迫るものなのか、恣意的な引用にとどまるものなのか、読者には最後までわからない。 歯止めがきかないと犯行はどれほどエスカレートするかや、生来のサイコパスがささいな示唆を自らアレンジしてどのような悪事を企てるかなど、導くべき真相は手口の詳細を集めても見えてこない。 M直伝の「家族乗っ取り術」とあるが、別に「闇の帝王」の手口を引き合いに出さなくても、黒人のスラム街のワルたちのあいだでは、付き合いはじめた女を奴隷状態にしてしまう伝統的な方法なんかもあるわけで、人身を掌握するやり方は古今東西ゴマンとある。 むしろ、いちいちやり方を教えてもらわないと何もできないサイコパスを想像する方が難しい。
0投稿日: 2016.05.20
翻訳百景
越前敏弥
角川新書
海外作品の読書を至福の時間に変えてくれる、翻訳というお仕事
翻訳家がどのような点に気を配り、翻訳を仕上げているかがよくわかった。 わかりやすい訳文はもちろんだが、柔らか過ぎる日本語ではかえって外国の雰囲気を台無しにしかねない。 そのため、わざと歯ごたえを残し、未知の世界を感じてもらう。 最終的には翻訳者の裁量で、咀嚼し、異言語に移し替えるのだが、原文の雰囲気は感じてもらいたいので、長文派の文章を切り刻むようなことはしない。 細部にも気を配るべきだが、忠実でありすぎれば全体を見失う恐れがあるので、広く見渡す視点も重要だ。 「ゆっくり読み込んで、さんざん迷いながら訳語をひねり出す」、これが翻訳家の「日々の仕事」なのだ。 東江さんの業績でも触れられているが、翻訳の作業は、原書に関係する分野の調べ物が非常に多い。 あまりに門外漢だと分からないところは監訳者に丸投げする訳者もいるかもしれないが、苦労して長く深く調べた経験は、訳文にきっと現れる。 東江さんの凄いところは、特定の作家だけの文芸翻訳だけでなく、政治から金融に至るまでの幅広いテーマのノンフィクションを次々に手がけていたところだった。 いまやTVで引っ張りだこの林修先生のように、予備校出身の人がマルチに活躍する姿を見ることが多いが、本書の著者も元講師で、講演や教室、ネットなど多方面で発信を続けている。 いまでは受験参考書の指南役も務める元外交官の佐藤優氏や、かつて塾の講師でも成功していたと思うと語った養老孟司氏など、こうした方面に親和性の高い人に共通しているのは、その道の専門分野について門外漢にもわかやすく解説し伝える能力と、学習の取り組み方に対する並々ならぬ自覚の強さだろう。
0投稿日: 2016.05.19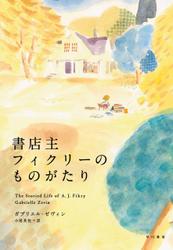
書店主フィクリーのものがたり
ガブリエル ゼヴィン,小尾 芙佐
早川書房
「本というやつは、しかるべきときがくるまで、読み手が見つからないことがあるんだね」
若い頃に読んだ本に、歳を重ねて違う出会い方をすることがある。 本書も、こうした本との出会いのタイミングを、人との出会いにも重ね合わせている。 ランピアーズ署長の言う通り、もし稀覯本が盗まれなかったら、フィクリーは店のドアを開けたままにしておらず、マリアンも赤ん坊を店にはおいていけなかった。 マヤによって島の人々とつながり、アメリアとも出会い直す。 フィクリーからずいぶん「単純化した」話だと皮肉られても、署長は「よいタイミングとはこういうことさ」と意に介さない。 マヤを口実に頻繁に店を訪れるうちに、本に目覚めたランピアーズ署長を、フィクリーは事細かく次に読むべき本を指導する。 ジェフリー・ディーヴァーに、ジェイムズ・パタースン、それからエルモア・レナードに「進級」させ、ウォルター・モズリイ、さらにはコーマック・マッカーシーへと「進級」させる。 「進級させる」ってなんだよと思いつつ、言い得て妙だなと感心させられる。 本との距離感がとても健全で、フィクリーの「ふん! 本なんておバカどものためのもんですよ。わたしたちみたいなおバカどもの」という台詞に、全力で頷いてしまった。
2投稿日: 2016.05.17
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
