
のばらセックス
日日日,千葉サドル
講談社BOX
カワイイは、グロい。
日日日といえば、「ちーちゃんは~」以降「狂乱」「アンダカ」「ささみさん」と何気なく目を通してきて、その理に走った感のあるコンセプト設計とかそれでも読ませる文章力の器用さが何となく思い浮かぶ身ではあるのですが。その理に走った感を撓める事無く、多筆で培った文章力を伸ばし続けていったらこうなった、的な作品でしょうか。 タイトルの通り、もはや成年向けライトノベルのように性描写が氾濫しております。全編色々と体液まみれ。乱暴に扱われる主人公・手練手管でなすがままにされる主人公・恋人と衆目下で愛し合う主人公とシチュエーションも様々。 とはいえ、そこまでエロいかと言うと、著者自身が苦戦した旨書いているように、色々主人公にとって不本意な展開が多い上に主人公視点な描写なので、読んでいてメンタルに痛かったりするのでご注意を。 それ以上に個人的に興味深かったのは、この主人公の立ち位置。 かつて文化史的に「子ども」と「大人」しか居なかった所に、学生なる身分が生まれた結果、「少年・少女」という身分が生まれたと側聞しておりますが。 まだまだ男性優位極まりなかったご時世での話なので、少女とは「妻・母になるまでのモラトリアムであり、男性にとっての商品価値を高める期間」的だったのですが、いつしかそれも一人歩きして。「カワイイ」文化を筆頭に、少女文化は男性の欲望とはかなり縁遠い独自の進化をしております。 何が言いたいのかというと、この作品の主人公=「少女」概念の擬人化と捉えうるのではないか、という事です。更に言うとDVのサバイバー的要素もある。 相棒の少年は?というと、頑強長命で理性よりも本能なフリークス(奇形種)なのにどう見てもロリータという、いわば「去勢された少年」。 そう読み込んでいくと面白いというか、色々考えさせられるのだけれど、読みながら頭を同時進行で二様に使う格好になるため、かなり胃もたれ気分にもさせられる。更に言うと、終盤に向かってから物語を纏めるまでの辺りはかなりラノベ・漫画の方程式に準拠した感があって、そこが少々物足りない。 そうは言ってもラストのイラストに象徴された、カワイイし平和な光景であるが同時に異様でもある結末は、中々味わい深いのではないかなと。
3投稿日: 2013.10.17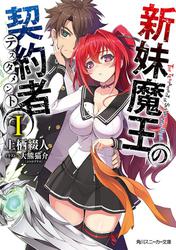
新妹魔王の契約者 I
上栖綴人,大熊猫介
角川スニーカー文庫
炸裂する中二エロスピリッツ
義妹が魔王の後継者とお付きのサキュバス。 サキュバスだから当然(表向き普通を装っていても)エロエロトークもアリアリのマシマシで! そして契約を完遂させるためという大義名分の下に、主人公が義妹(後継者の方)の豊かな胸を揉みしだく! ツンデレ成分高めな魔王後継者は当然抵抗するけど大義名分があるから揉む! 揉まれた義妹が何度も昇天! ……と。 現実ベースの舞台で「勇者と魔王」なテンプレネタを扱いつつ、ラノベ枠のエロ路線の限界を探るような展開を特色とした一冊。 勿論本筋の物語もあり戦闘もあり、魔王サイドにも勇者サイドにも色々ありそうではあるが、まだシリーズ1巻目なのでそちらは「今後にご期待を」という所になるかと。
3投稿日: 2013.10.11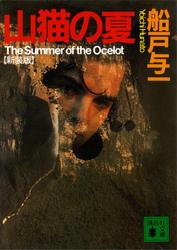
山猫の夏 【新装版】
船戸与一
講談社文庫
読まないのは人生の損失計上
船戸与一といえば、まず思い浮かぶのは日本の冒険小説史に残る(個人的見解)名作ビルドゥングス・ロマン「猛き箱船」。 南米三部作第一弾の本作もまた素晴らしい。読み進める毎に血が滾る。 ハンパ者のまま南米に流れて、そこでもまたハンパ者として生きている主人公が、「山猫」を名乗る男に翻弄されつつ成長していく物語という意味では、これもまたビルドゥングス・ロマン(成長譚)。 「山猫」のキャラ造形がいい。汚い事も平気でやるし人もバンバン殺す。破戒者もいい所ではあるが、生き方の根本の所でガッチリ筋を通しているため、一種爽やかさすら感じ、彼をどうしても嫌えない・憎めないという主人公に共感しながら読み進められる。 ストーリー自体は流血に次ぐ流血、事件に次ぐ事件、その果てに街そのものが大変な事になるワケだが、そこは読んでみてのお楽しみということで。 余談ながら。私個人としては本書を読むのは15年ぶりくらいになる。が、その間色々読書体験にも変遷があり、BLジャンルなども当たり前に読むようになっていたため、久し振りに読んでみると、なんとも主人公と「山猫」の関係がエロチックに感じられた。全身フェロモンの肉食獣系な中年のメンターに翻弄されながら成長する、ハンチクな青年。そりゃあエロいわ。 ということで。人の命が紙のように軽い舞台設定、その舞台設定故に女性が性的に酷い目に遭うシーン(特に扇情性は無い)などの心理的ハードルはあるものの、男女問わずに一度読んでみて欲しいタイトルだと思う。
1投稿日: 2013.10.10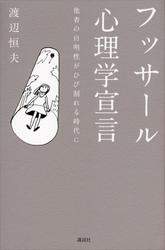
フッサール心理学宣言 他者の自明性がひび割れる時代に
渡辺恒夫
講談社
要・現象学の予備情報
発達心理学の知見として、子どもは生まれて間もなくから母親との関係を中心にして、間主観性(自分以外に意志を持った人間が居る)を自明の事として受け入れるとか。 ただ、「意識」が成長して観念的思弁を身につけるにつれ、いつか「なぜ(この思弁する意識の)私は、(今ここに肉化された)私なのか」という疑念を抱く時が来る。「なぜ私は今ココの私であって、他の誰かでないのか。別の時代の別の世界の誰かでもないのか」。 多くの人間は自明性に満ちた日常の圧力に流されてそれを忘れたまま過ごす事になるが、そこに躓いたままになってしまう人がいる。それも結構な割合で。 自分自身の自明性が壊れると、その補完処理を試みる果てに他者の自明性も壊れていく。こんな意識を持った自分だけが特別(自分が人であると同時に神である、自分だけが空っぽである等)という独我論に踏み込んだりもする。 著者はそこに現象学の知見を生かせると捉えている。具体的にはエポケー(自明の事を思考の上で括弧に入れ、例えば目の前の花瓶の存在を触覚だけで捉え直すような思考実験)を逃れられず強いられている状態という考え方になるだろうか。 かなり噛み砕いた説明が本書では行われているが、やはりフッサール現象学について何らか(現代思想の入門書等でも構わないが)の予備情報を頭に入れた状態で読み進めないと、なかなか歯ごたえのある内容になっているのでないかと。 個人的には忘れかけていたフッサールを再学習しつつ、マッハやシュレーディンガーといった古今東西の興味深い「症例」に接する事ができたので、楽しめたと思う。
2投稿日: 2013.10.09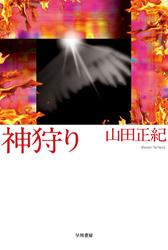
神狩り
山田正紀
ハヤカワ文庫JA
著者の商業デビュー作
数年ほどブランクを空けては忘れ、忘れては買い直して、これで通読3回目。 「情報工学の天才」な主人公が巻き込まれたトラブルから始まり、人智を越える論理構造の言語との格闘、 果ては霊感能力者までゾロゾロ登場してタイトル通り「神」を「狩り」たてようと試みる物語。 神は邪悪なりというテーゼを大前提とする展開になるため、その辺合わない人には厳しいかも。 執筆された時代の空気によるものか、今改めて読んでみると「幻魔大戦」を何となく思い出した。 (相手が強大すぎてオープンエンドにならざるを得ない所も含め) 同人誌用に執筆した原稿を代表が編集部に持ち込んでデビュー決定という経緯も異例だが、 同人でここまで描ききってしまう筆力は流石というべきか。
0投稿日: 2013.10.08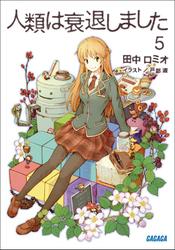
人類は衰退しました5
田中ロミオ,戸部淑
ガガガ文庫
今回もまったり。
前半章は女学生友情ネタ、後半章はレゲー愛好者がニヤニヤするゲームネタ。 相変わらずシリアスとは無縁のシリーズだが、前半章は「わたし」の性格の屈折ぶりの起源を 垣間見る事になり、ちょっと作品違うのではと軽く戸惑う羽目に。 なお、版元提供の電書の仕様によるものでしょうが、前半章の各小見出しが地の文に書体も変えずに 普通に紛れ込んでいる構成になっているため、読みながら小石に蹴躓くような違和感を覚えました。
0投稿日: 2013.10.07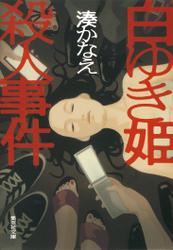
白ゆき姫殺人事件
湊かなえ
集英社文庫
「容疑者Mの消失」
他作者の「桐嶋、部活辞めるってよ」が、キーパーソン桐嶋不在で「藪の中」的に展開される周囲の思惑模様を描く内容とすれば。 こちらはキーパーソン不在のまま周囲の悪意と(善意による)悪行が展開される、実に実に湊かなえ節。 最後にキーパーソン当人の独白とともに真犯人と事件当時の事態も一応判明するワケですが。 真犯人も犯行手段も割とどうでもよくて、事件に踊る閉鎖社会の情念というか日常と隣り合わせの悪意というかが、ひたすら読者の事件展望を翻弄する内容でして。所謂ミステリーではない。 そういう著者独特の露悪趣味を楽しめるかどうかが一つの分かれ目になる作風ですな。
0投稿日: 2013.10.06
あかんたれさんのレビュー
いいね!された数97
