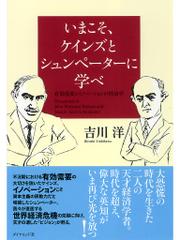
いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ
吉川洋
ダイヤモンド社
経済政策への蒙を啓く良書
まず前提として、当方教養課程で(新)古典派を学習、現代思想的関心による興味本位で資本論を読了。ケインズ派というかマクロはとっつき辛いと思っていたが山形浩生氏翻訳のクルーグマンの一連の公刊物で関心を抱き「一般理論」を(こちらも興味本位で)読了という経歴の、床屋談義メインな市井の野良ケインジアンという立場です。 現在の世界的不況、及びクルーグマンのノーベル賞受賞で(それまで古典派に何度目かの葬送が行われたにも拘わらず)改めて脚光を浴びたケインズ、そしてある意味ケインズ以上に「経済学者」でありながらあまり注目を浴びておらぬ同時代人のシュンペーター、この2人の人生を辿りながら、それぞれの主張と独創性を大づかみに描き出したのが本書といえます。 人生のタイムラインに沿った学説概略紹介は分かりやすく、また双方の欠点についても避けることなく触れているので、不況対策にどういう経済の捉え方をすればいいのかを理解するには好適書と言えるでしょう。個人的にはほぼ事前知識皆無だったシュンペーターについて理解を深められました。 現在アベノミクスへの評価という形で、(政権への支持は別として)消費増税以外は概ね支持を見せるケインジアン側と、強固な批判者として旧来のIMF的な財政健全論(これはかなり問題外)と「金融政策よりも構造改革」な古典派系との対立が見受けられ、両者の論議の断絶が気に掛かっていたのですが。 シュンペーターの主張する「イノベーション」を現在的に捉え直すと、「経済」はマクロな政策とミクロな経済活動、それと別の第三の評価検討軸として産業構造というものが必要になっているのではないでしょうか。産業全体を「第〇種産業の規模は…」と語るのでなく、各種産業自体の構造が硬直化していないか、「創造的破壊」を封殺して緩やかな自死を容認する構造になっていないかといった視点。そうすると、財政健全論はともかく構造改革論とケインジアン的マクロ政策論双方の強みを生かせるように思います。特に企業依存型経済になっている日本の場合においては。 シュンペーターが主に主張していた景気循環論は著者も批判しておりますし、個人的にも(経済史の視点としてならともかく)お話にならない印象があるのですが、この点については検討すべき視点を提供してもらえたし、価値があったと感じられました。
0投稿日: 2013.11.21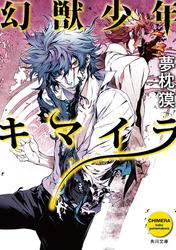
幻獣少年キマイラ
夢枕獏
角川文庫
ラノベ揺籃期に生まれた傑作シリーズ
子ども向けと一般向け小説の間隙に生まれたジュブナイル・ジャンルが、SFブームの若年向け受け皿となり、やがてメディア・タイアップノベル、キャラクター・ノベル化して所謂「ラノベ」へと変貌していったように記憶しておりますが。その中でも人気ブランドだった、今は亡き朝日ソノラマ文庫の看板タイトルの一つが本作。 元々のバージョンを知る身としては、天野喜孝氏でなく三輪士郎氏のイラストに(良い悪いではなく)軽い違和感を覚えるものの、いざ読み出せば中身は変わらぬキマイラ。張り詰めた筋肉と骨の軋む音の聞こえそうな夢枕獏氏ならではの肉弾戦描写を堪能できます。 美貌の少年2人の宿す共通の秘密「キマイラ」、2人の間に絡み合う因縁、2人を見守る雲斎や九十九の懊悩、人智を越えた強者達の戦い、…全てはここから始まりました。
4投稿日: 2013.11.18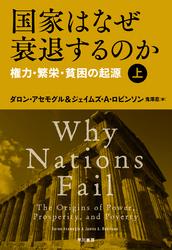
国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源(上)
ダロン・アセモグル,ジェイムズ・A・ロビンソン,鬼澤忍
単行本
凡庸なれど緻密な文明論(上下巻通読)
基本的に本書のテーマは王道にして明快。なぜ国家で貧富差が出るのか、なぜ国家が隆盛したり衰退したりするのか。 まず中央集権体制がなければ国民の生産活動もイノベーションもままならぬ、でも包括的制度でないと生産活動やイノベーションを胚胎し推進するインセンティブに欠ける。 ここで頻出する対立軸「包括的制度」=法の支配・万民の法の下での平等的政治体制、アンド万人が既存経済システムの創造的破壊を生じるイノベーションを生み出しうるような経済体制。対する「収奪的制度」=絶対者やエリートの専横による政治体制、アンド経済的強者が自分の利益の源泉たる経済システムを守るためにイノベーションを圧殺するような経済体制。これを念頭に置いて読む限り、全体に一般書として充分分かりやすく各種国家・文明の成り行きが描かれている。 要するに政治的自由主義の中でも多様性容認な現代型、そして経済でも自由主義が、国民の持てる総力を生産活動やイノベーションにつぎ込めるから強い、と。 どうすればそうなれるのかは、各国の「制度」に関わるため多様な経緯を辿るし偶然に依存する部分も多々あるが、その結論は変わらない。 恐ろしい程に王道でベタ。だけどそれを導出するために言及・調査されている世界各国各地域の量が膨大で、有無を言わせぬ程の説得力がある。 ある意味教養課程の経済史や、受験論述用の世界史の副読本としても利用価値があるのではないかと。 ただ、若干ひっかかりを禁じ得ないのは、本書の批判対象への言及。ジャレド・ダイヤモンドの地政学やヴェーバーの文化・倫理を一刀両断してしまっているのだが。 確かに両者ともに根拠や原因とするには弱いのだが、地政学は文明の発展にとって有利な条件ではあったろうし、ヴェーバーは元々社会事象の原因が多様である事を前提にした上で資本主義黎明期の駆動力に新教のメンタリティが資したという論調ではなかったかと(この点、マルクス主義側からのヴェーバー批判のように類型化が著しい)。 また、包括的制度の世界的極限たる合衆国が今陥ってる苦境はどう説明されるのか。例えば今の日本のように(他の原因も非常に多いが)一定水準の生活インフラが整ってしまった事で、イノベーションが生み出せても滅多な事で「創造的破壊」に至るような社会的インパクトが生み出せなくなってないか、とか。 それらの疑問は原著者の別のタイトルを参照すべき話ではあるのだろうが、いずれにしても本書の価値を減ずるものではなく、政治経済史・文明論として読む価値のあるタイトルだと思う。
3投稿日: 2013.11.14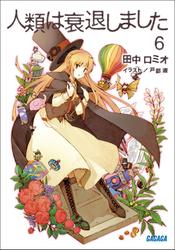
人類は衰退しました6
田中ロミオ,戸部淑
ガガガ文庫
一家に一人、ようせいさんを。
楽しそうでいいなあ。いやまぁ当の執筆者にとっては大変だろうけど。 今回は(技術力が失われているにもかかわらず無謀にも実施される)鳥人間コンテスト、そしてアニメでもぶっ飛んだ内容で楽しませて貰った同人誌制作&即売会ネタ。 後半パートの方では雑誌連載のスケジュールや構成プランがgdgdになって編集サイドがマトモなアオリ文をつけられないネタ等、所々に「分かってる人」向けのニヤリとさせられるネタが仕込まれていて、これが実に「人退」らしい面白さ。 メンタルに屈折して、ねじ曲がって、ぐるりと一周して、一見まっすぐに戻ったかのように見える田中ロミオワールドは癖になります。
0投稿日: 2013.11.05
海戦からみた太平洋戦争
戸高一成
角川oneテーマ21
今、艦これネタでコラボ販売展開してほしい一冊。(13年11月初旬時点見解)
……だって角川の刊行だし。二次大戦の海戦ネタなんだから、正にドンピシャリでしょう。寧ろなんでやらないのかと。 とはいえ、艦これライトユーザー的視点で読み出すとメンタル的に殺されます。 二次大戦の各種海戦で、どういう経緯でどういうメンバーがどういう判断を下し、そこからどういう結末が訪れたか。 主要海戦ネタを時系列に沿って敗戦まで解説しておるワケですが。 艦これで名前の挙がってくるあの船・この船が片っ端から轟沈撃沈していく展開が延々続くのですよ。 しかも原因が、戦術・戦略レベルの頑迷さや大艦巨砲主義への拘り、失策当事者にリベンジマッチの機会を与えるために碌な罰もない指揮体制、日本の被害最小化よりも海軍のメンツ重視な姿勢とか、そういうフォローのしようも無いダメダメな要素ばかりなワケですよ。 もう何と言うか、過去の猟奇事件の被害者の写真を偶然見て一目惚れし、気になって事件の概要を調べてみたら果てしなく陰惨な状況を目の当たりにしてしまったような、マイルドなメンタルレイプ喰らう気分ですよ。 でもいいじゃないですか。過去の史実が元ネタなんだし、ならば史実を多少なりとも把握した上で楽しみたい。当時の愚かしさを再現しちゃいけないって気持ちだって湧いてくるってモンですよ。
0投稿日: 2013.11.04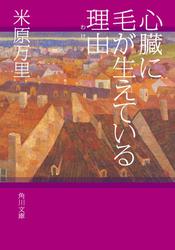
心臓に毛が生えている理由
米原万里
角川文庫
日本人でありながら外国人
著者の米原万里は日本人だが、親の仕事の都合で幼少時長期間プラハ(チェコ)にて過ごしていた。 当時は共産主義体制全開なので、当然学校に行くといってもソヴェト学校で、学校内ではロシア語が公用語。 その結果、長じてロシア語同時通訳という職を得る事になるのだが。 そのロシア事情の通暁ぶりは、外務省在籍時にロシア通として通っていた佐藤優すら驚くほどである(政治的観点から捉える佐藤に対し、生活者視点を確実に押さえていく米原)事は、著者の名著「嘘つきアーニャ~」の解説でも触れられている。 反面、当人は日本語で書く自分の文章に満足できていない事が本書で触れられている。ネイティブなら自然な崩し方を当たり前にしている所で、非常に綺麗な・丁寧な書き方をしてしまう所が、所謂「よく勉強した外国人」的になっていると感じているようで。 だが、それが逆に良かったのではないだろうか。 当たり前の日本人の視点とは違う、ロシア人・プラハっ子的視点で世界を捉える事ができる点が、著者の大きな魅力であるのも事実だが、日本語は崩し方に慣れてしまうとすぐ情に流されたウェットな文体になってしまうように思う。そのウェットな文体では、「嘘つきアーニャ~」のような、心にジワジワと染みこんでいくような感銘が出て来ないのではなかろうか。 そんな著者の日々のエッセイ。「嘘つきアーニャ~」執筆の裏話なども掲載されており、楽しく読了させて貰った。
4投稿日: 2013.11.04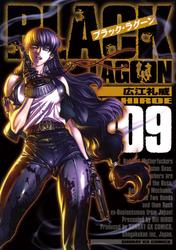
ブラック・ラグーン(9)
広江礼威
月刊サンデーGX
やっと配信が来たロベルタ編完結巻。
原著刊行時から賛否分かれたロベルタ編。 個人的には有りです。だってもうロベルタってリビング・ターミネーターなんだし、メインで出てきた時点でリアルよりも活劇優先にしかならないでしょ。 それよりも寧ろ、こういう破壊的・破滅的に暴走するキャラに対し、ロアナプラの主立った面々もなまじキャラとして立って行動特性も明確になっているために、「手綱を引く」事ができなくなっている所のピーキーな危うさというか緊張感が、読んでて胃にキリキリくる。 それ故にか、ロックがこれまでのストーリーから一歩も二歩も踏み込んだ「成長」(?)を遂げて、読者の代弁者であると同時に本作のストーリーテラーの代弁者でもあるかのような、キャラとしてのブレを見せていく。当然、本来被造物たるキャラの立ち入るべきでない危うい領域に踏み込んでしまっているだけに、結末は苦い物にしかならない。 そこが結構嫌われる要因にもなっているように思うが、著者の苦闘を(ストーリーというオブラートにくるんだ格好であれ)ライブ実感できるというのは、一つの楽しみ方ではないだろうか。肌のひりつくような緊張感と胃の痛くなるような危うさは、偶に堪らなく読み返したくなるのですよ。
3投稿日: 2013.11.04
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
マックス・ヴェーバー,大塚久雄
岩波文庫
分かりやすい現代語訳で古典の名著を
社会学的に避けて通れない程の名著。 久し振りに電書で読んでみたら、以前読んだのが何時のどの版かは定かではないが、随分噛み砕いた翻訳で読み易くなっていて驚いた。……とはいえ一種の「専門書」ではあるので。まずは訳者による解説を一読した上で、改めて本文を、脚注は飛ばして読み進めるのをお勧めしておきたい。脚注は全体像をそうやって把握した上で、著者の多面的な関心や著者への批判に対する反批判を押さえておくために読むのがベター。 (なお電子書籍版では後半1/2が索引と、ハイパーリンクでジャンプするための脚注[本文内に記載されたものと同内容]で占拠されているため、ぱっと見ほどのボリュームでもなく、割と楽に読み終えられる) 大澤真幸的理解で噛み砕くと。 それまでの中世的世界観は誕生>幼児>大人>老人>死の円環を、直近世代で若干の重なり合いを持ちつつも、延々繰り返す…厚みゼロの円を、世代を重ね延々繰り返すようなイメージだったと。 そこに宗教改革の波が押し寄せた。ルターがBeruf(天職)概念を聖書翻訳に導入し、カルヴァンで更にその世俗化(生臭な聖職よりも清くつましい生活を送る世俗者の方が救われるべき>修道士の生活スタイルで世俗生活を送る事が推奨され、儀式儀礼的なモノが排除される)が進められた。 更にカルヴァンの後継たるカルヴィニストらでは「神の恩恵が与えられるのは一部の選ばれた者だけ」という予定説概念が導入される。 その恩恵を受ける「予定」に入っているかどうかは、絶対者たる神と相対者たる人の間が断絶している以上説明も理解も不能。 しかし、「人間には推し量り得ないとはいえ、神は合目的性を持って世界を生み出した筈」「だから合理的な社会の実現のために邁進すべき」「そして被造物神化(偶像崇拝の拡張概念。物神崇拝)は厳しく抑制されるべきだから、生理的な欲求も厳格にマネジメントし、利益や財産の発生は否定しないがそれに安逸してはいけない」という、実践を行う事によって自分が選ばれた者である事を実感できる、という。 ここで最後の審判という無限遠点に至るまでの時間を、果てしなく微分した「今」の実践で時間を捉える…直線的・一方向進行的に時間を捉える…世界観が生まれたのだとか。 (ヴェーバーの本書に微分概念は出て来ない。また生活時間を一定時間で区切って管理するスタイルは修道士の模倣で生まれた事に注意) これは一種のカルトとも言える思考であり、メンタル貴族主義でもあり、常に自分が救われるべき存在である事を確信したいがために、強迫神経症的に「実践」を強いられる事になる。 その強迫神経症が資本主義黎明期の爆発的なエネルギーを生み出した、という考え方が本書の基本トーンになるだろうか。 大澤理解によれば上記の時間概念のパラダイム変化により、中世の資本主義=遠隔地貿易のリスクテイクによる利潤から、近代・現代の資本主義=時間の離れた未来に対するリスクテイクによる利潤、が生まれたという捉え方もできるが、それは本書から離れた別の話。 何はともあれ。折角読み易い翻訳で名著が刊行されているので、読まない手は無いのではないかと。
2投稿日: 2013.11.04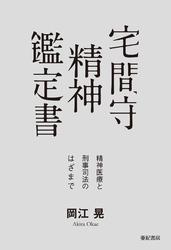
宅間守 精神鑑定書――精神医療と刑事司法のはざまで
岡江晃
亜紀書房
用法・用量注意。リアル「深淵」です。
「深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ」(ニーチェ)。 この言葉に準えるなら、本書はまさにリアルな深淵。 裁判所命令による鑑定のためそれほど時間・時期に余裕が取れなかっただろう事は十分推察できますが、その限度でこれだけの調査・面談・分析をよくぞ行ったと驚かされます。被告人宅間守の生活・生態が実像を伴ってイメージされる、それほどの情報量。 被告人に殆ど同情の余地が無い(社会規範の認識は十分にある事は本書からも伺え、それでなお犯行に及んでいる)のは事実ですが。 全体像として見ると怪物めいているものの、個々の「腹が立った」「イライラした」エピソードは、それを暴行や犯罪の実行に移すかどうかはさておき、何かしら身に覚えのある感情でもあるのもまた事実。 報道内容や被告人の言動の数々を見ると、「これぞサイコパス(精神病質)」(※サイコパスのカテゴリはDSM4で既に削除済)と言いたくなるところですが、ロバート・D・ヘアの「診断名サイコパス」を振り返るに、サイコパスの脳波等には一般人との間に顕著な違いがある、最早人の姿こそしているもののある意味別種だ的な描写があったかと。しかるに、本鑑定で詳細に行われた調査分析によれば、中脳の一部に軽度の小さい腫瘍の存在が疑われるものの、それが精神状態に影響したとは認められておりません。知能発達の多少の遅れ、幼少時からの情性欠如(共感・思いやりの感情欠如)による人格障害が認められるものの、それ以外の生物的・物理的異常は無い。 つまり、被告人の生態は、へだたる距離に長短あるものの、我々とあくまで地続きなのです。 情性欠如したまま独我論な世界像を抱き、自己愛を延々肥大させて、何かしたい・欲しいとなったらそれが犯罪でも暴力・脅迫など手段を選ばず実行し、一寸たりとて我慢できない。その癖、それ故に離反される自分・抽象的思考に劣る自分が自覚できているために、他者への猜疑心も自己愛に比例するように肥大させて、断続的な精神科通院や投薬と勝手な断薬による離脱症状などでブーストがかかり、この被告人は精神的に常在戦場状態になっていたのだろうと推測しますが、素人の組み立てたストーリーなんぞより著者の鑑定意見の方が億倍有用でしょうから、これ以上の私論は割愛させていただきます。
2投稿日: 2013.10.22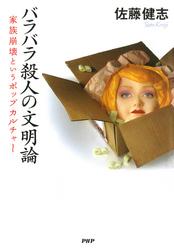
バラバラ殺人の文明論 家族崩壊というポップカルチャー
佐藤健志
PHP研究所
ネタ目的でならば。
私的事情を語るならば。私ゃ精神科入通院経験者で、所謂「寛解」(一応安定した社会生活が営めるが、再発の可能性は否めない。寧ろ一度この手の発症をしてしまうと、非発症者よりも可能性は高い)した身ですが。 発症した辺りの頃から、事件もの・殺人もののノンフィクションやルポを読む習癖ができてしまいました。「深淵を覗く時、深淵もまた~」というニーチェの言を出すまでもなく、コレは事件当事者の心理や社会の反応などを見て、自分の現時点での心理状況を「測量」したい意識によるものです。 本書はタイトルよりその路線を期待して衝動買いしたのですが、大きく思惑が外れました。 所謂「(政治的)保守論客による社会批評を、事件やサブカル論を交えて行っている」本です。 事件について正面から扱っているのは一章分のみ、それ以外では論争のネタ、若しくは別の批評中に引き合いに出される程度。 それはそれとして、折角正価で購入した本だから「よかった探し」でもして楽しもうと試みるのが書痴の習い性。 所謂「ネトウヨblog本」として読めばなんとか楽しめました、というのが正直なところでしょうか。 保守が基本スタンスで、事件・映画・ジブリアニメといったサブカル事象への批評を主軸とする所は、スタイルとしては今風で、趣味の合う人もそれなりに居るのではないかと。 政治的スタンスも事件分析も社会批評の視点も大きく異なる立ち位置の身としては、これ以上多くを語るには相応しくないでしょう。 なお、本書に限らず。町山智浩氏の「作品批評は作品を語ってるように見えて違う。作品をダシにして自分語りをしているんだ」という言葉(元ネタは小林秀雄の「様々なる意匠」と思われる)にもあるように、社会学者のサブカル論や、社会批評で採り上げるサブカル評は読む際に注意が必要かと思われます。ワイドショー解説などでよくある、俗流フロイド論のような「結論先取りで考えた事を敢えて隠蔽している」リスクがあり、採り上げた作品・事件その他に対してかなり強めにフィルターがかかっている事を折り込む必要があるためです。立論が家庭問題であれば尚更。 (※個人の体験及び感想です。効果・効能には個人差があります)
1投稿日: 2013.10.19
あかんたれさんのレビュー
いいね!された数97
