
NieA_7 Recycle
安倍吉俊,gK
ヤングエース
安倍吉俊氏の漫画家業の出発点
個人的に色々と関わったタイトルではあるので中立的に語るのが難しい所ではあるのだが。 lainのキャラデザインなどで注目を浴び、今やリューシカ・リューシカ連載中の安倍吉俊氏の商業誌デビュー連載作です。 同名アニメとのタイアップ連載でもあり既に其方を観た人も多いでしょうが、こちらも下品・悪趣味な危険球ギャグをポンポン繰り出しつつ、時折しっとりした描写の妙を楽しませてくれます。 惜しむらくは、電子化の際にコントラストを少し上げて欲しかった。 枠線を含めた全てを手書きの薄墨(?)で起こしているため、紙で見ると味わいを感じるのだが、電子端末では可読性が少々悪くなってしまっている。
3投稿日: 2014.01.02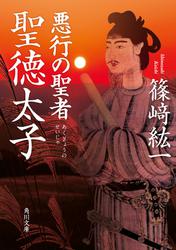
悪行の聖者 聖徳太子
篠崎紘一
角川文庫
史実から推理した人間・厩戸皇子
中々刺激的なタイトルだが、中身は割と堅実な歴史小説。 聖徳太子については人間離れした各種能力や斑鳩寺、六角堂、十七条憲法に冠位十二階などが知られているが、資料に残る足跡の少なさなどから、あくまで伝説上の人物とする見解もあるが。 本書ではその能力は政治的ライバルへの対抗上、部下が勝手につけたハクと片付けた上で、旧来の皇位を継承する身と仏教信奉者としての価値観の板挟みで苦悩する皇子の半生を描いています。 じゃあライバルは誰かというと、これが自分のイロを女帝・推古天皇に祭り上げて皇室内外で好き放題していた豪族の蘇我入鹿。 まだまだ中央集権が確立していない時代だからこその、分の悪い勝負ではあったのです。 太子の悩みや懊悩に至る考え方がやや現代的で軽く首を傾げたくなる所もあったものの、古代史キー・パーソンの生き様を知るには面白い書物かなと。
0投稿日: 2014.01.02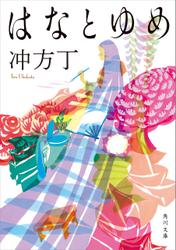
はなとゆめ
冲方丁
角川文庫
時代小説二作とは趣が違う歴史小説
天地に光圀と、男の心意気とか侘しさを熱く描き出した著者の新作という事で、事前調査もせずに勢いだけで購入。 タイトルが……うん?白泉社?(それは違う とか思ったりしたけれど、内容的にもかなり違うタイプのボール投げてきたなという感じ。 「この世をば望月と…」を詠んだ事、安倍晴明の上司としてなどで知られる平安宮廷政治の頂点・藤原道長の弱さやドス黒さを、ライバル側の中宮やそれに仕える清少納言の側から描いております。 (主人公が清少納言故に、語調は抑えながらもかなり辛辣) 現世的な栄華や絆は儚いけれど、心から愛し合えた者同士の幸せは一瞬であれ永遠の輝きを放ち、魂で結ばれた絆は永遠である事が淡々と描かれていきます。
6投稿日: 2014.01.02
原作屋稼業 お前はもう死んでいる?
武論尊
講談社
原作のノウハウや実態に期待する本ではない
……いや、書籍説明を見れば分かるように、フィクションなのですよこの本は。 著者が前書きで「そんなの書く柄じゃねえから」といった旨で全編そういう本になるように宣言しておりまして。 現代を舞台にした企業のグローバル化の進んだ社会で軽く落ちこぼれたサラリーマンが会社を辞めて一念発起、偶然出会ったブーさん(著者の武論尊氏)を師と仰ぎ原作者の道を志す、でも弟子を取るタイプじゃないブーさんは相手にしてくれず、取り巻きの出版社編集に指導を受ける、という内容。 それ自体は割と不思議でも何でも無い。ただ、ストーリーが進むに連れてどんどんキャラの方が独り歩きして、原作者の道も糞もない路線にどんどん進む進む。 貧乏な育ちの幼なじみは出るわ、ヤクザというかチンピラによる借金取り立ては出るわ、タコ部屋描写は出るわと、もう昭和の劇画世界が全開。 編集者たちも数多く出てきますが、昭和時代のアクの強い人物ばかりで平成の世ではコンプライアンスに問われそうなキャラばかりで、これも昭和感覚満点。 とはいえそう派手なアクションやバイオレンスがあるでもなく、最終的に収まるべき所に収まってチャンチャン、となるワケではありますが。 様々な人生経験や人間観察が必要、デビュー作よりも2作目以降をちゃんと書き続けられる事が大事、常に満たされない渇望が創作の原動力といった、割と原作者に限らず漫画家・執筆者全般に共通する一般論抽象論以上の何かがあるでもなく。行間から業界人の貴重な情報が得られるのかと期待すると肩透かしを食らってしまうのです。 それすらも劇中のブーさんに言わせれば「んな大事な事、ポンポン商売敵に晒せるかよ」と微苦笑されてしまいそうですが。
0投稿日: 2013.12.19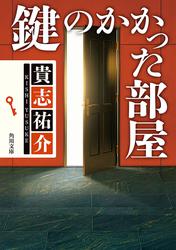
鍵のかかった部屋
貴志祐介
角川文庫
締まりのいい密室トリック集
「硝子のハンマー」(シリーズ1作目)を読了した後ウッカリ本書を読んでしまい、途中で2作目を読み忘れていた事に気付くという迂闊な真似をしてしまったが。 連作短編シリーズのメリットというか、割とそういう点に気を遣わずに読了できた(収録最終話は、流石に以前に事件のあった劇団ネタだったので若干厳しかったが)。 連作短編故に、防犯探偵・榎本と青砥弁護士の2人のキャラさえ最低限把握していればいいし、短編で密室トリックを扱っているためキャラの背景事情や関係性などを掘り下げるような、ある意味「寄り道」が無く、純粋に知的遊戯たるトリックの謎解きに集中して楽しめる。 「黒い家」等のホラーサスペンスや、「新世界より」のようなSF、「悪の教典」のようなピカレスクでもない、推理作家としての貴志祐介を気軽に満喫できるシリーズだと思う。
6投稿日: 2013.12.11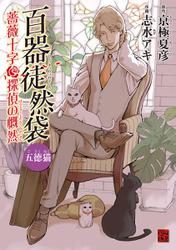
百器徒然袋 五徳猫 薔薇十字探偵の慨然
京極夏彦,志水アキ
コミック怪
相変わらず美しい、のだが。
志水アキの京極堂漫画は個人的にも「これこそ京極堂だよな」と思わされる説得力を持っており、相変わらず榎木津は榎木津で美しく傍若無人で素晴らしいのだが。 (脇役の顔が安定しているのに、京極堂本人の顔が今に至るまでその場のシチュエーション依存でコロコロ変わって安定していない、とかいった話はさておき) 本書も原作を読んでから相当にブランクがあった事もあり、十分に「快刀乱麻な榎木津探偵譚」を楽しませてもらったので星4つをつけさせていただいた。が。 巻頭口絵見開きは、せっかくのカラーページなのに割とザックリしたラフなタッチで榎木津を描いているのが非常に勿体ないなあ、と。 また、本書の場合目次がカバーの折り返し部にあるため電子化の際に表紙(カバー絵)の直後に収録されているのだが。目次の無い場合でもカットが描かれているのだから収録しておいてほしいし、カバーの中にある本体表紙では、(京極堂漫画では)カバー絵を踏まえてキャラを変えたイラストが収録されていたりするから、それも折角だから見せてほしい。そんな「電子書籍化の仕様」に関する不満足が、逆に目次が収録されていた事で思い出される事になった。これは著者の非というより版元や版元各社による仕様策定の問題だとは思うのだが。 漫画本編は相変わらずキャラも背景も非常に丁寧に描かれていて、いつもの「志水アキ京極堂漫画」になっており満足です。
1投稿日: 2013.12.11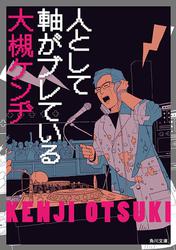
人として軸がブレている
大槻ケンヂ
角川文庫
いつもの大槻さんですね。
ミュージシャンであり小説家でもあり江戸川乱歩に一家言持ち、オカルトネタにも強い、とマルチに活躍している大槻ケンヂの、ぴあ連載コラム(と思われる)書籍化。 武道館ライブを何度もやっておきながら、プロレス観戦の思い出やクラプトンのライブの客席でアナウンサーの小倉氏を見かけた時の思い出しか無いとか、もういい歳なんでライブ中に血糖値が足りなくなってチョコを要求したエピソードとか、フェス参加時に(筋少復活までのブランクが長かった事もあり)他のミュージシャンと楽屋で会話を弾ませようとオカルト誌「ムー」を持参したりとか、色々期待通りの日々を送っている様が赤裸々に綴られています。 ……ああ、勿論後進ミュージシャンのために為になる事も書いてます。事務所に搾取された体験談とか、親がライブに来た時は関係者席のセンターには座らせるなとか。 個人的には、ちょうど執筆時期が筋少復活や絶望少女隊(「さよなら絶望先生」アニメ時の声優ユニット)活動時期とかぶっていたため、異色キャラな声優の小林ゆうのエピソードが収録されており、そのインパクトが強かったので、そればかり脳裏に焼き付いてしまいましたが。 まぁ具体的に何があったかは読んだ人のお楽しみ、という事でご容赦を。
6投稿日: 2013.12.11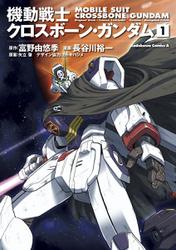
機動戦士クロスボーン・ガンダム(1)
長谷川裕一,富野由悠季,サンライズ
ヤングエース
貴重なガンダム正史オリジナル漫画
少年エース誌創刊時の密かな目玉の一つ、富野監督自身が原作を担当した宇宙世紀ガンダム漫画。 宇宙世紀系ガンダムのファンにとっても、当初オリジナルへの回帰を狙って富野監督・安彦氏と大河原氏によるキャラデ・メカデによって制作された劇場アニメ「F91」のTVアニメへの移行が頓挫した経緯を考えれば、「企画されども存在できなかったF91の正史続編」という事で意義深いタイトルです。 作画の長谷川氏は「マップス」(本作開始十年前からの連載)に代表されるようにSF・熱血路線の漫画には定評のある人気作家。絵柄が今の読者にはやや古さを感じさせるでしょうが、ちゃんと読めば逆に「漫画の魅力は絵だけでなくシナリオやコマ運び等の画面構成力が大きいんだ」と実感できる事でしょう。 メカデザインのカトキハジメ氏は今や「Ver.ka」でガンプラ・ブランドにもなっていますが、本作ではその路線とはやや毛色を異にして「宇宙海賊としてのガンダム」コンセプトを強調すべく、ドクロマークを大きくあしらった、ややマンガチックなデザインをしており、氏のデザイン史的にも意義が見出せます。 F91から引き継いでいるキャラはキンケドゥ・ナウ(シーブック・アノー)とベラ・ロナ(セシリア・フェアチャイルド)、ザビーネ・シャルの3名のみ。 大分宇宙世紀シリーズよりジュブナイル的SF活劇路線に踏み込んだ作風になっており、そこに長谷川カラーを強く感じますが、それもまた富野氏の意向でしょう(Gガンダムで今川監督を起用し既存ガンダム像を壊すよう指示した人でもあるだけに)。寧ろ紙の本のカバー折り返しの著者コメントでは、長谷川氏の描く女性キャラが全体に年齢低め・幼めに見える事がやや不満だった様子が窺えます。 そして内容は最後まで徹底して「宇宙に棲まう人類」と「地球」の関係であり、やはり紛れもない「ガンダム」。 「閃光のハサウェイ」同様に映像化からは黙殺されていますが、人気の高い「宇宙世紀ガンダム」である事に間違いはありません。 ゲームのスパロボへの登場を経てコミック廉価版(コンビニ本)がブレイクし、外伝「スカルハート」や続編「鋼鉄の七人」、「ゴースト(現在連載・刊行継続中)」が作られ、本電子書籍のマスターになったと思われる「(本タイトルの)新装版」も作られましたが、基本的に富野氏自身が手がけたのは本書のみ。 とはいえ、最後まで読み通した読者であれば、それら外伝・続編を読むことに最早抵抗は無いでしょう。そちらでも間違い無く本書のコアになったテーマは生かしつつ、「長谷川マンガ」になっているのですから。シリーズが続いて時代設定が後年になるほどに、「Vガンダム」との接続が見出されて興味深いです。
2投稿日: 2013.12.07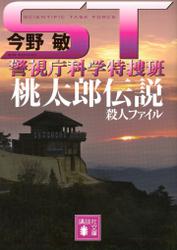
ST 警視庁科学特捜班 桃太郎伝説殺人ファイル
今野敏
講談社文庫
ライトでないキャラクター小説
大塚英志氏の立論以降、ライトノベル=キャラクター小説というイメージも随分定着し、最早ラノベを卒業して一般小説路線に転向される作家も散見されますが。 こちらのSTシリーズはそれとは異なるアプローチ。一般向けな事件小説であり警察小説だけど、ラノベもかくやのキャラの立ちっぷり。 科学特捜班のメンバーは百合根キャップとお目付役の菊川以外全員(警察組織外からの招聘ってこともあって)それぞれ一種人間離れした一芸能力を持ち合わせ、そのため凡人としての日常生活が困難に思われる程に性格も際だっており。 そのキャラ相互の遣り取りは「イラストの無いラノベ」と言っても過言でないレベルで、ラノベ以外の小説を滅多に読まない人にとっても気軽に読み進められるのではないでしょうか。基本的に一冊ごとに中心となって活躍するメンバーは一人に焦点を合わせた構成になっており、一冊読み切りが基本となってますし。 本書の場合、岡山を舞台に桃太郎伝説に関する民俗学的・歴史的アプローチを試みており、そこに紙幅を割いてしまったためか、表面上複雑に見える事件が割にシンプルな構造になってしまっており、ちょっと先読みしやすかった気がします。が、シリーズの持ち味となるリーダビリティーは健在です。
0投稿日: 2013.12.05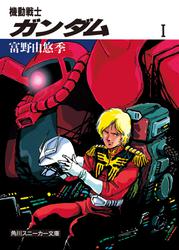
機動戦士ガンダム I
富野由悠季,美樹本晴彦
角川スニーカー文庫
挑戦という名の道標
初代のガンダムがTV再放送によりブームとなった時期に朝日ソノラマから刊行されたモノの出し直しバージョン。 (故に当時は放映半ばで安彦氏が倒れてしまった関係もあって、カバー絵はアリモノ版権のシャアの絵に背景を組み合わせただけ、挿絵も作監スタッフによるものになっていた) 既に人気が定着してからの刊行になるため、こちらのバージョンはカバー・挿絵が美樹本氏、巻頭にキャラ紹介やメカ紹介ページも加わりこちらも豪華スタッフそろい踏みの贅沢な構成になっております。本来見開き構成になっていたページを単ページ扱いで電子化した版元の処理は正直どうかと思いますが。 リアルタイムで紙の本を何度も読み返していた事もあり、今こうして改めて読み返しても当時の空気感が思い出されます。 キャラ設定やメカ設定がアニメと違う、ガルマの撃退が超絶アッサリどころか地球降下すらしないじゃないか、そもそも文章の「てにをは」が一部おかしいのはどうなのか、モノローグの主体が切り替わってる所で文節が上手く切れてないのはどうよ、と今の読者にとって色々ツッコミどころは尽きないとは思いますが。 この当時はこれが挑戦だったのです。 当時のロボットアニメは完全な商品のプロモーションツールで児童向けがメインであり、スタッフの名前すら(一部アニメファンを除けば)知られる事がなかった状況で。 それでもロボットアニメを作ってきたからこそ、富野氏はスタッフの作家的評価・地位向上のために色々試みておりました。阿久悠氏に教えを請うた(今に至るまで続いている)主題歌の作詞もそうですし、この小説もその一環と捉える事ができるでしょう。 ガンダムブームでロボットアニメをSFの一種として捉えるファンに対し、某SF作家が「ガンダムはSFじゃない」と公言して軽く騒動になったのもこの時期です。 そんな中で、コマーシャルフィルムの枠内で作られたアニメと(富野氏自身が考える)SF小説をなんとか融合させようとした試みの一つが、これだったのではないでしょうか。 本書終盤でララァは斃れ、ホワイトベースも沈み、ガンダムも廃棄され、アニメ同様に宇宙歴0080を迎えますが、戦争はまだ終わりません。 そこから先=2巻以降は、本書以上にアニメ本編から離れ、アニメのキャラとメカを借用した別の物語となっていきます。 アニメ本編で生硬な語り口になってしまったニュータイプ概念を捉え直すには、いいサブテキストになるやもしれません。
3投稿日: 2013.12.05
あかんたれさんのレビュー
いいね!された数97
