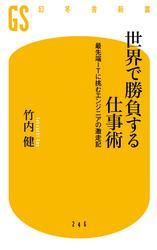
世界で勝負する仕事術 最先端ITに挑むエンジニアの激走記
竹内健
幻冬舎新書
半導体ビジネスの最前線で活躍する実体験に基づいた仕事術
本書は、変化の激しい半導体ビジネス環境で、常に第一線で仕事をし続けている竹内健氏の実体験記である。 私もそうだが、もしあなたが、守りを意識したミドルクラス以上のエンジニア、ビジネスマンならば、 「よし、私もできることから、前向きに仕事に取り組もう」 という気持ちにさせてくれる本であるし、若きエンジニアならば、ロールモデルとして本書は参考になるだろう。 というのも、本書は一般論を述べたビジネス書でなく、竹内健氏の実体験に基づいた言葉で書かれているので、説得力があるからだ。 竹内氏は、東京大学大学院を卒業後、東芝でフラッシュメモリの開発、スタンフォード大学ビジネススクールでMBA取得、フラッシュメモリ事業のビジネス責任者、東大への移籍、次世代メモリの研究、MOT(技術経営)の取り組み、というように変化の激しい半導体ビジネスの第一線で活躍されている。 そんな竹内氏が語る「走りながら考える」という仕事の姿勢は、私のような凡庸なサラリーマンにもとても参考になる考えだ。 『フラッシュメモリ開発で、私には「走りながら考える」という生き方が身につきました。』 『どんな仕事でも、クヨクヨ悩むより、まず走ってみることが大切だと思います。失敗したら、もう一度戻ってやり直せばいいのです。』 『しかし、跳ばないで待っているより、跳んで失敗した方が断然学ぶものが多いのです。最後に勝ち残るのは、リスクを怖がらずに跳んで、たくさん失敗した人です。』 『守りに入って生きていて、のけぞって後ろに倒れそうになると、人は案外冷たいものです。その一方、果敢に挑戦し、前のめりになって、つんのめりそうになると、人は手を差し伸べてくれる。』 また、その華やかな経歴からも、竹内氏は優秀で、才能があったから成功した、という見方もできるだろう。 しかし、そう考えるのは早計だ。 竹内氏は、苦労や下積み、そして人一倍の努力もされているのだ。 具体例としては、東芝に入社して待っていたのは、不良解析のため写真撮影という単純作業。しかし、それを地道にこなし、やがて、有効な回路アイディアを提案し続けることで、新たな業務ステップにはい上がっていく。 その頃のことを竹内氏は以下のように振り返る。 『いまになってみれば、それはとてもいい修業でした。貴重な下積み時代だったと思います。どんなことでも、地道に努力する以外に成長する術はありません。』 『いざというとき誰かに助けてもらうためには、自分はいつも最大限の努力をしていなければなりません。熱意をもってコツコツと頑張っていれば、それを見ていてくれる人は必ずいます。』 下積み、地道な努力、熱意を持った頑張り、など、ややもすると、普通のビジネス書では見過ごされがちな価値観の大切さを再確認できるだけでも、私は本書を読んでよかったと思った。 最後に。 例えば、Appleのスティーブ・ジョブズ氏のように、我々エンドユーザーにも分かる有名企業のカリスマ経営者の語る経営論や成功譚ではなく、重要な産業ではあるが、日の当たりにくい半導体ビジネスのエンジニアからこのような本が出たことは、これからの若きエンジニアにとっても喜ばしいことだと思った。
0投稿日: 2013.12.02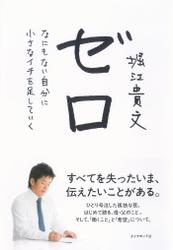
ゼロ
堀江貴文
ダイヤモンド社
自伝的形式をとりながら堀江貴文氏が「働く」ことについての考えを語った本
本書は、自伝的形式をとりながら堀江貴文氏が「働く」ことについての考えを語った本です。 なぜ働くのか?仕事とは何か?と悩み立ち止まっていたり、人生に前向きになれずにくすぶっている人に、本書はお奨めです。 もしこの本が、人生の成功者が「働く」ことの意義を語る本だったら、どこにでもある自己啓発書や、上から目線的な不快さを感じたかもしれません。 しかし、本書はそんな類の本ではありません。 堀江貴文氏は、我々と同じ「ゼロ」を出発点に「働く」ことの意義を語っており、説得力があると思います。 『僕は天才ではないし、名家の生まれでもなく、イケメンなわけでもない、ただの地方出身者だ』 という堀江氏は、人生の成長と成功には、「ゼロ」の自分に、小さな成功体験という「イチ」を積み重ねることが大切と言います。 『しかし、徐々に自分に自信を持てるようになっていく。 それはひとえに「小さな成功体験」を積み重ねていったおかげである。ヒッチハイクで心の殻を破り、コンピュータ系のアルバイトに没頭する過程で、少しずつ「やるじゃん、オレ!」と自分の価値を実感し、自分のことを好きになっていった。 なにもない「ゼロ」の自分に、小さな「イチ」を積み重ねていったのである』 『さあ、前を向いて最初の一歩を踏み出そう。バックミラーを見るのは、もうたくさんだ。有限の人生、絶望しているヒマなんかないのである』 ゼロにイチを足すためには、「最初の一歩」を踏み出すことが大切。 私自身、自分の仕事への取り組みや、働くことについて見つめなおすよいきっかけになった本です。 我々の気持ちを前向きにしてくれる本だと思います。
0投稿日: 2013.11.24
「原因」と「結果」の法則
ジェームズ・アレン
サンマーク出版
人生に理想を持つことが自分の人生を創り上げることにつながる
本書は、私自身もそうですが、人生の目標をつかめずにいる人にとって、自己啓発のバイブルとなる本です。 私は本書を読んで、人生に理想を持つことが自分の人生を創り上げることにつながる、ということだと理解しました。 今の自分の人生は、自分でコントロールできないまわりの環境のせいではなく、今までの自分の思いと行いの結果です。 だから、自分の人生を創り上げるためには、自分の人生に理想を持ち続けることが大切であり、それが、自分の行いを変え、自分の周りの環境を変え、やがて理想を現実化することにつながる事になります。 『私たちは、自分を環境の産物だと信じているかぎり、環境によって打ちのめされる運命にあります。しかし、「自分は創造のパワーそのものであり、環境を育むための土壌と種(心と思い)を自由に管理できる」ということを認識したときから、自分自身の賢い主人として生きられるようになります』 『気高い理想を掲げ、そのビジョンを見つづけている人間は、いつの日にか、それを現実のものにします』 『人間が達成するあらゆる成功が努力の結果です。そして、努力の大きさによって結果の大小が決定します。そこにはいかなる偶然も介在しません。物質的、知的、精神的達成のすべてが、努力の果実なのです。それらは、成就した思いであり、達成された目標であり、現実化されたビジョンです』 このように、本書は、自分こそが人生の創り手であるための原則的なことが書かれています。 迷いが生じた時など、折を見て、バイブルのように何度でも読み返しても良いと思います。
7投稿日: 2013.11.17
「7つの習慣」 第一の習慣:主体性を発揮する 選択する力
フランクリン・コヴィー・ジャパン
キングベアー出版
主体的に自分の人生を切り開きたいと考える人におすすめ
「7つの習慣」は、人生で成功するための原理原則についてまとめた本です。 主体的に自分の人生を切り開きたい、と考える人におすすめの本です。 私がこの本を信頼できると考えた理由は、人格主義をその基礎に置いているからです。 というのは、「7つの習慣」は、スティーブン・R・コヴィー博士が、「成功に至る原則」を研究したことがきっかけですが、テクニックやスキル、戦略的アプローチといった「個性主義」よりも、誠意、謙虚、誠実、勇気、正義、勤勉、節制などの「人格主義」的要素が重要だとしているのです。 『重要なことは、土台がないところでいくらテクニックを使っても長期的に機能することはない』 テクニックやスキルに重点を置きがちな、ビジネス書やハウツー本とは、明らかに趣を異にしています。 「人格主義」という土台をつくるところから始めるのは、効果がすぐ見えず一見遠回りかもしれませんが、しかし長期的には成果が出るのだと思います。 その証拠に、発売から10年以上たってもロングセラーでありつづけているのが、一つの証左でしょう。 「7つの習慣」を表すモデルは、「成長の連続体」というものです。 それは、依存から自立、自立から相互依存へと人が成長していくまでのモデルです。 その成長の過程で必要な習慣が7つにまとめられています。 本書では、一番の基礎である、主体性を発揮することで、「選択する力」を学ぶことになります。
5投稿日: 2013.11.06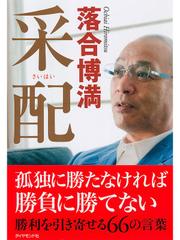
采配
落合博満
ダイヤモンド社
落合博満氏の人生哲学を知ることができる本
本書は、2004年から8年間務めた中日ドラゴンズの監督としての『采配』を通じて、落合博満氏が考えたこと、感じたことを語った本です。 落合博満氏の人生哲学を知ることができる本です。 テーマは、自立の必要性、勝負への心構え、人材育成、リーダー像等で、中堅クラス以上のビジネスマンにとっては、本書は日々の仕事の悩みににヒントを与えてくれるのではないでしょうか。 また、その人生哲学は、ビジネスの場面だけでなく、我々が生きるうえでの参考にもなります。 というのも、 『どうすれば成功するのか、どう生きたら幸せになれるのか、その答えがわかれば人生は簡単だ。しかし、常に自分の進むべき道を探し求めること、すなわち自分の人生を「采配」することにこそ、人生の醍醐味があるのだと思う』 と、落合氏が語るように、我々自身が、日々、自分の人生を「采配」しているからです。 実績の自慢話や、お山の大将的な話はなく、実体験にもとづいた落合氏の考えが淡々と語られており、視点も陰日向のバランスがあるところがとても好感が持てます。
0投稿日: 2013.11.04
トヨタの育て方
(株)OJTソリューションズ
中経出版
トヨタ流、自律的な社員の育成方法
本書は、元トヨタマンの書いたトヨタの人材育成のエッセンスを紹介した本です。 トヨタが考える人材育成のゴールは、自律的な社員の育成です。 『効率的にモノをつくり、生産性を最大限に高めるには、自分で考え、自律的に動ける社員を育てることが不可欠だという考え方が浸透しています』 そのような社員をどのように育成するか? 本書では、まず人材育成についてのトヨタの考え方をおさらいした上で、問題解決を通じた育成方法や、やる気を引き出す教え方、コミュニケーション方法、そして、リーダーとしての振る舞い、心構えが、具体的事例とともに紹介されています。 以下で本書のキーワードを拾い上げただけでも、社員の自律を促す育成方法の一端が想像できると思います。 ・人を育てるとは、「モノの見方を伝える」こと ・人づくりは、問題解決のプロセスにある ・「答え」を教えるな。「目的」を教えろ ・関心をもって、期待をかけて、対話する ・リーダーは中心にいてはいけない。外からメンバーを見なさい 部下を指導する立場にある人や、プロジェクトを推進する立場の人に参考となる書だと思います。 最後に1点。 トヨタでは、管理職の人事考課要素に、仕事の成果だけでなく「人望」があります。 なぜなら、「人望」が部下の育成に重要な要素だからです。 私はこれを読み、たまたま読み直した小倉昌男氏の「経営学」の中で、「人柄」の評価の必要性を説かれていたことを思い出しました。 一見、仕事の成果とは無縁な「人望」や「人柄」についての評価の必要性を実績ある企業や経営者が考えていることは、裏を返せば、成果主義だけでは会社は回らない証左なのだろうと思ったこと、付け加えておきます。
0投稿日: 2013.11.02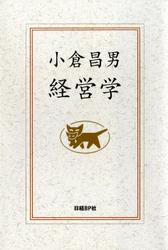
小倉昌男 経営学
小倉昌男
日経BP
宅急便を成功に導いた経営とは
本書は、宅急便創始者の小倉昌男氏の経営論です。 本書を読むと、「宅急便」の成功は単なる偶然ではなく、小倉昌男氏の経営哲学があったからこそなのだと納得させられます。 本書の最終章に、小倉昌男氏の考える経営リーダー10の条件があります。 1. 論理的思考 2. 時代の風を読む 3. 戦略的思考 4. 攻めの経営 5. 行政に頼らぬ自立の精神 6. 政治家に頼るな、自助努力あるのみ 7. マスコミとの良い関係 8. 明るい性格 9. 身銭を切ること 10. 高い倫理観 例えば、UPSの集配車がニューヨークの十字路の回りに四台停まっているのを見て、個人宅配市場の可能性を感じ取り、必ずもうかると確信するまでのプロセスは、「時代の風を読む」ことと、「論理的思考」が備わっていた小倉昌男氏だからできたことなのでしょう。 また、「行政に頼らぬ自立の精神」は、宅急便開発で運輸省や郵政省と戦ったことがいい例でしょう。 まさしく、この10の条件を持った小倉昌男氏がいたからこそ、宅急便は誕生し、成功したのだと思います。 「宅急便」の成功事例を通して、経営とは何かを考えるのに最適の本です。
0投稿日: 2013.11.01
リフレはヤバい
小幡績
ディスカヴァー・トゥエンティワン
リフレ政策がもたらす国債の下落と円安への警鐘
本書は、リフレ政策がもたらす円安と国債の下落への警鐘の書です。 2012年に発足した安倍内閣が掲げる経済政策「アベノミクス」。 これで広く知れ渡ったのが「リフレ」です。 小幡氏のリフレの定義は明快です。 『リフレとは、意図的にインフレーションを起こすことです』 日銀総裁が金融政策の目標として2%のインフレを掲げているように、リフレはまさしくこの定義の通りです。 そのリフレがなぜヤバいのか? それは、円安が国債の暴落をもたらし、銀行危機、そして実体経済危機につながる可能性があるからです。 円安から国債の暴落への考えられるシナリオは以下の通りです。 円安がもたらすドルベースでの国債価格の下落が国債の売りにつながり、売って得た円でドルを買うためさらに円安になり、そのためさらに国債が下落する、というように 『円と日本国債の暴落スパイラルが始まります』 そして、国債が暴落すると、国債を保有する金融機関の含み損が増え、それが金融危機につながり、更に実体経済の危機につながる可能性があります。 危機の具体的事例として、1997年の円安と日本の金融危機を例に説明されています。 さて、アベノミクスが始まって1年。 事実として、円安は進みましたが、幸いなことに国債の下落にはつながっていないです。 『円安で注意しなければならないのは、国債価格の下落、すなわち、名目金利の上昇なのです。逆に言えば、これさえ起きなければ、リフレ政策でも何でもやってかまわないと言ってもいいくらいです』 と小幡氏が語るように、今は結果オーライなのでしょう。 しかし、今後、さらに円安が進んだ時には、国債価格の下落には要注意なのかもしれません。 最後に、一言。 「ヤバい」、「暴落」、「危機」という言葉のイメージとは裏腹に、本書の内容はいたずらに不安をあおるようなトーンではなく、経済学と歴史的事実をもとに冷静に論を進めており、また、円安に頼らない日本のとるべき戦略なども語られており、参考になります。
0投稿日: 2013.11.01
どうして時間は「流れる」のか
二間瀬敏史
PHP新書
物理学者の考える時間とは
本書は、物理学者が時間をどのように考えているかを紹介した本です。 時間を考えることは、重力や宇宙を研究することと密接な関係にあることが分かります。 例えば、時間が過去から未来に一方向に流れることを「時間の矢」と称し、5つの「時間の矢」があります。 ・熱力学的時間の矢 ・波の時間の矢 ・進化の時間の矢 ・意識の時間の矢 ・宇宙論的時間の矢 これらの原因を突き詰めていくと、「宇宙の初期状態」があらゆる時間の矢の原因になっているそうです。 したがって、必然的に、相対性理論、重力論、宇宙論にまで話しは及び、時間が物理学の先端研究分野と密接な関係にあることが分かります。 たまたま、本書とは別に、重力や宇宙に関する新書を読んでいたので、時間との思わぬつながり意外さを感じました。 ところで、本書の中で私が印象に残った話の1つに、時間の矢が現れるのはいつか?についてのたとえ話があります。 内容は、机をたたいてコインをひっくり返すのをビデオで撮り、これを逆回しで見るとどうなるか、という話です。 コインの数が少ないうちは、ビデオを見ても逆回しかどうかわからないですが、コインの数が増えていくと、逆回しだと明らかに不自然に見えるようになります。 それが、時間の矢が現れたことだということだそうです。 このたとえ話は、熱力学の第2法則のエントロピー増大の法則を説明した話でもありますが、熱とは関係ない身近な例での説明で非常に印象深かったです。
2投稿日: 2013.10.27
ネットがつながらなかったので仕方なく本を1000冊読んで考えた そしたら意外に役立った
堀江貴文
角川書店単行本
堀江貴文氏のキュレーションした42冊の本
本書は、2年間の獄中生活の中で読んだ1000冊の中から、堀江貴文氏がキュレーションした42冊の書評集です。 紹介されている本は、ビジネス、科学・技術、歴史等々、様々な分野ですが、 『僕は「こうなればいいな」って世の中をつくったり、自分が欲しいサービス・モノをつくりたいと、ただただ思って行動している』 という、堀江貴文氏の生き様や考え方がそのまま反映されたセレクトになっていると思います。 例えば、DNAの二重らせん発見を巡るノンフィクションの『二重らせん』では、発見者のワトソンに対して、科学者の前に"ヤマ師"を感じ取る嗅覚は、堀江貴文氏らしいと思います。 意外だったのは、「人生で一番泣いた本」として紹介された重松清氏の『とんび』。 ビジネスに邁進する堀江貴文氏という印象が強いこともあり、現代の社会問題・教育問題・家庭問題をテーマとした作品の多い重松清氏を読まれているのは意外でした。 本書で紹介された42冊の内、私が読みたいと思ったのは、『新装版 こんな僕でも社長になれた』(家入一真)、『山賊ダイアリー』(岡本健太郎)、など、計8冊です。 早速読んでみたいと思っています。
3投稿日: 2013.10.19
grimonaさんのレビュー
いいね!された数133
