
新版 図解 仕事ができる人のノート術―アイデアマラソンが仕事も人生も豊かにする
樋口健夫
東洋経済新報社
ノートを活用することが人生をポジティブスパイラルにする
本書は、人生を豊かにするノート術について書かれた本です。 たかがノートが、なぜ人生を豊かにするのでしょうか? それは、ノートを活用することが人生をポジティブスパイラルにするからです。 樋口健夫氏は、日記でもアイディアでも、(ネガティブなことは避け)とにかく何でもノートに書くが大切と言います。 このようにアイディアを書き溜めていくことを樋口氏は「アイディアマラソン」と呼んでいますが、その効果について以下のように指摘しています。 (1)ノートを活用して、自主的に発想力、継続力、集中力を高めることができる (2)ノートを活用して、しっかりと知的財産を蓄え、人生戦略を形成していく (3)ノートを活用して筆力、筆致を確立する (4)ノートを活用し、アイデアマラソンの発想を書きためていくと、自らもっと勉強をする気が湧く。発想をもっと出すために、より深い知識が必要だからだ。自らすすんで行う勉強では、知識はよく吸収され忘れることも少なくなる (5)ノートを活用して、自分の人生に自信を持てる これが本当なのか、実践してみなくては分かりません。 ただ、毎年、3日坊主で日記が終わってしまうような私の経験でも、たしかにそんな気がする、と思えます。 というのも、日々の出来事や考えたことを言語化し記録する事は、知的財産の蓄積に繋がり、それを振り返ることが明日への発想の源になったり、人生を前向きにとらえるきっかけになると実感しているからです。 また、吸収した知識をノートにアウトプットすることは、知識を自分の中に定着することにつながるからでもあります。 最後に。 樋口氏は面白いデータを提供してくれています。 ノートに書き留めたアイディアの内、どれくらいが優れたアイディアだったかというもので、樋口氏自身の統計では、0.3%程度だったとのことです。 樋口氏をもってしてでもこれくらいの割合です。 逆にいえば、優れたアイディア裏には、書き留めただけの膨大なアイディアがあるようです。 優れたアイディアが思い浮かばないからとあきらめることなく、些細なことでもいいから、ノートに書く習慣をつけることから始めればよいのだ、と勇気づけられた次第です。
0投稿日: 2014.02.07
「使命」ありき3つのステップ キャリアの成功とは何か
伊賀泰代
ダイヤモンド社
キャリアを考えるときのフレームワーク
本書は、キャリアを考えるときのフレームワークを紹介した本です。 これからキャリアを踏み出す若者はもとより、自分のキャリアについて考えざるを得なくなる私のような中年世代にも参考になる本です。 本書では、次の3つのステップで、キャリアを考えていくことが、キャリアを成功に導くといいます。 ・ステップ1 自分が職業人生で達成したい使命が明確になる ・ステップ2 その使命の達成を自分の職業とできる ・ステップ3 職業人生におけるコントロールを握る 私もそうですが、おそらく多くのサラリーマンは、ステップ1の「自分が職業人生で達成したい使命」で立ち止まってしまうのではないかと思います。 そんな我々に対し、伊賀秦代氏は、こう助言してくれています。 『使命というと、「自分にはそんな大それたものはない」と思う人も多いだろうが、難しく考える必要はない。たとえば現在、筆者が職業上の使命と感じているのは、「日本における人材の最適配分に資する」ことだ』 『自分がどんな働き方や仕事に心躍るのかという条件を突き詰めていくと、その分野で突き詰めたい使命が見つかる』 『見つけるべきは「一生変わらない使命」でもないし、周囲を感嘆させるような高尚な使命でもない。その時点で自分自身が、人生の時間を費やす価値があると感じられるものを、そのまま言語化するだけでいい。組織や会社から与えられた業務目標に加え、個人として心からコミットできる使命を持って働くことは、組織に振り回されないキャリア形成への第一歩となるはずだ』 これで使命が見つかるかは、もう、その人の能力や情熱次第かもしれませんが、このような道案内は大変参考になると思います。 また、見つけた使命を職業とする(=ビジネス化する)ことは、これからの時代の重要なスキルであるという点は、私のような中年のみならず、次世代を担う若者の皆さんには重要な指摘であると思います。 『自分が実現したいことをビジネス化するという発想と、それを実現するための具体的なスキルは、これからの時代を生きる人にとって最も重要なキャリア形成スキルとなる』 ところで、本書の背景にある、伊賀秦代氏の一貫した考えは、 ・組織に振り回されないキャリア形成 ということだと思います。 そして、自分の職業人生を自分でコントロールすることは、自分の人生においても主体的に生きることにつながると言います。 『仕事上のプロジェクトでリーダーシップを発揮することと、自分の人生設計において、進むべき道の選択を他人任せにせず、主体的に選び取ることは、まったく同じ概念なのである』 この点に関し、使命を見つけて職業化しても自分で仕事をコントロールできない例として、好きな歌を職業としつつも、仕事が事務所に振り回される歌手の例は、伊賀秦代氏の考えの理解の助けになる印象的な事例でした。
2投稿日: 2014.02.05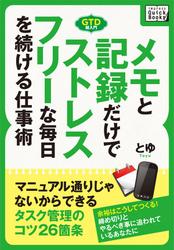
メモと記録だけでストレスフリーな毎日を続ける仕事術
とゆ
impress QuickBooks
行動を記録し振り返ることがストレスフリーの仕事術
本書は、メモを活用した仕事術を紹介した本です。 そのポイントは、行動を記録し振り返ることがストレスフリーの仕事術、ということです。 自分の仕事のマネジメントに悩んでいるサラリーマンの方にはおすすめの本だと思います。 かくいう私もその一人で、計画を立てて仕事を進めていても、 ・想定外のトラブルがあったり ・割り込みの仕事があったり ・そもそも業務量の見積もりが甘かったり で、ずっと続く繁忙感を前に、ストレスはたまるばかりで、もっとスマートな仕事のやり方があるのでは、と悩んでいました。 本書著者の「とゆ」さんも同じような悩みを抱えられていて、たどり着いた結論が ・行動を記録し振り返る(=処理・整理)ことがストレスフリーの仕事術 ということです。 一般的に、計画を立て、実行し、結果やプロセスを評価し、改善につなげる、というPDCAサイクルは広く知られた業務手法です。 「とゆ」さんの話は、これを個人レベルの仕事術に応用したものだと言ってもよいと思います。 ただ、ちょっと違う点は、初めに計画ありきでなく、行動してみて、それをフィードバックする形で計画を立てるという点でしょう。 「とゆ」さんは言います。 『俗に言う計画倒れです。そこで計画を立ててから行動するのではなく、行動してから記録をつけることを始めたところ、実際に自由に使える時間や所要時間が可視化できて、身の丈に合った現実的なスケジュールが組めるようになり、収集・処理・整理がうまく流れるようになりました』 『何をやっていたか、それにどれくらいの時間をかけていたかという記録をとっていて、仕事がいきなり順調にこなせるようになったわけではありません。しかし、視界は開けました。今までは通ってきた道がすぐにかき消えて、どういう道のりをどれくらいの時間で通ってきたかは記憶に頼っていましたが、記録をとるとそれが目に見えるようになります』 「とゆ」さんの指摘は、体験に基づいた実用的なものであり、今からでもすぐに実践できる仕事術だと思います。
7投稿日: 2014.02.05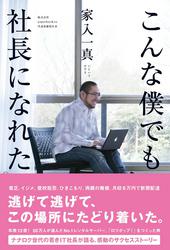
こんな僕でも社長になれた
家入一真
ワニブックス
人間としての本質的な情熱を持ち続けられる居場所を作る
本書はIT起業家、家入一真氏のサクセスストーリーです。 サクセスストーリといっても、よくある、「○○で世界を変える」という大言壮語な目標を持ち、自己主張の強さを感じさせるビジネス書とは趣を異にするのが本書です。 ひきこもりだった家入氏は、山田かまちの作品を通して、 愛し合いたい。 生きたい。 幸せになりたい。 自由になりたい。 という人間としての本質的な情熱が湧き上がるのを感じたといいます。 私は、そこが家入氏のサクセスストーリーの原点ではないかと思いました。 エピローグで、ひきこもりだった自分を振り返っての思いを語っているのが印象的です。 『学校に行けない、人の顔を直視できない、外に出られない。そんな悩みを抱えていたあの頃の僕に、今の僕から一つだけ、言葉を掛けてやれるとすれば、僕はこう言いたい 「逃げることは、悪いことじゃない」 (中略) 世の中は広い。地球は、途方もなく大きい。どんな人にだって、どこかにきっと、何も恐れることなく、ハッピーに暮らせる場所があるはずだ。前に進まなくたって、逃げたって、生きてさえいれば、きっといつか、そんな場所にたどり着く。逃げることは、決して悪いことじゃない』 この思いは、「居場所を作る」というキーワードで、家入氏が都知事選に立候補していることに通じることだと思います。 その居場所とは、人間としての本質的な情熱を持ち続けられる場所なのだと思います。
0投稿日: 2014.02.02
不格好経営
南場智子
日本経済新聞出版
長嶋監督のような経営スタイルへの違和感
本書は、DeNA創業者の南場智子氏が語る、DeNA創業と経営の記録です。 南場氏の前職コンサルタントと、経営は全く違うという指摘や、ネットオークションサイトを開発では直前になりソースコードが1行もなかったことなど、興味深い話が満載です。 今のDeNAを築くまでの経営の苦労や充実感などが、南場氏自身の言葉で語られており、「経営」に関心のある読者には、ケーススタディとなる読み物として良いと思います。 『他者に偽りのない尊敬と感謝の気持を持ち続け、その気持ちに基づいて行動する会社こそが真の一流企業だ』 という南場氏の持つ理念にも大いに共感します。 ただ、そう思いはするものの、一方では、私の読後感は、正反対のものもありました。 それは、「優秀な人材」にこだわることへの違和感です。 南場智子氏は語ります。 『創業時から一貫して、どんな人手不足のときでも、人材の質には絶対に妥協しないことをポリシーとしてきた。何か深い考えがあったというより、とにかく優秀な人が純粋に好きだったからではないだろうか。便利だからとか必要だからとかではなく、すごい!と思える人、尊敬できる人と一緒にいると自身の気持ちも高揚し、怠惰な自分も最高に頑張れる。それもあって、黒字化のめども立っていない時代からひとりひとり、これでもか、というピカピカの人材を口説き落としてきた』 最後の『怠惰な自分も最高に頑張れる』は謙遜でしょうが、たしかに、経営にとって『優秀な人』の確保は重要だと思います。 しかし、ここでいう「優秀」とはなんなのでしょうか? 例えば、卒業時、ある専門分野において「優秀」というように、ある時点のある側面についての「優秀」のことだけを指しているようにも思います。 会社は長期に存在するものであり、今の「優秀」さが、将来も優秀かというと、その保証は何もないです。 例えば、インターネットの世界がそうであるように、技術革新の激しい分野では、今の専門が将来陳腐化し、今「優秀」な人が将来「優秀」でなくなることも考えられます。 また、逆に、今「優秀」でないと思われた人が、時代の変化の中で将来、優秀な人材に変わることもあります。 つまり、優秀な人材確保も大切でしょうが、同時に、優秀さを維持したり、優秀でない人を成長に導いたりする「人材育成」も経営の重要な要素だと私は思います。 その点については、本書では、仕事を任せることで人が育つ、とだけ書かれていますが、これは今「優秀」な人材だから可能なことなのでしょう。将来、その人が「優秀」でなくなっても仕事を任せることで人が育つのかどうか、、、 「人材育成」の点で落とし穴はないでしょうか? 「優秀」な人材確保にこだわる経営スタイルは、各チームの一流選手をトレードで獲得しチーム作りをした巨人の長嶋監督を思い出させてくれましたが、私は、この長嶋監督のような経営スタイルへは違和感を感じてしまいます。 それよりも、私は、再生工場と呼ばれた、野村監督のような経営スタイルも重要ではないかと、本書を読み終わって感じました。
3投稿日: 2014.02.01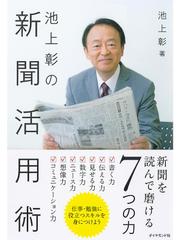
池上彰の新聞活用術
池上彰
ダイヤモンド社
池上彰さんが語る新聞への期待
本書は、ジャーナリストの池上彰さんが、新聞紙面批評を通して新聞への期待を語った本です。 例えば新聞の役割について。 テレビはもちろんのこと、今ではインターネットでも最新のニュースを知ることが当たり前で、新聞は即時性に劣ったオールドメディアと考えがちです。 しかし、池上彰さんは新聞ならではの役割があると指摘します。 『テレビやネットで結果がわかっているニュースを、夕刊で改めて読む意味は何か。 大きなニュースの場合、その出来事の意味を、新聞を読んでじっくり考えることだと私は思います。そこにこそ、新聞の大事な役割があると期待しています。 そのためには、その問題の専門家である記者が、出来事の歴史的意味や位置づけをしっかりと解説してくれなければ困ります。期待に十分応えられない紙面を見ると、残念でなりません。』 私も一時期、 「ニュースは、テレビや、Yahoo!ニュースで十分。新聞はいらない」 と考えて新聞をやめていた時期がありました。 しかし、テレビやインターネットのニュースだけでは、ニュースへの理解が表面的になっているのでは、という実感を持ち、今は新聞購読を再開しており、池上彰さんの指摘は納得感があります。 また、池上彰さんは、新聞はモノを伝える力を養う格好のテキストだとも指摘しています。 『新聞大好き人間の私が批判的に新聞を読み、朝日新聞をはじめとした新聞各紙に対し突っ込みを入れる。このプロセスで見えてきたものは、新聞は文章力や表現力、想像力やコミュニケーション力をも磨ける、格好のテキストであるということでした』 本書を読むとオールドメディアの新聞も捨てたものではない、と再認識させられます。 池上彰さんの期待に新聞が応えていくよう期待したいと思います。
1投稿日: 2014.01.22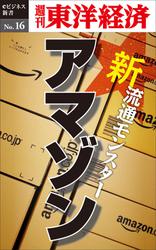
新・流通モンスター・アマゾン 週刊東洋経済eビジネス新書No.16
週刊東洋経済編集部
週刊東洋経済eビジネス新書
巨大な流通企業となったアマゾンの実像に迫ったルポ
本書は、巨大な流通企業となったアマゾンの実像に迫ったルポです。 例えば、アマゾンと他のネットショップとの違いについて。 ネットショップというと、設備投資も少なく、在庫リスクの少ないビジネスモデルという印象ですが、アマゾンはそうではありません。 メーカーや卸から商品を仕入れ、顧客に売る「直販型」が主です。 そのため、販管費の7割を物流とITに投資し、例えば国内では12の物流拠点を持っています。 店から場代を取る「モール型」の楽天の物流拠点が3つであることと比較しても、その違いが鮮明です。 このように、本書は、リアル店舗や、先行するネットショップとの競争の実態から、アマゾンの実像に迫ったルポになっています。 本書の最後に、創業者のジェフ・ベソズCEOのインタビュー記事があり、アマゾンの経営哲学が語られていて参考になります。 『アマゾンには原動力となる三つの考え方がある。一つはつねに顧客中心に考えること、二つ目は発明を続けること。三つ目は長期的な視野で考えること』 『アマゾンは普通のやり方は絶対に採らない』 この経営哲学が、アマゾンの成長を支えているのだと思います。
0投稿日: 2014.01.06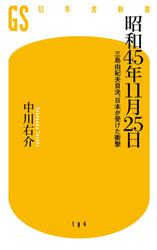
昭和45年11月25日 三島由紀夫自決、日本が受けた衝撃
中川右介
幻冬舎新書
三島自決を知った当日、何を思い、何を感じたかについての約百二十名の記録
三島由紀夫が自決した昭和45年11月25日。 本書は、三島自決を知った当日、何を思い、何を感じたかについての約百二十名の記録をまとめた本です。 百二十名は、有名・無名問わず、職業も文壇、政界、マスコミ人士等々、年齢も立場も様々な人たちです。 彼らが語る三島由紀夫自決の衝撃は文字通り百人百様です。 文学の破綻と見るもの、政治性を見るもの、狂気と見るもの。。。 この様々な登場人物に、三島由紀夫自決を語らせることで、あの自決の持つ実像に迫ろうという意欲的な作品だと思います。 個人的には、百二十名の中に村上春樹も取り上げられていたのが関心を惹きました。というのも「羊をめぐる冒険」の最初の章、「第一章 1970/11/25 水曜日の午後のピクニック」が、私自身、ずっと気になっていたからです。 「羊をめぐる冒険」の執筆時期の1981年のインタビューでは、村上春樹は三島由紀夫のことを「読まないし、わかんない」と言っていますが、果たして本当なのかどうか。 このことについて、著者の『作家の言うことを信用してはいけない。作家とは嘘をつくことを職業としているのだ』という切り込み方が、新鮮でした。 百二十名の記録とは別に、全集くらいでしか読むことのできない、「要求書」、「檄文」、三島由紀夫の演説内容書き起こしが収められているのはありがたいです。
2投稿日: 2013.12.23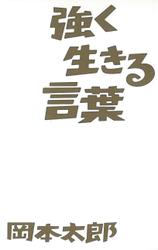
強く生きる言葉
岡本太郎
イースト・プレス
弱気な生き方になっている人に勇気を与えてくれる本
本書は、岡本太郎氏が語った言葉をまとめたものです。 その言葉のいずれにも、「強く生きること」を追求した岡本太郎氏の考えが貫かれており、読む人に勇気を与えてくれる本だと思います。 例えば、人は、他人の判断が気になったり、失敗を恐れて何もできなかったりで、知らぬ間に弱気な生き方になっていることがあります。 そんな時、次のような岡本太郎氏の言葉に接すると、モヤモヤとしていた視界がパッと開けた気持ちになります。 『自分の歌 他人が笑おうが笑うまいが自分で自分の歌を歌えばいいんだよ。 歌にかぎらず他人の判断ばかりを気にしていては 本当の人間としての責任がもてない。 もし自分がヘマだったら、“ああ、おれはヘマだな”と思えばいい。もし弱い人間だったら“ああ弱いんだなあ”でいいじゃないか。』 『失敗 何かすごい決定的なことをやらなきゃ、なんて思わないで、そんなに力まずに、チッポケなことでもいいから、心の動く方向にまっすぐ行くのだ。失敗してもいいから。 1度失敗したなら、よしもう1度失敗してやるぞ、というぐらいの意気ごみでやることが大切なんだ。 うじうじと考える必要はない。』 岡本太郎氏の「強く生きる」とは、自由闊達で人間らしく生きることなのだと、私は思っています。 少年時代や青年期ならまだしも、世の中の現実に目を曇らされた私のような中年期では、「強く生きる」ことは困難を極めます。 もしかしたらそのようなことは非現実的なのかもしれません。 しかしながら、岡本太郎氏の言葉に共感を禁じ得ないのは、「強く生きる」理想を捨てきれない自分がいるからなのかもしれないです。
1投稿日: 2013.12.22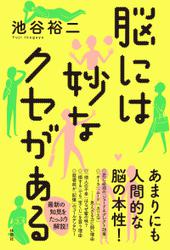
脳には妙なクセがある
池谷裕二
扶桑社BOOKS
人生をより良く生きるヒントが得られます
本書は、最新の脳科学の研究成果を一般読者向けに紹介した本です。 タイトル通り、脳には妙なクセがあるので、そのクセとうまく付き合うことで、人生をより良く生きることができる、そんなヒントを本書から得られると思います。 例えば、「脳は妙に不自由が心地よい」というクセ。 人間には自由意志があると考えがちですが、脳科学の観点からは、 『意志は脳から生まれるのではありません。周囲の環境と身体の状況で決まります』 ということで、一見、自由意志に基づく行動だと考えていたものも、無意識の「反射」だといいます。 その上で、池谷氏はこう指摘しています。 『このような適切な行動は、その場の環境と、過去の経験とが融合されて形成される「反射」です。 だからこそ、人の成長は「反射力を鍛える」という一点に集約されるのです。そして、反射を的確なものにするためには、よい経験をすることしかありません』 人間の自由意志が、生まれながらのものというよりも、周囲の環境や過去の経験といった後天的なことに影響されるということは、各個人の努力や家庭や学校での教育の重要性を再認識させてくれます。 これ以外にも、本書では、26の脳の妙なクセが紹介されており、 ・アイディアや創意工夫に満ちた着想には、一旦課題を放置する ・記憶力を高めるには、学習したものを使うことが重要 等々、脳科学の知見から、人生をより良く生きるヒントを得ることができます。
2投稿日: 2013.12.22
grimonaさんのレビュー
いいね!された数133
