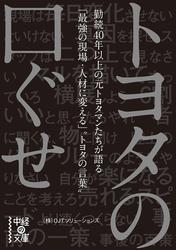
トヨタの口ぐせ
(株)OJTソリューションズ
中経の文庫
口ぐせに凝縮されている「会社を成長させるための考え方」
本書は、「トヨタで口ぐせのように語りつがれている言葉」をまとめた本です。 会社で係長、課長といった部下を持つ立場や、プロジェクトを率いる立場など、リーダーとなる人におすすめの本です。 口ぐせに凝縮されているのは、「会社を成長させるための考え方」です。 例えば、「スタッフは2つ上の目線で見なさい」という口ぐせ。 これは、係長ならば、課長のさらに上の部長というように、今の自分の立場よりも高い視点にたってものを見なさい、という考え方です。 これがなぜ口ぐせのように語られているのか? それは、個別最適でなく、全体最適に繋がる考え方だからです。 リーダーには、個人のスキルアップも重要ですが、より重要なのは組織や会社を成長させる視点です。 上記は一例ですが、本書には、トヨタの現場で語り継がれてきた「会社を成長させるための考え方」の口ぐせが計31個、下記5つの分野にまとめられています。 ・「リーダー」を育てる口ぐせ ・「できる人」を育てる口ぐせ ・「コミュニケーション」をよくする口ぐせ ・「問題」を解決する口ぐせ ・「会社」をよくする口ぐせ ビジネス書のような難解さはなく、手軽に読め、明日にでもすぐ実践に移せる本だと思います。
1投稿日: 2013.12.03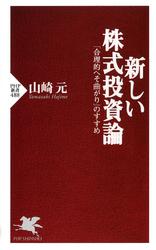
新しい株式投資論 「合理的へそ曲がり」のすすめ
山崎元
PHP新書
ゲームとしての株式投資論
本書は、ファンドマネージャーの経験もある経済評論家の山崎元氏の株式投資論です。 株式投資の理論やその社会的意義といった建前を重視しがちな投資家には一読の価値の本だと思います。 なぜなら、本書では株式投資のホンネが示されているからです。 著者の山崎元氏は言います。 『株式投資で成功するために必要なものは、一に「運」、二に「センス」だ』 『「あなたにとって、株式投資とは何か?」と、問われたとすれば、著者の答えは「私にとって、株式投資とはゲームである」』 『株式投資は、世のため人のために行うものではなくて、自分のために行うものだ』 私は、本書を読んで以来、肩の力が抜け、株式投資に対する態度もリラックスできました。 なぜなら、今までの私は、儲けたいという卑しい自分を糊塗するためか、「投機でなく投資」だとか、企業への出資だとかという株式投資の社会的意義をことさら意識したり、チャート分析や投資理論をかじったりして、これが株式投資だと自分に言い聞かせつつも、でも、どこか違うな、と感じてもいたからです。 そんな中で出会ったのがこの本で、そこには株式投資のホンネが開陳されていました。 少々長いが引用させていただくと 『近年、株式投資への啓蒙が盛んで、「株式投資は、ギャンブルではない」「あなたの投資が日本経済を活性化させる」、あるいは「自分が応援したい企業の株を買おう」といった、"株式投資のススメ"を頻繁に見聞きする。 しかし、よく考えてみると、株式投資がギャンブルであったって、儲かるならやればいいし、日本経済を活性化させるために自分のお金をリスクに晒すわけではない。応援したい企業が、必ずしも株式を買ってみて儲かる会社だとはかぎらない。 純粋に、参加する人の側から見て、株式投資がどんなものであるかについて、スッキリ納得してから、株式投資に取り組む方がいいにちがいない。結局、投資に失敗しても、「自己責任」という万能呪文の下に放っておかれるだけなのだから、最初から、「自分のため」を徹底して考える方がいい』 その『「自分のため」を徹底して考える』株式投資が、ゲームとしての株式投資論です。 山崎氏は、ゲーム参加の基本動作を述べています。 ・投資に関する意思決定は、リターン、リスク、コストを合算評価すること ・株式投資ゲームが現在どのように進行しているかを把握するには、利益予想の新規発表とその後の変化、市場の反応を押さえること この基本動作を押さえたうえで、 ・プロの知識と情報が活きない理由 ・ポートフォリオの平均を持つと長期的に有利 ・手数料がかさむ信用取引は慎む ・投資企業の分析より市場参加者の分析が重要 といった、ゲームとしての株式投資論が述べられています(第1章、第4章)。 これ以外にも、第3章の投資理論に関する話は私には難しかったですが、第2章の株式投資の本当の常識は、「目標株価の設定」「テクニカル分析」といった世間で流通している株式投資に関する常識がいかに怪しいものか、著者の視点で解説されていて参考になります。
0投稿日: 2013.12.02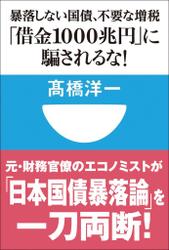
「借金1000兆円」に騙されるな!暴落しない国債、不要な増税(小学館101新書)
高橋洋一
小学館101新書
「国債」にまつわる誤解を解いた書
本書は、アベノミクスのブレーンの一人、高橋洋一氏が、「国債」にまつわる誤解を解いた書である。 高橋洋一氏が指摘する典型的な誤解の例を1つ挙げれば、 「日本の政府債務残高はGDP比200%」 という話である。 日本のGDPが約500兆円、国債残高が1,000兆円を超えているので、この指摘は正しい。 他の先進国の債務残高のGDP比は ・米国101.1% ・英国88.5% ・ドイツ87.3% ・フランス97.3% ・イタリア129.0% ・カナダ85.9% なので、日本は突出して大きく、このままでは日本は財政破たんするという警鐘を鳴らす識者は多い(数値は2011年のもの。本書より引用)。 しかし、 高橋氏は、 『国の債務残高を考えるときは、グロス(総量)ではなくネット(正味)で考えなければならない。つまり、債務の総額だけを見るのではなく、保有している資産があれば大した問題ではない。国際通貨基金(IMF)も、ネットの数字に注目している』 と指摘し、これに倣って計算すると、日本の債務残高のGDP比は70%でしかないという。 そして、GDP比200%という数値だけが独り歩きし、日本の経済政策がミスリーディングされることに警鐘を鳴らしている。 『本当に恐れなければいけないのは、国債暴落、財政破綻という言葉に脅かされて、経済成長力が損なわれることだ。(中略)。結局は経済が成長すれば、財政は再建されるのだから』 これ以外にも、本書では ・経常黒字、赤字、自国建てか否かと国債の関係 ・格付けにまつわる誤解 ・ギリシャ、スペイン、イタリアと日本の違い 等々、国債にまつわる世間で広がっている話について、過去のデータに基づき誤解を一つ一つ解いている。 第5章の「日本再生の経済運営とは」で、高橋氏は、日本経済再生のために国債を便利なツールとして使えばいいと主張している。 本書の発行は、まだ民主党政権であった2012年4月であるが、第5章の主張は、ほぼそのまま、アベノミクスの1本目の矢、「大胆な金融緩和」に反映されていることも興味深い。
2投稿日: 2013.12.02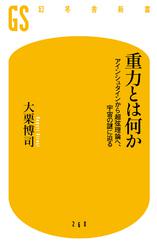
重力とは何か アインシュタインから超弦理論へ、宇宙の謎に迫る
大栗博司
幻冬舎新書
重力理論から最先端の超弦理論までを易しく解説した本
本書は、重力理論から最先端の超弦理論までを易しく解説した本です。 私のような一般の人々が、宇宙の成り立ちを巡る物理学の最先端の研究がどうなっているかを知るのに適した本だと思います。 私たちが身近に感じる重力。 その重力はニュートン力学によってその物理法則が明らかにされていますが、そこを出発点にしてアインシュタインの相対性理論までの古典物理学と、現代物理学の量子力学を俯瞰し、相対性理論と量子力学を融合しようという最先端の超弦理論までが解説されています。 重力という身近な力の研究が、超弦理論という最先端の科学につながり、それが宇宙の謎の解明に迫っているエキサイティングなものだと知り、非常に面白かったです。 私たちが教育の場で習うのは、ニュートン力学、マクスウェルの電磁気学、アインシュタイン理論、量子力学といった確立された学問です。 しかし、超弦理論は「これから」の理論です。 『本書をきっかけにこの世界に興味をもたれたら、ぜひ、今後の成り行きにも注目してください。(中略)。それが(=超弦理論)が進歩し、世界を説明する「究極」の理論に近づいていくのを同時代人として見る。あるいは、自ら研究者としてその当事者となってもいいでしょう。』 と著者の大栗博司氏も言うように、あらたな物理学の領域を切り開く理論に私たちは立ち会うことができるかもしれない、そう考えると心が躍ります。
2投稿日: 2013.12.02
海街diary 1 蝉時雨のやむ頃(1)
吉田秋生
月刊flowers
鎌倉を舞台にした異母4姉妹の家族の絆の物語
『海街diary』は、鎌倉を舞台にした、異母4姉妹の家族の絆の物語です。 私はまだ電子版の出ている3巻までしか読んでいないですが、 早く続巻を読みたいと思っています。 まじめでしっかり者の長女、香田幸、酒好きでちょっと奔放の次女、香田佳乃、天然系でユニークなキャラの三女、香田千佳、中学生ながら責任感のある四女、浅野すず。 そんな異母4姉妹が、父の死をきっかけに、鎌倉で一緒に暮らすことになるところから物語が始まります。 母と娘の複雑な感情、仕事や学校、恋の悩みも織り交ぜながら、この4姉妹が織りなす家族の絆が描かれており、良質の大人のコミックに仕上がっていると思います。 また、大仏、鶴岡八幡宮、御霊神社、七里ヶ浜の海、江の島、鎌倉の花火大会、切通し、谷戸(やつ)、路地の佇まい、梅や桜などの四季折々の花など、そんな鎌倉の歴史、風景、自然がこの物語に溶け込んでいて、作品に深みが出ていると思います。
5投稿日: 2013.12.02
鉄道会社はややこしい
所澤秀樹
光文社新書
相互直通の鉄道会社間のカラクリに迫った世にも希なる本
本書は、相互直通の鉄道会社間のカラクリに迫った本である。 相互直通とは、境界駅で乗客が乗り換えをしなくてもいいように利便性を考え、異なる鉄道事業社間で列車を直通運転させることである。 代表的な相互直通運転は、例えば以下のようなものだ。 ・地下鉄とJR・私鉄間(代表的なのが東京) ・複数私鉄間(代表的なのが関西方面) ・JR各社間 ・JRと第3セクター間 この相互直通運転のおかげで、我々は乗り換えなしに目的地に行くことができる。 一方、我々が利便性を享受する裏では、 ・車両や保安設備の統一 ・車両使用料の清算 ・連絡運輸の協定 ・駅、線路施設の利用 ・運転士、車掌の扱い 等々、様々な規則が各鉄道会社間で取り決められていて、それが複雑怪奇なのだ。 例えば、車両使用料の清算は、各社車両の相手線内での走行キロが均衡するような取り決めがされるそうなのだが、現実にはなかなか均衡せず、東武鉄道の電車が東急田園都市線の長津田~中央林間間の列車で運用されるという奇妙なことも発生するという。 本書には、このような相互直通運転にまつわる各鉄道会社間の複雑怪奇なカラクリの話が満載されていて、読む者を飽きさせない。 こんなカラクリに迫って 『そんなことの何がいったい愉しいのか、と、いわれてしまえば、それまでなのだが』 という著者のスタンスがいい。 本書は、まさに著者が書いているように、 『全国規模でこのような複雑な間柄を見ていき、そこに愉しみを見出そうとする、まさに世にも希なる一品である。』
2投稿日: 2013.12.02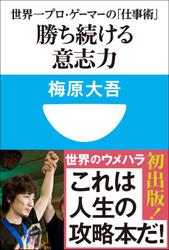
勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」 (小学館101新書)
梅原大吾
小学館101新書
勝つことが目的ではない、成長し続けることが重要
本書は、世界一プロ・ゲーマー梅原大吾氏が人生哲学を語った本である。 私は、競争社会の中で勝ち抜く秘訣のヒントにと思って読み始めたけれども、本書はそんな低次元の本ではなかった。 梅原氏は、勝負へのこだわりより、もっと大きな人生哲学を語っており、私は、自分のせせこましい動機が恥ずかしくなったとともに、この本から教えられることが多だった。 その人生哲学は、勝つことが目的ではなく、成長し続けることが重要だ、ということである。 梅原氏は次のように語る。 『僕はゲームを楽しみたいとか、ゲームで勝ちたいとか、その程度の気持ちではなく、もう少し別の次元で物事を考えている。やはり、ゲームはあくまでもゲームで、本当の目的は自分自身の成長にある』 『そのことに気づいてからようやく、勝つことより成長し続けることを目的と考えるようになった。ゲームを通して自分が成長し、ひいては人生を充実させる。いまは、そのために頑張っているんだ』 『僕にとって生きることとは、チャレンジし続けること、成長し続けることだ。成長を諦めて惰性で過ごす姿は、生きているとはいえ生き生きしているとは言えない』 『目的である自身の成長に目を向けている。それが「勝ち続ける」ことにつながってくる』 『継続的な成長を目指さないのであれば、競技から退いた方がいい』 梅原氏がゲームの世界で勝ち続けているのは、勝つことを目的として日々研鑽しているからではなく、日々の成長、自身の成長を目的として日々研鑽している結果としてなのだ。 ただ、一口に成長といっても容易いことではない。 なぜなら、多くの人にある、変化をおそれ、築き上げてきたものに固執しがちな心理が成長を妨げるからだ。 しかし、梅原氏はそれを一蹴する。 『築き上げたものに固執する人は結局、自分を成長させるということに対する優先順位が低いのだと思う。新しいことに挑戦する意欲も薄ければ、何かを生み出す創造性も逞しくないのだろう』 梅原氏は、成長し続けるためには、 ・失敗を恐れない ・継続的な努力 ということが重要だといいい、具体的には、 ・失敗こそが成長の指標になると捉え、変化をおそれないこと ・小さな変化にも喜びを感じ、継続的な努力ができるサイクルを構築 している。 勝つことを目的にすると、ひとたび勝って目的を達成してしまえば、失敗を恐れ変わろうとしない。 失敗を恐れ変わろうとしなければ、成長が止まり、新しい状況変化に取り残され、勝ち続けることは困難になっていく。 燃え尽き症候群などは、このいい例であろう。 失敗を恐れずに、成長し続けること、そのために継続的な努力をする。 これは、ゲームの世界だけの話でなく、ビジネスの世界、ひいては人生を送る上でも共通に言えることである。
1投稿日: 2013.12.02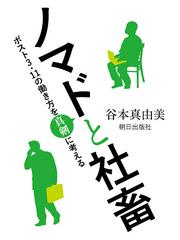
ノマドと社畜 ~ポスト3.11の働き方を真剣に考える
谷本真由美(@May_Roma)
朝日出版社
浮ついたノマドブームへの警鐘
本書は、浮ついたノマドブームへの警鐘を鳴らす本である。 ノマドとは、その語源は遊牧民だが、それから転じて以下の意味で使われている。 ・場所にとらわれずに自由な働き方をする ・フリーランサーや個人事業主(自営業者)として、雇われずに働く 簡単に言うと、サラリーマンと対極の働き方ということだ。 このような会社に縛られない自由な働き方から、今のノマドブームは、お洒落なイメージを醸し出している。 しかし、著者は、イギリスの実例を通して、ノマドの現実は甘くない、と警鐘を鳴らす。 『ノマドワーカーになるということは、スキルや専門性の高い人はどんどん稼げるようになり、そうでない人は低賃金で働かざるを得ない、という「激烈な格差社会」を意味する』 著者の指摘は、私もそうだと思う。 スキルを持つこと、手に職をつけること、これがノマドワーカーの大前提なのだが、ノマドブームではそこがすっかり抜け落ちて、自由な働き方というお洒落なイメージばかりが先行しているのだ。 そこに、著者の憤りがあるのだと思う。 『ノマドブームの行き着く先は、かつてのフリーターブームや起業ブームと同じような悲劇になるのではないか、と危惧しています』 『突出した個性や技能がないのであれば、「勤め人」として、誰かに雇用されるべきです』 著者は、ノマドワーカーを否定しているのではなく、ノマドの現実を知らずにノマドが語られていることに警鐘を鳴らしているのだ。 著者は、ノマドワーカーを目指す人に、4つの現実的な提案をしている。 ・実際にフリーランサーや自営業者として最低5年から10年働いている人に話を聞いて、実態を知ること ・「食べて」いけるスキルや技能を身につけること ・フリーランサーや自営業者として働くための基礎知識を身につけること ・英語を身につけること ノマドワーカーを目指す人は、学生時代にこれら4つを身につける努力をしてもいいし、それが難しいならば、「勤め人」として実社会で働くことを通して、この4つのことを身につけてもよいと思う。 そして、この4つを身につけたその先にノマドワーカーとして自立できる、ということを忘れないことが重要だ。 最後に、本のタイトルにも使われている「社畜」という言葉には違和感を感じた。 本文では3か所にしか出てこないが、前後の文脈から、勤め人の意味で使われているようだ。 ノマドとの対比を強調するためだけに、「社畜」という刺激的な言葉を用いているようだ。 本の内容は常識的なものなので、無理に「社畜」という言葉を使わなくてもよいと感じた。
1投稿日: 2013.12.02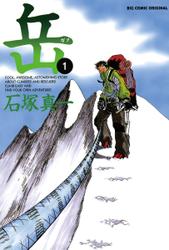
岳(1)
石塚真一
ビッグオリジナル
山を愛する島崎三歩の人柄が魅力的
本書は、山岳救助を題材としたコミックです。 主人公は世界の名峰を登頂し山岳救助の経験も積んだ島崎三歩。 そんな彼の北アルプスでの山岳救助ボランティア活動を軸に物語が展開していきます。 絵のリアリティだけでなく、随所に出てくる登山の専門知識や、救助で死の場面も多く出てきて、ストーリーとしてのリアリティもあり、読み応えがある作品だと思います。 加えて、登山や山岳救助のテクニカルな話に溺れることなく、山を愛する、そして、例えば亡くなった救助者にも「よくがんばったね」と労うように、山を愛する人を愛する島崎三歩の魅力的な人柄を描くことで、物語としての膨らみを持っている作品だと思います。 私は登山はしませんが、ソロクライマー山野井泰史さんの作品(垂直の記憶 (ヤマケイ文庫))や、冒険家植村直己さんの作品(青春を山に賭けて (文春文庫))を読んで、登山の世界に興味を持っていたので、それを絵で味わえるこの作品はありがたく思いました。
1投稿日: 2013.12.02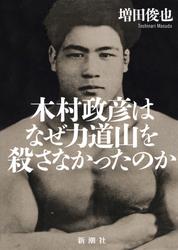
木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか
増田俊也
新潮社
ノンフィクションの醍醐味を満喫できる一冊
本書は、史上最強の柔道家である木村政彦がなぜ力道山に負けたのかの解明を試みた渾身の一冊である。 費やした期間は18年、千点以上の参考文献や資料、関係者へのインタビューなどを通してまとめた本書は、単行本では2段組み700ページ、電子書籍では1674ページという大著である。 しかし、他のどの書評でも言われているように、主題に向かって読者をどんどん引き込んでいく、読み応えのある作品である。 言葉を換えれば、昭和の巌流島と称された1954年12月22日蔵前国技館の木村政彦対力道山の日本プロレス選手権試合の謎の解明には、単にこの一戦だけを論ずるのでなく、もっと大きな視点でとらえなおす必要があるということだろう。 具体的には、本書では、木村の生い立ちから始まり、師と仰ぐ牛島辰熊との出会い、高専柔道との関わり、太平洋戦争と闇屋時代、プロ柔道旗揚げ、ブラジルへの渡航とエリオ・グレイシーとの戦い、等々の事実関係や時代背景を積み重ね、これらすべてが、木村政彦対力道山の日本プロレス選手権試合の謎の解明につながっていることが、本書を読むと納得させられるのだ。 また、著者、増田俊也氏の執筆姿勢がフェアなことも、本書の価値を上げていると思う。 格闘技やプロレスなどは、ファンの熱も上がりやすく、自分が好きな選手を贔屓目に見たり、神格化したりしがちだ。 事実、著者の増田俊也氏も、 『もともとこの作品を書き始めたのは一九九三年(平成五)、木村政彦が逝ったとき、すべてのマスコミが「力道山に負けた男」という単層的な見方で報じたことに反論するためだった。柔道経験のある私には許せなかったのだ。 木村先生は負けたわけではない--。』 と執筆の動機を語っている。 しかし、本書では、自分の思いに溺れることなく、取材や資料で突き止めた事実を丹念に積み重ねることで、謎の解明を試みており、そこから得られる結論が、例え自分の願望とは異なっていたとしても、、、 結論は本書の核心部分でもあるので、これ以上触れるのは止そう。 フェアで資料に忠実、中立な著者の態度は、著者もやるという柔道の精神に通じるものがあり、安心して読むことができ、実に気持ちよい。 最後に。 柔道、プロレス、格闘技といった血なまぐさい戦いの話の一方で、木村政彦と妻斗美との関係で、愛し、そして、愛されて生きることの救いも本書から得られたことを付け加えておきたい。 ノンフィクションの醍醐味を満喫でき、本当に満足である。
0投稿日: 2013.12.02
grimonaさんのレビュー
いいね!された数133
