
宮脇俊三 電子全集1『時刻表2万キロ/汽車旅12ヵ月』
宮脇俊三
宮脇俊三 電子全集
セピア色の白地図は宮脇俊三氏の鉄道への愛着の証
宮脇俊三氏の作品が電子版の全集で読めるようになったことは、本当に喜ばしいことだと思います。 この全集をきっかけに、宮脇俊三氏の愛読者が増えることを願っています。 全集1におさめられているのは、「時刻表2万キロ」と「汽車旅12ヵ月」の2作品ですが、巻末の付録も惹かれます。 というのも、「時刻表2万キロ」の中に出てくる、乗車した国鉄の線区を塗りつぶした白地図が載っているからです。 白地図と言っても、もう何十年も前のだからセピア色がかっています。 この白地図の余白には、1967年5月8日からの乗車キロの記録がメモされており、「時刻表2万キロ」で宮脇俊三氏が最後の未乗区間である足尾-間藤間を乗り国鉄全線完乗した時の記録も、 20,746.0(77.5.28)足尾-間藤(全) とはっきり記録されています。 そして、以降に開通した新線の乗車キロや、路線廃止による乗車キロ訂正もされており、最後は、1997年10月6日のJR東西線尼崎-京橋間の記録でした。 セピア色がかったこの白地図は、宮脇俊三氏の鉄道への愛着の証のように思えました。 ところで、「時刻表2万キロ」のエンディングは作家カレル・チャペックの「園芸家12か月」の最後の一節の引用です。 この全集1が、「時刻表2万キロ」と「汽車旅12ヵ月」という組み合わせなのは、これによるのかも知れないと勝手に推測しましたが、果たしてどうなのでしょう。
1投稿日: 2015.03.15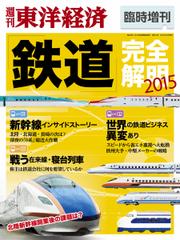
週刊東洋経済 臨時増刊 鉄道完全解明 (2015)
東洋経済新報社
東洋経済新報社
営業係数は鉄道経営の現実を教えてくれる
週刊東洋経済の鉄道完全解明シリーズの2015年版です。 雑誌だと保存に手間なため、前から電子版が出たら買おうと思っていたので、早速購入しました。 2015年版は以下の3つの構成で、鉄道ビジネスの最前線の記事がおさめられています。 ・新幹線インサイドストーリー ・世界の鉄道ビジネス異変あり ・戦う在来線 これらの記事とは別に、私は、本書末のJR・全私鉄の営業係数を眺めては、物思いにふけっています。 私は趣味で鉄道に乗るのが好きですが、乗りたいと思うローカル線の営業係数は総じて悪いです。 今や鉄道の経営は、新幹線か、大都市の通勤路線に支えられているのが実情で、少子高齢化で通学需要も減り、ビジネスや観光需要が乏しいローカル線の営業係数は押しなべて厳しい物があります。 営業係数は、私にとっては趣味の世界から一歩引き、冷静に鉄道経営の現実を教えてくれます。
1投稿日: 2015.02.21
ザ・ゴール コミック版
エリヤフ・ゴールドラット,ジェフ・コックス,岸良裕司,青木健生,蒼田山
ダイヤモンド社
書籍版のエッセンスが詰まっています
書籍版の「ザ・ゴール」のエッセンスが詰まっていると聞き、手にしました。 私が理解したのは、 ゴール、という目標に向かって最大のアウトプットを出すために、全体最適の視点で業務フローのボトルネックを改善していく ということです。 これを制約理論というそうですが、抽象的な概念をビジュアルを通して手軽に読めるのはとてもありがたく思います。
1投稿日: 2015.01.25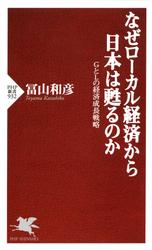
なぜローカル経済から日本は甦るのか GとLの経済成長戦略
冨山和彦
PHP新書
日本経済を考えるためのGとLというフレームワーク
本書は、これからの日本経済を考えるためのフレームワークを提示した本です。 そのフレームワークは、GとL。 Gはグローバル経済圏を意味し、例えば自動車や電機産業など、グローバルな市場で活動する経済のことを指します。 一方、Lはローカル経済圏を意味し、例えば公共交通機関や飲食店、宿泊業等のサービス業などの、ローカルな市場で活動する経済を指します。 本書では、GとLは別の経済特性を持ったものだと認識し、それぞれに合った経済政策や戦略を考えることが重要だとし、Gの世界では資本生産性を上げる施策、Lの世界では労働生産性を上げる施策を提案しています。 GとLの考えに至る著者の問題意識は、それまでの日本の経済政策の論争が、競争を重視した新自由主義か、平等を重視した社会民主主義かの二項対立が、 『現実の経済社会で起こっている姿をまったく無視した、抽象化されたベースで議論しているだけではないのか』 というところにあります。 経済は競争も重要だけど、その結果格差が生まれては問題なので、その意味で平等も重要、ということをどう整理して考えればいいのかと思っていたので、GとLという視点の整理は、非常に分かりやすく理解の助けになりました。 今後の日本経済を考えるために有用なフレームワークだと思います。 以下は余談ですが、私が本書を読もうと思ったのは、2014年10月7日の文部科学省の有識者会議(※1)での冨山和彦氏の報告(※2)に興味をもったからです。 その報告では、これからの大学では、例えば、シェークスピアや経済理論ではなく、説明力や会計ソフトの使い方を教えるなど、「学問」よりも「実践力」を教えることが重要とされていました。 この主張に、非常に違和感を持ったのですが、本書を読んでその背景と主張の意図が理解出来ました。 ※1「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議」 ※2「我が国の産業構造と労働市場のパラダイムシフトから見る高等教育機関の今後の方向性」
2投稿日: 2015.01.24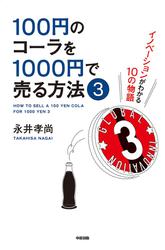
100円のコーラを1000円で売る方法3
永井孝尚
中経出版
ビジネスにおいて現状維持は衰退への道
経営戦略を物語形式で学ぶシリーズ3作目です。 1作目のテーマは真の「顧客中心主義」、2作目は「成功体験からの脱却」、そしてこの3作目は「イノベーションとリスクへの挑戦」です。 主人公、宮前久美のブレーン的存在だった与田誠がライバル企業にヘッドハンティングされて、商売敵となっていくところから物語が展開します。 コモディティ化された商品の競争環境を例に、それまで勝ち組だった企業は持続的イノベーションを続けることで業績が悪化し、新しく市場参入してきた企業は破壊的イノベーションで勝ち組になっていく様子が描かれています。 そして、さらに、業績が悪化した企業の取るべき戦略が描かれています。 私は、経済のグローバル化や情報のデジタル化により、成功した企業と苦境に陥った企業を頭に思い浮かべながら、本書を通読しました。 思ったのは、ビジネスにおいては現状維持は衰退への道、ということです。 持続的イノベーションも、実は、顧客が求める価値を今まで通りと考えている意味で、現状維持なのでしょう。 だから、あらたな顧客価値を追求した破壊的イノベーションを持った企業の登場によって、持続的イノベーションに陥った企業は衰退の道をたどるのでしょう。 巻末に、本書のもとになったビジネス理論が紹介されています。 現実は本書よりも複雑でしょうが、ビジネス理論のエッセンスを物語を通して理解できる良書だと思います。
1投稿日: 2014.11.30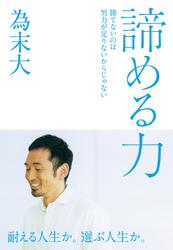
諦める力~勝てないのは努力が足りないからじゃない
為末大
プレジデント社
自分の能力を見極め、目標の達成可能な手段で努力すること
本書を一言で言うと、手段は諦めてもいいが、目的は諦めないことが大事、ということです。 これは著者の為末大氏の競技人生に端的に現れています。 『誤解のないように言っておくが、僕は四〇〇メートルハードルをやりたかったから一〇〇メートルを諦めたわけではない。初めて世界の舞台を見て、ここで勝ってみたいと思ったのだ。しかし一〇〇メートルにこだわっているかぎり、それは絶対に無理だと思われた。 多くの人は、手段を諦めることが諦めだと思っている。 だが、目的さえ諦めなければ、手段は変えてもいいのではないだろうか。 陸上界で最も「勝ちにくい」一〇〇メートルを諦めて、僕にとって「勝ちやすい」四〇〇メートルハードルにフィールドを変えたのは、僕が最も執着する勝利という目的を達成するために「必要だった」と納得できたからだ。』 ただ、これだとちょっと誤解があるので、私は、目標に向かって生きるためには、自分の能力を見極め、目標の達成可能な手段で努力すること、ということと理解しています。 可能性が満ち足りている若いころならまだしも、能力も時間も限界が見えている中年サラリーマンの私には、為末大氏の指摘に耳が痛くなります。 自分のキャリアの考え方に参考になります。
0投稿日: 2014.11.23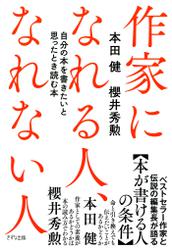
作家になれる人、なれない人(きずな出版)
本田健,櫻井秀勲
きずな出版
作家になれるといいなぁ、と考えている人へのエッセイ風読み物
本書は、作家になれるといいなぁ、と考えている人へのエッセイ風読み物です。 作家の本田健氏と、編集者・作家の櫻井秀勲氏の対談をまとめた本で、読みやすいです。 作家になるためのノウハウやスキルの話というより、作家になるまでの自身の経験や、編集者として担当した作家を見てきた経験に基づいて、作家になれる人はどんな人か、ということが語られています。 作家、というと文章力が大事、と私は思ってしまいますが、情報力が重要、と言われていたのが印象的でした。 『本を書くというときに、自分には文章力がないからダメだという人がいますが、たいていは、文章力よりも情報力がない場合が多いように思います』 『小説家と、実用書の作家を比べたときに、一般的には、小説家は、やはり文章力があります。もっといえば、文章力をつけなければ、小説家はめざせません。 でも、それ以上に、経験を積むこと、情報を集めることが、どんな作家にも必要なように私は思います』 櫻井秀勲氏が担当した、松本清張、三島由紀夫、川端康成などとのエピソードも織り交ぜられていて、大作家の素顔の一端も知ることができます。
0投稿日: 2014.11.15
ゲーデルの哲学 不完全性定理と神の存在論
高橋昌一郎
講談社現代新書
世界は合理的である
本書は、アリストテレス以来の論理学者と言われたゲーデルの哲学に迫った本です。 ゲーデルが考える来世や神の存在論は、「世界は合理的である」という彼の哲学的見解に基づいたものであることが、彼が晩年に書いた4通の「神学的手紙」によって明らかにされています。 『世界は、合理的に構成され、疑問の余地のない意味をもっているという信念を、私は神学的世界像と呼んでいます。この信念は、即座に次の結論を導きます。私達の存在は、現世ではきわめて疑わしい意味しか持たないのですから、それは、来世の存在という目的のための手段に違いありません。そして、すべてのものに意味があるという信念は、すべての結果に原因があるという科学的原理とも対応しているのです』 ゲーデルといえば「不完全性定理」です。 それがどんなものか、素人の私の理解の一助にと思い本書を手にしたのですが、それとは別に、晩年のゲーデルが来世や神の存在論に行き着いたことを本書で知り、大変興味深く読ませていただきました。 著者、高橋昌一郎氏には、人間の理性の限界を一般向けに解説した「理性の限界」という著作があります。 その中で「不完全性定理」も取りあげられていますので、興味のある方はこちらも読まれてはいかがかと思います。
1投稿日: 2014.11.09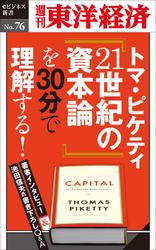
トマ・ピケティ『21世紀の資本論』を30分で理解する! 週刊東洋経済eビジネス新書No.76
週刊東洋経済編集部
東洋経済新報社
大著を読み解く自信はないので、せめてどんな内容か知りたいと思い、本書を手に取りました
今、世界で話題の「21世紀の資本論」。 年末には日本でも発売されるそうですが、私にはこの大著を読み解く力に自信がないので、せめてどんな内容か知りたいと思い、本書を手に取りました。 著者のトマ・ピケティ氏への独占インタビューや、専門家による解説もあり、読んで正解でした。 「21世紀の資本論」の大きな成果は、資本主義では貧富の格差が拡大する、ということを世界各国の一次データにより実証したことです。 マルクスの資本論になぞらえて、「21世紀の資本論」と言われるのもなるほど、と思います。 電子版の特典としてついている池田信夫氏の解説も、「21世紀の資本論」の理解の助けになります。
5投稿日: 2014.11.02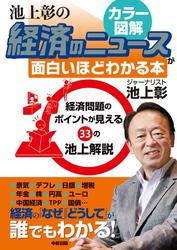
経済のしくみをカラー図解で読み解く! 池上彰の経済のニュースが面白いほどわかる本
池上彰
中経出版
解説だけでなく、その先の「なぜ?」に答えてくれてます
本書は経済ニュースを理解するための解説本で、取りあげられるテーマは下記の6つです。 1. 実はこうなっていた「景気」のしくみ 2. 知っておきたい「金融」のキホン 3. 「お金」と向き合うためのルール 4. いまさら聞けない「株」の話 5. 「世界経済」の動きをつかむ 6. 「日本の借金」はこれからどうなる? 経済の基本的な部分から世界と日本の経済のこれからについて分かりやすくまとめられていると思います。 池上彰さんのニュース解説がためになると思う理由は、誰でもできる通り一遍の解説ではなく、読者や視聴者が感じている、その先の「なぜ?」に答えてくれることにあると思います。 本書で言うと、私の場合は、2001年から2006年に実施した日銀の「量的緩和」です。 「金利の引き下げではなく中央銀行の当座預金残高量を拡大させることによって金融緩和を行う金融政策」 「市中銀行は日本銀行に置いてある当座預金残高の額に比例して融資を行うことができる。量的金融緩和政策とは、この当座預金の残高を増やすことで、市中のマネーサプライ(マネーストック)を増やそうとする政策である」 というのが、量的緩和の通り一遍の解説です(Wikipediaからの引用)。 意味は、私も何とかわかりますが、問題はその先です。 そもそもゼロ金利になっても銀行から企業にお金が回っていないのに、なぜ、量的緩和が景気回復の施策になるのか、恥ずかしながら私にはさっぱりわからなかったです。 池上彰さんは、銀行が抱えていた不良債権のため、量的緩和を行っても銀行の融資額は増えなかったことを指摘し、 『世の中に出回るお金の量を増やすことを「量的緩和」といいます。しかし、お金が増えたから「給料が上がった!」なんて話は聞きません。「金は天下の回りもの」になっていないのです』 と言います。 私は、そういうことなのか、と合点した次第です。
2投稿日: 2014.11.01
grimonaさんのレビュー
いいね!された数133
