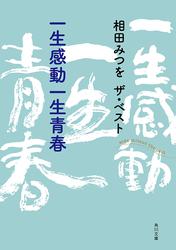
相田みつを ザ・ベスト 一生感動一生青春
相田みつを
角川文庫
宗教心に裏打ちされた相田みつを氏の言葉
相田みつを氏のエッセイ集。 相田みつを氏の書と言葉に触れると、忘れかけていた人間の原点に気付かされます。 例えば、優しさの実践だったり、認め合うことだったり、弱さに素直になることだったり、です。 本書を読むと、相田みつを氏のこのような人間の原点への眼差しは、彼の宗教心に裏打ちされたものだということが分かります。 私が本書で印象に残ったのは「親切という文字 どっちがほんもの」。 「発達障害」と「教養婦人」から差別されているKちゃんという娘が、自分はびしょ濡れになりながらも突然の雨で困っている人たちに傘を届けた出来事を間近で体験したことに触れたもので、長いですが、引用すると、 『わたしは、教育というものの、そしてまた、自分の思い上がった心の中の盲点を突かれた思いがしました。 いま、仮にね、書き取りのテストで親切ということばが出たとします。当たりまえのことですが、その文字が正確に書けなければよい成績は取れない、よい成績がとれなければよい学校にゆけない、よい学校にゆけなければ、よい就職ができない、よい就職ができなければカッコいい生き方ができない--という一連の考え方。そこを一貫して流れているものはすべて<そんとくそろばん>だけです。 世の中を少しでも住みよいものにし、人間の心に、ほのぼのとしたうるおいを与えてくれるものは、そんとくで覚えるテスト用の知識としての<親切>ではなくて、Kちゃんのような、身体で具体的に示す、<親切そのものの行為>であり、温かい心の実践です。Kちゃんのことを差別する教養婦人に比べた時、裸の人間として、果たしてどちらがホンモノでしょう。 Kちゃんのように暖かい心と実践力を持っている人のことを、仏教では仏心のある人と言います。仏心は学歴や教養の有無には一切関係ありません。大学を出れば仏心が身につくか?というとそんなわけにはゆきません。仏教と学問の根本的な差はそこにあります。だから学問だけだと人間は、生きることに於て不完全になるんです。』 私も「そんとくそろばん」の世界にどっぷり浸かって、「親切」というものは「知識」で知っているだけだったのではと、ハッとさせられました。
1投稿日: 2015.09.05
投資は「きれいごと」で成功する
新井和宏
ダイヤモンド社
社会性と経済性を実現する投資
鎌倉投信でファンドマネージャーをつとめる新井和宏氏。 本書では、世界トップクラスの投資銀行をやめて鎌倉投信を設立した経緯や、「R&Iファンド大賞2013」の1位となった投資信託「結い2101」に込めた思いが語られています。 そこからは分かるのは、新井和宏氏の「社会性と経済性を実現する」という投資哲学です。 社会性は、例えば環境問題や地域社会づくりなど「社会課題の解決」です。 経済性は、言うまでもなく利益の創出です。 社会課題の解決には利益が犠牲になる、というのが今までの常識でしたが、新井和宏氏、そして鎌倉投信が目指すのは「社会的課題の解決と企業の成長を、同時に実現する」投資なのです。 そして、その目的を達成するための投資先選択のベースにしているのが、「信頼」です。 新井和宏氏は、それまで投資銀行で格付けに基づく「科学的な投資」を行っていましたが、リーマン・ショックでその限界を知り、投資先との「直接的な関係」から生まれる信頼の重要性を知ったといいます。 『でもリーマン・ショックで、格付けに極端に依存してはダメだと教わりました。だからその代わりに、私たちは「直接的な関係」を重視したのです。レバレッジのもとは、「友達の輪」。自分の目で確かめ、信頼している人をまた信頼し、信頼している人の信頼している人を信頼し、投資先の取引先をまた信頼する。その信頼の輪によって、商品を維持しようと考えました。 第三者の評価をもとにレバレッジをかけるのではなく、自分の目で見て信頼をもとにレバレッジをかける。目に見えないもので「信用創造」をするのではなく、目に見えるもので「信頼創造」をする金融に変えたのです。 実態のないものにレバレッジをかけた結果、金融バブルははじけました。でも信頼ははじけません。崩れる可能性はあるかもしれないけれど、一歩一歩、積み上げる努力もできる。実態があるからです』 『信頼にレバレッジをかけ、「表情」のついたお金で、人と人、企業と投資家をつなぐ。これが鎌倉投信で働く私の仕事の本質なのでしょう』 「投資」というと、つい、儲け話だけに陥りがちですが、本書を読んで、社会性という軸を立てることで、投資の新たな可能性を感じさせてくれました。
0投稿日: 2015.08.13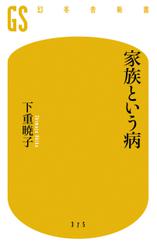
家族という病
下重暁子
幻冬舎新書
個人を蔑ろにしている家族観に違和感を唱えた本
今年ももうすぐお盆の帰省ラッシュが始まります。 この時期のニュースの定番は、新幹線のホームや空港のロビーで、帰省した家族を出迎え、孫との再会を喜ぶおじいさん、おばあさんの光景。 昔は何とも思っていませんでしたが、今は、あまり好きではなく、このようなニュースが始まると、すぐにTVのチャンネルを変えます。 同じような気持ちは、家族写真付きの年賀状をいただいた時にもあります。 私の心がせまいのかも知れませんが、これは偽りのない気持ちです。 この本の著者、下重暁子氏は言います。 『私は、家族写真の年賀状があまり好きではない。善意であることは間違いないし、たくさんいただくので差し障りはあるのだが。 幸せの押し売りのように思えるからだ。家族が前面に出てきて、個人が見えない。感じられない。お互いの家族をもともと知っている場合は別として、私はよその家族を見たいと思っているわけではない。へそ曲がりといわれるかもしれないが、頼んでもいないのに子供の写真を見せられるのに似ている。』 上記は一例ですが、本書は、個人を蔑ろにしている家族観に違和感を唱えた本です。 家族という重みに自分が押しつぶされそうに感じたら、この本を読んでみてはいかがでしょうか。
8投稿日: 2015.08.02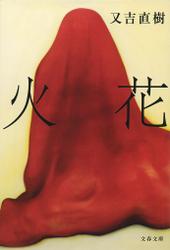
火花
又吉直樹
文春文庫
又吉さんの優しさ
芸に純真なゆえに破天荒な生き方をしてしまう「神谷さん」と、漫才師を志す主人公「徳永」との10年に渡る師弟関係を描いた作品。 著者がピース・又吉さんなので、つい、エンタテイメント性を期待してしまいますが、本作品は紛れもない芥川賞作品。 作品の後半、いよいよ生活まで破綻をきたしはじめた師匠「神谷さん」の笑いの追求が屈折した形になった時、それを見た弟子「徳永」が涙混じりに言います。 『全然、面白くないわ。そんなんキャラクターでも、なんでもないねん。ただの変な奴やんけ。あんた面白いんちゃうんか』 この後、師匠に語る面白くない理由が、常識的で少し物足りなさを感じましたが、しかし、それは又吉さんの優しさでもあると思っています。
1投稿日: 2015.08.01
資本主義の終焉と歴史の危機
水野和夫
集英社新書
近代資本主義を歴史的パースペクティブから捉える
近代資本主義を歴史的パースペクティブから捉えたのが本書です。 資本主義の特徴は利潤の極大化を求めることですが、その資本の利潤と概ね同じ動きをするという10年国債利回り。 1997年に日本の10年国債利回りが2%を下回ってから既に20年余り、今では0.5%前後。 また、米英独仏など主要先進国の10年国債利回りも2%前後か、それを下回る水準です。 歴史上、国債利回りが複数年に渡って2%を下回ったのは、紀元前3000年のシュメール王国以来の5000年の歴史では、17世紀初頭のイタリア・ジェノヴァの時代だけです。 著者の水野和夫氏は、ジェノヴァ時代と現代を比較し、 『単なる偶然では片付けられない相似性が次々と見つかり、「長い一六世紀」と同様の「歴史の危機」にあることを意識するようになって行きました』 と言います。 「長い一六世紀」とは、中世封建システムから近代資本主義システムへの転換が起こった期間のことで、歴史家フェルナン・ブローデルが名づけたものです。 その転換期に起こったのがジェノヴァの利子率低下でした。 利子率=利潤率が2%を下回れば、資本側が得るものはほぼゼロで、これが長期間続くと、既存の経済・社会システムの維持は困難になり、実際、「長い一六世紀」ではシステム転換が起こりました。 そして現在、先進各国で超低金利が続いていることは、今の資本主義経済システムでは投資機会がもはやなくなったことを意味しているのではないか、と指摘します。 では、この先、どのような経済・社会システムを構築すればいいのかは、簡単に答えの出ない、難しい問題です。 水野氏は言います。 『その先にどのようなシステムをつくるべきなのかは、私自身にもわかりません。定常状態のイメージこそ語ったものの、それを支える政治体制や思想、文化の明確な姿は、二一世紀のホッブズやデカルトを待たなければならないのでしょう。 しかし、「歴史の危機」である現在を、どのように生きるかによって、危機がもたらす犠牲は大きく異なってきます。私たちは今まさに「脱成長という成長」を本気で考えなければならない時期を迎えているのです』 現在の金融市場の最大の関心事は、FRBの利上げ時期と言われていますが、今の世界的金融緩和が続くにしろ、FRBが利上げするにしろ、本書を読むと、これらは今の経済・社会システム維持のための弥縫策と映るでしょう。 果たして、今の経済・社会システムを維持できるのか、二一世紀のホッブスやデカルトを待つのか、当然、私ごときが答えは出せませんが、本書を読んで色々考えされられました。
1投稿日: 2015.07.20
直感を裏切る数学 「思い込み」にだまされない数学的思考法
神永正博
ブルーバックス
直感という近道はなし
直感的には正しそうに思えても、実は数学的には正しくないということが証明されている、 そんな事例を分かりやすく紹介したのが本書です。 私が本書を読んで一番興味をもったのが、「アークサインの法則」です。 例えば、野球でもサッカーでも、実力が拮抗しているチームと対戦を続ける場合、最初に勝とうが負けようが、勝率は5割に落ち着くように思うのですが、数学的にはさにあらず。 最初に負けると後まで影響してなかなか逆転できない、ということが数学的にも証明されているとのことです。 勝負事は初戦が大事、ということですね。 その他にも、3択ゲームで、2度目の選択では1度目の選択を変えた方が当たる確率が上がるという、アメリカのゲームショー番組で有名になった「モンティ・ホール問題」も取りあげられていて、興味深く読ませていただきました。 著者の神永正博氏は言います。 『数学に「直感」という近道はありません。結局は、問題を粘り強く考え続けること、論理を一つ一つ丁寧に追いかけることが、正解への唯一の道なのです』 このことは、数学にかぎらず、日常生活や仕事などで我々がなにか問題に直面した時に必要な態度でもあります。
1投稿日: 2015.06.28![[新訳]フランス革命の省察](https://ebookstore.sony.jp/photo/LT00003160/LT000031601000424697_LARGE.jpg)
[新訳]フランス革命の省察
エドマンド・バーク,佐藤健志
PHP研究所
保守主義のバイブルが新訳でリバイバル
古典的名著が、新訳となってリバイバルされました。 本書は保守主義のバイブルと言われていますが、その理由は、深い人間洞察に基づいたフランス革命批判だからだと思います。 1789年7月14日のバスティーユ牢獄襲撃で勃発したフランス革命、その翌年に刊行されたのが本書です。 まだ、国王ルイ16世も王妃マリーアントワネットもギロチンにかけられていない、この時点で、フランス革命が掲げる「自由・平等・博愛(友愛)」という高邁な理念とは裏腹に、この革命がもたらすであろう暴力、無秩序、恐怖政治などの大混乱を予見しているのは驚きです。 それが可能なのも、著者のエドマンド・バーク氏が、 「人間の限界や欠点を直視したうえで、なお社会のあり方をできるだけ望ましくしようとする姿勢」 であるからです。 本書のプロローグで、翻訳者の佐藤健志氏が「『フランス革命の省察』から学ぶもの」と題して、本書にまつわる時代背景や評価、また本書をリバイバルした意図を解説しており、『フランス革命の省察』のより深い理解の助けになります。
2投稿日: 2015.05.23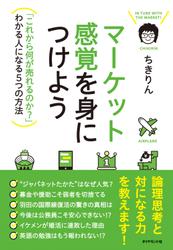
マーケット感覚を身につけよう
ちきりん
ダイヤモンド社
市場化される世界でビジネスをしていくために必要なスキル
本書は、「マーケット感覚」とは何かの説明とその重要性、そして、「マーケット感覚」を身につけるための具体的方法論について書かれた本です。 ピーター・ドラッカーは「企業の目的は顧客の創造である」と言いましたが、顧客の創造に必要なスキルが、本書で言う「マーケット感覚」なのだと思います。 ちきりんさんの言う「マーケット感覚」とは、 ・社会や人がどのような「価値」に基づいて行動するのかを理解する能力 のことです。 この能力(=マーケット感覚)を身につけ、社会や人を動かす「価値」を見出すことが大事な理由をちきりんさんはこう指摘します。 『既存の市場を取り合う競争では、勝つ人がいればその分を負ける人がいるというゼロサム(合計がゼロの)ゲームにしかなりませんが、新たな価値を見いだすことができれば、新たな市場、そして大きな経済価値が生まれます。まだ取引されていない潜在的な価値に気がつき、市場化する——多くの人がマーケット感覚を持つことで、個人はもちろん、世の中もどんどん豊かになっていくのです』 「潜在的な価値に気がつき、市場化する」、これはまさしく、ドラッカーのいう「顧客の創造」のことです。 そしてそのために必要なスキルが「マーケット感覚」なのです。 私が印象に残ったのは、終章の「変わらなければ替えられる」。 主にIT技術の進化に伴う新規ビジネスの登場や、世界的な規制緩和の流れなどで、我々を取り巻くビジネス環境は変化が激しくなっています。 そんな中、変わることを恐れ、守りに入った会社、組織、仕事は、市場の力によって別の会社、組織、仕事に取り替えられてしまいます。 そうならないためにも、「マーケット感覚」を身につけ、時代に適応できる価値を見出し、変化をしていくことの重要性を説いています。 「マーケット感覚」は、市場化される世界でビジネスをしていくために必要なスキルでもあるのです。
0投稿日: 2015.05.10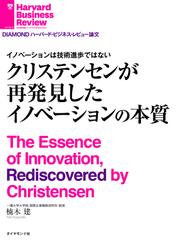
イノベーションは技術進歩ではない クリステンセンが再発見したイノベーションの本質
楠木建
ダイヤモンド社
イノベーションの本質の理解の手助けになる良書
本書は、ジョセフ・シュンペーター、ピーター・F・ドラッカー、クレイトン・クリステンセンらのイノベーションの議論を整理したものです。 イノベーションの本質の理解の手助けになる良書だと思います。 楠木建氏は、イノベーションを考える時の重要なポイントは、「非連続的な変化」と「価値次元の転換」と指摘します。 『一九一一年の『経済発展の理論』においてジョゼフ・シュンペーターが示したオリジナルの議論に戻れば、イノベーションという現象を特徴づけるのは「非連続的な変化」である。これを受けて、ピーター・F・ドラッカーは「価値次元の転換」にイノベーションの非連続性の正体を求めた。この二つの条件が、イノベーションを考える時の重要なポイントになる。』 その上で、「イノベーションのジレンマ」で有名なクリステンセンの議論を以下のように整理します。 『クリステンセンが提唱した「破壊的イノベーション」の概念は、非連続性と価値次元の転換に注目しているという意味で、言葉の正確な意味でのイノベーションである(これに対して「持続的イノベーション」はむしろ「技術進歩」であり、本来の定義からすれば、「イノベーション」ではない)』 では、企業がイノベーションを起こすにはどうすればよいのでしょうか? クリステンセンは既存の組織とは別立ての組織を作る重要性を指摘しましたが、著者はイノベーションを起こすために企業ができることは「がんばるな」ということであり、具体的に「やってはいけないこと」を以下の4つ示しています。 1. 既存の顧客の声を聞かないこと 2. 技術進歩を追わないこと 3. 競合他社のベンチマークをしないこと 4. 意思決定にコンセンサスを求めないこと これらは、一般に「経営」で語られる、顧客第一、たゆまぬ技術進歩、競合他社の分析等の重要なポイントとは真逆の指摘なのが興味深いです。 それは、企業組織と相容れない性質をイノベーションが持っているからです。 『組織や外的な機会ではなく、一個人の内発的な思いつきからイノベーションは始まる。組織が外部から圧力をかけると、イノベーションは卵と同じように破壊される。経営システムをうんぬんする前に、内発的なアイデアやイマジネーションを豊かに持つ個人を自由にさせることだ。』 イノベーションは個人の独創性が重要という意味で、芸術のようなものなのかもしれないと思います。
0投稿日: 2015.05.02
ヤマケイ新書 アルピニズムと死
山野井 泰史
山と溪谷社
人生をかけるに値するクライミング
本書は、「天国に一番近い男」と呼ばれたソロクライマー山野井泰史氏が、自分の登山経験を振り返ったエッセーです。 私は、冒険はもちろん、登山もしない一平凡な市民ですが、本書を手にしたのは、山野井泰史氏の生き方に心惹かれるものがずっとあったからです。 山野井泰史氏のクライミングは、未踏の大岩壁を中心に、より高く、より困難なものに挑戦し続けるものです。それは死と隣り合わせです。 山野井泰史氏は本書で以下のように書いています。 『惚れ惚れするくらい美しい山、誰も到達していない頂、自分を勇気づけさせてくれそうな山々へ、能力の限界を超えないように計画し、また実践してきたのです。 限界のように思えていた一線を越えた瞬間は表現できないほどの喜びがありますが、大幅に限界を超えてまで生還できる甘い世界でないことを知っているつもりです』 『山での死は決して美しくない。でも山に死がなかったら、単なる娯楽になり、人生をかけるに値しない』 「人生をかけるに値する」目標を持つ山野井泰史氏の生き方に、羨ましさと同時に、私は心惹かれるのです。
1投稿日: 2015.04.11
grimonaさんのレビュー
いいね!された数133
