
保守の遺言
中曽根康弘
角川oneテーマ21
保守思想に根ざした日本への遺言
本書は、中曽根康弘氏の保守論であり、保守思想に根ざした日本への遺言です。 本書が出版された前年の2009年、日本も選挙による政権交代がありました。 しかし、「保守とは何か」ということが明らかにされないまま、自由民主党と民主党という、保守二大政党が曲がりなりにもできつつある現状に、中曽根康弘氏は危機感を持ち、書かれたのが本書です。 中曽根康弘氏の考える「保守」は、歴史、伝統、文化によりどころを求めて進化していくことです。 エドマンド・バークを引用して次のように書いています。 『一八世紀のイギリスの保守主義思想家エドマンド・バークは、「保守せんがために改革する」という名言を遺した。すなわち現状を打破するのみで、精神的基礎が非常に薄弱なフランス革命に対するアンチテーゼとして、民族や国家が持つ歴史、伝統、文化を継承する思想として「保守主義」を提唱したのである。ただ、保守というのは、伝統や文化を壊すために改革するのではなく、歴史や文化を大切にし、真の保守に高め、進化させていくために改革が大切なのだということを説いた言葉である。』 「保守」は、ややもすると、現状維持、既得権保護というイメージが先行し、守旧派というレッテル貼りをされかねないです。 しかし、本来の「保守」とは上記のように、「保守せんがために改革する」というものです。 この保守思想と、ご自身の政治家としての体験から、中曽根康弘氏は、これからの日本に、まさに「保守の遺言」という形で様々な提言をされています。 『私は、これからの政治家には、日本という国家の大黒柱にあたる背骨、つまり憲法改正、教育基本法、安全保障政策などといった国家百年の計を考えるような雄々しい政治家が一人でも多く出てきてほしいと思っている』 『私が念頭に置く理想の教育基本法の根底には、子供たちが人間として、また国家、民族の子として、歴史と伝統に育まれた郷土を愛し、自然を尊び、個の尊厳を畏れ、公共に奉仕する気持ちを持つようにする教育である』 『私はこれからの日本が生きていく道は、経済力を備えた文化力で世界に貢献することにあると考えている。多極化した世界では、国家や文化の多様性、文化性を互いに認め合う寛容的な姿勢がなくてはならない』 これらを読んで見えてくるのは、哲学を持った、骨太で芯のある政治家像です。 国政でも、地方議会の場でも、政治家としての資質に疑問を持たざるをえないような、政治家のスキャンダルが目立ち始めた昨今、中曽根康弘氏が抱く危機感は去っていないようで、残念に思います。 最後に、中曽根康弘氏の人生哲学を感じさせる文章がありましたので、引用します。 『私の持論は、「自分の存在というのは、無限への一過程」(in transit to eternity)にある、だ。人生は短いものだが、宇宙の円環の一部をなしている。たとえ「一部」であっても、私という存在がなければ円環は完結しない。だからこそ、それぞれの人生は、それだけで意味があるのだ』 これは、過去から伝統を受け継ぎ、未来へ引き継ぐという、保守思想の考えがにじみ出た言葉だと思います。
0投稿日: 2014.10.25
鉄道フリーきっぷ 達人の旅ワザ
所澤秀樹
光文社新書
フリーきっぷのディープな楽しみ方を紹介した本です(鉄分のある人向け)
本書は、フリーきっぷのディープな楽しみ方を紹介した本です。 一般旅行者というよりも、ちょっと鉄分のある人におすすめの本です。 私も乗り鉄をする時、フリーきっぷを見つけたら、迷わず使う質なので、楽しく読ませていただきました。 構成は、まず、フリーきっぷの基礎知識をおさらいし、その後、フリーきっぷを使った楽しみ方の実践編が3つ紹介されています。 「大井川・あぷとラインフリーきっぷ」を使った大井川鐵道の旅 「地下鉄一日乗車券」をつかった、東京地下鉄の旅 「週末フリーパス」を使った、JR東日本、信州、南東北の旅 フリーきっぷの楽しみ方のポイントは、テーマやこだわりを決めて旅することです。 例えば、「週末フリーパス」の実践例では、ご無沙汰の路線に乗る、名山を堪能する、急勾配の難所を巡る、というテーマを決めて、フリーきっぷで乗れるところは乗り尽くそう、という旅になっています。 観光地の往復にフリーきっぷを使うのもいいですが、それではフリーきっぷのポテンシャルを活かしきっていない、というのが所澤秀樹氏の考えのポイントです。 私も多少鉄分があるので、同感です。 興味深かったのは、路線を双六になぞらえて旅する東京地下鉄の旅。 ゲームの要素を持ち込み、サイコロの目に旅の行く末を託すところは、鉄道が趣味だから楽しめる旅だと思います。
0投稿日: 2014.10.25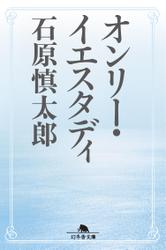
オンリー・イエスタディ
石原慎太郎
幻冬舎文庫
読んでいて、羨ましくも懐かしくも感じられる濃密な交遊録
本書は、石原慎太郎氏の交遊録です。 石原慎太郎氏の交遊録では、政治の回顧録「国家なる幻影」や、文壇、芸能界、スポーツ界の交遊録「わが人生の時の人々」があります。 田中角栄、渡辺美智雄、森繁久彌など重なる部分がありますが、本書で登場する人物は、主に、趣味のヨットの世界や、経済界を中心に石原慎太郎氏と付き合いのあった人々です。 皆さん、その分野では功成り名遂げた人々です。 これは、石原慎太郎氏が、若くして芥川賞作家としてデビューし、その才能を芸術、政治と様々な分野に広げて来たゆえに、縁あった人々なのでしょう。 全18章で取りあげられたのは、一癖も二癖もあるけれど、一本気で、芯が通っていて、義理人情に厚い人たちばかりです。 そんな彼らと石原氏とが織りなす濃密な交遊が、読んでいて、羨ましくも懐かしくも感じられました。
0投稿日: 2014.10.22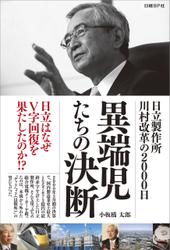
異端児たちの決断 日立製作所 川村改革の2000日
小板橋太郎
日経BP
V字回復を果たした日立製作所の内幕に迫ったドキュメンタリー
2014年3月期に5328億円の営業利益を計上し、23年ぶりに最高益を更新した日立製作所。 そのわずか5年前の2009年3月期は、7873億円という国内製造業史上最大の赤字を計上していました。 本書は、文字通りのV字回復を果たした日立製作所の内幕に迫ったドキュメンタリーです。 主人公は、2009年4月に社長に抜擢された川村隆氏をはじめとする6人組。 川村氏は当時69歳。社内の出世レースから外れ、子会社の会長をしていたといいます。 このような「異端児」ともいうべき6人組は、これから目指すべき日立製作所のビジョンを定め、そのビジョンと資本の論理にもとづき、事業の選択と集中を行っていったのです。 一口に「事業の選択と集中」と言っても、オーナー企業やベンチャー企業とは違い、100年の歴史があり、傘下の会社は1000を超え、総従業員数は30万人を超える日立製作所。このような巨艦の改革は容易でないこと想像に難くないです。 例えば、これから日立製作所が目指すべきビジョンとして定めた「社会イノベーション事業」。このビジョンに向かい、巨艦をどう動かすか。 『「社会イノベーション」と言ってはみたものの、形がなければ社員はついてこない。川村らは早急にその「プロトタイプ」を作ってみせる必要があった。 新体制発足直後、六人組の最年少で、執行役専務から情報・通信担当の副社長に昇格したばかりの髙橋直也は、川村や三好、八丁地からこう指示を受けた。「社会イノベーションを形にしてみせる融合事業を作り出してくれ。当面は電力や社会インフラ事業とITの融合だ。』 これは一例ですが、本書を読むと、6人組が、それまでの日立製作所内部の経験則に囚われない手法で改革を実現していく様子がわかります。 実績を残しながらも、次世代の日立製作所のことを考え、地位に汲々としない川村隆氏の身の処し方がとても印象的で、この人だからこそ、改革が実現できたのだなと思いました。
2投稿日: 2014.10.18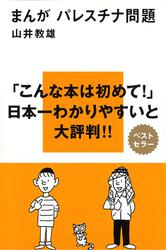
まんが パレスチナ問題
山井教雄
講談社現代新書
読後感は、民族問題に対して何ができるか、自問自答せざるをえなかった
本書は、パレスチナ問題を考える入門書ですが、読後感は、民族問題に対して私には何が出きるか自問自答せざるを得ないものでした。 本書が生まれる背景となったのは、著者の山井教雄氏が、1991年、ユーゴスラビアで行われた国際漫画会議に出席したときの体験です。 当時、ユーゴスラビアは、人口2300万人、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字を持つ1つの国家でした。 しかし、国内では内戦が勃発し、アジテーターに各民族意識が掻き立てられた結果、自分はユーゴスラビア人だ、という人は5%しかいないとのことでした。 これは、1984年にユーゴスラビアのサラエボで冬季オリンピックが開催されてからわずか7年後のことです。 このとき山井教雄氏は次の3つのことを考えたとのことです。 『①民族および民族意識はその時の政治の都合により、人工的に作られるものだ。 ②民族は命をかけて戦い、護るほどの確固たる概念でもないし、崇高なものでもない。 ③今後民族主義は国際的に広がり、人類にとってはガンになるだろう。私は反民族主義の漫画を描き続け、この流れに抵抗しよう』 このような背景があり生まれたのが本書です。 本書の最後に、南アフリカの黒人解放運動のリーダーで後の大統領、ネルソン・マンデラ氏の行動を振り返る形で、民族紛争解決のポイントが2つあげられています。 ・憎しみや恨みを忘れて、テロと報復の連鎖を断ち切ること ・隔離や分離をしないで多民族が平和に融合した世界を目指すこと この2つはあまりにも当たり前のことですが、しかし、パレスチナ問題の歴史1つをとっても、この当たり前なことがどれほど困難なことかと考えさせられてしまいます。 世界は、例えばEUのよう既存の国家の枠組みを越えた政治、経済の統合の動きがある一方、パレスチナに限らず、ロシア、中国、中東でも見られるように民族独立の動きもあります。 特に後者の動きは、先のスコットランドの独立の住民投票のような平和的な手順で進むのはまれで、テロや内戦などで、時の国家や国際社会と武力衝突が多く発生しています。 平和とは対極の事態をもたらす民族問題に、私には何が出きるのか、正直、容易には答えを見つけられません。 ただ、ひとつ実感としてあるのは、民族問題を遠い世界の出来事ととらえず、身近な問題としてとらえることによってでしか、自分なりの答えとやるべきことは見つけられないだろう、という思いです。
0投稿日: 2014.10.13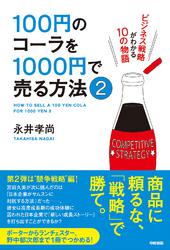
100円のコーラを1000円で売る方法2
永井孝尚
中経出版
経営戦略を物語形式で学ぶシリーズ2作目、「成功体験からの脱却」
経営戦略を物語形式で学ぶシリーズ2作目です。 シリーズ1作目のテーマは真の「顧客中心主義」、2作目のテーマは「成功体験からの脱却」です。 与田誠の指導のもと、真の「顧客中心主義」を理解し、「会計ソフト」の商品開発を成功させた宮前久美でしたが、2作目ではその成功体験がビジネスの成長の妨げになっています。 作者は成功体験からの脱却に必要な3つのシフトを物語の中で展開していきます。 『①網羅思考から、仮説思考・論点思考へのシフト ②すべてやる思考から、やらないことをあえて決断する思考へのシフト ③成功体験にこだわる同質集団から、成功体験にとらわれない多様な集団へのシフト』 1990年代以降の日本の失われた20年の背景には、過去の成功体験にとらわれていることだという作者の問題意識があります。 同じ問題意識を持ちながら、本書を読むと、更に理解が深まると思われます。
1投稿日: 2014.10.04
いまこそアダム・スミスの話をしよう
木暮太一
マトマ出版
アダム・スミスが考えた道徳観から経済理論の理解に迫った本
経済学の父と呼ばれ、「神の見えざる手」で有名なアダム・スミス。 本書は、彼の重要な2つの著作「道徳感情論」と「国富論」を通じ、アダム・スミスが考えた道徳観から経済理論の理解に迫った本です。 アダム・スミスは、「道徳感情論」では他者への共感を必要とする人間像を描く一方、「国富論」では、利己的な行動をする人間像を描いています。 この一見矛盾した人間像をどう理解すればよいのか。 『まずは人間同士が問題なく社会生活を営むことができる「理由」を考え、また人間としてあるべき姿、持つべき道徳観を説いています。そしてその「ヒトとしてあるべき姿」を前提として、経済を発展させる方法を考えているのです』 著者は、「道徳感情論」と「国富論」の原文を丁寧に読み解きながら、アダム・スミスの経済理論は道徳観をベースにしたものであることを、我々一般読者にもわかりやすい形で説明されています。 経済は、「経世済民」の略であり、意味は「世をおさめ、人をすくう」ことです。英語のEconomyもほぼ同義です。 アダム・スミスは、一貫して、「世をおさめ人をすくう」ための人間像と経済理論を考えていたことが、本書を読むとあらためて理解できます。
3投稿日: 2014.09.27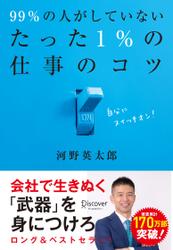
99%の人がしていないたった1%の仕事のコツ
河野英太郎
ディスカヴァー・トゥエンティワン
仕事ができるようになるヒントがあります
本書には、仕事ができるようになるヒントがあります。 具体的には、下記8つの仕事のコツが計87紹介されています。 ・報連相(ホウレンソウ) ・会議 ・メール ・文書作成 ・コミュニケーション ・時間の使い方 ・チームワーク ・目標達成 どれも著者の実務経験を元にしたもので説得力があります。 私のサラリーマン経験からも、肯ける内容でした。 おそらく、多くのビジネスマンも本書で紹介されているコツを実践していると思います。 そのコツをあらためて整理されると、より意識してコツを実践することができるのではないかと思います。 例えば、私の場合、メモについて、あらためて教えられました。 本書では、 『したがって、目標達成のためのメモは、すべて次の行動につながるものになっていなければ意味がありません。 具体的には、すべてのメモを「◯◯を伝える」とか「××を作成する」といった「アクションアイテム」形式にすることです』 というように、メモのコツは、行動につながるキーワードだけにすることと紹介されています。 私も、これからの仕事をメモしますが、自分のメモを振り返ってみると、必ずしも行動につながるアクションアイテムだけでなく、単なる記録も含まれていて、その記録を後から読むと、「さて、何をするんだったっけ?」と戸惑うことが度々ありました。 本書を読み、メモのコツの気付きにつながりました。
0投稿日: 2014.09.27![読書は1冊のノートにまとめなさい[完全版]](https://ebookstore.sony.jp/photo/LT00001372/LT000013728000323580_LARGE.jpg)
読書は1冊のノートにまとめなさい[完全版]
奥野宣之
ダイヤモンド社
私の読書の悩みに答えてくれた5段階ステップの読書術
読書に関し、私は次の3つに悩まされ続けています。 ・本を衝動的に買ってしまう ・本が積ん読になってしまう ・読書後、内容が頭に残らない 本書には、これらの悩みの答えとなる読書術が紹介されています。 その読書術とは、5段階ステップを意識した読書です。 1. 探す 2. 買う 3. 読む 4. 記録する 5. 活用する この5段階を意識して、本を選び、読書し、それをノートに記録し、活用するのです。 例えば、「探す」、「買う」のステップでは、何も意識しないと、すすめられるがままに本を選んだり、広告やランキングにつられて本を衝動買いしたりしてしまいます。 結果、積ん読になってしまったり、無目的な読書になったりで、本の内容が頭に残らないことにつながります。 また、「読む」、「記録する」、「活用する」のステップでは、本を読み自分の感じたことをノートに書き読み返すことが、目的をもった読書につながり、本の内容の記憶への定着をもたらし、読書ノートを援用した知的生産と自己形成が可能になると指摘されています。 私が本書を読んで印象深かったのは「読書体験」について書かれたところです。 『わかりやすく言えば、「本にこう書いてあった」というのが「情報の摂取」。 「本にこう書いてあったのを私はこう受け取った」 「それをきっかけにこう考えた」 というのが「読書体験」です。 要は、本の内容に対するレスポンスとしての自分の考えがあってはじめて、本の内容が身についたことになる。第3章で、読書ノートに自分の感想を書くようにと強調しておいたのも、これが理由です。 本の受け売りから、自分の考えへの跳躍を生むツールこそ読書ノートです。』 私は自分の読書が「情報の摂取」に陥っていなかったかと、ドキリとさせられました。 読書し思考する、という真の「読書体験」を積み重ねていけるよう心掛けたいです。
0投稿日: 2014.09.21
「できる人」という幻想 4つの強迫観念を乗り越える
常見陽平
NHK出版
耳障りの良い言葉で語られる、仕事の「できる人」幻想への警鐘
本書は、耳障りの良い言葉で語られる、仕事の「できる人」幻想に警鐘を鳴らす本です。 具体的には、経営者やコンサルタントが語る、「仕事のできる人」の4つのキーワードが浮ついた言説であると、現場目線で批判しています。 その4つのキーワードは以下です。 ・即戦力 ・グローバル ・コミュニケーション能力 ・起業 例えば、「起業」について。 『二〇代でFacebollkを上場させたマーク・ザッカーバーグなど、一部の「天才」を前提とした話が、メディアでは取りあげられる。すると、若者たちの間で起業家たちが必要以上に英雄視される。これが、平成の起業家を巡る狂想曲である』 というメディアで語られる起業家像は浮ついた言説であることを、サイバーエージェントの藤田氏が味わった苦悩、楽天の三木谷氏の経営面の堅実さ、そして常見陽平氏自らのベンチャー企業経験での苦労から批判されています。 常見氏の批判する仕事の「できる人」に関する4つのキーワードは、耳障りが良い所だけが誇張されがちなのが共通点です。 しかし、仕事の現場では、苦労、失敗、課題の克服などの地道な活動に支えられています。 これからキャリアを積んでいく若者も、私のような中年サラリーマンも、このような耳障りの良い言葉で語られる仕事の「できる人」の言説に踊り、踊らされないために、バランスのある視点を忘れないことが大切だと思います。
0投稿日: 2014.09.15
grimonaさんのレビュー
いいね!された数133
