
週刊ダイヤモンド (2016年7/9号)
ダイヤモンド社
ダイヤモンド社
落語を取り巻く今の状況が分かる
落語を取り巻く今の状況が分かる、約40ページに及ぶ特集です。 今、落語ブームだと言われています。 例えば、首都圏で開かれる落語会の開催件数は月あたり1000件を超え、この10年で約2倍になったそうです。 私も9月中席の末広亭に行ったら、あいにくの天気にも関わらず、2階席まで満員の大入りでした。 落語を聴こうと思えば、テレビ以外にも、YouTube、DVD、CDなど様々なチャネルで楽しめます。 しかし、それには満足できず?に、寄席や落語会に足を運んでライブで楽しむファンが増えているのは、興味深いことです。かくいう私もその一人です。 今や、音楽業界の収益の柱はCDではなくライブであり、プロ野球の観客動員数は2015年に過去最高を記録したといいます。 落語に限らず、エンターテインメントは、メディアを通してでなく、本物を楽しみたい、という世の中の流れがあるのですかね。
0投稿日: 2016.09.25
Googleの哲学
牧野武文
だいわ文庫
Googleを知るための入門書
本書は、Googleを知るための入門書です。Googleの企業活動の根底にある考え方が分かりやすくまとめられています。 それは、一言で言えば、「理念に基づいた企業活動」です。 「Google の使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることです」 これは、Googleのホームページに載っている企業理念です。 Googleは、常に、この理念に基づいた企業活動をしています。 例えば、一見、「なぜGoogleが?」と思わせる自動運転車の開発も、実は、この理念に基づいた企業活動ということが、本書を読むと理解できます。 また、よく知られた、仕事時間の20%を与えられた仕事以外の好きなプロジェクトに使える「20%ルール」。これも、Googleの理念がエンジニアに共有されているから機能している制度なのでしょう。 本書を読んで印象に残ったのは、Googleでは、学歴だけでなく人物本位の採用がされているということです。 『グーグルでは優秀な人間であっても、協調性がなかったり、エゴの強い人間は採用されないのです。ですから、グーグルで働いているスタッフは、みな同僚が大好きで、毎日長時間働いていても、楽しくてしかたないといった人たちです。 徹底した学歴主義と、徹底した人物主義をうまく組み合わせたのが、グーグルの採用基準なのです。』 この点については、Googleの人事トップの著書、「ワーク・ルールズ!―君の生き方とリーダーシップを変える」も参考になります。
0投稿日: 2016.08.22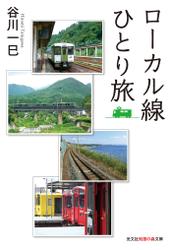
ローカル線ひとり旅
谷川一巳
光文社知恵の森文庫
ローカル線の旅は楽しい
ローカル線。 実際に乗ってみると、観光客で賑わっているわけでもなく、何の変哲もない、地元の足として親しまれている鉄道だったりするのですが、鉄道を乗ることが趣味の私には、旅情を掻き立てる汽車旅に思えるから不思議です。 青春18きっぷの発売シーズンになると、今度はどこのローカル線を旅しようかと、時刻表と地図を相手にああでもないこうでもないと悪戦苦闘するのが至福の時間であったりもします。 そんな私にとって、本書は、ローカル線の旅の楽しさの再確認に役立ちました。 本書では、ローカル線を旅するにあたってのプランの立て方、車両や切符の選び方といったテクニカルところから、日本の地理や鉄道の歴史を知ることで深まるローカル線の旅の楽しさまで、ローカル線の旅の極意が紹介されています。 著者の谷川一巳氏は、ローカル線の旅の良さを次のように語ります。 『「ガイドブックに載らない」というより「載るはずもない」光景を見に行くのだ。すると、体がぞくぞくするような光景に出くわすこともある。』 『そもそも何かの節目に旅行をしようというのではない。卒業、結婚、退職、あるいは子育てが終わったなど、何かと理由をつけて気負って旅行するよりも、普段着で、ぶらりと旅に出てみたいものだ。頭で考える前に、体が勝手に動き出すような旅が理想だ。 (中略) 旅はもっと気負わずに行きたい。それは学生のように体力勝負の旅ではなく、鉄道マニアのように列車だけに目を向ける旅でもなく、団体ツアーのやかましい旅でもない。ちょっと西の方へ様子を見に行く、最近、北の方はどうなっているのか確かめに行く……。そんな旅でいいのだ。 旅することが日々の生活に溶け込んでいるような、旅慣れた〝おとな〟でありたい。』 私も同感です。そして、「旅慣れた"おとな"」にいつかなりたいと思っています。
1投稿日: 2016.07.24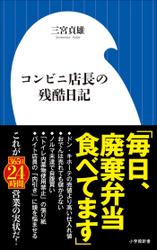
コンビニ店長の残酷日記(小学館新書)
三宮貞雄
小学館新書
コンビニ店長の苦悩と誇り
本当に身近になったコンビニ。 私もよくコンビニを利用しますが、いつも感心するのは、単に商品のレジ処理だけでなく、宅配便の発送や、受け取り、公共料金の支払、お中元・お歳暮の申し込みなど、おそらくサービス毎に異なるであろうレジ手順を手際よく、間違いなく処理するなぁ、ということです。 もちろん、多種多様なサービスがコンビニで可能な裏には、人知れぬコンビニ店長の苦労があるようです。 そんなコンビニの仕事の実態を知りたくて、本書を読みました。 読んでみると、レジでの接客だけでなく、本部との関係、アルバイト、トイレ、ゴミ、万引き等々、コンビニの実態を前にした、店長の抱える苦悩がこの1冊に凝縮されています。 「残酷日記」と刺激的なタイトルですが、いわゆる暴露本の類とは違います。 『今年も嫌なことも辛いこともあったけど、やっぱり、俺はこの仕事が好きだ。みんなが必要なものをいつでも提供できる。社会に貢献できていると思えるからだ。それになんといっても人が好きなのだ。これからもあれこれぼやきながら、この仕事を続けていくのだろう。「ご来店ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております」』 コンビニ店長としての誇りも感じさせてくれる本です。
0投稿日: 2016.06.18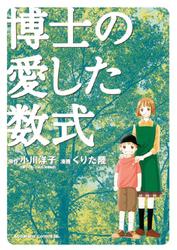
博士の愛した数式
小川洋子,くりた陸
BE・LOVE
原作の良さに触れられるコミック版
ベストセラーで、映画化もされた「博士の愛した数式」。そのコミック版です。 私は、このコミック版だけしか読んでないですが、心温まる作品でした。 原作の小川洋子さんが、あとがきで次のようにを書いています。 『自分の小説に新たな命が吹き込まれるのを間近にできるとは、何と幸せなことだろうか。くりたさんは何度も原作を読み返してくださったそうだ。書いた本人の私でさえ気づいていない、小説の奥底に隠れていたものをくりたさんが救い出し、コミックという新しい場所で再生して下さったのだ。』 コミック版でも、原作の良さに触れられたと思っています。 巻末には、原作者の小川洋子さんと、漫画家のくりた睦さんの対談も掲載されており、原作の誕生秘話や漫画化の苦労話も知ることができます。
0投稿日: 2016.05.01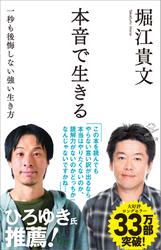
本音で生きる 一秒も後悔しない強い生き方
堀江貴文
SB新書
他人の人生ではなく、自分の人生を生きる
本書は、他人の人生ではなく、自分の人生を生きるための堀江貴文氏からのアドバイスです。 学問、ビジネス、趣味、など、自分の本音では「これをやりたい」と思ったことでも、 「自分には能力がないから」 「親が反対するから」 「家族がいるから」 「世間ではまだ認められていないから」 など、「やれない理由」を見つけて、現状から一歩が踏み出せない人がいます(かく言う私も大いにそのひとりです)。 本音を胸の内に閉まったまま生きる人生は、結局、それは自分の人生ではなく、他人の人生を生きていることに他なりません。 このことは、ベストセラー「嫌われる勇気」でもよく出てくる指摘です(本書でも随所に「嫌われる勇気」からの引用が出てきます)。 本書では、胸の内の殻を打ち破り、本音で生きるための堀江貴文氏からのアドバイスを読むことができます。 本書から1つだけ引用します。 『些細なことでよいから、常に小さなチャレンジを行ない、少しずつ少しずつ成功体験を重ねていく。なんでもうまくこなせる人間と比較して落ち込むのは無意味なことだ。ここで比べるべきは、過去の自分。自分の成長を実感できれば、それが自信になる』 現状から一歩が踏み出せない人というのは、「やれない理由」を見つける以外にも、リスクに尻込みしているということもあると思います。 ついつい、タイトルだけで想像すると、本書は、「リスクなんて考えずに、本音で生きろ」、と言っていると勘違いしてしまいますが、そうではなく、蛮勇と勇気の違いを見極めたアドバイスです。
3投稿日: 2016.05.01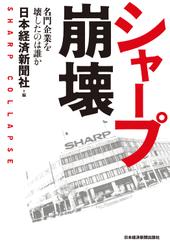
シャープ崩壊--名門企業を壊したのは誰か
日本経済新聞社
日本経済新聞出版
会社は経営者ひとつで傾きもするし立ち直りもする
どうしてシャープが経営危機に陥ったのかを知りたくて、一気に読みました。 シャープが経営危機に陥った直接の原因は、液晶への過剰投資。 しかしそれは起きてしまった過去。過去との決別なしには新しい一歩に踏み出せません。 このような時、経営者に求められるのは、 ・過去の課題へ対処するための痛みを伴う改革を実行すること(選択) ・将来のビジョンを定め会社を成長フェーズにのせる改革を実行すること(集中) というように、経営危機の本質を見極め、事業の選択と集中を実行する能力です。 しかし、シャープの経営者は、事業の選択と集中が必要な時に、過去との決別も、将来のビジョンも曖昧なままにし、時間だけが過ぎ去りました。 たしかに、時の経営者は、 ・「液晶の次も液晶」 ・「けったいな文化を変える」 と、会社の方向性を示しはします。 しかし、経営危機の本質を見極めているとは思い難く、また、危機克服のためには力強さにかける内容に思われます。 例えば、同じ電機業界で、リーマン・ショック後に経営危機に陥った日立製作所では、異端児と呼ばれた6人組の経営層が、「社会イノベーション事業」を会社の進むべきビジョンと定め、事業の選択と集中をし、見事V字回復を果たしました(「異端児たちの決断 日立製作所 川村改革の2000日」)。 本書を読んで、経営危機後の経営層の人事抗争が、シャープを混迷に追いやった様子を知るにつけ、会社は経営者ひとつで傾きもするし立ち直りもするのだ、ということをあらためて思った次第です。 2016年4月2日、鴻海精密工業によるシャープ買収契約が締結されました。 IEEEマイルストーンを3件受賞している名門企業シャープ。 新しい経営者の下、シャープが再建されることを願っています。
0投稿日: 2016.04.02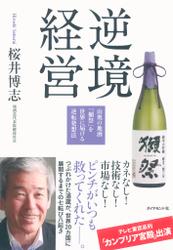
逆境経営
桜井博志
ダイヤモンド社
逆境や困難に立ち向かうことが成長や成功に繋がる
純米大吟醸酒のトップブランド、「獺祭」。 本書はその誕生と成長の物語です。 1984年、著者の桜井博志氏は父の急逝を受け家業の旭酒造を継ぎます。 その頃の日本酒市場は、第一次焼酎ブームのあおりを受け、縮小の一途。 加えて、旭酒造は、山口県で4番手という地方の小さな酒蔵で、主力製品といえば、普通酒でしかも品質は二の次と言われた「二級酒」。 このままではジリ貧という経営環境の中、立ち返ったのは、「旨いお酒を造る」という企業存立の原点です。 この原点を目標に据え、挑戦したのは、小さな酒蔵だからこそできる高品質な大吟醸酒づくりです。 もちろん初めから大吟醸酒造りがうまくいくはずもなく、初めて造った大吟醸酒はなんとも言えない味だったそうです。 しかしこのことが「徹底的に美味しいお酒を造る」という決意をもたらし、挑戦と変革を実行していきます。 それは、米や酵母への徹底的なこだわりであったり、四季醸造という今までの日本酒造りの習慣を変えるものだったり、獺祭の美味しさを理解してもらうために海外にも直営店を儲けることだったり、です。 私が通読して思ったことは、企業でも人でも、逆境や困難に立ち向かうことが成長や成功に繋がる、ということです。 もちろん、逆境や困難は徒手空拳で立ち向かえるものではなく、自らの能力や置かれた状況を理解したうえで初めて、本当の目標が見え、そのための戦略や戦術を立てることができ、その後の成長や成功に繋がる、ということだと思います。 著者の桜井博志氏が「逆境経営」に込めた思いも、そういうところにあるのでないかと思っています。
0投稿日: 2016.03.20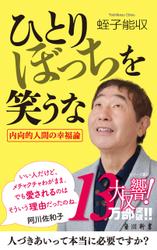
ひとりぼっちを笑うな
蛭子能収
角川oneテーマ21
「絆」へのアンチテーゼを求めて手にした本ですが、、、
社交的でなく、会社でもぼっち飯の私は、巷で話題の、蛭子さんのこの本を興味深く手に取りました。 蛭子さんの言うように 『いまの時代、「友だち」や「仲間」、あるいは「つながり」や「絆」を、必要以上に重く考える傾向があると思います。でも、そうまでして「友だち」って必要なのかなあ。』 というのには共感して、ページを進めたのですが、蛭子さんの言いたいことは、ひとりでいることが好き、でも、良き伴侶を見つけることが大事だよ、ということで、私には少々消化不良でした。 『『ひとりぼっちを笑うな』──この本には、そんなタイトルをつけてみました。でも、僕が一番言いたいのは、ひとりぼっちを笑わないことではないかもしれない。もちろん、いつもポツンとひとりでいる、僕も含めた内向的な人たちを笑うことは、とても愚かなこと。ただ、それ以上に大事なことがあると思うんです。 それは、ひとりぼっちでいることをけっして笑うことなく、そんな自分を微笑みながらいつでも受け止めてくれる人を見つけること。 僕がこれまでの人生をとおして一番みなさんに伝えたいのは、その大切さなのかもしれません。』 蛭子さんの結論は、私も理解できるのですが、ただ、「絆」へのアンチテーゼを求めて手にした本でしたので、残念ながら期待外れでした。
1投稿日: 2016.02.27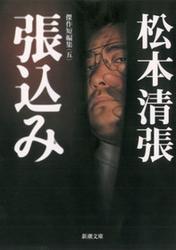
張込み―傑作短編集(五)―
松本清張
新潮社
人間の業を描く推理小説
「張込み」が読みたくて購入しました。 20年近く前に新聞のコラムで知り、読みたいと思っていた本でした。 読後感は、もちろん、満足です。 1955年の作品だから、もう60年以上経っていることに驚きましたが、今でも読み応えがあります。 それは、松本清張氏の作品が単なる推理小説ではなく、人間の業を描いているからなのだと思います。
2投稿日: 2016.01.20
grimonaさんのレビュー
いいね!された数133
