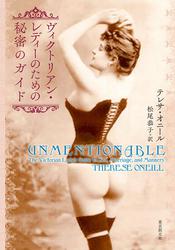
ヴィクトリアン・レディーのための秘密のガイド
テレサ・オニール,松尾恭子
東京創元社
ヴィクトリアンでもなければレディでもない
タイトルから受ける印象に反して本書はイギリス史ではありません。基本的に「19世紀アメリカ」です。「ヴィクトリア朝といえばロマンティックなイメージだけど、実際は臭くて汚くて差別的だった」ということを19世紀アメリカ(!)を例に、皮肉と冷笑を交えて紹介します。確かに当時のアメリカはヴィクトリア朝イギリスの文化的影響下にあり、ヴィクトリアニズムとも言われる禁欲主義はアメリカでも強く見られましたが、物質的な側面から言えば、むしろ君ら「西部開拓時代」だよね、と言いたい。 このように本書は歴史書ではなく、エッセイ?くらいの内容です。歴史的な写真、図版、イラスト(ほぼすべてアメリカのもの)は豊富ですが、出典や解説はなく、著者のコメントが付いているだけです。 また、あまり値段については言いたくないのですが、これで4000円はかなり割高感あります。4000円といえばちょっとした専門書が買えます。専門書ではないですが、ルース・グッドマン『ヴィクトリア朝英国人の日常生活』がハードカヴァー、上下2冊でちょうど4000円。おなじ4000円ならそっちを推します。
1投稿日: 2019.08.10
「発酵」のことが一冊でまるごとわかる
齋藤勝裕
ベレ出版
分かりやすいけど……
イラストや写真が多く、分かりやすいが本題以外の部分、話の枕としてのトリヴィアルな話題はかなり適当で間違いも多く見受けられる。ゼロから勉強を始めるための「準備」としてはいいかもしれないけど、値段を加味して他人にお勧めできるかというと……微妙。オマケして星3。
0投稿日: 2019.06.17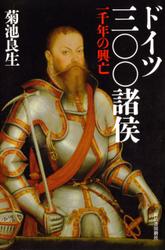
ドイツ三〇〇諸侯 一千年の興亡
菊池良生
河出書房新社
長めの歴史エッセイ
ドイツ文学系の著者なので、読みやすく、面白いが、文学、エッセイからの引用が多く、あまり学術的な厳密さは重視されていない。例えば本書の主題である「諸侯」についてだが、確かにドイツは神聖ローマ帝国解体後、最終的に300を超える領邦に分裂する。しかし本書の扱う期間の大部分において諸侯(フュルスト)という身分はいくつかの例外を除けば原則的に辺境伯以上、後のドイツ帝国で「侯爵」(フュルスト)として扱われる大貴族だけに限定されていた。本書では「城伯」(ブルクグラーフ)以上を諸侯として扱ってしまっている。ランクとしては2ランクほど(城伯<伯<辺境伯)サバを読み、数としては10倍になってしまっている。これはあまりに乱暴であろう。 他にも学説としてはあまり最近の知見は反映されていない感じがある。一方で学術書や論文ではあまり見られないゴシップなどにも言及があり、これはこれで理解の一助となる。 レポートなどの参考文献にするのには向かないが、読み物としてはおすすめできる。
0投稿日: 2019.06.14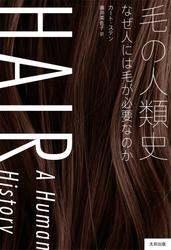
毛の人類史 なぜ人には毛が必要なのか
カート・ステン;藤井 美佐子
太田出版
髪と毛皮の物語
元イェール大学の教授で、アデランスの研究所にもいたという(現在は別の研究所所属)医学・生理学の研究者による「毛」の概説書。生命の進化から始まり、哺乳類の毛の獲得、人類の祖先による体毛の喪失など。英語のhairは人間の髪だけでなく、哺乳類の体毛なども含まれ、本書では毛皮や毛織物などに関する歴史も扱っている。毛髪・体毛の科学的な解説がウール製品などの文化的・経済的な話題に関連してくるのが面白い。 頭髪が気になる人も、そうでない人にもおすすめの一冊。
0投稿日: 2019.05.06
茶の世界史 改版 緑茶の文化と紅茶の社会
角山栄
中公新書
定番の入門書
日本における社会史の開拓者、イギリス史研究者角山榮氏による「お茶の歴史」の入門書。半分は著者の専門分野であるイギリスが中心、もう半分は開国と明治維新後の日本茶輸出にむけた努力のお話となります。 初版は1980年と結構前になりますが、内容に古さは感じません。歴史学者の手によるだけあって、下手な紅茶のうんちく本とは違い、史実に基づいたしっかりした内容ですし、新書ということで値段的にも内容的にも最初に手に取ってみるのに最適と言えます。紅茶好きなら読んでおきたい一冊です。
0投稿日: 2019.03.27
戦争の技術
ニッコロ・マキァヴェッリ,服部文彦
ちくま学芸文庫
ぼくのかんがえたすごい軍制
『君主論』のマキャベリが考えた「すごい軍制」です。「戦争の技術」というタイトルからは戦術論的な内容を思い浮かべたとしたら、少し肩すかしを受けるかもしれません。 本書を読む前に当時の状況を理解する必要があります。マキャベリが生きたのは中世から近世への過渡期ともいうべき時代で、当時、戦争の主役は騎士から傭兵へと移り変わっていました。この頃の傭兵は戦争が終わると部隊ごと解雇されます。この解雇された傭兵隊が(生きるために)周辺の村や都市を襲うことがよくありました。これがイタリアに限らず当時のヨーロッパの大問題でした。そこでマキャベリは大好きな古典古代に範をとり、傭兵に頼らない市民による軍隊の創設を提案するわけです。市民なら自分の街を守るため仕事を休んで無給で戦うのは当然でしょ?訓練だってちゃんとするでしょ?……この前提から始まり、マキャベリは戦場での布陣や宿営の設営まで細かく指示をしています。主にギリシア・ローマの故事を根拠として。……この辺、無駄に指定が細かくて机上の空論感があります。 ところで、その後のヨーロッパの歴史から見ると、この問題に対する正解はマキャベリの提案とは正反対の所にあります。すなわち「傭兵を解雇せずに常備軍化する」です。香辛料貿易を独占し経済力をもったオランダが「正社員」化した傭兵を用いてスペインから独立できた理由として、あるいはその後イギリスがオランダを凌駕し、フランスを破りヘゲモニー国家となった理由として、マクニール(『世界史』シリーズ)やハワード(『ヨーロッパ史における戦争』)といった史家が指摘するところです。マキャベリは本書で「傭兵を平時も雇える国家は存在しない。破産してしまう」と、その可能性を最初に切り捨てていますが、本来すべきはどうにかして破産せずに傭兵を常時雇用する方法を探すべきでした。可能であるかは別として。 という訳で、間違った前提から出発した上にやたら細かく具体的な本書の内容は現実的な問題への処方箋とはなり得ないし、すべきでもないでしょう。一方で、当時の各兵種に対する考え方、特に大砲の扱いなどは非常に興味深いものがあります。純粋に史料としての価値は高いので、近世初期のヨーロッパの軍事などに興味のある方にはおすすめです。
0投稿日: 2019.03.10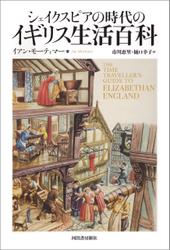
シェイクスピアの時代のイギリス生活百科
イアン・モーティマー,市川恵里,樋口幸子
河出書房新社
エリザベス朝タイムトラベラーガイド
原題は"The Time Traveller's Guide to Elizabethan England"。三冊出ているシリーズの二冊目とのことです。他の二冊は中世と王政復古期で未邦訳。 エリザベス1世時代の社会・生活全般の解説が主な内容です。衣食住といった歴史書の概説ではあまり書かれなかったり、書かれたとしてもかなり専門的になることの多い事柄などが解説されています。著者は研究の傍ら歴史小説を執筆しているとのことで、本書も学術的な裏付けがしっかりと感じられる一方で、専門外の人でも分かり易いように書かれています。 ちなみに本書は紙の本の出版から電子化まで一年半ほど。ご参考までに。
1投稿日: 2019.01.27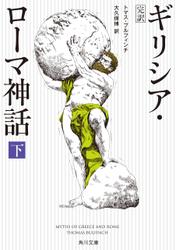
完訳 ギリシア・ローマ神話 下
トマス・ブルフィンチ,大久保博
角川文庫
19世紀版教養としての神話
原著は19世紀初版なのでちょっと21世紀日本語読者とは前提とされる知識に違いがあり、英文学については知っている前提で話が進みます。エロとかグロは控えめでマイルドな全年齢版。ギリシア神話というよりも、英文学の本として読むのが面白いかも。机の脚にまで靴下を履かせたヴィクトリア朝の倫理観がアメリカまで影響を及ぼしていたことの好例が見て取れます。 下巻はギリシア以外の神話もちょっとあります。 上下合本版もありますので、ご検討を。
0投稿日: 2019.01.05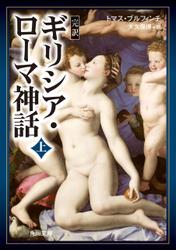
完訳 ギリシア・ローマ神話 上
トマス・ブルフィンチ,大久保博
角川文庫
19世紀版教養としてのギリシア神話
19世紀における教養としてのギリシア神話。平然とバイロンとか、シェリーとか引用してくる。近代英米文学、特に英文学の知識はそれなりにあるけど、ギリシア神話はよく知らないという人に向けて書かれている(初版は19世紀半ば)ので、現代日本の読者に最適化されているわけではない。翻訳が良く、読みやすいので、入門書に向いていないことはないものの、他にあるよね、という印象。 19世紀らしく、成人向け要素は意図的に避けられているので、そういう点では中高生の入門書にはいいかも。 上下合本版もあるので、読み切るつもりならそちらも要検討。
0投稿日: 2019.01.05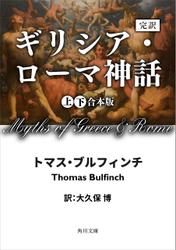
完訳 ギリシア・ローマ神話 上下合本版
トマス・ブルフィンチ,大久保博
角川文庫
19世紀版教養としてのギリシア神話
1855年、ボストンで初版が出版された"Age of Fable"の翻訳。「伝説の時代」、「神話の時代」くらいの意味になりましょうか。大部分はギリシア・ローマというか、ギリシア神話で、最後の方の10%ぐらいが東洋(インドから中東あたり)と北欧に触れています。1970年に日本語訳され、その際、出版社側のリクエストでギリシア・ローマを強調した現在の題名となり、2004年に増補改訂版が上下巻で出版されました。 ローマ経由のギリシア神話を19世紀の英米文学の文脈で解説するという、ちょっと特殊な形式となっています。「ホメロスを引用したウェルギリウスを引用したバイロンを引用して解説」と言えばよろしいでしょうか…… また当時の倫理観を反映してか、ギリシア神話の下世話で猥雑な部分がかなりマイルドにぼかされています。一般的なギリシア神話の入門書としてはあまり向かないかもしれません。 19世紀までの英米文学を読みたい、読んでいるけれども、ギリシア神話の比喩がまったく分からないので入門書を探している、という人がもしいれば本書がうってつけかもしれません。
0投稿日: 2019.01.05
iciさんのレビュー
いいね!された数95
