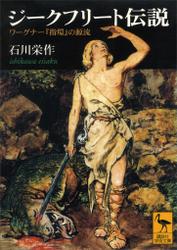
ジークフリート伝説
石川栄作
講談社学術文庫
ジークフリート物語
メインはあくまでもワグナー版であり、そこに至るまでのヴァリエーションというか、変遷を追い、時代ごとの作者たちによる翻案やその意図が論じられています。つまりオリジナルの伝説ではなく、そこから派生し、創作された物語こそが主題。これは「ジークフリート伝説」とは言えないのでは?作者が明らかになっているお話しは「伝説」とは呼ばないでしょう? 「伝説」を調べたいなら同じ講談社学術文庫から出ているグレンベック『北欧神話と伝説』に直接あたった方が良いかも。トゥールのグレゴリウス『フランク史』(新評論)やティエリ『メロヴィング朝史話』(岩波文庫)もオススメ。
0投稿日: 2020.12.27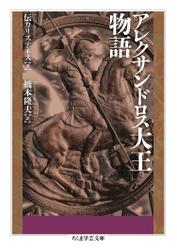
アレクサンドロス大王物語
伝カリステネス,橋本隆夫
ちくま学芸文庫
伝説としてのイスカンダル
概要に書かれているように、史実ベースではなく、あくまで「中世ヨーロッパにおいてアレクサンドロス大王の伝説がどのように語られてきたか」を知るための本です。複数の版が収録されており、それぞれの差分も確認できます。要所を抑えた上で色々と脚色があったり、荒唐無稽な「東洋」の神秘が盛り込まれていたりなので、「聖書に次いで読まれた本」というアオリは付いているものの、アレクサンダー大王について調べる時に最初に読む本というよりは、別の概説書で史実と基本を抑えた上で応用編として読むべき本、といった所かと思います。 また「アリストテレス宛の手紙」は講談社学術文庫の『西洋中世奇譚集成 東方の驚異』にも収録されていますので、読み比べてみるのも良いかもしれません。
0投稿日: 2020.11.22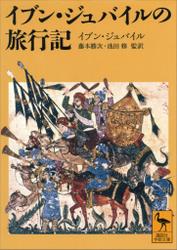
イブン・ジュバイルの旅行記
イブン・ジュバイル,藤本勝次,池田修
講談社学術文庫
読む人を選ぶ
十字軍時代の旅行記。現在でいうスペインからエジプトを経て、メッカ巡礼後にスペインに戻る間の記述に当時の社会が垣間見える。全部読むというよりも、興味のある所だけ拾い読みする方がいいかも。個人的には著者がエジプトを支配するサラディンに寄せる絶大な信頼が面白かった。またノルマン朝シチリア王国でのキリスト教徒とイスラム教徒の(なんとか)共存する様子なども興味深い。
0投稿日: 2020.10.18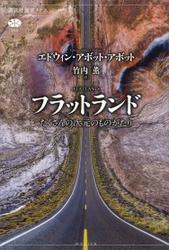
フラットランド たくさんの次元のものがたり
エドウィン・アボット・アボット,竹内薫,アイドゥン・ブユクタシ
講談社選書メチエ
主人公は正方形(職業弁護士)
二次元(フラットランド)の視点から、零次元、一次元、二次元、三次元がそれぞれどう見えるかという思考実験をベースに社会風刺を混ぜて物語風に仕立てた作品。あまり長くはないので気軽に読めるが、分かりやすいかというとそうでもない。考えるな、感じろとしか良いようがない。 1884年出という時代的隔たりにもかかわらず、思考実験部分には古さを感じない。風刺部分については、まあ、当時の人に向けて書かれているだけあって、ヴィクトリア朝社会一般についての知識がある程度ないと受け取るのが難しいよね、という感じ。一次元(ラインランド Lineland)は当然のようにRheinlandラインラントすなわち当時建艦ブリテンと建艦競争を繰り広げていたドイツを思い起こさせるとか。多分。 見所は球によって(文字通り)次元の違いを教えられた正方形が逆転を果たせるのか、といったあたり。
0投稿日: 2020.09.05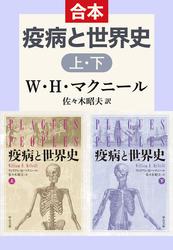
疫病と世界史(上下合本)
ウィリアム・H・マクニール,佐々木昭夫
中公文庫
『世界史』だけじゃないマクニール
マクニールの『世界史』(よく「東大生協で一番売れてる歴史書」みたいな売り方してるやつ)三部作の二作目。 紙書籍版は結構前の出版ですが、人の移動による伝播や集団内における免疫と周期的な流行を扱っていたり、中々タイムリー。というか、むしろ時勢を受けて電子化したのかな。 個人的に三部作の評価は3(『戦争の世界史』)>1(無印)>2(本書)。当時の人の遺伝的特性や免疫なんて実証出来ないので、推論の域を出ない所が多いのがちょっと気になります。軍事的な勢力を「寄生」と見做して、疫病と比較したり、三作目は本書の内容を軽く踏まえた話になるので、本書も読んでおきたいです。三作目はマジ名著だから。
0投稿日: 2020.08.01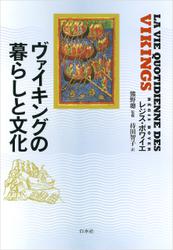
ヴァイキングの暮らしと文化
レジス・ボワイエ,熊野聰,持田智子
白水社
ヴァイキングの日常生活
「ザ・蛮族」として扱われることの多い「ヴァイキング」の日常生活と文化を描いた名著。専門的ではありますが読みやすく、幅広い層にオススメできる本です。 原題は"La Vie Quotidienne des Vikings"、ほぼそのまま「ヴァイキングの日常生活」と訳せます。1992年に原著が出版され、2001年に邦訳(多分ハードカバー)、2019年にソフトカバーの新装版が出ており、電子版はこの新装版を元にしています。原著初版から30年、日本語版ハードカバーから20年くらい経っているものの、内容的な古さを感じさせないのは凄い。著者はフランスにおける中世北欧文化研究の大家だった方(2017年没)とのことで、やはりガチの中世史はフランスが強いなあという印象。ただ図版や写真はもうちょっと欲しかったです。
0投稿日: 2020.06.08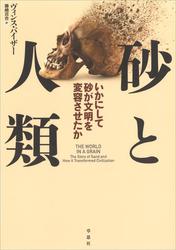
砂と人類:いかにして砂が文明を変容させたか
ヴィンス・バイザー,藤崎百合
草思社
ドキュメンタリー風
セメントになったり、セメントと混ざってコンクリートになった、ガラスになったり、シリコンチップになったり、水と一緒に地下深くに撃ち込まれたりと現代文明のあちこちで不可欠な働きをしている砂。一方で用途が広すぎて資源として枯渇が危惧されたり、採掘による周辺環境への影響が取り沙汰されている。著者はジャーナリストで、本書もインタビューや調査を元にしたドキュメンタリーを思わせる構成となっている。科学や歴史の啓蒙書というよりは、砂にまつわる問題を知らしめることを目的として書かれているように思われる。 科学的な典拠となっているのが、ポピュラー・サイエンス(一般向け自然科学啓蒙書)だったり、修士論文だったりで、信頼性に欠けるとまでは言わないものの、もうちょっと頑張ろ?ちゃんと専門書に当たろ?という不満が残るものの、読みやすく分かりやすいので、まあ、許容範囲か。
0投稿日: 2020.04.08
西洋中世奇譚集成 魔術師マーリン
ロベール・ド・ボロン,横山安由美
講談社学術文庫
光と闇が合わさり最強に見えるマーリン
13世紀初頭(訳者解説によれば1210年頃)にロベール・ド・ボロンによって書かれた『魔術師マーリン』の翻訳。マーリンの誕生からアーサー王の即位まで。アーサー王の父ウーサー(本書ではユテル)の代が中心アーサー王伝説で言えば前日談から本編プロローグ部分に相当します。 解説によれば、ウェールズの伝承にある王子?ミルディンとブリタニアの歴史の中で語られた夢魔と人間のハーフであるメルリヌスをジェフリー・オヴ・モンマスが一つにまとめ、そこに本書の著者ロベールがキリスト教説話的な要素を加えたのが本書とのこと。マーリンの予言者としての能力については夢魔(悪魔)が反キリストを生み出すために与えた過去を知る能力に加え、それに対抗して神が与えた未来を知る能力を併せ持つことによるものとされています。つまり神と悪魔の力を併せ持った、当時の人が考えた最強の魔術師がマーリンというわけです。 アーサーの他はケイが少し、ガウェイン、ガレス、モードレッドが顔出し程度で、その他の円卓の騎士は出番なし。マーリンが湖の乙女ヴィヴィアンに監禁される件もなし。若干、原作者の解釈違いが危惧されるものの、ケイの小物ムーヴに「乳母に育てさせたからひねくれた」という説明がされていたり、本編への理解が深まる記述もあります。アーサー王伝説の作中の時系列的には最初の部分になりますが、入門書には向きません。とはいえ一通り流れを抑えた上で、中級編として読むのであればお勧めできます。
0投稿日: 2020.01.15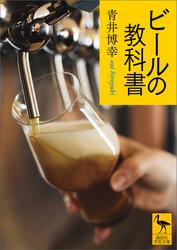
ビールの教科書
青井博幸
講談社学術文庫
雑
講談社メチエの同名書の文庫版。 ビールの製造実務に関してのノウハウは経験者だけあり、光るものがある。 それ以外はなんというか、かなり雑。ちくま文庫の『ビール世界史紀行』を始めとするビール本の受け売り、時々致命的に間違ってるという感じ。 全体としてエール、ラガーの二分論を前提としているが、Oxford Dictionary of Englishでは現代語とての"ale"を「ラガー、スタウト、ポーター以外のビール」と定義しているように、上面発酵・下面発酵の二分法をそのままビールの種類に敷衍するのは無理がある。また元はメルマガで配信していた内容を下敷きにしているとのことで、そのせいか言っていることが変わっていたりもする。プロイセンとバイエルンとフランク王国が並立していたドイツとか、そんな時空どこにも存在しねえよ。講談社学術文庫編集部、大丈夫か?メチエでもヤバいわ。でも一番のアホはこんな本をメチエと学術文庫で二回も買った俺自身。
0投稿日: 2019.12.12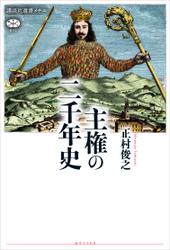
主権の二千年史
正村俊之
講談社選書メチエ
思想史よりの内容
まず本書は科研費(研究)の一環ということで、一般読者に向けて書かれていないのか、あまり読みやすくはありません。学部三年以降向けという所でしょうか。 政治学、なかでも政治思想史寄りという内容ですが、理論に理論を重ねてあまり地に足のついた議論にはなっていないという印象です。近代以降に確立され、定着した概念をあまりに所与のものとして前近代に適用しすぎている気がします。また「二千年史」という割に歴史学の成果をほとんど取り入れていないのも気になります。ローマ法、キリスト教ばかり強調し、西欧におけるゲルマン的要素を無視するのはあまり意味のある議論になるとも思えません。時代区分もルネサンス期そのままでちょっとびっくりです。
0投稿日: 2019.11.21
iciさんのレビュー
いいね!された数95
