
はじめての構造主義
橋爪大三郎
講談社現代新書
レヴィ=ストロース入門
『はじめての構造主義』と銘打つものの、八割方はレヴィ=ストロース。一割はソシュール。最後の一割でその他の構造主義者や自称ポスト構造主義者を扱う感じです。分かり易く、レヴィ=ストロースの著書の内容を解説しています。最初は遠近法だの、幾何学だのがどうして構造主義に関係するのか想像つきませんでしたが、読み終わってみれば納得。構造主義関係の文献リストも付いて便利です。
5投稿日: 2014.06.13
知の教科書 フーコー
桜井哲夫
講談社選書メチエ
フーコー入門
フーコーの著作自体というよりは、人となりに寄った伝記風入門書。フーコーの人生を概観し、彼の主著の主張と関連を明らかにしている。平易で分かり易い反面、著作の解説的には少し物足りない。同じ著者が本書以前に詳細な概説書を書いているとのことなので、そちらも合わせて読んでみるとよいかも。 正直な所を言えば、ちくま文庫でフーコー入門に失敗したクチなので、本書の様に分かり易く解説した本があるのは非常に助かりました。同じく構造主義四天王の一人を扱った橋爪大三郎『はじめての構造主義』と合わせてどうぞ。
3投稿日: 2014.06.13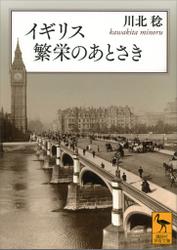
イギリス 繁栄のあとさき
川北稔
講談社学術文庫
第一人者による軽めの歴史エッセイ
日本におけるイギリス近代史研究の第一人者であった著者が20年ほど前に書いた歴史エッセイを講談社学術文庫で再版し、電子化。元々がビジネス誌に連載していたエッセイだけあってそれほど硬くはない内容。読む人によっては講談社学術文庫から電子化したにしては物足りないと感じるかもしれません。それでも20年前の学会の雰囲気を感じることができるのは面白い。本書で取り上げられている内容は、世界システム論にしろ、ジェントルマン資本主義にしろ、その後のイギリス史においては学部生のレベルでも常識となったものばかりです。逆に「抵抗勢力」とも言えるマルクス主義史学や大塚史学などは、底本が最初に出版されて数年のうちには(学術的には)見向きもされなくなってしまいます。そんな時代の変わり目の空気を残した本書、単なる歴史エッセイとしてのみならず、日本西洋史研究史の一次史料として読んでも面白いと思います。
2投稿日: 2014.06.13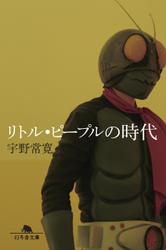
リトル・ピープルの時代
宇野常寛
幻冬舎文庫
特撮に見る社会の変化
結論の「ハッキングのように世界を変えることで良くしていくことができる」ってのは要は考え方次第、ってことでしょうか。結論は今一つですが、本論の昭和の社会情勢から見たウルトラマンから仮面ライダーへの転換は中々面白い。それ以外の内容は同じ著者の『ゼロ年代の想像力』とそれほど変わりません。両方未読でどちらか一冊を読むのであれば、こちらをお勧めします。
1投稿日: 2014.04.28
ゼロ年代の想像力
宇野常寛
ハヤカワ文庫JA
良くも悪くも「サブカル」評論
巻末の著者インタビューによると、東浩紀とその追従者を批判するために書かれた本とのことです。実際に何度も何度も入れ替わり立ち替わり、舞い戻っては東浩紀批判とが繰り返されます。また「大きな物語」「ポストモダン」などの用語が特に詳細な説明もなく、自明のものとして使われています。評論全般というよりも、東浩紀氏の著書をある程度読んでいる人を対象としているものと思われます。 が、その批判の内容はあまり公正とは言えません。東氏の主張をいわゆる「セカイ系」と関連付けて批判を展開していくのですが、東氏の著書の内容を引用し「セカイ系=きみとぼくの関係が中間要素を介することなしに直接世界の終わりに関係している」として紹介しながら、本文中では「精神主義・ひきこもり」を意味する用語として批判しています。そしてその定義のすり替えは本文ではなく、章末の注釈に小さく書いているだけです。これでは著者が批判する意味での「セカイ系」を東氏が本当に擁護しているのか明らかではありません。こうなると、所々で出て来る、出典を示さずに「東氏はこう言っている、しかしそれは間違っている」という形での批判が本当に正当なものなのか、誤読、こじつけではないか、という疑問も出て来ます。 東浩紀批判以外の本書の内容はアニメ、特撮、ゲームに留まらず、テレビドラマ、邦画などを手広く扱い、著者の言う「決断主義」(究極的には無根拠でありながらもあえて一つの立場を選択すること、だそうです)をいかに克服するかを論じています。が、この「究極的には無根拠」という点がどうにも同意できません。その人の立場や価値観によって根拠が違うという場合はもちろんありますが、それを突き詰めれば無根拠というのは違うと思います。著者の言うように、究極的には無根拠(どちらが正しいかわからない)でもあえて一つの立場を選ぶということもあることは否定しませんが、それでも常に「究極的に無根拠」と言い切ってしまうのは、思考停止であり、中二病をこじらせただけの様に思われます。 著者は同時多発テロと小泉構造改革で「引き籠もり(セカイ系)のようなことを言っていては生き残れない」(「サヴァイヴ感」だそうです)となり、決断主義主義が台頭したとしていますが、特にそれ以上の社会、国際情勢に対する説明はしていません。大きな物語、ポストモダンを口に為ながら、ソ連の失敗とか冷戦構造の崩壊とかが出てこないのは斬新といえば斬新です。社会評論には手が届かないかわりに手広く「サブカル」作品を扱った、良くも悪くも「サブカル評論」としか括りようのない本、といった所でしょうか。
0投稿日: 2014.04.28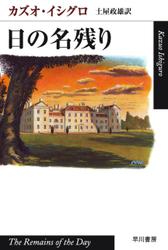
日の名残り
カズオ・イシグロ,土屋政雄
早川書房
過去と現実を受け容れることで、前向きになれる
ブッカー賞受賞作にして同名映画の原作。アメリカ人大富豪に仕える老執事スティーブンスはかつての同僚、女中頭のミス・ケントン(現ミセス・ベン)からの手紙をきっかけに休暇を貰い、主人から借りた自動車で旅に出ます。旅の途中、折に触れてミス・ケントンやかつての主人ダーリントン卿との過去に思いを馳せるのですが、その結果、物語は「現在」の1956年と「過去」である1923年(最終的には1936年も)を行ったり来たりするため、少々分かり難いかもしれません。 「日の名残り」という題名が暗示している様に作中の「現在」は、二回の世界大戦でイギリスは没落し、まさに斜陽の時代です。ダーリントン卿も既に亡く、ミス・ケントンはミセス・ベンになってしまっている。一方、過去である1923年は多少陰りは見せつつも、いまだ世界一の大国としての地位を保ち、主人は健在、ミス・ケントンも同僚と、スティーブンスにしてみれば出来ることなら戻りたいが、決して手が届くことはない失われた黄金時代といえます。「現在」のスティーブンスは折に触れ、偉大さとは何か、品格とは何かを自問し、既に失われてしまったか、あるいは失われつつある、それを守ってきた自分に職業的な誇りをを感じています。にも関わらず、彼はダーリントン卿に仕えていた過去を、自らの経歴・誇りと不可分であるその事実をしばしば隠そうとします。それは彼の弱さの表れであるとともに、現実(過去は取り返しが付かないこと、ダーリントン卿の被った不名誉、屋敷はアメリカ人の手に、etc)を正面から受入れずに、自分を誤魔化しつつ受け流していることの表れであると私には思えました。しかし、そんなスティーブンスも旅の終わりに、取り返しがつかない現実も正面から受け止め、受け容れます。そして現在の主人に前向きに仕えていくことを心に決めます。ミス・ケントンとどうなるわけでも、ダーリントン卿の名誉が回復するわけでもありませんが、それを受け容れることで非常に前向きになる、もしかすると、それがイギリスらしさ、あるいは作中の言葉を借りると「偉大さ」「品格」ということなのかもしれません。 イギリスの歴史(?)小説ということで、日本人には知らないと分かり難い点も少々あります。 時代背景として、戦間期イギリスの対独融和政策を踏まえておく必要があります。ドイツが第一次大戦で敗北し莫大な賠償金を課されたこと。フランスによる過酷な対独政策が反感を生み、ナチス躍進の素地を作ったこと。ドイツで政権を取ったヒトラーとナチスに対し、イギリスはラインラント進駐、再武装、オーストリア併合などに文句は付けつつも最終的には「これが最後」という言葉を信じて領土拡大を追認してしまったこと。このあたりでしょうか。 スティーブンスの葛藤も分かり難いかもしれませんが、身も蓋もない言い方をしてしまえば「父親の健康、職場の同僚との関係など面倒なことから仕事に逃げた男が、老境に差し掛かり、俺の人生、これでよかったのかな?と疑問に思いつつもその気持ちを認められずにいる」という状況です。 ところで映画を見た方ならお気づきでしょうが、原作と映画では現在の主人であるアメリカ人の設定が異なります。原作ではファラデー氏という特に因縁のない陽気な大富豪。映画では過去編にも登場した外交官のルーイス氏。見比べてみると面白いかもしれません。個人的な意見ですが、いくらなんでもスティーブンスが因縁のルーイス氏に仕えるとは思えないので、原作の設定に軍配を上げたい所です。
8投稿日: 2014.02.25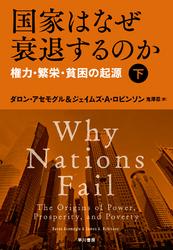
国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源(下)
ダロン・アセモグル,ジェイムズ・A・ロビンソン,鬼澤忍
単行本
上巻よりおすすめ
脱植民地化を経てもアフリカに収奪的構造が温存される理由についてのケーススタディは興味深く、一読の価値がある。上巻よりオススメ。というか、下巻からでよい。
2投稿日: 2013.11.04
帝国海軍 戦艦大全
菊池征男
学研M文庫
良い入門書
帝国海軍の戦艦は数有れど、本書では太平洋戦争に参加した金剛、比叡、榛名、霧島、伊勢、日向、長門、陸奥、大和、武蔵を扱っており、色々と丁度良いかと。各艦ごとに一章を割き、戦歴のみらなず改装内容や歴代の艦長までを網羅しています。また巻尾の付録では砲火を交えたアメリカ戦艦の概略も乗せられており、内容を理解する上での助けとなりました。 軍事史には疎く、他との比較は出来ませんが、入門書として最適な本でした。
1投稿日: 2013.10.13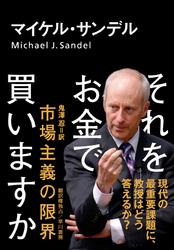
それをお金で買いますか 市場主義の限界
マイケル・サンデル,鬼澤忍
早川書房
市場至上主義は是か非か
少し(結構?)前に流行った「ハーバード白熱教室」のサンデル教授の新刊。サンデル教授の本は他に『これからの正義の話をしよう』(早川書房)と『公共哲学』(ちくま学芸文庫)を読んだが、本書はちょうどその中間、『これからの正義の話をしよう』よりは硬く、『公共哲学』よりは分かり易い。なので順番としては『これからの正義の話をしよう』の後に読むのが良いかもしれない。ただし政治哲学の入門書的な位置づけであった『これからの正義の話をしよう』とは異なり、本書では具体的な思想家の名前や「○○主義」といった言葉はほとんど出てこない。より身近なテーマ、命題を扱い、そのことの是非を肯定側、否定側双方の見方から紹介している。政治哲学の歴史に興味がないなら本書から読むのも良いだろう。 本書で取り扱われている問題のなかには、そのまま日本にも当てはめることができる問題もあるが、そうでない問題もまた多い。そうした問題の存在そのものから見えてくるのは、アメリカもまた極めて特殊な国であるということだ。アメリカでは今、何が問題となっているのか、何故問題なのか、そのことからアメリカ社会の一端を窺うことができよう。以て他山の石とすべし、である。
2投稿日: 2013.09.27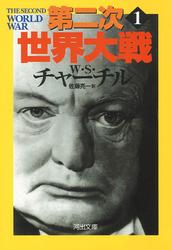
第二次世界大戦 1
W・S・チャーチル,佐藤亮一
河出文庫
歴史書としても読み物としてもおすすめ
チャーチル自身が第二次大戦を振り返って書かれた回顧録の抄訳。内容に関しては今更言うまでもないだろう。 原爆投下の事前協議など、つい最近機密指定を解かれた内容も、既に包み隠すことなく語られており、第一級の史料と呼ぶに相応しい。また冷戦中に書かれたことを反映してか、ソ連とスターリンに対する視線は、当時の「敵国」である日本に対するそれよりも厳しいものになっているのが興味深い。 いくらか誤訳や一般的な用語とは違う訳語なども目に付く。また全訳ではないので原著との対応が取りにくく、気になった一節を英語版で確認するのに難儀した。それでも全文を英語で読む苦労とは比べものにならない。地図や図版などに付された説明の文字が小さく拡大が効かないなど、電子書籍のメリットを完全には活かし切れておらず改善して欲しい点もあるが、本の内容を大きく損なうものではない。読み物としても面白いので、是非読んで見て頂きたい。
0投稿日: 2013.09.27
iciさんのレビュー
いいね!された数95
