
21世紀の資本
トマ・ピケティ,山形浩生,守岡桜,森本正史
みすず書房
21世紀の実証主義的経済史
一時期評判を呼んだ経済書、というか経済史書。著者が自ら本書の序文で書いているように、フランス発祥のアナール派歴史学の影響が大きく見られ、一般的な経済学の本とは趣きが異なっています。 日本での出版直後はメディアでも引っ張りだこでしたが、「経済成長がないと貧富の差が広がる」、「金持ってる老人に課税すべき」といった本書の内容が、メディア側の言って欲しかった言葉とは正反対だったのか、いつの間にやら露出がぱたりとなくなってしまいました。とはいえ内容的にはごくまともで、常識的です。長大な内容からすると意外といっても良いくらいです。 そもそも本書のキモである「経済成長が少ないと経済格差が広がる」という主張は景気変動を扱った本ではよく見られるものです。有名どころだけでも80年代に一世を風靡したウォーラーステイン、最近では「ハーバード白熱教室」のマイケル・サンデルなどの著書でも周知の事実として扱われています。では本書の意義はどこにあるかと言えば、従来から知られていたこの「事実」を、統計ベースで長期間にわたって実証した所にあるといえます。文体は柔らかく読みやすいとはいえ、この実証パートがかなり長いのでそれなりに本を読み慣れている人でないとつらいかもしれません。 本書では各国のなかでの経済格差を詳細に取り扱う反面、国際的、あるいは地域間の経済格差はあまり重視されていません。著者によればデータから見るとそれほど「搾取」は大きくないとのことですが、外部化された環境コストやそもそも値段が安すぎるといった「アンフェア」なトレードは統計に出てきにくい気がします。そのあたりの統計には出にくい要素を意識しながら読むと一層よろしいかと思います。
0投稿日: 2018.12.30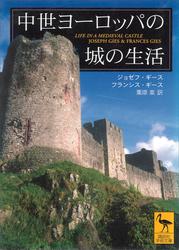
中世ヨーロッパの城の生活
ギース,J.,ギース,F.,栗原泉
講談社学術文庫
堅めの入門書
ギース夫妻による城、農村、都市という「中世の生活」三部作のひとつ。三部作といっても順番はあまり関係ない。むしろ内容的には三部作外の『中世ヨーロッパの騎士』(夫妻共著ではなくフランシス・ギースによる単著)と重なる所が大きい。 生活以外にも城の構造の変化や封建制の基本的な所に関しても書かれている。中世社会史、生活史は文献が少ないこともあり、学術的なアプローチとしてはほぼ鉄板の入門書。ただ、それなりに堅い内容なので、大学生以上向け。 「中世ヨーロッパ」とはいうものの、主に西暦1000年以後のイングランド(とイングランド支配下にあったフランスの一部)。他の三部作に限らず、同じ著者の他の本もこれは同様。(イギリス系の西洋中世史は割とそういう傾向) この時期のイングランドは王権が他国と比べると例外的に強い(ノルマン・コンクエストのせい)反面、領主権は比較的弱く(農奴の身体支配まで及ばないタイプ)、また税による軍役免除がいちはやく導入されるなど、中世ヨーロッパの典型としてはあまり適切ではないことに注意が必要(もし典型的な中世ヨーロッパなどというものがあるなら、という話だが)。
0投稿日: 2018.12.14
この世界が消えたあとの 科学文明のつくりかた
ルイス・ダートネル,東郷えりか
河出文庫
名前だけは習った技術、発明などの解説書
ハードカバーの同名書の文庫版。 活版印刷、輪作(あるいは「ノーフォーク農法」)、高炉(製鉄)、ハーバー・ボッシュ法(化学肥料、人口硝石)など、世界史で一度は習う重要事項、されど重要さに反して数行程度しか説明されない大発見を分かり易く説明していきます。簡単な化学が出てきますが、文系でもまったく問題ない程度です。 原題は"Knowledge"、本書の内容によると「文明が崩壊した未来に伝えるべき知識」という感じになります。「この世界が消えたあと(略)」というのは本来はサブタイトルになります。そのせいか事前にタイトルから期待した内容とはちょっと異なりました。How toというか、DIYというか、「鉄鉱石からトースターを作ってみた」的な内容を予期していたのですが、実作ではなく基本的な原理を解説していくという内容でした。本書だけを手掛かりに人口肥料プラントや高炉を作るのは難しいかもしれません。それでも個人的には長年の疑問が幾つか解決したので満足です。活版印刷で重版をかける時はどうするのか?磁器を焼くのに高温が必要なのは何故か?天体観測で経度を知るには?……そんな教科書には書かれていないのに、単純すぎて専門書では無視される疑問をお持ちの方にお勧めです。 ……本書が役に立つ未来の来ないことを祈りつつ。
0投稿日: 2018.10.24
仕事としての学問 仕事としての政治
マックス・ウェーバー,野口雅弘
講談社学術文庫
はじめてのヴェーバーに最適
本書は1919年にミュンヘンで行われた講演内容を本にまとめたものです。もともとが講演だけあってヴェーバーにしては短く、読みやすいという特徴があります。 日本では『職業としての学問』、『職業としての政治』として岩波文庫版が読み継がれてきましたが、この度、新訳ついでに一冊にまとまっての登場です。 1936年初版の岩波文庫版と比べて当然ながら翻訳が現代的で読みやすくなっています。 政治や学問を仕事にしていなくても、そういった「専門家」が何かを言っているのを目にした時、耳にした時、その内容の是非を考える時のために読んでおきたい本です。
0投稿日: 2018.10.16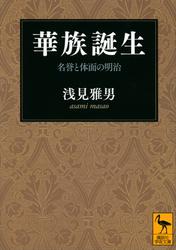
華族誕生 名誉と体面の明治
浅見雅男
講談社学術文庫
華族制度設立のドタバタ
書簡や日記から、江戸時代の課税石高と家格から爵位を決める非公開の内規作成の過程、実際の授爵、貰った爵位に不満のある華族による昇爵運動およびそれが一段落して華族制度の設立が一段落するまでを扱っています。日清・日露戦争の勲功により新たに叙爵された軍人華族は範囲外となります。一般向けというにはやや堅いものの、学術書というほどではなく、専門外の読者でも大丈夫です。華麗な華族を求める方には申し訳ないのですが、本書ではごく一部の例外を除いて華族のどうしようもなさばかりが目立ちます。そのあたりを踏まえた上でご覧下さい。
0投稿日: 2018.05.11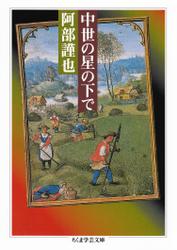
中世の星の下で
阿部謹也
ちくま学芸文庫
(だいたい)一般向け歴史エッセイ集
日本における西洋中世社会史の第一人者であった阿部謹也による歴史エッセイ集。 新聞から学術誌まで様々な媒体に掲載されたエッセイを集めているので、一般向けに分かり易く書かれたものもあれば、数は少ないものの、ある程度の専門知識を前提としているものもあります。前半の、星をテーマにした一般向けの連作だけでも読む価値はあるかと。 個人的には所々ににじみ出るドイツ史学贔屓と第二世代以降のフランス系アナール学派への隔意が興味深かったです。
0投稿日: 2018.04.13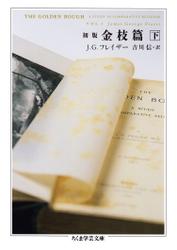
初版 金枝篇 下
J.G.フレイザー,吉川信
ちくま学芸文庫
下巻から読もう
上巻のレビューにも書いたのですが、まず下巻の結論部と解説を読みましょう。それから上巻に戻って読み進めるのがお勧めです。 収録された各地の習慣、習俗などの具体例が本編みたいな所があるので、下巻だけ読むのはお勧めできません。ちゃんと上巻も読むのがおすすめです。「鯉のぼり?メイポールの一種だよ」みたいななんちゃって知識を振り回すのもよし、強い聖性が穢れと同様に扱われるという点について真摯に考えるもよし。単純に前近代についての本を読むときに理解の深さが変わって来たりもします。長い本ですが頑張って。
0投稿日: 2018.04.10
初版 金枝篇 上
J.G.フレイザー,吉川信
ちくま学芸文庫
教養として読んでおきたい古典
世界各地の神話、伝説、伝承を集めて書かれた「本から出来た本」。根本的なテーマは「ネミ(古代イタリアの部族)で祭司が代替わりする際に、黄金の枝を折り取って前任の祭司を殺す必要があったのは何故か」というもので、ほとんどの読者にとってあまり興味のわかないものかもしれません。一方でこの問題提起に添って列挙される各地の伝承や習俗に見られる共通点は、その差異も含めて非常に興味深いものがあります。なかには日本についての言及もあり(ちょっとアヤしい所もあるけど)、西洋人から見た東洋の神秘を垣間見ることが出来ます。でもまあ、最初に結論と解説に目を通してから読むのがお勧めでしょうか。 ジャンルとしては神話学のジョゼフ・キャンベル(『千の顔を持つ英雄』など)と重なるのですが、20世紀のキャンベルが集合的無意識を前提としていたりして神秘主義に寄っているのに対して、19世紀に書かれた本書の方が合理主義的な内容になっています。なので非常に長いことを除けば人を選ばずに読んで貰えると思います。 また本書に付された「初版」の文字ですが、『金枝篇』には初版、二版、三版(+補遺)、簡約版があります。基本的には版が増えるにつれて実例と脚注が増えていくことになります。初版でも十分長いのですが、三版に補遺が付くと、それはもう、凄いことになっていたそうです。これではイカンと思った著者が脚注を削除し、実例も大幅に減らしたものが簡約版になります。岩波版はこの簡約版を底本にしているそうです。分量としては初版と簡約版は同じくらいということなので、どちらを選んでもそれほど違いはないかもしれませんが、翻訳が新しい分、この筑摩版の方が良いかと思います。
0投稿日: 2018.04.10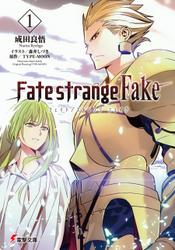
Fate/strange Fake(1)
成田良悟,森井しづき,TYPE-MOON
電撃文庫
良く訓練された型月信者向けIF
『バッカーノ!』、『デュラララ!!』等、群像劇と話がなかなか進まないことで定評のある成田良悟によるFateのifストーリーです。 本作品は完全に別の世界線である旨が明言されています。 基本的にFateに限らず他のType Moon関連作品を履修済の読者向けとなっており、特に『ロード・エルメロイ二世の事件簿』、『Fate/Grand Order』は必修となります。多分、『Fate/Prototype』も。未履修の方は先にそちらの方を済ませてからの方が良いでしょう。
0投稿日: 2018.02.16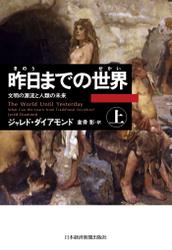
昨日までの世界(上)―文明の源流と人類の未来
ジャレド・ダイアモンド,倉骨彰
日本経済新聞出版
シリーズ完結編かつ入門編
『銃・病原菌・鉄』、『文明崩壊』に続く三部作?完結編です。 ニューギニアの回想から始まった『銃・病原菌・鉄』のように、本作もまた著者の原点であるニューギニアから始まります。フィールドワークの体験談が多く、読み物としてもなかなか面白くなっていますが、後半の、宗教の機能と発達への文化人類学的アプローチやニューギニアで急増する成人病に対する生理学的な説明などに広範な専門知識を持つドクター・ダイアモンドらしい非凡さが顕れています。 全体的な構造としては、1931年のニューギニア人「発見」当時と現在を対比させ、「昨日までの世界」と「今日」を比較していますが、これは前著『文明崩壊』において「過去の社会」、「現代の社会」として提示されていた(それぞれ前掲書第二部、第三部のタイトルです)見方をそのまま引き継いだものとなります。両方を取り上げた前作とは異なり、本作では「過去の社会」であるところの「昨日までの世界」を主に取り上げています。『銃・病原菌・鉄』においても「部族社会」として取り上げられていたあたり(前掲書下巻14章)ともリンクする内容であり、著者が度々取り上げてきたメインテーマの一つだということが分かります。 とはいえ、前作、前々作とくらべるとかなり取っつき易い内容となっており、本書から入ってもまったく問題はありません。シリーズ未読・既読を問わずお勧めできます。 一点、ご注意を。本書はハードカバー版を底本としているのですが、物理書籍版では文庫本が既に出ているため、電子版も遠からず文庫版ベースのものに切り替わるのではないかと思います。念のため。
0投稿日: 2017.12.28
iciさんのレビュー
いいね!された数95
