![[新版] 馬車が買いたい!](https://ebookstore.sony.jp/photo/BT00002302/BT000023027100100101_LARGE.jpg)
[新版] 馬車が買いたい!
鹿島茂
白水社
フランス文学の読み解き方
「註だけの本が書いてみたかった」と著者があとがきで書いているように、フランス文学(書院じゃない方)で描かれ、当時の読者には常識として説明するまでもないことであったものの、違う時代、国に生きる我々には分からない習慣や制度などの隠された含意を、著者が「我らが主人公」と呼ぶ、立身出世の大望を抱いて地方からパリに状況してきた若者というフランス文学の類型的主人公の生活を通して説明しています。『馬車が買いたい!』というタイトルはそんな主人公たちの野望を一言で言い表したものです。一昔前の日本なら「庭付き一戸建てが欲しい」、今の若者たちなら「起業家になりたい」とかでしょうか。 上京するための交通手段から始まって、衣食住、娯楽、そして超高級アイテムとしての馬車(タイトルに反して馬車の専門書という訳ではありません)。半分の章が雑誌連載、もう半分が描き下ろしということで、専門家ではない一般読者向けとなっています。しかし本書をもっともおすすめできるのはフランス文学の読者に対してでしょう。著者が企図したようにフランス文学の解説書、あるいは副読本的な読み方がまず第一になるかと思います。しかしそれだけではなく、フランス文学を題材にした社会史としても読むことができます。(現在では割とポピュラーなアプローチですが、本書の初版が出版されたころはまだ新しい手法であったはずです。)ですので、フランス近代史、特にパリの歴史に興味のある方にもおすすめです。 逆に仏文系でも、近代史系にも興味のない方にはあまり面白くないかもしれません。
1投稿日: 2015.06.28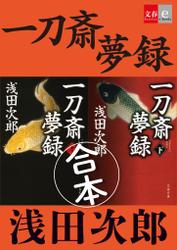
合本 一刀斎夢録【文春e-Books】
浅田次郎
文春e-Books
三部作完結編
浅田次郎版「新撰組」三部作完結編です。語り手が次々に変わった前二作と異なり、今作では斎藤一がひたすら語り手を務めます。京都から戊辰戦争、そして警視庁抜刀隊の一員として戦った西南戦争までです。そういう意味では、厳密には「新撰組」モノとは言えないかもしれません。 前二作をお読みになった方ならお分かりかと思いますが、こんなにヒドい斎藤一は他の新撰組作品では見たことありません。にもかかわらず、(あるいは、だからこそ)他のどの斎藤一よりも人間的で、不思議なほど魅力的な人物となっています。……まあ趣味の違いはあるかもしれませんので、前二作を読んで浅田次郎版斎藤一がどうしても肌に合わないという方は回避した方がいいかもしれません。そうでない方は是非とも手に取ってご覧になってみてください。
2投稿日: 2015.05.30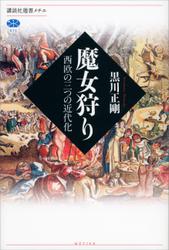
魔女狩り 西欧の三つの近代化
黒川正剛
講談社選書メチエ
かなり専門的
魔女狩りといえば、密告・拷問・裁判(という名の処刑)という流れる様な三段活用がすぐに思い浮かびますが、「その中にもいろいろな論争があってヨーロッパ近代につながる萌芽があったんだよ」、というのがおおまかな本書の内容になります。 著者の博士論文が元ということで、かなり専門的で堅い内容です。魔女、魔女狩りといったオカルティックでサブカルな事柄への興味で手に取るには向きません。むしろ魔女狩りや魔女裁判を通じて当時の情勢や心性(マンタリテ)を探るというのが本書のメインテーマとなります。素人はもとより、筋金入りの歴史ファンにもおすすめはできません。本格的に研究したい、勉強したいという人向けです。
0投稿日: 2015.05.30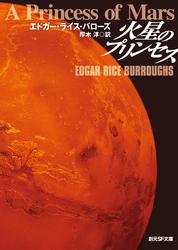
火星のプリンセス
エドガー・ライス・バローズ,厚木淳
創元SF文庫
裏返しのオリエンタリズムと物質文明批判
「異世界で主人公が無双する話」といえば昨今よくある異世界召喚モノみたいですが、本作がそこいら作品と違うのは主人公が遅れた文明から来た「野蛮人」として描かれていることです。主人公はまず火星と地球の重力の違いから来る身体能力で活躍し、次いでその勇気、信義、慈悲といった火星では失われつつある精神性で信頼を得ていきます。いわば主人公はオリエンタリズムの一類型である「高貴なる野蛮人」として描かれているのです。この旧南軍騎兵大尉(白人で教養もある一方で負け組)である主人公が野蛮人として描かれるというのが本作のミソとなります。 南北戦争が単に「奴隷解放のための正義の戦い」ではなく、北部産業資本主義の利害も反映していたことはよく知られていますが、物語開始時点で「旧南軍騎兵大尉」である主人公は物質文明に対する敗北者という属性を負っています。その一方で白人としては、「インディアン」に対して物質文明の側に立つのという重層的な構造も見て取れます。しかし火星においては、「赤色人」(インディアンの暗喩とみるべきでしょう)が地球よりはるかに進んだ文明を持っており、地球から来た主人公は野蛮人となってしまいます。その上で、火星では失われた精神性や美徳(それと腕力)によって信頼と地位を得ていく、という言わば二重の逆転が見て取れます。そこからある種のメッセージや文明批判を読み取ることも可能でしょう。勿論、良質の王道ヒロイック・ファンタジーとして素直に楽しむこともできます。 このあたり、やはり名作として読み継がれる作品は違うな、という感じです。 ……まあ、こんな読み方もありますよ、ということで。
1投稿日: 2015.05.20
増補改訂版 日本史に出てくる官職と位階のことがわかる本
『歴史読本』編集部
中経出版
分かることは分かるが……
官職、位階以外にも朝廷、幕府の職制や、旧帝国陸海軍の階級、仏教関係の称号(?)なども扱っています。 時代やテーマごとに、ライター、小説家、郷土史家、大学教授など幅広い職業の方が書かれており、内容的にも様々です。史料をもとに手堅く解説する方があるかと思えば、一部には脱線したり、行間を膨らませ見てきたかの様に物語る方もいたりします。また内容が重複することもあり、体系的に網羅し解説するというよりも、雑多な寄せ集めという感が否めません。もし具体的に調べたい時代や内容が決まっているのなら、本書ではなくその道の専門書を読まれた方が良いと思います。 逆に漠然と全体的にそれなりに調べたいということであれば本書で良いかと。
0投稿日: 2015.05.13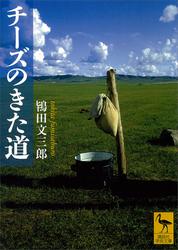
チーズのきた道
鴇田文三郎
講談社学術文庫
いかんせん古い
電子版底本の講談社学術文庫版は2010年の出版ですが、大本の河出書房版は1977年とのことで、本書のそこかしこに時代を感じます。チーズといえば雪印のプロセスチーズだった初版当時と比べ、現在ではちょっと気の利いたスーパーに行けば10や20は簡単に超える種類のチーズが手に入るわけで、文字通り隔世の感があります。粉チーズのパルメザンと「チーズの王様」パルミジャーノ・レッジャーノを一括りで扱いながらチーズ本を名乗るなど現在ではとても許されないでしょう。 チーズの歴史を扱った本として見ても、根拠のない著者独自の説と文明論が前に出すぎていて、現在の水準からするとそのまま採用することはできないという印象です。まだ日本人がチーズに馴染みのなかった当時だからこそ許された本なのかな、と感じます。でも、「程度の低い文化」とか書いてしまうのは当時としてもどうかと思います。 あえて褒めるところを探すとすれば、著者の専門分野である発酵の科学的側面(現在の水準から見てどうかまでは判断できません)とアジアにおけるチーズ様食品の情報でしょうか。ただ著者の専門を反映してか、酸によるチーズ作りや熟成させないフレッシュチーズ、牛以外の動物のチーズなどを軽視している印象があります。参考程度としたほうがよいかもしれません。 チーズの歴史を扱った本としては電子化されていないものの、ポール・キンステッドの『チーズと文明』が良い本でした。電子化が待たれるところです。
0投稿日: 2015.04.08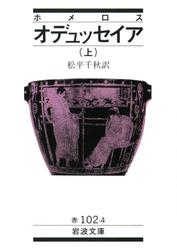
ホメロス オデュッセイア 上
松平千秋
岩波文庫
イリアスよりホメロス入門におすすめ
もし「イリアス」と「オデュッセイア」、どちらかを読もうと迷っているとしたら、こちらをお勧めします。 話としては「イリアス」が先ですが、おそらく諸々の配慮から色々な人物を活躍させなければならなかった「イリアス」と違って、「オデュッセイア」は主役が「堅忍不抜」のオデュッセウスで筋が明確になっており、非常に分かりやすいです。「イリアス」で延々臍を曲げていたアキレウス同様、オデュッセウスも長々とヒモ暮らしをエンジョイしていたようなのですが、幸いなことに、心を入れ替えて家路を目指す所から物語は始まります。さらに主に人間相手(たまに神様が混ざってることもある)の戦争を描いた「イリアス」とは異なり、一つ目の巨人サイクロプス(キュプロクス)や歌声で旅人を惑わす海の怪鳥セイレーンなど、有名どころの怪物も登場し(むしろ原典です)、古代ギリシア感もばっちりです。 以上のことから考えて、ホメロスを読み始めるのならば、「イリアス」より「オデュッセイア」から読まれることをお勧めします。本書がどうにも合わないという場合は、おそらく「イリアス」も同様かと思います。
1投稿日: 2015.04.03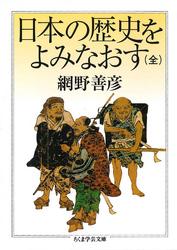
日本の歴史をよみなおす(全)
網野善彦
ちくま学芸文庫
網野史学入門編
土地を基盤とした武士による画一的な支配ではなく、多様性に満ちた日本中世を描き出しています。語り口は専門外の人にもわかりやすく、まさに網野史学入門という感じです。なお「(全)」というのは、「日本の歴史をよみなおす」と「続・日本の歴史をよみなおす」、二冊分を収録ということです。
8投稿日: 2015.04.02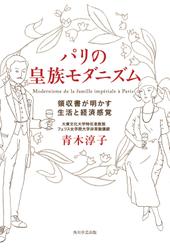
パリの皇族モダニズム 領収書が明かす生活と経済感覚
青木淳子
角川学芸出版単行本
お忍びパリ滞在記
1922年から1925年までパリに滞在した朝香宮夫妻、その生活ぶりを残された領収書から読み解いています。タイトルからするとかなり難しそうですが、実際にはそんなことはなく、研究者ではなく一般の読者向けに書かれた本です。 朝香宮夫妻といえば現在では東京都庭園美術館となっているアール・デコ建築の傑作、旧朝香宮邸で有名ですが、その「モダンさ」はどこから来たのか、というのが本書のタイトルの由来となっています。 領収書とはいっても現在の無味乾燥したものではなく、大判で美々しいロゴが入った見栄えのするものです。海外で買い物した際に免税申告用に出してもらえる明細が感じとしては近いでしょうか。あれをもう一段か二段、「おフランス」な感じにしたものを想像して貰えればいいと思います。取り上げられた領収書のほとんどは一ページまるまる使った大きな写真で掲載されていますので、何が書かれているか、実際に読み取ることができます。流麗な筆記体あり、タイプライターあり、店ごとに特徴があり見ていて飽きません。その他に必要に応じ、電報や地図、現地の写真なども掲載してあり、当時の様子を想像しやすくなっています。 ところで、朝香宮夫妻はお忍びで滞在ということになっていたらしく、正式な外交日程以外では皇族(朝香宮妃は明治天皇の皇女、つまり朝香宮は当時の大正天皇の義弟)としての身分を隠し、「朝伯爵夫妻」を名乗っており、領収書にもその名前が記載されています。ちょっと歴史ロマン溢れすぎじゃないかと思います。
2投稿日: 2015.04.02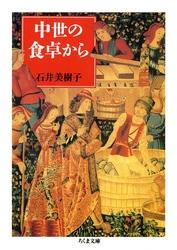
中世の食卓から
石井美樹子
ちくま文庫
気軽に読める西洋中世の食と文化のエッセイ
元が雑誌連載ということで表紙から受ける印象より気軽な内容です。「中世の食卓から」というタイトルですが、食卓に上る料理を超えて幅広く食、食糧に関する事柄を取り扱っています。反面、個々の料理の詳細やレシピ的なものはあまりなく、そういったものを求める向きには少し物足りないかもしれませんが、我々にあまり馴染みのない食文化や慣習も分かりやすく説明してくれていますので、中世ヨーロッパの生活に(あるいは現代のヨーロッパの生活にも)興味のある方はお気軽に手にとって見てはいかがでしょうか。
5投稿日: 2015.03.27
iciさんのレビュー
いいね!された数95
