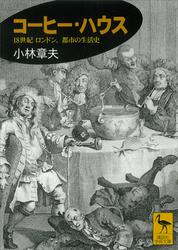
コーヒー・ハウス 18世紀ロンドン、都市の生活史
小林章夫
講談社学術文庫
文学、文芸史が主題かも
ブリテンといえば紅茶の国という印象はあるが、そうなったのは19世紀以降にすぎない。本書では「紅茶の国」になる前の17、18世紀に興隆したコーヒーハウスが扱われている。 第1、2章でコーヒーハウスの勃興と流行店の入れ替わりを描き、第3章でコーヒーハウスを舞台とした文人、才子らの言論空間の変化を扱っている。あくまで主題はコーヒーではなく、コーヒーハウスと文学、文芸となっている。どちらかといえば著者の書きたかったのは第3章という印象。また最後の方でコーヒーハウスの衰退についても説明はしているものの、要因をいくつか挙げているだけで駆け足という印象はぬぐえない。コーヒーハウスの衰退については詳しく知るためには、紅茶なり、パブなり、別のテーマの文献を読む必要があろう。
0投稿日: 2016.11.25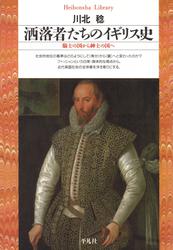
洒落者たちのイギリス史
川北稔
平凡社ライブラリー
ファッションと贅沢禁止令と社会の変化
歴史上、あちこちの国や地域で度々出されてきた「贅沢禁止令」。近世イギリスもまた例外ではなく、たびたび議会に提出されては否決されたり可決に至ったりしています。本書はその贅沢禁止令の可否から近世イギリス社会の変化を読み解いていきます。 「近世イギリスの贅沢禁止令」というと、我々とは縁遠いテーマの様に思われますが、背景にある考えを理解すると、決して我々とも無縁ではないということが分かります。新入社員が安物のスーツから始めて、少しずつ良いものにしていく、それでいて上司より高いスーツや腕時計は遠慮する、そんな有形無形の圧力も、根底にあるのは贅沢禁止令と同じ「既存秩序の維持」という考えです。社会が変動し、既存の身分秩序が揺らぐとき、地位の表象としてのファッションにどのような影響と圧力があるのか、それは現代の我々にとっても無関係ではありえません。その点で本書は現在においても読む価値のある本だと言えます。 元々、著者の初期の名著と名高い『工業化の歴史的前提』と一連のものとして構想されていたとのことですが、一般向けに再構成され、特に歴史が専門でなくとも問題はないでしょう。
1投稿日: 2016.09.16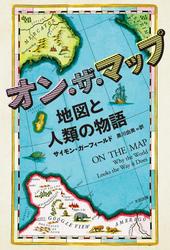
オン・ザ・マップ 地図と人類の物語
サイモン・ガーフィールド,黒川由美
太田出版
地図にまつわるエピソード
歴史上、大きな役割を果たした地図の製作秘話や、もう出来上がった地図を巡るあれこれなど、地図を軸に様々なエピソードが紹介されています。基本的には単発のエピソードですが、話を追うにつれ地図に対する意識の変化も見えてきます。 時々ちょっと誤訳くさい所があるので、後の版では変わっているかもしれません。
0投稿日: 2016.09.16
知られざる鉄の科学 人類とともに時代を創った鉄のすべてを解き明かす
齋藤勝裕
SBクリエイティブ
わかりやすい
高校の化学くらいの内容から高度な内容まで分かり易く書かれている。一方で、歴史的な内容に関しては若干適当、というか間違っている所もある。 参考文献が著者のものだけというのはどうなんだろう……
0投稿日: 2016.09.16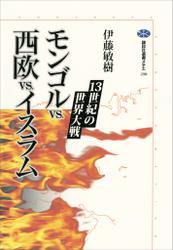
モンゴルvs.西欧vs.イスラム 13世紀の世界大戦
伊藤敏樹
講談社選書メチエ
世界大戦は言い過ぎ
キリスト教対イスラム、イスラム対モンゴル、モンゴル対ヨーロッパといった単純な二項対立を否定し、三すくみの上にさらに各勢力内部での対立まで描いているのが面白い。プロテスタントはまだないが、カトリックとオーソドックス、スンニ派とシーア派の分裂が当時から存在し、各勢力が一枚岩ではありえなかった点は現在まで続く禍根の深さを物語っている。 全体としておすすめではあるが、著者はもともと文学が専門の方のようで、用語の選択や遣い方が歴史学における一般的なそれとは時々異なっていたり、また所々に、「○○こそ本来の目的ではなかったか」のような、あまり実証的、あるいは学術的ではない記述がみられ、人によっては読んでいて違和感を持つかもしれない。
1投稿日: 2016.09.16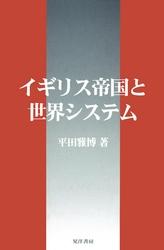
イギリス帝国と世界システム
平田雅博
晃洋書房
イギリス帝国論の入門に最適(ただし学部生以上向け)
ホブスン=レーニン的な古典的帝国主義論から、ギャラハー=ロビンソンの自由貿易帝国主義、ケイン=ホプキンスのジェントルマン資本主義までここ100年ほどのイギリス帝国論の変遷を論じつつ、ウォーラーステインの世界システム論的見地や帝国意識、文化論からもアプローチしている、非常にオーソドックスかつ包括的な論文集です。イギリス帝国史研究の入門書として読むこともできます。帝国史に限らず、イギリス近代史を専攻している学生なら是非読むべきと言えます。ただ普段から専門書を読みなれていない人がいきなり手に取ると難しいかもしれません。
0投稿日: 2016.07.21
ガリア戦記
カエサル,近山金次
岩波文庫
岩波文庫にこだわる人向け
カエサルの代表作。ローマ史だけでなく、西洋古代史を見る上で避けて通れない名著……なのですが、いかんせんいささか翻訳が古い。読みにくいというほどではないものの、時々漢字づかいなどが慣れてない人にストレスとなるかもしれません。またカエサルによって著されていない八年目と九年目が省かれて七年目で終わってしまっています。文学的に見ればカエサルの著作という点を重視するのは正しいのでしょうが、史料として考えるとポンペイウスとの決戦を描いた『内乱記』との間に二年間の空白を生じさせてしまっており、不完全と言わざるを得ません。 岩波書店からは電子化されていないものの、新訳が発行されていますし、電子化されたものであれば、講談社学術文庫版や平凡社ライブラリー版があります。そう考えると岩波文庫にこだわる理由がないのであれば、他の版を読まれるのが良いかと思います。
1投稿日: 2016.06.24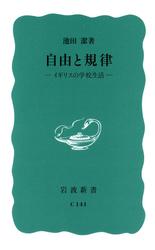
自由と規律-イギリスの学校生活
池田潔
岩波新書
古き良きイギリス・パブリックスクールの回顧録
往時のパブリックスクール経験者の貴重な体験談です。パブリックスクールの研究書、論文などであれば割と見つかるのですが、実際にどんな生活であったのかといったような話は日本語文献では中々見つけることができません。その点で本書は非常に貴重な一冊と言えます。 一方で書籍の出版が1949年ということからも察せられるように、色々な点で古さが目についてしまいます。特にイギリスに対する、ある種の理想化ともいえるような評価は、冷戦以降の歴史を知る我々のそれと大きく異なるかもしれません。いずれにせよ、本書がイギリスのパブリックスクールに関する貴重な史料であることに変わりはありません。イギリスに特有のパブリックスクールにおける生活に興味のある方は是非手に取ってみて下さい。
0投稿日: 2016.06.01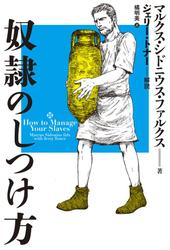
奴隷のしつけ方
ジェリー・トナー,マルクス・シドニウス・ファルクス,橘明美
太田出版
出典説明付ローマ社会と奴隷制の入門書
架空(?)のローマ人マルクス氏が、各章のテーマごとに、様々な挿話とともに奴隷にまつわるあれこれを紹介し、そこから奴隷はいかに扱うべきかを述べ、その後に著者の「解説」が入るという変則的な著述形式になります。「奴隷制度は許されない。だから批判以外の文章は存在すべきでない」という向き(いないとは限らない)からの攻撃を避けるための苦肉の策かもしれません。どちらのパートも読者に語りかけるような文体で書かれており、専門外の人でも読みやすくなっています。 書籍紹介には「人を使う技術」だの「立派な主人になるためのヒント」だのビジネス書の様な言葉もありますが、前提が違い過ぎてそちらを求める方にはあまり役には立たないかと思われます。「最初は甘やかして食事を多めに与えても良いが、段々減らして必要最低限にせよ」とか、「なるべく自由行動させるな」とか、「褒美(インセンティヴ)用奴隷ワイン(酢と塩水で薄めたワイン)の作り方」とか、どちらかといえば役に立てちゃいけないノウハウが身に付くかもしれません。 ありがたいことに、各エピソードの出典が参考文献一覧や註ではなく、解説パートでしっかりと説明されています。これは『プリニウス書簡集』、あれはプルタルコス、といったように。岩波文庫か講談社学術文庫に入っているような有名どころも多く、ある意味、「研究入門」的にも使うことができます。 ざっくりと「奴隷制ってどんなだろう?」という疑問をお持ちの方や、ローマと奴隷制について割と真面目に調べたいがどこから手を付ければよいか分からないという方などにおススメです。
1投稿日: 2016.04.29
贈与論
マルセル・モース,吉田禎吾,江川純一
ちくま学芸文庫
贈り物にまつわる義務と慣習
構造主義の流れでしばしば名前が出てくるモースの『贈与論』です。ただ基本的な趣旨は「書籍説明」で書かれている通りで、特に付け加えることはありません。プリミティヴな社会の風習を集め、「書籍説明」に書かれている内容を論証していきます。そういう意味ではあまり優先度の高い本ではないかもしれません。(個人的な見解です。もう一度読み直せばまた違う発見があるかもしれません。) では本書の魅力がどこにあるかと言えば、個人的にはモースが蒐集した「未開社会」の風習のレポートそのものにあると思います。族長は宴会を開かねばならない。誘われたものは出席しなければないない。贈り物にはお返しをしなければならない。そこに「未開社会」における富の再分配を見出すこともできますし、あるいはかつての日本社会との類似を見て取ることも可能かもしれません。お中元・お歳暮の意味、内祝いの必要性、上司と部下の割り勘の是非、そんなことを考えさせられる一冊です。……多分、著者の意図とは著しくかけ離れているとは思いますが。
1投稿日: 2016.04.20
iciさんのレビュー
いいね!された数95
