
古代技術
ヘルマン・ディールス,平田寛
ちくま学芸文庫
100年前の講義録
原著は1924年出版の"ANTIKE TECHNIK"。1912年、1913年、1917年の講演を出版したものです。翻訳はまず最初に1943年。次いで1970年に改訳。この1970年版を文庫化(および電子化)したものが本書となります。つまり50年前に出版された、100年前の講演についての本です。古典として読みましょう。ただし文献ベースなので、それほど古さは感じません。
0投稿日: 2024.08.02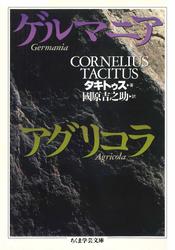
ゲルマニア アグリコラ
タキトゥス,國原吉之助
ちくま学芸文庫
岩波版より読みやすい
タキトゥスの代表作。中級者以上向けですが、ゲルマン人の習慣、社会状態など、よく引用されるあたりは初学者でも面白いかも。岩波文庫版より訳が新しく、おすすめです。アグリコラも付いてくるし。ただ、あちこち付箋を貼って調べ物の度に読み返すたぐいの本なので、物理書籍の方が便利かもしれません。
0投稿日: 2024.05.16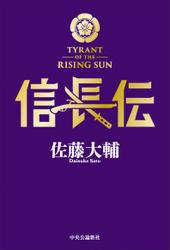
信長伝
佐藤大輔
中央公論新社
信長が生存した世界で書かれた作品
一見すると「織田信長が本能寺で死ななかったら」という、よくある架空戦記に見えますが、読んでいくと大サトーらしい仕掛けに気づかされます。ネタバレになってしまいますが、本書は「織田信長が生き延びた世界線で書かれた歴史小説」として書かれています。 歴史小説では時々「後世の視点からの記述」が挿入されることがありますが、その視点が本作では信長生存IF世界線のものになります。鎖国をせずに西欧諸国と競い合った先にある架空の「現在」から分岐点としての本能寺以降の信長を描く、言うなれば「偽史の中の架空戦記」という大サトーのエッセンスが凝縮されたような作品といえます。惜しむらくは、例によって未完ということでしょうか。 原題は版元が変わるたびに何度も変わっているようで、『逆転・信長軍記』、『異聞戦国記 覇王信長伝』、『信長征海伝』、『信長新記』と来て、最終的に『信長伝』となった模様。 一緒に収録されている短編「葉桜」は時代小説繋がりで収録されているだけで、『信長伝』部分とは特に関係はありません。
0投稿日: 2024.05.12
史的システムとしての資本主義
ウォーラーステイン,川北稔
岩波文庫
ウォーラーステイン日本語版で唯一の電子版(たぶん)
ウォーラーステインの著作群はメインストーリーである『近代世界システム』1~4巻を中心に、それを取り巻く外伝的な単行本や論文集から構成されています。本書は第2巻と第3巻の間に位置しており、ここで提起された「反システム運動としてのナショナリズム、労働運動」という概念はメインストーリーである第3巻にも取り入れられています。その点では「外伝」の中では優先度の高い本となっています。ただ扱う範囲がピンポイントであることと、ヴァージョンでいったらVer. 2.5か2.9くらい(最終Verは4)の内容であるため、全体的な入門書に最適とまでは言えません。 しかし電子書籍という要素を加味すると、本書の価値は飛躍的に高まります。ウォーラーステインの著書は、日本ではほぼ名古屋大学出版会か藤原書店からしか出ていないため、電子化は望み薄としか言えないからです。あのウォーラーステインが電子で読める!ならば多少古くても、ピンポイントでもいいじゃないか。そういう方に本書はおすすめです。(シンプルにウォーラーステイン自身による入門書が欲しい方には『入門・世界システム分析』(藤原書店)が良いかと思います)
0投稿日: 2024.02.29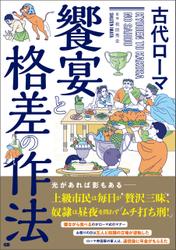
古代ローマ 饗宴と格差の作法
祝田秀全
G.B.
雰囲気はわかるのでは?
参考文献は専門書ではなく、一般向けに分かり易く書かれた本がメインになっています。生活費と奴隷の値段などは参考文献に挙げられている『奴隷のしつけ方』に出ている数字がそのまま書かれていますが、これはその直後の解説で「生活費はもっと高い」と否定されています。参考文献をちゃんと読んでないのだろうな、と推測できます。 また「豊富なイラスト」をうたっているものの、特に一枚一枚に考証がされているわけではなく、それっぽいイラストを並べているだけです。当時はゲルマン系などの白人奴隷が多かったはずですが、奴隷のイラストはすべて肌が黒い人物として描かれています。 信頼度でいえば漫画版『テルマエ・ロマエ』には遥かに及ばず、映画版とどっこいどっこいくらい。雰囲気くらいは掴めるかも、でも学生のレポートには間違っても使っちゃダメだよ、くらいの信頼度の本です。そう考えると、かなり割高では?
0投稿日: 2024.02.29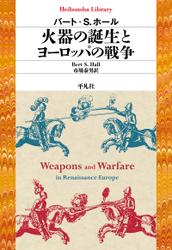
火器の誕生とヨーロッパの戦争
バート・S.ホール,市場泰男
平凡社ライブラリー
そんな火薬で大丈夫か?
原題は"Weapons and Warfare in Renaissance Europe"、「ルネサンス期ヨーロッパにおける武器と戦争」。長らく絶版で古書でさえ入手困難であった1999年刊行の同名ハードカバーが復刊+電子化で大変喜ばしい。 原題ではルネサンスに、邦題では火器に寄ったタイトルではあるが、中世末から近世の火器を中心にしつつ、それ以前の火薬を使わない飛道具や接近戦も含めた戦術全体の変化など、幅広い内容を扱っている。軍事史というよりも技術史寄り。 近い内容の書籍としては、ウィリアム・マクニール『戦争の世界史』、マイケル・ハワード『ヨーロッパ史における戦争』、クライヴ・ポンティング『世界を変えた火薬の歴史』あたり。お互いに補完的なので一緒に読んでおきたい。
0投稿日: 2023.06.17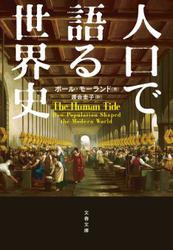
人口で語る世界史
ポール・モーランド,渡会圭子
文春文庫
人口しか語らない
19世紀のイギリスと中国のように人口が圧倒的に多い方が負けている例は「工業力に差があったから」でサラッと流してるのが気になる。じゃあ本書が言っているのは「同じくらいの工業力なら人口、特に若い人が多い方が強い」っていう当たり前すぎることだけになる。人口や人口動態が重要な要因というのには異論はないものの、それしか論じないのは如何なものか。
0投稿日: 2023.02.11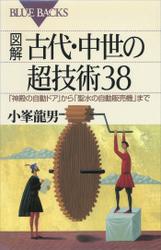
図解 古代・中世の超技術38 「神殿の自動ドア」から「聖水の自動販売機」まで
小峯龍男
ブルーバックス
机上の空論気味
古い文献で言及された機械類について「こういうやり方なら実現できるかも」というアイデアを並べている。考古学的なアプローチはほとんどなく、当時の技術や材料で可能かどうかはあまり考えてない。現在のステンレス削り出しなら可能だとしても、当時の鋳造青銅の加工精度でできるのだろうか、という疑問が付きまとう。いくつかの案件では試作をしているものの、牛乳パックとストローとかを使った小学生の自由研究レベルであり、実物の大きさと重量で動作するかどうかはやはり疑問が残る。 歴史的な説明に関してはすごく古かったり、新旧以前に間違ってたり、特に根拠もなく断言してたりする。沢山の鏡や磨いた金属で光を一箇所に集める所謂「アルキメデスの鏡」が本書では凹面鏡を使った「熱線砲」なっており、無理矢理「超技術」にしてる感が酷い。 あと普通に近世以降の話も出てくる。
0投稿日: 2023.01.28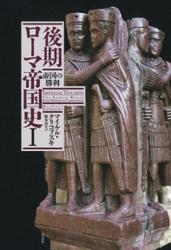
後期ローマ帝国史Ⅰ:帝国の勝利
マイケル・クリコフスキ,阪本浩
白水社
読んでおきたい通史
原題は"Imperial Triumph : The Roman World from Hadrian to Constantine"、「帝国の勝利 : ハドリアヌスからコンスタンティヌスまで」。コンスタンティヌスまで、と言いながら息子のコンスタンティウス2世の最期と甥の「背教者」ユリアヌスの正帝昇格までを扱っています。原題では特に1巻と銘打たれているわけではないですが、2巻にあたる"Imperial Tragedy"「帝国の悲劇」が本文中でも「続編」として何度か言及されているので、両者の関係が分かり易くなって良い改題かと思います。 内容としては最近珍しいくらいにガッツリ政治史という感じですが、パルティアやササン朝ペルシアとの関係ではユーラシアの地域史として状況を論じており、旧態依然という訳でもありません。アナール以降の政治史離れの後にリファインされて戻ってきた新しいスタイルといえるかもしれません。 本文は割と重めですが、論じているのは実証的で地に足が着いた内容なので、じっくり読めばしっかり理解できるはずです(多分)。
0投稿日: 2022.08.09
タキトゥス 年代記 上 ティベリウス帝からネロ帝へ
国原吉之助
岩波文庫
上巻はほぼティベリウスのみ
ローマ史の中・上級者向け。 最低限、共和政末期から帝政初期、できればトラヤヌス帝統治期までの歴史とカエサル家の系図を把握してないと分かりにくい。その上で読んでいくと、「タキトゥスさん、ティベリウスのこと嫌いすぎでは?」という印象が残る。スエトニウスに比べるとまともに見えるが、ティベリウスのやることを特に証拠もなしに悪意で判断している。ドミティアヌスへの恨みをティベリウスへ投影しているのかもしれない。とはいえ現存するなかでは最も信頼性がマシな文献なので、概説書の二、三冊も読んだ後でなら、史料批判に気を留めつつ、あくまでタキトゥスの見解として本書を読むのも良いかと思う。
0投稿日: 2022.07.02
iciさんのレビュー
いいね!された数95
