
三四郎
夏目漱石
青空文庫
最後まで読めずにいました
やっと読み切りました。初めて手にしたのは高校時代でした。なぜか途中まで読んでそのままにしてしまっていました。それ以降何度か読みかけては挫折していた本書を、ついに読破することができました。 高校当時の自分はなぜ読み切れなかったんだろう?もう理由も状況も忘れてしまいました。でも読み終わったいまは、やっぱり高校時代に読んでおきたかったなと思います。三四郎の考え方とか行動って、現代でもすごく共感できる人、特に若い人で多いんじゃないでしょうか。
5投稿日: 2014.09.24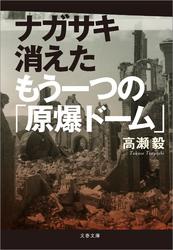
ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」
高瀬毅
文春文庫
驚愕のルポルタージュ
これは絶対に読むべき一冊です。 浦上天主堂という物を私はまったく知りませんでした。 戦争の悲惨を物語る遺物や遺構は年とともに風化し、人々の記憶もやがて薄れていくものですが、あれだけの、人類の歴史上あれほどの大量殺戮を、私たちは忘れてはならないし、もう二度と繰り返してはいけないと思います。それはもう、地球に生きる一人の人間として思います。戦争に勝った負けたなどというくだらない話ではなく、戦争を二度と起こしてはならない。 そういう決意にもとづけば、記憶や、記憶を呼び覚ます遺物は、あらゆる努力で風化に抗う責任があり、多くの資料館や式典などがそれを可能にしてくれています。しかし、私たちは記憶を呼び覚ますための最も貴重な遺物のうちの一つを失った。人の手で、意図して、消し去ったのです。この地上から永久に。戦災で傷ついた街並みが復興するように、復興の励みとして。被災した浦上天主堂です。 今、その遺物を思えば、その失った事実自体がまず辛すぎるのですが、この本は、それ以上の辛い可能性を伝えています。天主堂が作為によって撤去されたかもしれない、と言うのです。取り壊しの経緯に潜む愚かな策謀があったかもしれない事を指摘しているのです。長年の調査による、驚くべき根拠を示しながら。著者のその努力にただただ感謝しながら、読みました。 本書を3カ月前に読んだのですが、そのときはこのwebページがレビューを書けるようになっていなかったので、本当に残念で、わざわざソニーに電話までして問い合わせたのですが、著者の意向かそういう本もあるとのことでレビューを書くのを諦めていました。69回目の原爆忌に報道で浦上天主堂が取り上げられたこともあり、再度このページをみたら、現在はレビューが書けるようになっていたので、書きました。 皆さん、本当に、ぜひ読んでください。
4投稿日: 2014.08.11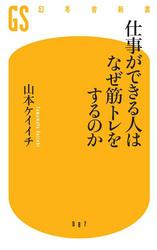
仕事ができる人はなぜ筋トレをするのか
山本ケイイチ
幻冬舎新書
タイトルが与えるセンセーションよりも…
新書にありがちな胡散臭いタイトルですが、そしてその胡散臭さに惹かれてこの本を読んだのですが、中身はもっと本質的で、 「フィジカルを鍛えるためのメンタリティの重要性」が、一貫して書かれています。フィジカル面を恒常的に鍛えられる人はメンタル面の鍛えられた人で、それは「仕事ができる」(とタイトルにはありますが)以前の、人間性の問題だ、と著者は述べています。 「健康のため・若さを保つため」と思い筋トレを始め、「やればやるほど自信がつくなぁ」と思いながら続けていた今の私にとって、筋トレはメンタルを鍛えるためのフィジカルトレーニングだったのですが、この本を読んで、やはりフィジカルとメンタルは鍛えれば相乗効果で両方とも高まるものだと思いました。表紙以上のことは書いてあります。
4投稿日: 2014.08.11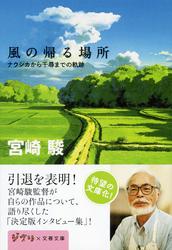
風の帰る場所 ナウシカから千尋までの軌跡
宮崎駿
文春文庫
時代を見つめる眼がすごい
素晴らしいの一言。やはり人生をかけて物を描くことを生業にされてきた偉大さを感じました。まず、その観察眼というか、物を感知する能力が卓越していると思いました。そしてその感じ取ったものを描写する力も、普通の人間の及びもしないようなはるかな高みにあられるのだな、と思いました。さらに時代を読み取る力、時代の空気や流れていく方向を感じる力のすごさみたいなものも、本書を読み通して知ることができました。そして創造するための信念というか、心の軸みたいなものの大切さにも気づかせてくれる一冊でした。さすがに、多くの人々を感動させる作品を数多く作ってこられた方だなと、創造する姿勢について本当に多くのことを教えてくれる一冊だなと、思いました。 また、それぞれの作品が発表されたころの監督の心境や作品への愛情の深さ、制作時のエピソード、それにその時代の思想的流行などを知ることができるという点など、いろんな視点で本書は読む価値があります。
5投稿日: 2014.07.31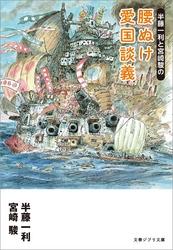
半藤一利と宮崎駿の 腰ぬけ愛国談義
半藤一利,宮崎駿
文春ジブリ文庫
骨太の愛国談義
映画「風立ちぬ」を見て、この本を読もうと思いました。 はっきり言って面白かった。2人の生々しい人間性が、対談という形を通して浮き上がって見えてくる感覚に、思わずのめり込み、引き込まれました。 2人ともにずいぶん年齢を重ねて来られたのに、若い頃、小さい頃の事をよく覚えておられて、私の知らない昭和史を分かりやすく、時に面白く語りかけてもらっているような感覚になりました。 この人たちはどうしてこんなにはっきりと当時の事を覚えていらっしゃるんだろう、と不思議に思いつつ読み進めていきました。人が記憶している事は人に伝えたい事でもあるのですよね。昭和のある一時期、日本は間違った方向に進んでしまった。二度とあんな過ちを繰り返してはいけない。そういう思いで、何があの時代にあったのか、私たち次の世代に伝えたくて、その事を記憶してこられたのでしょう。私たちの世代には、その記憶をできるだけ正確に理解し、また次の世代に伝えていく責務があります。 太平洋戦争を経験した人の話を聞くということを、その大切さを改めて痛感した本でもありました。
3投稿日: 2014.07.05
経済成長という病 退化に生きる、我ら
平川克美
講談社現代新書
示唆深い一冊
非常に興味深く読みました。 とは言っても、最初の方は読んでいて少しまどろっこしい感じもしましたが、その取り留めのなさは、作者があとがきで触れているように、それぞれ異なる時期に異なる目的で書かれた文章が一見脈絡無く並んでいるかのようだから、でしょうか。 生きるということは老いるということ。人が永遠に成長し続けることができないように、高度に発達した資本主義社会において、その成長が鈍化するのはある意味では自明のことのような気がします。経済成長という妄執に囚われる事の愚かさを知りました。 他にも読んでいて心を揺さぶられるような、目から鱗が落ちるような至言・名言が数多く見られました。本論からは逸れつつも、中で一つ取り上げるとしたら、とある協会のスローガンを逆手にとった「人が人を殺すのではない。武器が人を殺すのだ」を説明するくだりは拍手喝采ものでした。いや、作者はその協会への批判など些事に過ぎないと考えていらっしゃる(もしくは、そもそも批判などしていない)のですが。 その他にも派遣労働の問題や、教育問題、秋葉原通り魔事件の問題など、本論からはやや逸れる事柄にも非常に興味深く、紹介しておきたい見識が多数ありますが、それは読んでみてのお楽しみ、です。オススメです。
1投稿日: 2014.07.04
【日本語訳/英語原文 同時掲載】雪の女王/THE SNOW QUEEN ~七つのお話でできているおとぎ物語~
ハンス・クリスティアン・アンデルセン
ゴマブックス
名作
初めて物語を文章で読みました。童話らしい生き生きとした表現で展開が良く、自然や動植物などの描写も素晴らしく、また示唆的で、とても面白かったです。ゲルダの頑張りに、自分までも励まされるようで、読んで幸せな気分になりました。物語の終わり方も素敵ですね。日本語・英語、両方の文章が読めるのも得をした気分でいいです。どちらの文も読んでいて心地よく、堪能できました。
2投稿日: 2014.06.17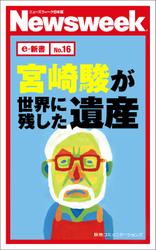
宮崎駿が世界に残した遺産(ニューズウィーク日本版e-新書No16)
ニューズウィーク日本版編集部
ニューズウィーク日本版e-新書
引退宣言が残した動揺の様なもの
宮崎駿氏に引退しないでって、もっともっと物語を見せてって、伝えたい人がたくさんいるということが、改めてよく分かりました。
1投稿日: 2014.05.17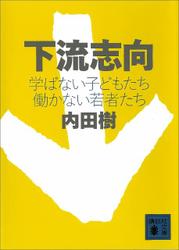
下流志向 学ばない子どもたち 働かない若者たち
内田樹
講談社文庫
教育崩壊の実態
なぜ子どもたちが学びを放棄してしまうのか。 教育現場で起きている「学ばない」という問題の原因が分かりやすく書いてありました。 学校教育の制度、特に公教育の制度が根幹から揺らいでいることを感じさせられます。より良い次世代を、より良い社会を創り出し発展させていくために、そもそもの学校というもののあり方を議論してもいい時代に来ている気がします。
1投稿日: 2014.05.01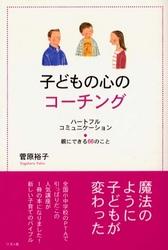
子どもの心のコーチング
菅原裕子
リヨン社
子育てはじめたばかりで
とてもありがたい本でした。右も左も分からなくて、子育ての秘訣は何か、知りたくて、すがるように読んでみました。 ヘルプとサポートの違い、子どもに教えたい三つのこと、子どもを幸せにするしつけ方、子どもの話の聞き方など、非常に参考になることばかり書いてありました。
1投稿日: 2014.05.01
hisashi9さんのレビュー
いいね!された数103
