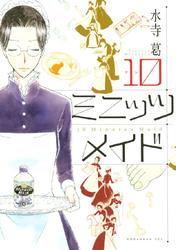
10ミニッツ メイド
水寺葛
ITAN
10分でどんな事を頼もう?
書評で知り、読んでみようと思うに至った本です。ふだんマンガは読まないのですが、時々読むのもアリですね〜。絵が持っている力には、文章とはまた違ったものがありますね。 ランプの魔人を思わせる古典的な設定ではあるけれど、デキるけどでしゃばらない今風な考え方の主人公に共感するところが多いです。ドラえもんのように都合良く便利な道具をポイポイ出してしまわずに、もう少しリアルの中で解決する主人公であれば、四十に手が届きそうな男である私でももっと楽しめたかな、と思います。いや、楽しかったですよとても。そのアリエナイけどアハハ感がマンガの妙なるところだと思いますし。なにより、作者の人柄の良さを感じました。召喚した側の人たちの振る舞いが、それを感じさせます。自分ならどんな事を願うかな、と考えながら読むのも面白いだろうな。
1投稿日: 2015.09.17
ファシリテーション力が面白いほど身につく本
高野文夫
中経出版
タイトルどおり、ファシリテーションを知りたい人のための本
職業柄、単独で仕事をすることがほとんどなく、異なる世代の人と協力して事に当たらなければなりません。とこう書くと、多くの人も同じ思いではないでしょうか。 会議がスムーズに進んだり、チームの生産力や推進力、発展的人間関係をこの上なく渇望しています。と言うと、これに関しても、多くの人が共感されるのではと思います。そんな人にはこれは便利な本だと思いました。 本の内容は表紙が物語っていますが、そしてわざわざこの本にたどり着いた人には言うまでもないことでしょうが、このファシリテーションという比較的新しい、聞きなれないタームが、なんだか魅力的なんです。 本文中にもあるのですが、コーチング技術が1対1ならファシリテーション技術は1対多で、ファシリテーションによってチーム・組織・会社全体の活力向上を目指すという考え方です。これはもう、集団を形成する者にとっては常に必要な技術ですよね。 技術というよりも発想の転換というか、いつもの振る舞い(癖や習慣)を変えてみる、思考パターンを変えてみる、みたいな感じで、自己啓発的な話に若干偏り気味にも感じましたが、明日からちょっと変わってみよッ、と思わせてくれる熱意みたいな何かはありました。 図やイラストも各セクションふんだんに掲載されていて、ファシリテーションの手法や分析が視覚的にも理解しやすいです。ただリーダーでは、そういったキャッチーなはずのページの表示能力があまり高くなく、視認性も悪いと言わざるを得ませんが…。 とにかく、読んで良かったと思いました。
3投稿日: 2015.04.07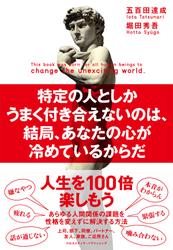
特定の人としかうまく付き合えないのは、結局、あなたの心が冷めているからだ
五百田達成,堀田秀吾
クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
心を温めたい人への一冊
ラクな文体で学術的なことが簡潔に書かれていて、読みやすかったです。 各方面の研究や実験なども紹介しつつ、それらを実際の日常にある習慣や、(職場・家庭・男女などの)共同体の中に潜む人間関係の問題に結びつけ、学説やタームを使って分かりやすく解説してくれます。マンガのキャラや若者のジャーゴンもふんだんに出てくるので、ハハハッて笑いながら読めました。そして読み終わってなんとなく、冷めてた心温まりました。 人付き合いって、人それぞれ違ったスタイルを持っているんですよね。着る服を選ぶ時のように、付き合う人や付き合い方もみんなそれぞれ自分のお気に入りや定型を持っているみたいに。 人間関係をより円滑にしたい、と誰もが思うものでしょうが、いつも同じところに来て失敗するとか、同じパターンに陥るとかって、自分が持っているクセから来てるんだろうな、とこの本を読んで思いました。まあ、多くの人は感覚で分かっていることですよね。そこらへんの感覚的なものを分かりやすく解説してもらって、ついでにコミュニケーションへの勇気みたいな、応援みたいなものまでもらえた気がするので、オススメします。
4投稿日: 2015.02.17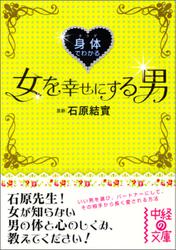
身体でわかる女を幸せにする男
石原結實
中経の文庫
健康に老いましょうの本
またも面白そうなタイトルにつられ、その実中身はタイトルほどセンセーショナルでない本でした。 もう少しHな内容を期待してたのに(?)、運動が大事、食事が大事、と喧伝しまくる本でした。俗にカッコいいと言われる体型より、例え見た目はカッコいいと言えなくても、こういう人は絶倫なんですよ、こういう体型を目指しましょう、と言われてる感じの本です、極端に言うと。絶倫になるかどうかはとりあえず別にして、本書で紹介されているような部分を鍛えて、健康で若々しくいたいいとは思いました。 気になったのは若干誤字があることです。また、ごく当たり前の、言い古された健康法も随所に見られました。そして漢方の説明なんかもあり、一見眉唾ものの記述もあるので、余計に感じてしまったのですが、何か、よくわからない物質や用語を並べられると、ついその気になってしまうのがこの手の本の怖いところですよね。とある食品が健康にいいと言われると、たちまちスーパーでその品が売り切れてしまう、みたいな。そう書いてあるからそうなんだろうと思い込むのもどうかな?と。 とは言え、男の美容と健康について、これは良いよ、これはダメだよみたいなことがスッキリまとめられているので、おおいに参考にはしたいと思います。やっぱりモテたいですから。(と言いつつも妻一筋なんですけどね〜)
0投稿日: 2015.01.13
The Chrysanthemum and the Sword 菊と刀
ルース・ベネディクト,ジェイク・ロナルドソン
IBCパブリッシング
手軽に読める英語の本
英語の勉強をと思っています。このストアで洋書が増えることを期待しているのですが、そしてなかなか増えていないようですが、このシリーズはそういう需要に応えてくれる上に、レベルもさまざまあるようですし、手軽に名著といわれるものを読むことができるわけで、いいですよね。もっとたくさんシリーズが増えて、読む人が増えたら、ストアも本格的に洋書を販売するようになるでしょうか。 さて、本書も誰もが知っている作品の英語縮約版です。こういうものを読んでみようかな、と思ってしまうのは、世相を反映してのことでしょうか。ちなみに原書は1946年出版。とはいえ、古さはまったく感じませんでした。 第三者的観点から対象を批判するのは容易い。本書(しかし私は原書またはその日本語版そのものは読んだことがありません)で ルース・ベネディクトは外国人としての視点で日本を分析してはいますが、日本を劣等であるかのような批判は想像していたほど多くはないと感じました。 むしろ日本人である私が曖昧にしか分かっていないことや、考えたこともなかったことが多々書かれてありました。戦後レジームをそう簡単には否定できないし、かといって戦前の日本を旧時代的で未熟で、欧米に比較して劣等であると指弾するようなことも、私にはできません。太平洋戦争に突き進む中で、当時の日本にあったのは、日本的な価値観・日本的なアイデンティティだけであり、それは欧米のそれとは異なっていたというだけの事の様に感じます。 恐らく長年に渡って時代ごとの批評にさらされてきた本書でしょうから、そしてそれでもなお参照されることの多い本書ですから、ぜひとも読むべき本といって間違いはないでしょう。ただ、名著を短時間で読みたいとか、英語力をアップグレードしたいなど、原書ではなく、また日本語版でもなく、わざわざこの縮約版を読むのはそれなりの目的を持った人に限られると思います。(例えばこのストアには洋書が少ないと感じている人とか)
6投稿日: 2014.12.24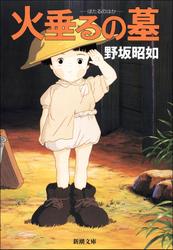
アメリカひじき・火垂るの墓
野坂昭如
新潮社
傷を癒すために、誰かに伝えるように
ジブリ好きで、読んでみました。ぜひみなさん読んでください。 命の尊さとか自由平等とか言いますが、つい70年くらい前は紙切れのように命は軽かったんでしょうね。物語はあくまで虚構であると分かっていますが、どうしてもノンフィクションの部分に思いが巡ります。清太や節子を可哀想に思うけれども、日本中に清太や節子が溢れていたんでしょうね。誰か清太のような子たちを非難できるのでしょうか。戦争をすることのいかに愚かなことか、を思います。 他数編、収録されているいずれも心打たれる物語でした。戦争によって負った傷は永い時間が経過しても、いつまでも消えないんだと思いました。 読むにはたいへん、たいへん辛い本書ですが、ぜひ多くの人に読んでほしいです。
3投稿日: 2014.12.08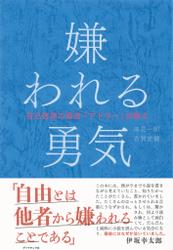
嫌われる勇気
岸見一郎,古賀史健
ダイヤモンド社
いろいろ疑問と多少の不満
みなさん好意的なレビューですが、私は多少批判的に書いてみます。そのために最初に断っておこうと思います。何人かの方と同じく、私も「売れてるから読んでみた」という1人です。アドラーという人をまったく知らなかった自分にとって、その入門書として、アドラーの考えを理解するのにはとても良い本だと思いました。以下、感じた疑問をいくつか。 一つ目の疑問:哲人が言う「アドラーはこう言います」「アドラーはこう考えます」という部分は納得できるし、実際にそのように振る舞えたら、すごく幸せだろうし、みんながアドラー的世界観の住人であれば、世の中はもっと違った所になるんだろうな、と思いました。 でも、アドラーやその伝道者が「他者の課題」に対して介入する事に積極的でないので(課題の分離)、「共同体的感覚」はあくまでも個人の主観による幻想でしかないように感じます。実際の共同体(構成員全体)が「共同体的感覚」を持ち得て、「住みよい世の中になったな」と感じたり、「他者信頼」や「他者貢献」を実行に移したりするかどうか、は重視されません。あくまでも、個人の問題のみに議論が終始して、「個人が変われば、みんなが変わる」というような結論に少しがっかりしました。 二つ目:「他者信頼」と「他者貢献」に加えて、同じく重要視される「自己受容」について。そのような心的態度を醸成したり、自然と習得したりできるような環境ってあるのでしょうか。実際の家庭や学校、職場では現在のところ「競争」や「縦の関係」の思想がある程度定着してますよね(もちろん時代とともに共同体のありようは変わっているわけで、将来において「他者信頼」や「横の関係」が根付く可能性は否定しませんが)。現時点では「自己受容」が「ライフスタイル(アドラーの言う性格)」として自然に身についたりはせず、まさにアドラーの伝道者のように、それを教える人が必要となると思うのですが、そこについては「馬を水辺に連れて行く」ほどのことしか説明されません。実際、例えば現在の日本の学校現場なんかを見ていて、説明不十分な気がします。 三つ目の疑問:そこで本書のようなアドラー解説書の必要性が出てくると思うのですが、読み終わってみると「嫌われる勇気」というタイトルには、強い違和感を覚えました。目を引くタイトルですが、そして実際に売れているようですが、本書の言い表したいことを端的に示しているとは思えませんでした。 四つ目の疑問:対話形式について。ソクラテスの対話篇に似せて作られた事があとがきでも述べられています。私はソクラテスの対話篇を目にしたこともないのでそれについてはよく分かりませんが、青年と哲人による本書の対話は、リアリティに欠けるように感じました。特に青年は生身の人間ではなく、哲人が思うように議論を進めるための道具(または哲人の分身)のように感じます。結局、哲人の思うとおりに議論は進んでいくのです。そして青年は自分の疑問を忘れたかのように、哲人の望む段取りで、次から次に話題を提供していくのです。他の方のレビューではこの対話形式が読みやすいとされていますが、私自身はダメでした。 私自身は哲学や心理学についてまったくの素人です。そして最初に述べたように、アドラーの考え自体は興味をもって読むことができました。本書で私がハイライトした箇所は100近くになりました。 ですが。だとしても、アドラーを知るために、この本でなくてもいいと思いました。
5投稿日: 2014.11.10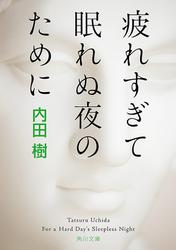
疲れすぎて眠れぬ夜のために
内田樹
角川文庫
寝る前に読むには面白すぎます
内田樹の本はこれで3冊目です。いつもの通り面白く、一気に読めました。サザンのことを書いているレビュアーもいらっしゃいますが、私としては3箇所ほどある村上春樹論もなるほど、と思いました。 それにしても、いつも思うことですが、覚えておきたい言葉がたくさんありました。中でも、 「愛想がいいというのは、すごく良質な文化です」 「「レイバー」はそれ(ビジネス)とは違います」 「「個性的である」というのは、ある意味で、とてもきついことです」 「武士が歩いているとき、その意識は「背中」にあった」 「マジョリティとともにあることは決して安全を意味しない」 などなど(まだまだありますが、きりがないのてやめておきます)、気になる言葉があちこちにありました。 あとがきにあるように、この本は話した事をもとにテープ起こしして、それを加筆修正することで出版されるという経緯を辿っていて、そういうこともあってのこのタイトルなのでしょうが、寝る前に読むには十分に深くて濃すぎる内容です。私は通勤電車の中で読みました。
9投稿日: 2014.10.22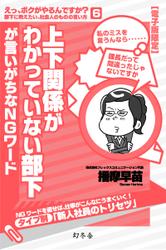
上下関係がわかっていない部下が言いがちなNGワード
播摩早苗
幻冬舎
うちの職場のあるある
相当、悩んでるのかな?と、購入ボタンを押しながら、つい思ってしまいました。 実は職場の後輩で1人困った子がいて、どう接したらいいか迷いつつ、自分の心を乱されたくなくて、しばらくそっとしておくことに決めたのですが、やっぱりこういうタイトルの本を買ってしまうって、相当、ですよね。 読んでみて、やっぱりオドロキでした。ここにある事例すべて当てはまっているんです。悩まなくて良かったんだ、と思えたことがこの本を読んで一番に感じたことですが、たぶんここに書いてある対処法を実践しても私の後輩には何の変化も起こさないだろうということも感じました。
0投稿日: 2014.10.18性愛英語の基礎知識
吉原真里
性愛英語の基礎知識
吉原真里
新潮社
盗み見的な楽しさ
興味本位とリビドーと、学究的な欲求に突き動かされて(踊らされて)読みました。英語が極端に苦手でなければ、すんなり読めます。 紹介されるフレーズそのものもそこまで多い訳ではなく、どちらかと言うと、それぞれの言葉にまつわる背景知識や男女の恋愛における習慣や様式、著者の好きな映画やドラマの話題の方に多く紙幅を費やしています。全体を通してみたら、非常にあっさりと爽やかに読み通すことができて、ああ大人の恋がしたいなぁ、と思いました。
1投稿日: 2014.10.09
hisashi9さんのレビュー
いいね!された数103
