
校閲ガール
宮木あや子
角川文庫
「解説」込みで
TVドラマとは、ちょっとおもむきが違う感じ。 「校閲」という仕事の凄さ、魅力が伝わってくる。 悦子と一緒に校閲にチェレンジしてみるのも楽しみの一つ。結構難しい。。。。 ただ誤字を探すだけかと思っていたのが、大変申し訳なくなってきます。 巻末の角田光代さんの解説も読むと、さらに校閲の凄さがわかります。 話としては、悦子のその後が気になる。
7投稿日: 2016.10.11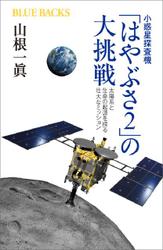
小惑星探査機「はやぶさ2」の大挑戦 太陽系と生命の起源を探る壮大なミッション
山根一眞
ブルーバックス
熱い想い
前半は、「はやぶさ」が持ち帰ったイトカワのかけらについて。 小さな小さなイトカワのかけらを無駄なく取り出そうとする姿に心打たれます。 「はやぶさ2」の方は、各部署担当の方の「はやぶさ2」にかける想い、開発秘話、そして1999 JU3(リュウグウ)が目的地に選ばれたわけも書かれています。 そして最後に次への目的地 木星への熱い想いも。 とりあえず、先ずは2018年 無事にリュウグウに到達することを願う。
0投稿日: 2016.10.04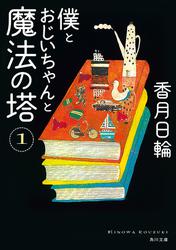
僕とおじいちゃんと魔法の塔 1
香月日輪
角川文庫
いい子って?
「いい子」ってなんだ? ここから始まる物語。 ファンタジックなお話ですが 善とは?悪とは? 集団の恐ろしさ。 個性の尊重。 などなど色々考えさせられます。 龍神(主人公)の成長をみると子供の可能性を大人の凝り固まった頭で摘んではいけないなと思います。 大人にも子供にも読んで欲しい作品。
1投稿日: 2016.10.04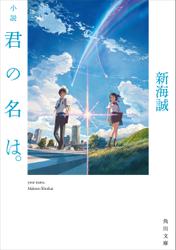
小説 君の名は。
新海誠
角川文庫
どちらも良さがある
先に小説を読んでから後半のシーンを映像で観たいと思い映画館へ。 結果、どちらもそれぞれの良さがあるので両方おすすめ。 後半に進むにつれスケールの大きな話になっていくのでやはり五感にうったえてくる映像にかなわない部分もありますが、三葉の現状に満足していないもやもやした心や神社の存在意義等は小説の方がわかりやすかったかなと思います。 映画だと神楽の部分がサラッとしてるので小説の方が1200年前の人々の「忘れてはいけない」という気持ちが強く感じやすいかな。 この作品を読んで(観て)星空がとても近く感じるのは、星が近く綺麗なところで育った監督自身の距離感なのかなと、ふと読んでいて思いました。
3投稿日: 2016.10.04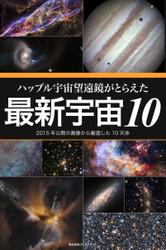
ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた最新宇宙10 2015年公開の画像から厳選した10天体
岡本典明
ブックブライト
子供達にも観てほしい
これから宇宙のことに興味をもつ子供たちにも観てほしい作品。 ただ星が綺麗ってだけじゃなく、最新技術でとらえた約8000年前の超新星爆発の残骸や核融合の始まっていない生まれつつある星、重力により変形した渦巻銀河など文字で読んでもわかりづらい(想像しづらい)画像は価値あるものだと思います。
0投稿日: 2016.09.29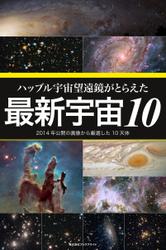
ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた最新宇宙10 2014年公開の画像から厳選した10天体
岡本典明
ブックブライト
興味が広がる
星のまたたく様子や色の鮮やかさが本当に綺麗です。 「創造の柱」は、ハッブル宇宙望遠鏡ならではではないでしょうか。 こういったところから星が生まれるのかと思うとワクワクしてしまいます。 木星の大赤斑が徐々に小さくなってる様子も3枚の写真の対比で良くわかります。 宇宙への興味がさらに広がる作品。
1投稿日: 2016.09.29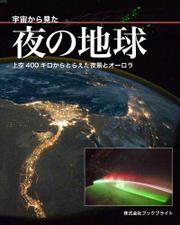
宇宙から見た夜の地球 上空400キロからとらえた夜景とオーロラ
岡本典明
ブックブライト
人工と自然の光の対比
前半は夜の地球に浮かび上がる人が作った光。 地球上での人間の主張みたいなものを感じ、怖いぐらい圧倒されます。 後半は、自然の光であるオーロラ。 前半の単一的な光の鋭さに比べ、色鮮やかなオーロラの画像はなんだかとても癒されると同時に自然の凄さも感じます。
1投稿日: 2016.09.29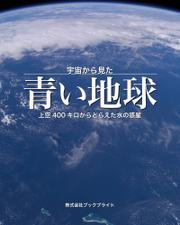
宇宙から見た青い地球 上空400キロからとらえた水の惑星
岡本典明
ブックブライト
黒と青の境が素敵
ISSからの撮影画像。 宇宙の黒と地球の青の間の大気層の幻想的な色がとても素敵です。 お気に入りは、地球の大気層の向こうに浮かぶ月の画像。 ちょっと台風(ハリケーン)の画像が多いのが残念。 とはいえ、台風の大きさに圧倒されます。
0投稿日: 2016.09.29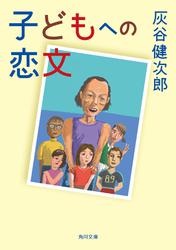
子どもへの恋文
灰谷健次郎
角川文庫
詩が素敵
灰谷氏の子供達への想いがあふれたエッセイ。 そして、今の日本の教育、教師への不満。 内容は様々だが、ここに載せられている子供達の詩が全てを語ってくれている。 子供の心、素晴らしさを大切にしたいなと思わせる作品。
0投稿日: 2016.02.03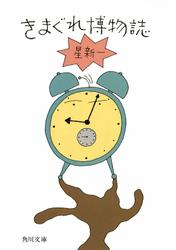
きまぐれ博物誌
星新一
角川文庫
クスッとしてしまう
星氏らしいエッセイ集。 こういう思考の持ち主だからああいう作品が生まれるのだなぁ~と妙に納得。 コタツでお茶でも飲みながらのんびりとお爺ちゃんの話を聞く感じで読むと面白いです。
1投稿日: 2016.02.03
shinoさんのレビュー
いいね!された数94
