
天文の世界史(インターナショナル新書)
廣瀬匠
集英社インターナショナル
昔の人の観察眼に脱帽
望遠鏡もない時代、夜空を肉眼で観察し、惑星などの動きを分析し、政治や占星術などに応用する、昔の人の観察眼には、頭が下がります。天文学者ではなく、歴史学者である著者による記述は、地域によって異なる占星術などについても豊富な説明があり、読み物として楽しめます。もちろん、最近の宇宙についての記述もあり、気楽に読める天文に関する本と言えるでしょう。
0投稿日: 2018.03.02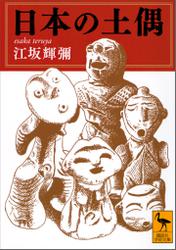
日本の土偶
江坂輝彌
講談社学術文庫
土偶のデザインは、縄文土器のデザインに先行する
各地の博物館や歴史資料館では、縄文土器の展示は多く見かけますが、土偶の展示は少ないように感じます。その土偶の解説が、豊富な写真とともに、年代的に、系統的になされています。我々が土偶に持っているイメ-ジが、後期の一部のものであることが理解できます。また、今後解明されなければならない多くの疑問があることも、理解できます。
0投稿日: 2018.02.21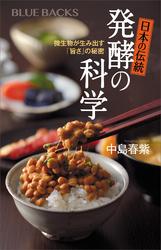
日本の伝統 発酵の科学
中島春紫
ブルーバックス
お茶の発酵には、微生物は関係していない
味噌、醤油、清酒などの発酵技術について、歴史などにも触れながら、科学的、総合的に理解することができます。麹、乳酸菌の生物学的差異を理解することは、漬物などに応用できるかもしれません。
0投稿日: 2018.02.10
地名の謎を解く―隠された「日本の古層」―(新潮選書)
伊東ひとみ
新潮選書
地名は、縄文人が使用していた言葉
人々に使用されていた地名が、律令国家の確立の一部として、字数や使用文字の制限を課せられ、漢字で表記されるようになる。これが明治維新での中央集権体制の確立のために、再整理される。さらに、昭和の大合併、平成の大合併などで再整理されるといった、地名がたどった歴史的運命の解説です。何気なく使用していた地名について、新たな視点を与えてくれました。
0投稿日: 2018.02.01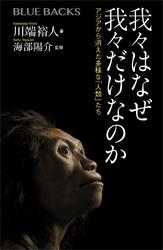
我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち
川端裕人,海部陽介
ブルーバックス
読みやすく、入門書として最適
アジアの人類が、ホモサピエンスに集約されていくことについての、人類学的な研究結果を、科学ジャ-ナリストである著者が、研究者に取材して著述した本です。研究者ではなく、ジャ-ナリストと記載であるため、非常に理解しやすいものになっています。ジャワ原人の研究が、日本人研究者を参加して、現在も活発に行われていることを知ることだけでも、貴重な情報かと思います。
0投稿日: 2018.01.24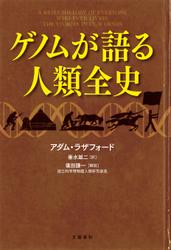
ゲノムが語る人類全史
アダム・ラザフォード,垂水雄二
文春e-Books
差異は人種間より人種内でのほうが大きい
ヒトゲノムの分析技術が進んだ結果、それがもたらすものの詳細な分析です。古代人のゲノム分析は、考古学の証拠にもなるし、新たな事実をもたらすことなどから始まり、新たな優性学に利用されるのではないかといった危惧などにも触れられています。そのなかで、”差異は人種間より人種内でのほうが大きい”、”DNAに人種はない”という事実が重要であることを強調しています。やや言い回しが多く、難解な部分もありますが、ゲノム分析がもたらしたものを理解するには良い本と思います。
0投稿日: 2018.01.17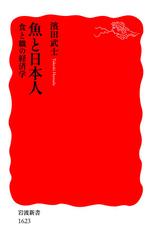
魚と日本人 食と職の経済学
濱田武士
岩波新書
魚料理は日本食の中心のはずですが
バブル期以降、日本では、魚を食べる量も、漁獲量も減少しているという事実に、まず驚かされます。そんななかで、市場を通さない魚の流通量の増加、漁師や養殖者、水産加工物業者の減少など、魚を取り巻く環境の変化について、詳細に分析しています。永く続くデフレの影響もあるのでしょうが、魚好きにとって、非常に憂慮すべき報告がなされています。
0投稿日: 2017.10.26
煮えたぎる川 (TEDブックス)
アンドレス・ルーソ,シャノン・N・スミス
朝日出版社
地質学の学術書ではない
ペル-のアマゾン地帯にある煮えたぎる川の話を、曽祖父から聞いた経験のある著者が、実際に地質学者になってから、その川に遭遇する話です。といって、地質学の学術書ではなく、スピリッチュアルな影響を受けた著者が、その研究・保護に活動するエッセイです。当地の油田開発会社に勤める地質学者が、ジャングルの破壊を嘆き、その保護をアドヴァイスする記載には、印象づけられるものがありました。油田開発会社への投資が終了し、会社の活動がなくなれば、保護されているジャングルは破壊されてしまうだろうという主張に、今後のヒントがあるのかもしれません。
0投稿日: 2017.10.22
銀の世界史
祝田秀全
ちくま新書
産業革命がイギリスで起きた理由が理解できます
大航海時代から、日清戦争の終了ごろまでの、銀本位制であった世界の歴史の解説です。新大陸からスペインに大量に流れ込んだ銀が、どのように流れ、最後に、産業革命を経たイギリスが、世界の覇者となってゆくダイナミックな動きが理解できます。資本主義の発展、グロ-バリズムといった現代につながる世界を理解するにも、最適な本かと思います。
0投稿日: 2017.10.21
したたかな寄生 脳と体を乗っ取り巧みに操る生物たち
成田聡子
幻冬舎新書
ヒトの性格が寄生生物によって変化する可能性もある
寄生バチなど、他の生物に寄生する生物の生態の詳細な説明です。寄生する生物の脳をコントロ-ルすることによって、その子孫が生存する可能性を高めるといった、考えてみれば恐ろしいメカニズムには、脅威を感ぜざるをえません。人間の腸内細菌の話やトキソプラズマ症の記述からは、ヒトの性格とはなんであろうかとも、考えさせられます。
1投稿日: 2017.10.15
TANさんのレビュー
いいね!された数37
