
超能力微生物
小泉武夫
文春新書
発酵の奥深さ
極限状態に生きる微生物の説明から始まりますが、中盤で、藍染料の製造、柿渋の製造など、歴史的に既に日本人などが利用していた技術と、微生物のかかわりの説明に移行します。発酵という現象の奥深さに、改めて驚かされます。世界の発酵食品などの記述には、どのようにしてそんなことを思いついたのだろうと考えさせられます。未来に向けた微生物を利用した展望については、大いなる期待を抱かされます。
0投稿日: 2017.06.09
すごい畑のすごい土 無農薬・無肥料・自然栽培の生態学
杉山修一
幻冬舎新書
重要なのは窒素フロ-
木村リンゴ園の実例から、自然栽培の科学的、技術的分析を行っていますが、筆者自身も触れているように、木村リンゴ園の分析結果はまだ少なく、一般論の説明となっています。有機栽培を含めて、畑に窒素成分などをあらかじめ投入しておき含入量を多くすることが栽培の基本であるのに対して、自然栽培では、窒素などを流入させるメカニズムが確立することが必要であり、そのための多様な植物、生物を共生させること、窒素を代謝する細菌叢が存在することなどが必要であることが理解できます。さらなるデ-タの分析を期待したい内容でした。
0投稿日: 2017.06.04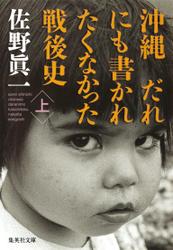
沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史 上
佐野眞一
集英社文庫
ヤクザから尖閣諸島まで
沖縄のヤクザ、芸人、琉球の王家であった尚家などの取材から、本土では、沖縄戦、復帰運動、反基地運動などの視点で報道されることの多い沖縄の戦後史が、また異なった視点で記載されています。。本土の人間は、戦後史というと、マッカ-サ-に象徴されるGHQの占領からの独立、高度経済成長とういう視点で理解しがちですが、アメリカによる軍政から本土への復帰とういう歴史下で、色々な人々が生活し、時が経過してゆくと、報道では知ることができない複雑な事情があることが理解できます。沖縄の人々のこの本にたいする評価が気になるところですが。
0投稿日: 2017.05.07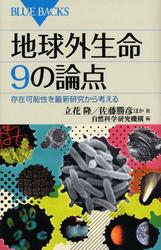
地球外生命 9の論点 存在可能性を最新研究から考える
立花隆,佐藤勝彦,長沼毅,皆川純,菅裕明,山岸明彦,重信秀治,小林憲正,大石雅寿,佐々木晶,田村元秀,自然科学研究機構
ブルーバックス
知的生命体というよりも
地球での海底熱水帯での化学合成を行う生物の発見、星間物質の発見、地球型惑星の発見、土星の衛星における火山活動の発見、衛星などにおける液体の存在の予想などから、化学合成を行う生物の可能性について論じており、SETIが対象とする知的生命体については、この時点ではあまり想定していないようです。比較的最新の知見を知るといった目的では、読みやすい本かと思われます。
0投稿日: 2017.04.28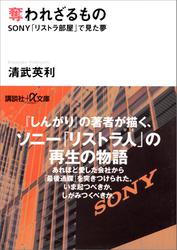
奪われざるもの SONY「リストラ部屋」で見た夢
清武英利
講談社+α文庫
リストラの波
”モノづくりのソニ-”から”コンテンツを売るソニ-”への変換の過程での、際限なく続くリストラについてのドキュメントです。想像していた以上の大量リストラであったことが理解できますが、扱っている事例が良好に推移しているものですので、救われるような感じはします。(すべての人がそういった状態ではないのでしょうが)。c-MOS関連の業績がよいと言われている最近のソニ-の状態とどう繋がるのか知りたいものです。
0投稿日: 2017.04.26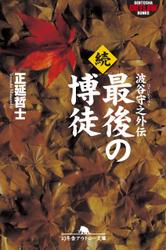
続 最後の博徒 波谷守之外伝
正延哲士
幻冬舎アウトロー文庫
前作と一緒に読めばさらに
賭博のみをシノギとして生きてきた人のドキュメントです。アウトロ-として生きて人々がスジを通し、法秩序を守るべき人々が冤罪を作り上げるこの対比に興味を覚えます。広島の”仁義なき戦い”のドキュメントでもあり、映画が作られた背景なども理解できます。さらに、法廷で争う過程で、他の冤罪も明らかになるという展開は、非常な迫力をも感じさせます。
0投稿日: 2017.04.22
ふしぎな国道
佐藤健太郎
講談社現代新書
酷道、険道
国道マニアという人々がいることを、初めて知りました。そんな人々がこだわる色々なこと(階段の国道から始まり、国道を使用しない走行まで)が記載されています。複雑な道路行政の実態や、その歴史など、非常にまじめな内容です。ただ、国道にはまると、全国各地を走りまくり、調べ、写真などを撮らなければならず、かなりシンドイことではないかという印象を持ちました。
0投稿日: 2017.04.16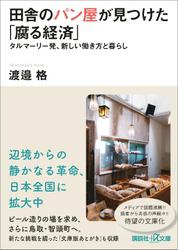
田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 タルマーリー発、新しい働き方と暮らし
渡邉格
講談社+α文庫
稲妻の語源
”自力で採取した麹が最大に活動するのは、自然農法で収穫された米であった。”こんな記載には、非常な不思議さを感じます。活動の場所を選択し、試行錯誤を繰り返しながら、酒種パンなどを完成する記録ですが、筆者の生い立ちや、マルクス経済学に基づく筆者のパン職人としての考え方にも、興味を感じました。稲妻の語源も解ります。
1投稿日: 2017.04.05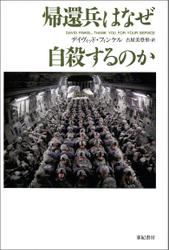
帰還兵はなぜ自殺するのか
デイヴィッド・フィンケル,古屋美登里
亜紀書房
暗い話題ばかりではない
アフガニスタン、イランの戦争を取材した記者が、帰還した兵士からのメ-ルで、様々な問題で苦しんでいる人がいることを知り、丹念な取材を行ったドキュメントです。暗い話題ばかりですが、解決に尽力する人が少なからず存在し、それらの人々に救われる人がいることには、希望が持てる結末になっています。まだ、ヴェトナム戦争の後遺症に苦しんでいる人もいることには、驚きを隠せません。PTSD、TBIと簡単な言葉で表現される状態は、多種多様な内容を含んでおり、解決法も明確ではない現実が理解できます。
0投稿日: 2017.03.31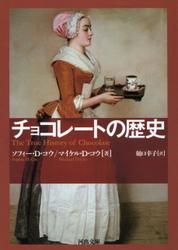
チョコレートの歴史
ソフィー・D・コウ,マイケル・D・コウ,樋口幸子
河出文庫
中央アメリカでのカカオの歴史が中心ですが
中央アメリカといえば、トウモロコシというイメ-ジが強いのですが、最近の考古学的研究成果も参考にして、飲み物としてのカカオの歴史や、中央アメリカでの食材としての重要性の説明がされています。スペインによる植民地化によって、このカカオがヨ-ロッパにもたらされ、最初は飲み物として利用されるカカオが、北ヨ-ロッパ、イギリス、アメリカで、現在我々が知っているチョコレ-トへと変容してゆく過程も、また面白い内容となっています。著者の一人である夫人が、マヤ族の料理の研究家であったこともあって、所々に記載されている詳しいレシピにも興味をひくものがあります。カカオの生産地がアフリカへ移動したり、栽培するカカオの種類が変わってゆくことにも簡単に触れられていますが、中央アメリカとヨ-ロ-ッパでの記載が中心となっています。
0投稿日: 2017.03.27
TANさんのレビュー
いいね!された数37
