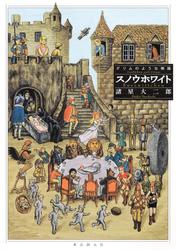
スノウホワイト
諸星大二郎
東京創元社
懐かしい童話の、新しい発見。
「トゥルーデおばさん」に続く、諸星大二郎描くグリム童話。「狼と七匹の子やぎ」や「白雪姫」のような誰しもが知るメジャーどころから、「奇妙なおよばれ」「藁と炭とそら豆」「コルベス様」のようなマイナーなものまで、幅広い作品群が楽しめる。 「奇妙なおよばれ」は、童話の持つ不思議で独特な不気味さが、諸星氏の作風とマッチしていてグッド。理由無き暴力を昔話かつちょっとSF風に描いた「コルベス様」は、作者が楽しんで書いているな!という感じが伝わってくる。「ラプンツェル」は、同じくグリム童話を描いた「トゥルーデおばさん」にも同題の作品が収録されているが、こちらはまた違った味付け。読み比べてみるとなお面白い。 巻末に作者自身による(!)解説が付いているので、グリム作品に詳しくなくても安心。私もオリジナルの半分以上は知らなかったが、解説を読んでから本編を読み返してみて、また違った切り口で楽しめた。 諸星氏独特のコメディチックな話もあるので、氏の作品に馴染みのない人は展開に「?」と思ってしまうかも。初心者の方は他の作品で慣れてからの挑戦をオススメする。
0投稿日: 2014.02.10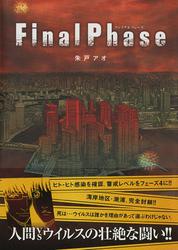
Final Phase
朱戸アオ
PHP研究所
「ベストを尽くします。」
「Phase(フェーズ)」とは、WHOの定義したパンデミックの警戒レベル。 とある埋立地に突如発生した致死性を持つ感染病により、次々と倒れていく人々。そして地区一帯が封鎖されていく様が非常にスリリング。 病気に医師として敢然と立ち向かう女性医師・鈴鳴や、天才肌の疫学者・羽貫など、登場人物達も魅力的。愛する人間を失いながらも、困難に向き合い、立ち上がっていく人々の姿が、心を揺さぶる。 羽貫が「災害ユートピア」と評する封鎖地区で、人間はウィルスに打ち勝つことができるか-。緊迫の医療ドラマ。
1投稿日: 2014.01.25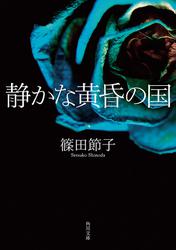
静かな黄昏の国
篠田節子
角川文庫
暗く、静かな恐怖に引き込まれる。
計8編の短篇集。SF・オカルト・人間心理などジャンルは様々だが、どの作品も静謐で暗い恐怖を漂わせ、読んでいると知らず知らずのうちに背筋がスッと寒くなるような。 近未来、とある夫婦の老後の行く末を描いた表題作「静かな黄昏の国」は、現在の日本と照らして決して絵空事とは思えない、ホラーとは違った恐怖がある。経済的に日本が小国に陥っているという設定は、いかにもありそうで怖い。震災後に追加されたあとがきも、本作に連動した内容で考えさせられる。 図らずも恋愛ゲームのノベライズを引き受けた、落ち目の作家の顛末を描いた「ホワイトクリスマス」は、作家が恋愛ゲームにのめり込んでいく様がリアルなのだが、「これを書くために篠田氏はゲームを結構やり込んだのでは?」と想像すると、なかなか興味深い。 いずれの作品も安定した篠田節子氏のクオリティで、引き込まれる。大人の恐怖を求める方にオススメ。
4投稿日: 2014.01.25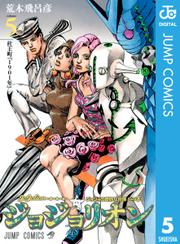
ジョジョの奇妙な冒険 第8部 ジョジョリオン 5
荒木飛呂彦
ウルトラジャンプ
シリーズならではの魅力
「カツアゲロード」後半。定助と常秀は、第4部の仗助と億泰とはまたちがった良いコンビになりそう?ラストの定助のはっちゃっけっぷりには、ちょっと笑った。 そしてついに、家系図のとある人物と杜王町のつながりが、「伝説」として語られる…! 第7部からの読者にはちょっとショッキングな内容だが、「ジョジョリオン」が「SBR」の正統な続編であることを強く印象づける内容。物語の歴史から深みを感じることができるのは、ジョジョシリーズならではの魅力。
2投稿日: 2014.01.25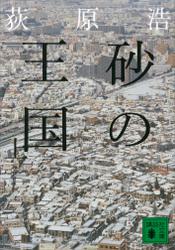
砂の王国(上)
荻原浩
講談社文庫
全体のバランスが…
上下巻を読んでの感想。 前半、主人公が送るホームレス生活や、出会った仲間と逆転を狙って宗教団体を立ち上げていく様は、なかなかリアル。 が、前~中盤の間延び感・盛り上がりの弱さと、後半~終盤の怒涛の展開が、アンバランス。一部の伏線も回収されず。 主人公の大義を一貫して強く描き、後半の空気を前倒しすることができたなら、もう少し違った読後感になったかも。
2投稿日: 2014.01.25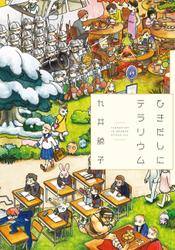
ひきだしにテラリウム
九井諒子
イースト・プレス
ひきだしいっぱいのショートショート
日常的妄想、昔話風、SF、ほのぼの、クスリと笑える話など、バリエーションに富んだショートショート集。 どの話も楽しんで読めたが、未来の恋人候補のカタログを見た男の選択―「恋人カタログ」、とある女性の脳内で繰り広げられる裁判の行方―「代理裁判」、謎の奇病に悩む村人は元凶と思われる猫神を殺そうとするが?―「神のみぞ知る」、が好き。 ジャンルの豊富さもさることながら、絵のタッチを話の雰囲気に合わせて変えていることがスゴイ。小説とはまた違った、コミックならではの魅力がある。九井諒子氏のひきだしに詰まったショートショートが堪能できる一冊。
4投稿日: 2014.01.24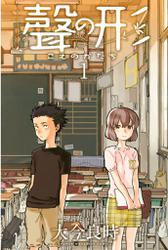
聲の形(1)
大今良時
週刊少年マガジン
この物語の結末が気になる。
「聴覚障害(劇中でも「障害」との表記だったので、こう書きます)」を扱って話題になったマンガ、という程度の認識で読み始めた。 が、誰しもが持つ小学生の甘酸っぱい思い出…、とは程遠い、ヘビーな内容でびっくり。今風の絵柄(余談だが絵のレベルは相当)でやわらいではいるが、正直、胃が痛くなる場面も。 授業中、先生の声を聞き取っての板書が困難、発音ができない、音楽の授業でうまく歌えない、など耳が聞こえないことによるハンデ。それを幼いがゆえにからかいの対象としてしまう、主人公をはじめとする級友たち。そしてある日突然かわるいじめのターゲット。「小学校のクラス」という、独特で閉鎖的なコミュニティの描写にリアリティがあり、胸に刺さる。 レビューの都合上☆4つをつけたが、1巻を読んだだけで評価をすることはとても難しい作品。と同時に、気が早いが、作者がこの物語をどのように終わらせるか、が非常に気になった(2014年1月現在、連載中)。大今先生の描く「聲」の「形」を見届けたい。
21投稿日: 2014.01.22ミラーボール・フラッシング・マジック
ヤマシタトモコ
ミラーボール・フラッシング・マジック
ヤマシタトモコ
FEEL YOUNG
気怠さとユーモアが、ジワジワ来る。
男女問わずどこかアンニュイな雰囲気を漂わせる、ヤマシタトモコ氏描くキャラクターが魅力的。 夜空に降った一つのミラーボールが、とある三組のカップルに起こした「奇跡」を描いた表題作「ミラーボール~」は、ちょっと笑える。 恋・愛・SEXに時に傷つき、身もだえる彼・彼女たちを、気怠く、かつユーモラスに描くヤマシタ節が、ジワジワ来る短篇集。
0投稿日: 2014.01.12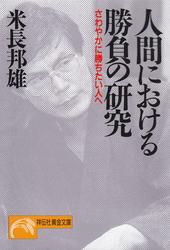
人間における勝負の研究
米長邦雄
祥伝社黄金文庫
一流棋士は考え方が違う。
伝説の(?)棋士、米長邦雄氏が語る勝負哲学。 「勝負の要素は確率・勢い・運」「頭が悪いから、(三人の)兄達は東大に行った」「(運をつかむために)自分の利害にはたいした影響のない勝負で、必死に頑張る」といった、一流棋士ならではの独自の思考・理論が、既存のビジネス書や自己啓発書とは一線を画していて、おもしろい。 元々は昭和の刊行で、どちらかと言えば男性向けな内容である本書。氏のルーツに始まり、勝負観・生き様・子育て論まで、米長氏のユニークさを堪能できる一冊。
3投稿日: 2014.01.12
機動戦士Zガンダム(1)
近藤和久,富野由悠季
電撃G'sマガジン
懐かしい…。
Zガンダム本放映と並行して、ガンダムコミックの第一人者である近藤和久氏にて、コミックボンボンで連載されていた作品。当時、何故か2巻しか持っていなかったので(笑)、今回電子書籍化にて全3巻を読破。いや、懐かしい…。 テレビアニメと並走してのコミカライズということで、ストーリー進行はかなり駆け足だが、独自の展開やMSが出てきて、なかなか面白い。特にハマーンがキュベレイに替わり搭乗するG-3(ゲー・ドライ)は注目(3巻に登場)。 あらかじめZのストーリーを知らないと理解が難しい部分もあるので、決して万人向けの内容ではないが、シリーズのファンであるならば、新しい発見があるのでは。
3投稿日: 2014.01.12
ペンギンずさんのレビュー
いいね!された数435
