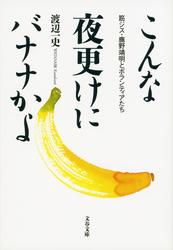
こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち
渡辺一史
文春文庫
おもしろいタイトルだが非常に中身の濃いノンフィクション。
筋ジストロフィーにより寝たきり、動くのは指先が少しという重度身体障害者である鹿野靖明氏と、彼を支えるボランティア達、そして介護・福祉に関わる今日の問題点を伝える著者・渡辺一史氏による渾身のノンフィクション。 おもしろい。 何がおもしろいかというと、鹿野氏の強烈なキャラクター。自らが「生きる」ためにボランティアたちを集め、教育し、時には「帰れ!」と怒鳴る。そこに一般の人間が抱く、「介護をしてもらう」という障害者像はない。普通は入院してケアを受けるべきところを自宅で暮らし、人工呼吸器をつけた状態での発声を可能にした鹿野氏のパワーに圧倒される。 そしてボランティア達。本書は鹿野氏だけにとどまらず、彼の生活をサポートしてきた通称「鹿ボラ」の活動・心情に大きく内容を割いている。鹿野氏と彼らは「介助ノート」と呼ばれる交換日記的なノートによって意見を交換し、それを元に著者が個々のボランティアにインタビュー。そのことによって名も無きボランティアではなく、一人の人間としての彼らの人生が浮かび上がり、非常に興味深い。 24時間の介助を必要とするということ。そのために全てをさらけ出すということ。障害者が自立するということ。ボランティアをするということ。何故鹿野邸に集うかということ。そして生きるということ。こう書くととても重たいテーマだが、誤解を恐れずに書くと鹿野氏のキャラクターによってとても楽しく読める。気楽に読み始めてOK、そして一気読み必至。「生きる」ことの意味を考えさせられる素晴らしいノンフィクション。
7投稿日: 2014.11.22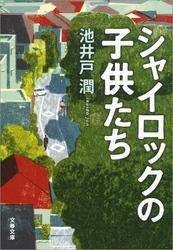
シャイロックの子供たち
池井戸潤
文春文庫
クオリティの高い短編。そして全体を通しても満足の読後感。
とある銀行で働く人々を描いた連作短編集。歯車として生きる者、それに疑問を抱く者、激務の苦しみが報われる者、対照的に散る者…。「銀行員」というエリート稼業の裏にある過酷な業務の描写は、さすがの池井戸クオリティ。息苦しくなるほどのリアリティを持って読者に迫ります。 そんな話が続くのか…と思いきや事件は起こります。ある女子行員に降りかかった現金盗難疑惑。そこに端を発し、やがて事件は思わぬ方向に。独自に調査していた行員が失踪し、やがて真実が明らかに…。 出世レースを戦う人間の息の詰まるような思い、それを支えあう家族、そしてミステリー要素。短編でありながら各話が少しずつ繋がり、そして最後に余韻を残す読後感。短編としても、全体を通しても、非常に読み応えのある満足の一冊でした。
6投稿日: 2014.11.22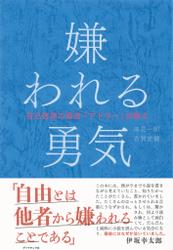
嫌われる勇気
岸見一郎,古賀史健
ダイヤモンド社
人生における最大の嘘、それは「いま、ここ」を生きないこと
レビューのタイトルは本文より。もしこの言葉にドキッとしたら、この本を読むことをオススメします。 「嫌われる勇気」=「アルフレッド・アドラーの著書」と思われがちですが、これはアドラーの手による書物ではありません。岸見一郎氏と 古賀史健氏による「哲人と青年の対話を通してアドラーの教えを学ぶ」本です。全編、「世界はシンプルであり、人は今日からでも幸せになれる」と主張する哲人と、それに懐疑的な青年の対話、という形で描かれます。もちろん青年は読者です。 最初は哲人の言葉に反発するかもしれません。しかし対話を読み進めるうちに、自然とアドラーの教えが腑に落ちるでしょう。なぜ自分は不幸なのか、なぜ劣等感を抱くのか、そしてどうすれば幸福になれるのか。あなたも青年となって、哲人の言葉に耳を傾けてみてください。 あなたが「今の自分に満足しているが、もう少し上を目指したい」という状態ならば、この本を読む必要はありません。しかし「今、悩み、苦しみ、そしてよりよく生きたい」と考えているならば、一度手にとってみてください。きっと新しい発見に出会えるはずです。
5投稿日: 2014.11.12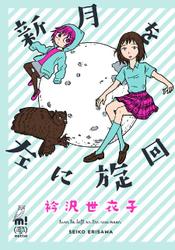
新月を左に旋回
衿沢世衣子
もっと!
「ユウコ」と「このは」のちょっと不思議な物語。
中学生の「ユウコ」と、彼女の家族に「このはずく様」と呼ばれる謎の少女「このは」。何気ない日常にちょっと不思議要素をプラスした物語。 いたって普通の主人公のもとに不思議なキャラクターがやってくる、というパターンは、日本人おなじみの藤子不二雄的構図。それが衿沢世衣子氏のえがく世界となんともマッチしているのは新発見。少しダークな雰囲気が漂うのも、衿沢作品としてはめずらしく、新鮮。もっともっと、この雰囲気にひたっていたいと感じる、良い作品。サイダーにシュワシュワするこのはがカワイイ。
2投稿日: 2014.07.25
星のポン子と豆腐屋れい子
小原愼司,トニーたけざき
アフタヌーン
あなたの想像の斜め上を行くSF。
「二十面相の娘」の小原愼司氏原作、「AD.ポリス25時」(なつかしっ!)のトニーたけざき氏作画、という、実力派作家ふたりの合作。まずは試し読みを読んでみましょう。うん、良い作画。町の豆腐屋一家に謎の宇宙生物「ポン子」がやってくる、という○子不二雄的展開が何ともほのぼのしてていいなぁ。しかしこのポン子、ちょっと怪しげ…? おっと!私に書けるのはここまでだ!何を書いてもネタバレにつながりそうな、レビュアー泣かせのこの作品。もう読んでください、としか言いようがない。予想外の展開に、きっと口をあんぐりさせることでしょう。私は3回ほどあんぐりしました(笑)。単巻完結の名(迷?)作SF。 ※レビューになってなくてすみません。
2投稿日: 2014.07.25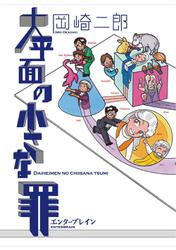
大平面の小さな罪
岡崎二郎
HARTA COMIX
「平面管理委員会」、そんなんでいいんかい?
世の中の全ての「平面」は、「平面管理委員会」によって管理されていた!広告会社勤務のAD・宇田川は、委員会の美女・セーナと一儲けを企むが―? 岡崎二郎氏お得意の、SFミステリー。平面を自在に移動したり、内容を書き換えたり、といった発想がおもしろい。一話、セーナと宇田川の出会い以降は、彼らが「平面」に絡んだ謎を解決していく。しかし、なんで「委員会」の人間はいともたやすく犯罪をおかすのだろうか(笑)。「委員会」の存在意義も良くわからなかったので、そのあたりのディテールにもう少し説得力が欲しかったところ。 巻末収録の登場人物によるメイキング(あとがき)マンガは、作者の制作背景が読めて興味深い。
0投稿日: 2014.06.28
珈琲時間
豊田徹也
アフタヌーン
コーヒーが飲みたくなる短編集。
短編・全17話。コーヒーは基本的に小道具。うんちくマンガでは無い。 内容は種々雑多。何気ない日常だったり、シリアスだったり、ユーモア、SFっぽかったり。一つひとつの話は非常に短いが、その中にドラマがあり、もっともっと、色んな話を読んでみたくなる。 第一話「Whatever I want」から、つかみはオッケー。女性チェリストが、喫茶店で出会ったうさんくさいイタリア人。コーヒーを片手に繰り広げられる二人の会話に、クスリとくる。 それにしてもこの作家さん、絵がうまいなぁ…。描かれる構図が、映画のよう。キャラクターもオシャレな色気があって良い感じ。コーヒーを焙煎する「おば」と「めい」の、何気ない会話を描いた第三話「すぐり」は、話に派手さはないが、ついつい各コマに目を止めてしまう。 というわけで私も今からコーヒーを飲みます。インスタントだけど。
4投稿日: 2014.06.25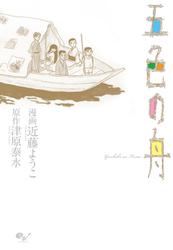
五色の舟
近藤ようこ,津原泰水
月刊コミックビーム
衝撃的。
原作は未読。感想は…、いや、色んな意味で衝撃的だった。 近藤ようこ氏の朴訥なタッチにて描かれる世界は、静かで、淡く、幻想的。が、見世物小屋の一座を舞台に描かれる内容の、何と残酷なことか。戦時中という、昏く、混沌とした時代ならではの描写は、近藤氏の絵柄で和らげられているとはいえ、なかなかショックを受ける。 そして舟が川を流れるがごとく物語は進み、「くだん」を求める家族をやがて待ち受ける運命。読後には、満足感というか、寂寥感というか…、何も言えない不思議な気持ちが残る。近くを見ているようで、心はどこか遠くにある、そんな主人公達の表情が印象的。一度は読んでおきたい、価値ある作品だと思う。
3投稿日: 2014.06.23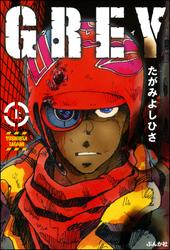
GREY 上巻
たがみよしひさ
ぶんか社コミックス
懐かしいアクションSFの名作。
今はなき「少年キャプテン」に連載されていた単行本全三巻を、上下巻に再録した本作。かつてアニメ化もされました。荒廃した世界で繰り広げられる、ハードな戦闘描写が、全編で乾いた空気を醸し出す。アジアンテイストなメカ群も、他の作品とちょっと毛色が違っていて面白い。 本作の魅力はなんといっても、主人公・グレイ。たがみ作品独特のちょっとキザなセリフ回しが似合う、クールでスカしたカッコ良いヤツ。特に後半冒頭のグレイは、成長した風貌とも相まって、何ともシビれる。 下巻、割りとぶっ飛んだ展開になるが、全体としてはコンパクトにまとまった良SF作品。
3投稿日: 2014.06.22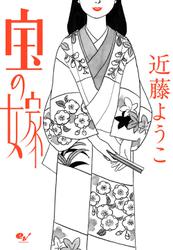
宝の嫁
近藤ようこ
月刊コミックビーム
「懐かしさ」が響く、近藤ようこ氏えがく「おとぎ話」
優しいタッチで描かれる、おとぎ話計8編。「石の赤子」「かくれ里」「花守り」「苦い泉」「宝の嫁」「君よ知るや南の国」「夢の底の人形」「稀人」を収録。 過去のあやまちに苦しめられる僧侶のたどった結末―「夢の底の人形」、死罪となった父の罪を背負って、寺の住職にこきつかわれる娘は、ある日ふしぎな旅の一座と出会い―「稀人」、の二編が個人的に好み。作者いわく、元ネタはあったりなかったりするそうだが、優しい話や救われない話、因果応報など、どの話も日本人が幼いころから親しんできた「むかしばなし」風。派手さは無いが、淡白な絵柄と相まって、どの話も心に馴染む。こういう話が前置きなしにスッと受け入れらるのは、やっぱり「まんが日本昔ばなし」で育ってきた、という下地があるからだろうか。
3投稿日: 2014.06.22
ペンギンずさんのレビュー
いいね!された数435
