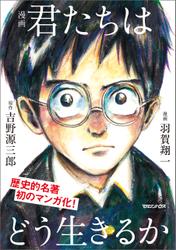
漫画 君たちはどう生きるか
吉野源三郎,羽賀翔一
マガジンハウス
今も変わらない「人として大切なこと」を学べる本
中学一年生のコペル君こと本田潤一君の人間として学び成長していく様を描いた小説になります。 コペル君には、お父さんがいません。ただ、お父さんの代わりに優しく色々と相談に乗ってくれる伯父さんがいます。 叔父さんは、コペルの話を聞いて、「人として大切なこと。考えて欲しいこと」をノートに記していきます。 そのやり取りを通して、「人としてどう生きるか?」を学ぶ事ができる本になってます。 ・人は、一人では生きていけない ・無償の愛で成り立つ人間関係の素晴らしさ ・過ちを認める勇気 道徳教育の教科書としてとても素晴らしい本になっています。 大人にとっても、改めて「優しい気持ち」を思い出せる素敵な本です。 「子供に読ませたい本」の理由もわかります。 是非オススメです。
1投稿日: 2018.04.30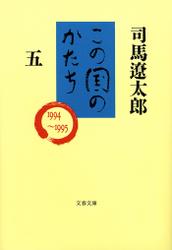
この国のかたち(五)
司馬遼太郎
文春文庫
歴史を通して「日本」を学ぶ
「この国のかたち」の第五巻になります。 司馬遼太郎さんの本は、美しい日本語で書かれており、時々読みたくなってしまうそんな魔力を持っています。 この本も御多分に洩れず、気持ちの安らぐ美しい日本語に溢れています。 この5巻では、主に「神道」「宗学」について触れられています。ただ、「この国のかたち」では、色々な時代に関連付けて説明されているので、日本の歴史を体系的に学ぶことが出来ます。司馬遼太郎さんの小説とは違った楽しみがあります。 著者は、「幕末維新の日本人」の中で、読者に対しての想いとして、 「せめて日本人が、基本的な日本人像をきっちり持ってくれていると、ありがたい」 と書いています。 読者として、この気持ちに応えられるように司馬遼太郎さんの本から学び、これからの世代にも「日本」という国をしっかり残していきたいです。 本当に素晴らしい本です。
1投稿日: 2018.04.25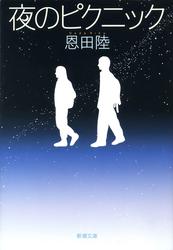
夜のピクニック(新潮文庫)
恩田陸
新潮文庫
読了後に温かな気持ちにさせてくれる青春小説
この小説では、ある高校で行われる「歩行祭」を通して成長していく高校生が描かれています。 その高校生の中でも、三年生西脇融と甲田貴子を中心に物語は進みます。 彼らは、実は異母兄弟の同級生。彼ら以外は、知らない秘密のはずが・・・・ シビアな境遇の中で育ってきた少年少女が、「歩行祭」での交流を通して、背負ってきた「十字架」を下ろしていきます。 淡々と進む物語の流れが、真夜中の静寂さとその静寂さの中での足音が聞こえてくるようでした。まるで「歩行祭」を一緒に歩いてるようでした。 その中でやり取りされる出来事一つ一つがなんだか高校の頃を思い出させてくれて懐かしい気持ちにさせてくれます。 読んだ後に、幸せな気分になれるそんな小説です。こんなにキラキラしてなかったかも知れないけど、自分の「高校時代」を思い出すそんな小説でした。 是非、読んでみてください❗
1投稿日: 2018.04.23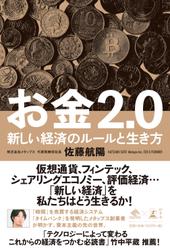
お金2.0 新しい経済のルールと生き方
佐藤航陽
NewsPicks Book
自分の価値を高める「これからの働き方」について
この本では、「これからの働き方」について語られています。 著者は、これからの社会は、お金を増やすことが目的の「資本主義」でなく、自分の価値を高めていく事が目的の「価値主義」に変わっていくと述べています。 すでに、これまでの国家が運営する「中央集権的なお金の経済」から国以外の団体が運営する「トークンエコノミー」へ移行しつつあります。 「トークンエコノミー」は、同時発生的に「分散化された経済」を作り出しており、「国家の運営するお金」でなく様々な「価値」を元に経済が回っています。 そのような「分散化された経済」において「お金」はひとつの価値に過ぎず、個人個人が、お金以外の様々な価値を蓄えて行くことが大切であると説いています。 そのためのこれからの働き方について著者の持論が書かれています。 確かに、「ビットコイン」を含むその他のトークンエコノミーについてニュースとしても聞く機会が多いです。 テクノロジーの進化の速さに付随して「世の中」が大きく変わっていく予感を感じています。 「そんな中で自分に何ができるのか?」 「少なくとも自分の価値を高めて行く必要があるのではないか?」 「じゃあ、そのためどうするか?」 今後の自分の「あるべき姿」を考えさせて思わくれる本でした。 是非、読んでみてください。
2投稿日: 2018.04.21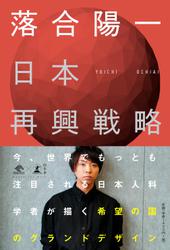
日本再興戦略
落合陽一
NewsPicks Book
刺激的で新鮮な「日本再興戦略」
これまでの働き方や考え方に慣れている為か、 落合さんの持論全てがとても刺激的でした。 日本を変えたいと思う気持ちがひしひしと感じられるそんな本でした。 ただ、全ての持論に対して、根拠が示してあるので納得感は得られます。ただ、いきなり全てを受け入れるのは難しいほど刺激的で新鮮なアイディアに溢れています。 全体を通して、少子化などの日本にとってマイナスの要因に対しても、ポジティブな捉え方をしています。 この発想こそが、これからの日本に必要なアイディアであり、変化を起こす為に必要な考え方だと感じました。 これから先、世界はどんな風に変わっていくかはわかりません。 ただ、変化のスピードの早い現代において、落合さんが提唱する「ポジションを取れ。とにかくやってみろ」という気持ちがとても重要になるだろうと感じました。 是非オススメの本です。
2投稿日: 2018.04.05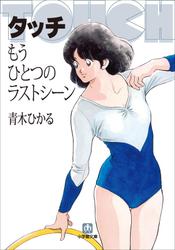
タッチ もうひとつのラストシーン
青木ひかる
小学館
孝太郎の目から見た「達也・和也との青春時代」
懐かしい〜。 この小説を読んでまた1巻から読みたくなりました。 基本的には、漫画のタッチにあったエピソードを文章にして起こしています。 少し冗長な背景描写や言い回しが多く感じました。ただ、同時に改めて「あだち充」さんの漫画のリズム感や全体的な描写の美しさを感じてしまいました。 この小説では、孝太郎の視点で物語が進んでいきます。この点は面白かったです。 タッチの中で親近感のわく孝太郎目線で描かれる青春時代は、懐かしい気持ちを思い出させてくれます。 自分の「あの頃」を思い出させてくれる本でした。 オススメです。
1投稿日: 2018.03.20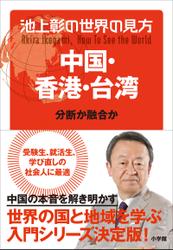
池上彰の世界の見方 中国・香港・台湾
池上彰
池上彰の世界の見方
サラッと読める中国・台湾について
仕事の都合上も、台湾の方や中国の方と仕事するので、それぞれはどう思っているのかを知りたく手にとった本です。 やっぱり池上彰さんの本は分かりやすい❗ 台湾の方に親日の人が多い理由。 中国と台湾の立ち位置。 中国に今後、超高齢化社会が始まること。 等を縦の繋がり(歴史観点)と横の繋がり(地域観点)を意識的に書かれているので理解が深まりました。 社会とか歴史を理解するには、関連性を意識するいいんでしょうね。 分かりやすい説明ってどういう構成か?を知る上でも役に立つ本でした。 学生の頃、池上さんの授業で歴史や社会を受けたかったなぁ〜
1投稿日: 2018.03.18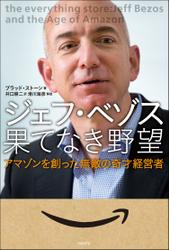
ジェフ・ベゾス 果てなき野望 アマゾンを創った無敵の奇才経営者
ブラッド・ストーン,井口耕二,滑川海彦
日経BP
全ては「顧客の価値向上」の為。アマゾン成長の系譜
アマゾンを立ち上げたジェフ・べゾスの物語です。 D・E・ショーというヘッジファンドで働いていたべゾスが、インターネットの可能性に気付き「エブリシング・ストア」を目指し世界有数のカンパニーに如何にしてなったのかについて、書かれています。 べゾスのモチベーションは、「顧客の価値」です。全ては「顧客の価値」のために行動しています。 この本で改めて企業とは「顧客の価値」を考える事が本分であること認識しました。 また、アマゾンは、成長の過程で企業買収や新規事業を多く失敗しています。 しかし、ただ失敗するのではなく、失敗しても何かを得て成長を続けています。 ただでは、転ばないところに会社としての凄みを感じました。そんな「アマゾンの凄み」を読んで感じられる本です。 オススメの本です
1投稿日: 2018.03.08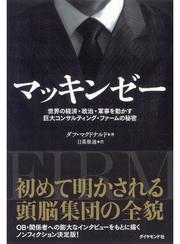
マッキンゼー
ダフ・マクドナルド,日暮雅通
ダイヤモンド社
最強頭脳集団 マッキンゼーの成長と思考の歴史
「マッキンゼーとは一体どんな会社なのか?」 この疑問から手にとった本です。 この本では、マッキンゼーの生い立ちから変遷、問題点と課題を書かれたノンフィクションの本です。 マッキンゼーがいかにして巨大で影響力のある組織になったのか時系列的に書かれているので、アメリカの経済史も理解できる本になっています。 マッキンゼーと言えば、「アップ オア アウト(昇給するか出ていくか)」が有名です。 ただ、会社を辞めた後も、マッキンゼー出身者は、「アラムナイ(同窓生)」という組織で繋がっており、辞めた後も「マッキンゼー」として各業界に影響を与え続けている事に「マッキンゼー」繁栄の理由を感じました。 「リーダーシップとは人々を従わせることだが、従わせる前に、進む方向を選ぶ必要がある。このようなサービスには常に需要があり、それこそがまさにマッキンゼーが提供しているものなのだ。(p.388)」 相談相手の欲しいトップのCEOにとってたとえ高額な支払いが必要でも頼りたくなるのがマッキンゼーなのでしょう。 知らない世界を垣間見れた気がして大変興味深い本でした。オススメです。
1投稿日: 2018.02.25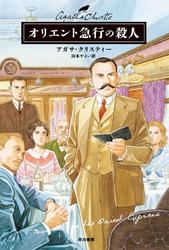
オリエント急行の殺人
アガサ・クリスティー,山本やよい
クリスティー文庫
絶対読むべき不朽の名作。最近の最後まで楽しめました
すごく面白い推理小説でした❗最後の最後まで犯人が誰なのか想像できませんでした。 流れとしては、「事件発生→推理開始→犯人追求」となっています。 流れは、オーソドックスですが、結末が秀逸で最後の最後まで楽しめました。 また、この時代特有の「階級や国毎の偏見に満ちた社会」も楽しめたポイントです。 時代としては第二次世界大戦前です。ヨーロッパ諸国それぞれの国に対する偏見みたいなものが見てとれて各国の民族感にも触れられて興味深いものでした。 ポアロの紳士然とした立ち居振舞いもこの本の面白いところです。 「冷静で、知恵があって、慎重な頭脳の存在が感じられます。アングロ・サクソン系の頭脳とでもいいましょうか」 節々に現れるヨーロッパ優位な考え方も前時代的で面白いですよね。 久しぶりに小説読みましたが、面白い作品でした。アガサ・クリスティ作品にハマりそうです!! オススメです!!
1投稿日: 2018.02.03
Y-sukeさんのレビュー
いいね!された数109
