
マギ(22)
大高忍
少年サンデー
表紙の人は誰?
表紙を見てアラジンが一気に青年に成長しちゃうわけ?と思ったら…さて、これは誰でしょう。 これだけで当てられたらちゃんとマギを読めている人だと思います。って私はわからなかったのですが…w マギが持つ多重構造的な世界観がグッと明らかになる本刊。マグノシュタット編が終わって、ギャグ中心だった前刊と比べ、マギ2部とも言うべき展開が本格化してきました。 そうきますか。
3投稿日: 2014.10.20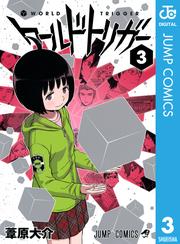
ワールドトリガー 3
葦原大介
週刊少年ジャンプ
チーム結成!
さらわれた兄妹と友人を探すためにボーダーへの入隊を決意したチカ、 チカが心配で手伝いたい世話焼きのオサム、 自分のことは自分で、自己責任を徹底しているユーマ。 「人を助ける」ことが「自分の目的」になるオサムの中に、 「自分のミスが原因」で「身代わりに死んだ」父親が最後に笑っていた理由を見出そうとするユーマ。 3人の行動する理由ががっちりと組み合わさり、このマンガの軸が強力に固まった感じ。 うまいストーリーだなぁ。
3投稿日: 2014.10.07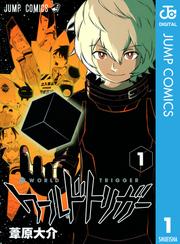
ワールドトリガー 1
葦原大介
週刊少年ジャンプ
上質の王道SFバトルマンガっていうだけじゃないです
アニメ化+1巻無料のコンボにつられて読んでみたところ、まんまとハマってしまった。 一晩で7巻読破・・・。 これは面白い。久々のジャンプ王道アクションでの会心作ではないだろうか。 ナルトやワンピレベルまで化けるかもしれない。 すごいと思ったのには、一流の作画、1話ごとのネームのクオリティ、ワクワクする世界観といった ジャンプでヒットするための大前提を鮮やかにクリアしつつ、以下の点で突出していたから。 ① 今までの王道少年漫画と違い、少年だけがかっこいいのではなく、大人もちゃんとかっこいいこと。 少女もかっこよくて、このあたりは鋼の錬金術師を思い起こさせる。 それぞれの利害関係・背景を緻密に練り上げていて、組織的な対立をしっかり描いている。 ② 戦闘能力が、才能ではなく道具であること。 もちろん才能による部分もあるが、基本誰でも使える汎用道具の使いこなしによって勝敗が決まるところが面白い。 どう努力すれば強くなれるか、自分ならどうするか、といった想像がはかどる。 話の合間にある武器の設定の裏側を読むのも楽しい。 ③ キャラの豊富さと個性付けの上手さ。 登場から数コマでキャラの印象付けをするのがとても上手い。 巻数を重ねると登場人物と戦闘場所の多さにちょっと全体図が把握しずらくなるが、 地味なキャラでも魅力をしっかり持たせていてすばらしい。 チーム戦なのもたのしい。 武器や編成もまったく異なるので多様な戦い方が楽しめる。 ④ 設定のうまさ。 SF的な世界観の構築も見事なんだけど、 1番アクションの見せ方として上手いと思ったのは、戦うときは「トリオン体」という生身とは違うからだなので 腕をぶった切られたり首が吹っ飛んだりというグロテスクで少年誌では書けないショッキングな表現もちゃんと書けること。 設定を知らないでジャンプ立ち読みしたときは驚いた。 ⑤ みんな賢い。 性格がいやなやつはいても、みんな理由があってそうなっていて、ハリウッド映画でよくある 理解しがたい自分勝手な行動で周りをピンチにしてしまうようなトラブルメーカーがおらず、 謙虚で客観的な目線のあるキャラたち。 みんな自分で反省する力がある。 この辺はネット世代の、知識があふれている時代だからなのかな。 この点についてはもしかするとすっとぼけキャラだらけのルーズさで話を展開するワンピースと比べ、 緻密すぎてあとあと苦しくなるケースがでるかも・・・、という気もするけど。 たくさん書いてしまいましたが、とにかく面白いです。 今後もっともっと面白くなることを期待して★5つ!
10投稿日: 2014.10.03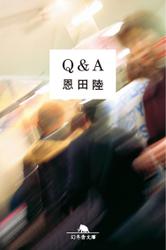
Q&A
恩田陸
幻冬舎文庫
サスペンスというよりファンタジーホラー
初めての恩田陸作品。大型スーパーで起きた事故に巻き込まれた人々にインタビューを行い、事件の正体を突き止めて行くQ&A形式を取った実験的な作品。同じスタイルで書かれた貫井徳郎の「愚行録」が面白かったのでこちらに挑戦することにした。 結果は、いまいち。 愚行録はこれでもかと人間の薄汚い面をリアリティを持って描き切った怪作だが、こちらはトンデモ人物とトンデモ設定で、サスペンスではなくほとんどファンタジーホラー。謎が謎を呼ぶ展開の先にあったのは納得し難い結論だった。 Q&Aをしている人物が誰なのかを注意深く読み進めれば、最後に謎が解けると思ったら、後半のある1章を読むだけで事件の正体がつかめてしまったり、その正体もおよそ現実にあるとは思えない幼稚なもので、がっかり。 緻密なパズルを組み立てて行く知的快感は、最後まで得られなかった。 愚行録がインタビュアーが固定されているのに比べ、こちらは明らかに口調が違う人物が突然でてきたりでこれがどうハマるのか、愚行録と違う面白さに胸を高鳴らせていただけに失望した。 というわけでQ&A形式の良作小説を楽しみたければ愚行録の方をお勧めします。
4投稿日: 2014.09.17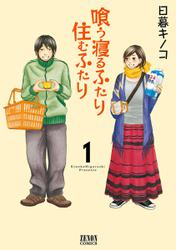
喰う寝るふたり 住むふたり 1巻
日暮キノコ
月刊コミックゼノン
なんだこの破壊力は!
付き合って10年、同棲8年のカップル。 男女両方の視点から描かれる何気ない日常。 なぜ10年もの間、この人を選んでやってこれたのか?という疑問を持ちながら、安心できる着地点に落ち着くのがとても心地よい。 男女両方の目線から書かれていて、両方とも「ありそう」と思わせるリアリティがある。20代後半から30代くらいの、結婚を意識する世代には看過できない、立ち止まって考える瞬間があります。 男子がイケメン過ぎないのがいい感じ。そのおかげか、「リア充死ね!」ともならないと思います笑 青年コミックに属しているけど、やや女性コミック寄り。でも、性別問わず楽しめます。
7投稿日: 2014.09.12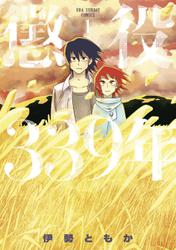
懲役339年(1)
伊勢ともか
マンガワン
良作みーつけた!
「Reader Storeのおすすめ」にあった「懲役339年」というタイトルに惹かれて購入。 まったくのジャケ・タイトル買いで予備知識なし。結果は、吉だった。 某事件で懲役339年を求刑された「ハロー」。前世のつながりを信じるその世界では、ハローが死んでも刑は終わることがなく、生まれ変わりとされる人間がその罪を償うことになる。このあたりの設定は、手塚治虫の火の鳥っぽい。火の鳥と違うのは、本当の転生ではなく、国が勝手に前世がハローだと決めた人間に罪を着せ、それが当たり前になっていること。 なんとも理不尽で、残酷だ。 過酷な監獄での環境で長生きできるわけもなく、歴代のハローは投獄からせいぜい10年から30年くらいで死んでしまう。その度に濡れ衣を着せられた人間がハローにされていくのだが、本人もそれが当然だと思っているのが独特。手塚治虫だと本人がその仕組みのおかしさに気づいて反乱を起こしていく展開なのだが、本書は、看守がそれに違和感を覚えて脱走をもくろむ。 これ以降はぜひ読んでもらいたい。 絵は独特に単純化された線で書かれていて(ちょっとワールドトリガーっぽい?)少し人を選ぶかもしれないが、慣れてしまえばむしろ作品にあっている感じがしてくる。 まだメジャーじゃない良作を見つけるのもコミック読みの楽しみですよね、と。 雑誌は違うけど、なんとなくアフタヌーンあたりの空気感を感じた。黒田硫黄とか芦奈野ひとしとか、漆原友紀とか好きな人も向くかもです。 あ、佳作SFという意味では、「預言者ピッピ」とかが好きな人も楽しめると思います。 次も買おうと思います。
10投稿日: 2014.09.08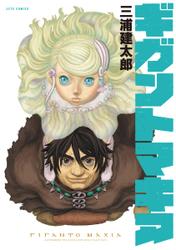
ギガントマキア
三浦建太郎
ヤングアニマル
風の谷の進撃のベルセルク・プロレス(謎)
ベルセルクの作者、三浦健太郎の新作、ギガントマキア。ベルセルクと同じファンタジーだが、また少し違った、滅びかけた世界を舞台にしている。 ベルセルクと同じく、驚異的な書き込みで読者を圧倒する。生理的な不快感をうまく盛り込んだ独特のキャラクター造形も見事。 物語の骨子は特殊な能力をもった少女と青年のコンビが旅をしながら、ある目的を成そうとしているようだかまだはっきりしてこない。 アクションシーンはさすがの迫力で、この作家の底力をまざまざと見せつけられる。 …と、真面目にレビューするとこんな感じなのだが、アクションのハイライトはまさかのあれ。あれ、人気ですよね。「ギガント」ついてるしね、タイトルにね。そしてそこに絡むまさかのプロレス。三浦さん、描きたかったんでしょうね、これ。思わず半笑いになってしまった(笑) 色んな要素を盛り込んで好き勝手書いてる感じがして、これだけ振りきれてるならもう笑うしかないです。これ、まだまだ続くのかな…。 ファンとしては、ベルセルクはどうすんの?というのはやっぱり言いたいかも(笑) なんかネタっぽくなってしまいましたが、良作のファンタジーなので買って損はないです。ベルセルクに興味はあるけど長いので手が出しにくいという人にもおすすめかも。
4投稿日: 2014.09.04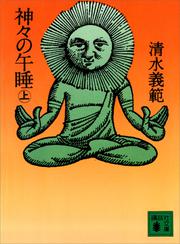
神々の午睡(上)
清水義範
講談社文庫
うーむ、玄人向けなのかな・・・
仏教、キリスト教、イスラム教の3宗教をモデルとした、架空の宗教の成り立ちから物語は始まる。 あきらかに各宗教をモデルにしているのだが、宗教の名前も人名もありそうななさそうな絶妙な名前に置き換えられていて、ちょっと奇妙な気持ちになりながら物語は進んでいく。 1つの宗教の物語が終わると次、と順に進んでいくのだが、なんとなく内容を知っている物語なので特に面白いこともなく、作者もそれを知っているものとして淡々と書いて行っていて、なんとも驚きがない。 文章は小気味よく上手なのだが、なんというか物語にハラハラさせられたり、どうなっちゃうのだろうと心配したりだとかということがなく、感情を揺さぶれないまま淡々とページをめくっていって途中で飽きてしまった。特に読む気を失ったのは、通常は真面目な言い回しで過去の偉大な人物を物語っているのに、突然、現代の口語体でしゃべりだす箇所があるところ。マンガなどで突然登場人物が読者に話しかけてくる、いわゆる「メタ・フィクション」の手法っぽいのだが、いかんせん本編の物語が面白くないのに技巧ばっかり凝っているので興ざめしてしまった。 私はそれほど小説を読む方ではないので、この辺の高度な言葉遊びなどが楽しめないのかもしれない。 逆に言えば、私は小説というフォーマット自体であそぶような高度な小説より、登場人物の喜びや苦しみ、純粋な物語のダイナミズムに魅力を感じるのかもしれないと思わされた作品ともいえる。 たぶん、私のようなタイプの人には向かない本です。 初めて読み切らずにレビューを書いてしまった。。。 西原理恵子との共著の解説者の立場だととても面白いのになぁ。清水さん。
4投稿日: 2014.09.03
35歳のチェックリスト
齋藤孝
光文社新書
「私ができるのは部長です」と将来言わないために
35歳という社会人として成熟してきた人に向けて書かれた本。 35歳のキャリアで求められるチェックリストが、斎藤孝からの質問として投げかけられる。 「仕事の量が増えると、ワクワクしますか?」 「プロジェクトチームに呼ばれていますか?」 「「これで攻める」という自分流のスタイルを持っていますか?」 という仕事に直接関わる質問から、 「「今、これがあると幸せだ」と思える瞬間はいつですか?」 「社会の再生産について考えたことがありますか?」 「家族の「形」について考えたことがありますか?」 といったプライベート、人生における幸福についての質問まで多岐にわたる。 質問が具体的かつ本質的なので、ひとつひとつ自分の身に当てはめて、できていて安心したり、できていなくて反省したりを繰り返しながら読んでいくことになる。 普段やっている仕事、生活を客観的に捉えなおせることが本書の価値だろう。 一番ぐっと来た質問は「あなたは何ができますか?」だった。 部長職にあった人が、「私は部長ができます」と答えるという笑い話があって、スキルを聞いているのに立場を答えてしまっていると。 自社の内部のことばかり考えていると、とんちんかんな答えをしてしまう人間になってしまうのだなぁと思い、身が引き締まる思いがした。 私自信斎藤孝氏の本は何冊か読んでいるので、特別新しい内容はなかったが、対象年齢がドンピシャだったこともあり、自分の問題として入り込んで読めたことが良かった。 同年代の方におすすめします。
2投稿日: 2014.09.03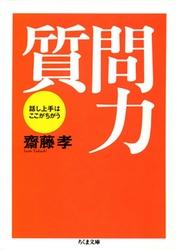
質問力――話し上手はここがちがう
齋藤孝
ちくま文庫
ダニエル・キイスと宇多田ヒカルに見るコミュ力の真髄
「質問力」というタイトルだが、授業や会議で質問がうまくなる、というだけの話ではなくコミュニケーション全般に関わる内容。 コミュニケーションにおいて「質問力」が極めて重要だとしている。 知識量が多い、とか記憶力が高い、テストで高い点を取れる、いい大学を出ている、ということではない、地頭のよさ、人との関わり方(いわゆる「コミュ力」)をここまで平易な言葉で説明できるのか、と感心した本。 理論だけでなく、実例が豊富なのがいい。純粋に読み物としても面白い。 谷川俊太郎といった詩人から、ダニエル・キイス(アルジャーノンに花束をの作者)と宇多田ヒカルの対談、モハメドアリのインタビューに、ジャズの巨人マイルス・デイビスまで。 本書の特筆すべきところは実例のどこがすごいのか、極めてわかりやすく説明している点だ。 質問の種類を4種類に分類しており、 ①抽象的かつ本質的 ・・・ 例:なぜ人は生きるのか? ②具体的かつ非本質的 ・・ 例:普段何をしていますか? ③具体的かつ本質的 ・・・ 例:今、どこにいますか? ④抽象的かつ非本質的 ・・・ 例:どうでもいいこと ③の「具体的かつ本質的」な質問が重要であると説いている。 「具体的かつ本質的」な質問の重要性が前段で説明されているので、谷川俊太郎の「きらいなことわざをひとつあげてください」や「あなたが一番犯しそうな罪は?」という質問のすごさがわかる。 本来は教育者の著者ならではというか、いかに必要な点に絞り込んで単純化して伝えるか、という視点が徹底していてすばらしい(この点は、私は斉藤孝と池上彰、河合隼雄の3人を心の師にしている。勝手に)。 文章は中学生でも読める程度に書いてあり、とても読みやすいが、書いてある中身は、立ち止まって自分の頭で汗をかいて考えないと呑み込めない本質的なもの。 ぱあっと視野が広がるような知的興奮を味わえる読書ができます。
9投稿日: 2014.08.26
クラフト★ビア★マンさんのレビュー
いいね!された数603
