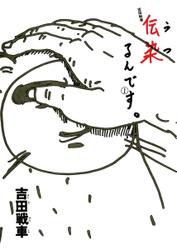
伝染(うつ)るんです。(1)
吉田戦車
ビッグスピリッツ
シュールという概念を教えてくれた4コマの金字塔
私は、「行け!稲中卓球部」と「伝染るんです」の笑いが共有できる人はまず仲良くなれる自信がある。 もう発売から20年は経っているのだけど、今読んでも破壊力抜群。 当時中学生だった自分に「シュール」という概念を教えてくれた本。 「ふつうこう」というフォーマットを逆手に取ったズレを楽しむメタ的な笑いというか、高度なコンテキストが共有できないと笑えない、洗練された作品。 サブカル的な作品ではあるのだが、吉田戦車の本作は安易なシュールではなくて、ズレの強弱がとんでもなくセンスがあったり、ふつう説明のあるキャラや場面の背景を徹底的に描かないことで生まれる奇妙な空気(ちょっと味付けするとホラーになりそうな感じは松本仁志の「ビジュアルバム」と共通した感じがする)がたまらなく上手で、サブカル耐性がない人でもしっかり楽しめるだろう。1巻は結構試し読みできるのでまずはそちらを(あと、是非2巻の最初の話も!これやばい)。 4コマに限らず、あらゆる漫画好きな人にはぜひ読んでほしいギャグマンガの金字塔。電車の中で読むと吹き出すと思うのでご注意を。 他の似たような作品とは一線を画している(相原コージの「コージ苑」は今読むと大分古くてつらいし(涙))。 というか本作の影響でシュールなギャグ漫画というのが流行ったのだと思う。シュールという言葉もこの漫画の頃からではなかったか? 伝染るんです、とはよく言ったものだ。
8投稿日: 2015.03.31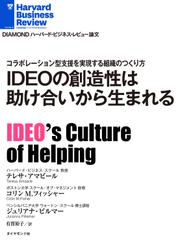
IDEOの創造性は助け合いから生まれる
テレサ・アマビール,コリン・M・フィッシャー,ジュリアナ・ピルマー
ダイヤモンド社
ちょっと具体性に欠ける(それとページ数が少ない
世界で活躍するデザイン集団IDEOの組織と仕事の進め方を学べると思い購入。 「助け合いが大事」という論に終始しており具体性に欠ける論考。自分に置き換えて自分でも実践できる内容を期待していたが精神論くらいしか学べなかった。 「相手が困っているポイント以外の助言は逆に困った事態を引き起こす」「助言も過ぎるとプロジェクトの乗っ取りになる」といった、「そりゃそうでしょうよ」といいたくなる一般論ばかり。 「○○自動車の案件では、こういったコラボレーションで窮地を脱した。これはあなたの会社でも参考になるだろう」とか、そういった情報が欲しかったのだけど、ついぞ出てこず。500円を超える本なので200ページくらいは当然あると思っていたら130ページくらいしかなかったりで全体としてちょっと期待外れな印象。 とはいえ、よいところもあったので抜粋。 「助言を求める人は、未完成の仕事の中身をありのままに伝えてもよいと思える人はだれか、考える必要がある」 「『私達』ではなく『私』という表現を繰り返し用いる人に対しては、首を傾げたくなる。一方、他社のおかげで成長できたと鷹揚に語る人は、自分もまた同僚に手を差し伸べられるはずだ」 IDEOに興味がある方はあまり期待しないで読んでみる、のはありかと。 1時間もあれば読めます。
7投稿日: 2015.03.25
漂流する巨船 ソニー 週刊東洋経済eビジネス新書No.101
週刊東洋経済編集部
東洋経済新報社
ソニーの各時代の経営者たちの声(盛田さんはいない)
アプリのおすすめに表示されて衝動買い。 ソニーの各時代の経営者たちのインタビューがバラバラと掲載されている。 井深、大賀、出井の旧世代の経営者の、歴史を感じるインタビューに加え、 現在の経営層の平井・吉田・十時の世代まで。 (盛田さんとストリンガーの記事はない) 記事の順番がバラバラしていて恣意的。なんでこの並びなのかはよくわからなかった。 出井さんの時代以降は厳しめの記事が並んでいる印象なのは、そういう風にソニーが見られているということなんだろうな。 不思議なのは、出井さんの記事の「デジタル・ドリーム・キッズ」という言葉には時代を感じるが、 井深さんの「アイデアやヒントはいくらでも転がっている。そのアイデアを具体的にしていくことのほうがよっぽど重要」という言葉には まるで古さを感じないこと。 昔から本質は変わらないのだなぁと思った。 改めてソニーという会社がどんな道のりを歩んできたのか、 今どういう局面にいるのかをざざっと読みたい方におすすめ。
12投稿日: 2015.03.23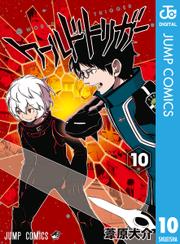
ワールドトリガー 10
葦原大介
週刊少年ジャンプ
思ったよりシビアで大人な展開
丸5巻続いた大規模侵攻編がとうとう終結! 連載10巻のうち5巻(約1年分)を費やした長編でした。 キャラクターと世界観、敵の目的がかっちりはまった緻密な構成は見事。 かなりトリガーの理解も進んで、これからの展開が楽しみになりました。 大規模侵攻編が終わってからの展開が、あれだけ苦労した三雲くんがヒーロー扱いや病人扱いされるでもなく 結構シビアな記者会見でスピーチさせられるあたり、思っていたより大人な展開。 実は死人が結構でてたり、大量に人さらわれてたりして、甘くないです、この漫画。 トリオン体で戦ってるので人は死んだりしないし気楽に読めるな、と思ってたのですが、ベイルアウト(緊急避難)機能がC級隊員と敵にはなかったりして、トリオン体でなくなったら簡単に殺されてしまうわけなんですよね。ゲームじゃなくてガチの戦争だったのだなぁと。 しかし三雲くんはまだ中学生なんだよなぁ・・・大学生くらいの貫録ですわ。 ようやく普通の順位戦が始まり、キャラも大規模侵攻編のおかげで慣れてきたので「誰だっけ?」って前の巻に戻らずに読めるようになってきました。
4投稿日: 2015.03.10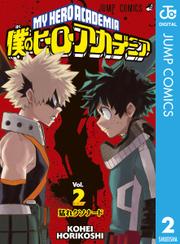
僕のヒーローアカデミア 2
堀越耕平
週刊少年ジャンプ
それほとんどホラーですやん
学園ものとして物語がいい感じに進んできたところで、学園という守られた空間外からの敵の侵入。 ほのぼのとした少年マンガのタッチから、一気に伊藤潤二ばりのホラーテイストに持っていく温度差にゾッとさせられた。「子供を殺せば来るのかな?」というセリフには敵がどれだけヤバいやつなのかが凝縮されている。 クラスメートがそれぞれの個性を生かしてピンチを乗り越えていく様は楽しい。移動中のバスでの雑談も楽しい。 最後の引きもよくて、あっという間の2巻でした。完璧です。
6投稿日: 2015.03.02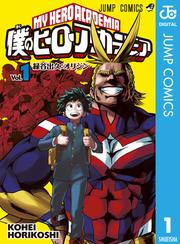
僕のヒーローアカデミア 1
堀越耕平
週刊少年ジャンプ
羨望を糧に喪失からはい上がる王道少年マンガ
そこいらで評判がよいので期待してはいたのだが、読み始めたとたんに泣かされ、心をわしづかみにされた。 1巻で3回泣いたよ。なんだこのマンガ、むちゃくちゃ面白いじゃないか。。。文句なしの★5つ。 もう10回は読み直してしまった。なんでこんなに面白いのだろう。 「猛れクソナード」「はりさけろ入学」独特な勢いのある言葉選び、 主人公の憧れるヒーローが一人だけアメコミ画風、 少年ジャンプ連載3度目のキャリアを活かしたハイレベルな作画、 全力で個性的なキャラ達・・・と上げればまだまだあげられるよ?!嫌いじゃないよ?! という感じだけど、何より主人公がいい。 主人公の出来(いずく)は、「個性」と呼ばれる特殊能力を持つのが当たり前になった社会で、「個性」がない人間として育つ。 それにも関わらず、人一倍ヒーローにあこがれ、羨望と喪失のはざまで生きている。 憧れのヒーロー「オールマイト」に出会い、持たざる者が持つものの心を動かし、受け入れられる過程は胸が熱くなる。 「君はヒーローになれる」 このセリフは何度読んでも涙腺が緩む。あきらめなくてもよかったんだと、自分の人生は前に進めていいのだと認められた瞬間。 たった一話でこのマンガのファンになってしまった。 電子で買ったけど、紙でも買おうと思ってます、今。 最近の少年ジャンプはワールドトリガー、僕のヒーローアカデミア(ヒロアカと略すらしい)と、新しい世代が本格的に油がのってきた感じで読みごたえがハンパない。 葦原大介、堀越耕平といった連載がいまいちうまくいかなった作家をしっかり育てて花を咲かせてきたジャンプ編集部の手腕もすばらしい。 今、一番面白いマンガじゃないだろうか。これがあったからジャンプ編集部もナルトを終わらせられたんだろうな。 僕のヒーローアカデミア、ワールドトリガー、七つの大罪、マギ、進撃の巨人、アルスラーン戦記あたりを今連載中の少年マンガでは読んでるけど、自分の中でヒロアカが一つ頭抜けた感じ。
10投稿日: 2015.03.02
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション(1)
浅野いにお
ビッグスピリッツ
デデデデ
相変わらずの浅野いにお節満載で前作「おやすみプンプン」よりもテンション高めか? 読み手の予想を斜め130度くらいで飛ばしてくる独特の読みくちはそのままに、嫌になるほど現実的な日常を、何をするでもなく、ただ無為に過ごしては絶望に負け越していく気味の悪さはプンプン以上かもしれない。 って、プンプンは中盤からあまりの重さに読むと本気で鬱になるので途中でやめてしまったのだけど。 それでもこの作家から目が離せないのは、実験的で、マンガを知り尽くした完成度の高さに加え、とにかく社会に絶望していて何だか大人になりきれていないところに惹かれているせいなんだと思う。基本、とてもパンクな作家。 そろそろ大人の社会の中で違和感に苦しむ子供から抜け出してもいいんじゃないの?という気もするけど、この人はどこか絶望していることが作家としてのアイデンティティなのかなぁ。世の矛盾や理不尽さに心底愛想が付きながらも、歯を食いしばって現実と折り合っていくのが大人なのだとしたら、この人の作品はちっとも現実を飲み込めずに壊れていくので、そういう意味で完全にモラトリアム文学。子供の物語なのだと思います(褒めてます)。 ただ、あまりにも理不尽なことが起きるのでそこが何とも言えない。 プンプンとは違う方向に進んでくれたら…と思いながら次の巻を待ちたいと思います。 普通のマンガでは飽きたらない人は是非挑戦してみては。
10投稿日: 2015.02.16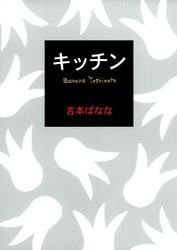
キッチン
吉本ばなな
幻冬舎
喪失のなかにこそ希望って見えてくるわけで
自分にとって初のよしもとばなな作品「キッチン」。 まず驚いたのは、1988年発表だというのに言葉遣いや登場人物が古くさくなく、むしろ今っぽいこと。同じ80年代を描いた「イニシエーションラブ」がところどころトレンディ過ぎて(笑)読むのに赤面したことを思うと雲泥の差だ。 特に、主人公が転がり込んだ雄一の人物造形はまさに草食系で、その当時はかなり珍しいキャラだったんじゃないか。今だと割りと「あーあーいるいるこういうがっつかないのに気付くと知らない女の子と飲んでるやつ」という感じだけど。まあ、勝手に女子が寄ってくるモテキャラな訳です。 物語そのものは、身近な家族の死を少しずつ受け入れていく悲痛さを、主人公みかげが最も落ち着く場所、キッチンを軸に、リズミカルでふくよか、時に残酷な文体で紡いでいく、喪失と再生の話。 唯一の肉親である祖母を失って何もかもやる気がなくなる描写はとてもリアリティがあって、そんななか唯一できたことが料理で、それを糧に緩やかに回復を見せるみかげの心象は誰もが共感できるものだろう。意外と、何もかも失った時にこそ、最も大切な自分の軸が見つかったりするわけで。この点、うんうんうなづきながらじっくり読ませてもらいました。 雄一とその母(元父)えり子とのみかげの関係性は「おばあちゃんの行きつけの花屋の仲良し」というだけなのに、家に転がり込ませてあげるえり子と雄一の感覚ってとてもおかしいのだけど、えり子の人生がもっとぶっ飛んでいるのでこんなもんかと変に納得してしまう。 よしもとばななという作家がずっと人気な訳が少しつかめたような気がしました。 とにかく、カツ丼が猛烈に食べたくなります。
8投稿日: 2015.02.13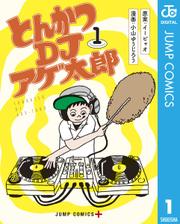
とんかつDJアゲ太郎 1
イーピャオ,小山ゆうじろう
少年ジャンプ+
ただのネタから抜け切れるか
Twitterやらtumblrあたりでちょいちょい目にしていた「とんかつDJアゲ太郎」。 「とんかつとDJって同じなのか!!??(BPMと皿とフライヤーに共通点)」 「ただアゲてぇんだ フロアを!とんかつを!」 って無理やりな言葉遊びでDJととんかつに共通して流れるグルーヴをねじ込んで来る。 何を言っているのかわからなくなってきたがそういうマンガである。 渋谷にある老舗のとんかつ屋(意外と渋谷の裏のほうってこういう渋いお店あるよね)の息子アゲ太郎が、配達に行った先のクラブでグルーヴに目覚めてDJととんかつ職人を目指すという話。アホな設定だけどなんだか突き抜けてて面白い。 はてさて冗談のような設定で1巻描ききれるのか?とおもって思わず購入してしまったが(笑)、結果からいうと1巻読み切るまでにちょっと長く感じたので完成度はまだまだな感じ。とんかつとDJの共通点を中心に引っ張るのかと思いきや、それは最初の2話くらいだし、かといってマニアックな音源の話を中心に据えるでもなく(具体的な曲やアーティスト名はほとんど出てこないので、どういった曲をDJがかけているのかでは楽しめない)、キャラの個性ももう一つ欲しい印象で、いまいち夢中になりきれない。 レコードジャケットのパロディネタやDJの基本テクニックの紹介は割と面白いので頑張ってほしい。 やっぱ核は音楽そのものだと思うので具体的な曲名とか伝説のDJがなぜすごかったかとかを具体的に書いてくれると興味がもっと湧くんだけどなぁ。 なんというか、取材不足というか、想像で描いてる範囲広すぎというかそういう印象がある。 とはいえ、ネット上でのちょっとした話題作ではあるので、新しいマンガを探している人は話のネタにはありだと思います。
3投稿日: 2015.02.12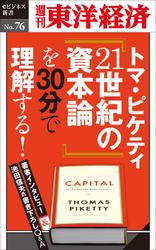
トマ・ピケティ『21世紀の資本論』を30分で理解する! 週刊東洋経済eビジネス新書No.76
週刊東洋経済編集部
東洋経済新報社
資本主義は富める者のためにあるのか?
最近メディアで耳にする機会の多いトマ・ピケティ。分厚い経済書はなかなか読みきれないので要点をまとめたこちらに手を出してみた。 要点は3つ。 1.資本収益率は経済成長率を上回っている 2.所得と富の不平等は21世紀を通じてさらに拡大する 3.格差を食い止めるにはグローバルな累進課税が必要 1は要は働いて稼ぐ給与よりも、資産が生み出す利益の方が大きい、つまり、元々資産を持っている資産家はより富んでいき、もたない給与取得者は追いつくことはない、ということ。 このピケティ氏が話題なのは、それを過去200年の世界中の記録から実証してしまったことにある。資本主義が前提にしてきた「頑張れば金持ちになれる」という希望を覆してしまった。「金持ちはより金持ちになり労働者は追い付けない」というわけだ。このことは、特にアメリカンドリームの国で大きな驚きを持って受け止められ、飛ぶような勢いで「21世紀の資本論」は売れているらしい。 ピケティ氏は、貧富の差を生み出す資本収益率と経済成長率の乖離を解決するには、資本への課税率を上げるべきとしている。とりわけ、3の論点で、グローバル企業の租税回避地を使った納税逃れに対して、課税をすべきだとしている。が、それは現実的には機能できる仕組みはまだ確立されておらず、理論の範疇とのこと。 基本的な話は上記の通りだが、これを受けて識者が解説、反論、展開させた論を唱える構成。個人的には池田信夫氏の論考は少し難しく感じた。 全体としては、かいつまんで話題の書の要点だけ押さえられるよいまとめだと感じた。30分ではちょっと手に余ったのは久しぶりに経済書を読んだからかもしれない。
14投稿日: 2015.02.09
クラフト★ビア★マンさんのレビュー
いいね!された数603
