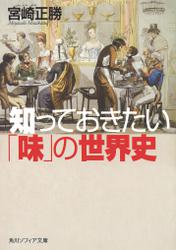
知っておきたい「味」の世界史
宮崎正勝
角川ソフィア文庫
辛味、甘味、塩味、苦味、酸味、旨味から紐解く人間の欲望と世界史
五大味覚と言われる辛味、甘味、塩味、苦味、酸味に加え、日本人が発見した旨味。 当たり前だと思っていたこれらの味わいが100年単位で流行り廃りを繰り返し、現代まで繋がっていることを実感することができる良著。 世界史や地理、文化人類学の観点から見ても面白い。 トマトとこぶだしにグルタミン酸の共通点があったりして、人類が美味しいと感じる味には共通項があって、それを別の場所で、違う方法で見つけて大事にしてきた文化があることが文化人類学冥利につきるというか、好奇心をそそる。グルタミン酸(昆布など植物系)とイノシン酸(カツオだしなど動物系)を組み合わせると「うま味の相乗効果」で飛躍的にうまみが増すとのことだが、日本のだしは、なんと合理的なものだったのか誇らしい気持ちになる。 フランス革命と現代のフランス料理・レストラン文化という、「社会体制」と「味」の民主化が連動しているのが目から鱗だった。美味しいものは貴族が独占してたんだなあ。旨いものは価値があり、莫大な金が動いていたと。奴隷制度の必要性もそのあたりにあるとすると、なんだかフェアトレードなんかにも興味が湧いてくる。 ものを食べるということを新しい視点で捉えたいひとは是非。雑学自慢としても使えます。
8投稿日: 2015.09.07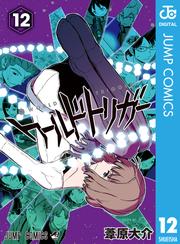
ワールドトリガー 12
葦原大介
週刊少年ジャンプ
ますます面白くなる!戦術・戦力・時の運、それと地形戦。
B級ランク戦第3戦決着! 荒船隊・諏訪隊との第2戦以上に読めない戦局、微妙なバランスの崩れで一気に傾くスリリングな展開に興奮が止まりません。 各チームのエースをいかに効果的に動かすかの戦術、兵としての戦力、そして時の運。 短・中・長距離の戦力と組み合わせに注目していると、個人の背負った積み重ねや、地形戦の妙に持ってかれます。 眠ることで強くなる村上と、眠れないことを活かして強くなるユーマの対比も見事の一言。 いやあ、視野の広い戦いで、この作家は本当に楽しませてくれます。 得意なところでぶつかる、というユーマの戦い方、いいです。 方や戦術はよいが、戦力としての限界を感じるオサム。弱点のばれつつあるチカ。 さてこれからどうする。 また、負けたチームに対するフォローもしっかりしていて、こんな風に評価されるならみんなやる気になるよなぁと。 こういう会社あったら私も働きたい(笑) 相変わらず組織を描くのもうまい。 本刊では、ランク戦の要素だけでなく、ネイバーの世界の要素と、そもそものオサム・チカの戦う理由といった物語の芯の部分も入ってきて、立体的なストーリー展開。いやはや早く先読みたい。
7投稿日: 2015.09.04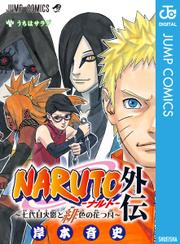
NARUTO―ナルト―外伝~七代目火影と緋色の花つ月~
岸本斉史
週刊少年ジャンプ
もう休ませてあげて!でも面白い
連載が終わったのにスピンオフが映画や小説になったりしまくっているNARUTO。 本作は映画がナルトの息子、ボルトを主人公にしているのに対して、サスケの娘、サラダを主人公にしている。 ナルト、サスケが圧倒的に強すぎるのでバトルとものとしては物足りないけど、原作ファンとしてはその後の人間関係や、10代前半の親に対する悩みを軸にした話は、昔のナルト達のそれと重なってなんだかんだ面白い。 やっぱ岸本さんは図抜けて面白いマンガ描くなぁ。次回作に期待しているので、集英社さん、そろそろNARUTOビジネスは収束させてください…。
6投稿日: 2015.08.11
繋がる個体(1)
山本中学
モーニング
ちゃんと人間を描いている佳作
全く知らない作品だったけど、なにかとお勧めにでてきたり、本屋でみかけたりしたのでなんだかんだ購入。最初は理由もなくモテる男性にとって都合のいい話?と思いつつ、はっきりしない恋愛模様にイラつきつつ、気づいたら結構夢中して読んでました。 恵まれた容姿を持ち自信満々なココ。 まっとうな社会人のようでどこか虚無感が抜けないくるみ。極めてマンガ的なご都合展開もありつつ、テンポよく話が展開していく。引き込まれたのは、恋愛を中心としつつも、家族や個人の心のありようにちゃんとフォーカスを当てているところ。 苦しんで自分を見つめた先に、幸せへの出口が初めて見えるという、逆説的だけど現実にはよくあることがとてもしっかりかけていて、1、2巻を読みきった読後感はなかなかよかった。 もやもやした恋愛をしている人や、すっかり忘れてしまってちょっと思い出したい人にはハマると思います。
5投稿日: 2015.08.07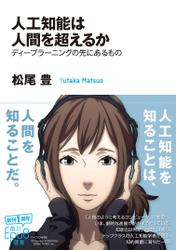
人工知能は人間を超えるか
松尾豊
角川EPUB選書
人工知能が変えるもの、変えないもの
「人工知能=AI」という言葉を知ったのは、ドラゴンクエスト4の戦闘システムだった。「ガンガンいこうぜ」「いのちだいじに」という、あれだ。 「ディープラーニング」という言葉をちらほら聞いたことがあったので、ちゃんと理解したくて衝動買い。 小難しい本で挫折してしまう懸念は杞憂に終わり、難解なイメージのある「人工知能」「ビックデータ」「ディープラーニング」を平易な言葉で、簡単な例を挟みながら丁寧に説明していく。人工知能の知識がほとんどない人でも十分理解でき、新しい知の世界が広がること請け合い。個人的に今年1番のヒット本になりそう。 「ターミネーター」「マトリックス」などのSF映画では定番の、人間よりも人工知能が賢くなり、人間が支配される世界観。人工知能が自身よりも能力の高い人工知能を生み出せるようになる「シンギュラリティ」は2050年にくるという予測があるが、本書はそれが極めて難しいことを論理的に示してくれる。 Googleが行っている画像認識技術に用いられている「ディープラーニング」の仕組みも、何が革新的なのか、なぜGoogleでないとできないのか精緻な説明があり納得できる。「ディープラーニング」の図に出てくる、多層構造で、具体的な情報の抽象化を繰り返し、重要な「特徴量」の精度を高めていく仕組みは、クリストファー・ノーランの「インセプション」の夢の階層構造を思わせ、SFファンとしては胸が高鳴った。 反面、人工知能でできないことも示され、機械が「重要なこと」と「重要でないこと」を認識できず、途方もない無駄の処理をすることで動きが止まってしまう「フレーム問題」は非常に興味深い。このあたりは人工知能だけでなく認知科学の世界でも出てくる話で、佐々木正人氏の「アフォーダンス――新しい認知の理論」を合わせて読むと理解が深まる(Reader Storeでの取り扱いあり)。 言語学者であり構造主義の大家でもあるソシュールが提唱したシニフィエ(概念、意味されるもの)とシニフィアン(名前、意味するもの)の考え方がないと解決できない「シンボルグラウンディング問題」も面白い。人は、「馬」と「縞模様」を知っていれば初めてでも「シマウマ」が理解できるのに対し、シニフィエの扱えない機械では「シマウマ」という別の情報として新たにインプットしないと認識できない、という。シニフィエを機械が扱うことができるようにする試みも進んできているようで面白い。 人間の仕事を機会が奪うのでは?といった不安は現実に来る領域もあるが、そうでない領域もあるといった今後の未来の具体的な例も提示され、これからの世界の変わり方を読みながら想像するのも楽しい。また、人工知能の開発が1950年代から始まっており、今のブームは第3次ブームであること、そのブームの再燃の背景にはインターネットがもたらしたビックデータの蓄積があることなど、様々な視点から人工知能についての理解を深められる本。とにかく、これだけ複雑な内容を中高生くらいでも読める内容にまとめ上げている著者の実力に感服。 お勧めです。
41投稿日: 2015.07.21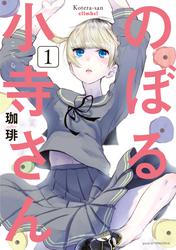
のぼる小寺さん(1)
珈琲
good!アフタヌーン
日常系ボル漫画
なんでも漫画にしてしまう昨今。 とうとう地味に流行っている(オリンピックの正式種目候補に残っている)ボルダリングまで漫画に。 がっちりボルダリング漫画?と思いきや学園モノのなかに織り交ぜて壁登り系ストイック女子小寺さんがたんたんとボルダリングする日常系漫画。 ちょっとかじってる身としてはもっとテクニカルな魅力も描いて欲しいと思いつつ、なんだか後引く世界観でした。 ボルダリングってどんなものか見たい人、日常系学園モノのが好きな人は間違いない感じです。
6投稿日: 2015.07.16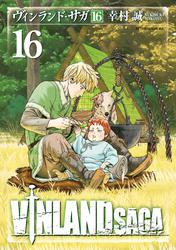
ヴィンランド・サガ(16)
幸村誠
アフタヌーン
表紙のデザインが15巻から明るくなったんですね
シリーズの表紙をよく見たら、前巻の15巻から明るい配色になっていて、戦と奴隷生活に苦しめられたトルフィンの生活の変化を象徴しているのだなぁと気づきました。 って、本16巻の最後の展開を見ていたら、決して彼に平穏な時間は来ないのだという悲しい気持ちにされられましたが。
3投稿日: 2015.07.01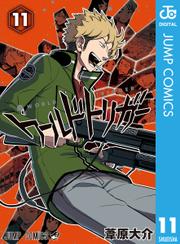
ワールドトリガー 11
葦原大介
週刊少年ジャンプ
敵との戦いでなくてもここまで面白いとは!
敵との命の取り合い(というか誘拐されるのを防ぐ)というガチの戦いではなくなったけど、ボーダーという組織内でのランク戦でここまで面白いとは思わなかった。 ボーダーという組織として本来の形に戻ったわけだけど、そうなったのがこの漫画上は初めてなのでとても新鮮でめちゃ面白い。 3人のチーム3組で、戦略を練りあう知略の戦い。武器、個性に加えてステージの地形や天候までからめてきたところで、キャラごとの戦う理由も織り込んでくるしたたかさ。 そこでさらには「サイドエフェクト(特別な才能)」の要素も絡み、多彩な要素を見事にストーリーに盛り込んでくる。つくづくこの作家は感覚ではなく理性と世界観が圧倒的な漫画家だなぁと思わされた。 通常のランク戦でここまで面白いということは、それがある程度落ち着いたら来るはずの「ネイバー遠征」はどうなるのかとても楽しみ。 というかランク戦だけで1年以上十分持つくらい、十分面白い。。。 もう続きが読みたい。。
3投稿日: 2015.06.05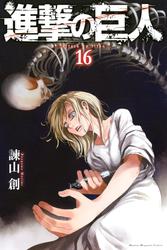
進撃の巨人(16)
諫山創
別冊少年マガジン
利己と利他、個人と組織、家族と人類
寄生獣で田村玲子が受けていた大学の講義のテーマが「利己的な遺伝子」。進撃の巨人の前巻15巻でエルヴィンがザックレー総統に指摘された、人類よりも自分の夢、野望を重視する人間なのだという話。本16巻で、自分の都合よりも一人でも多くの人間を救うことを重視するというピクシスの宣言。やむにやまれず大人たちの都合で人類の命運を負わされたエレンとヒストリアの立場。 そしてこの物語は進撃の巨人。なんてらしい選択をするのだろうなと。上橋菜穂子さんの「獣の奏者」の主人公エリンの導き出した答えに似ている。 利己と利他、個人と組織、家族と人類の対比も進撃の巨人を読む上で重要なテーマなのだと感じた。 余談だけど、相変わらずのヒリついた緊張と絶望描写は本当に突出した作品だなぁと感じた。コニーがすっかり危機的な状況に慣れきっててちょっと飽きてるのがウケました。
8投稿日: 2015.04.11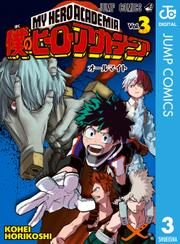
僕のヒーローアカデミア 3
堀越耕平
週刊少年ジャンプ
学園ものがはじまるよ
学園という日常に突如殺意という非日常をもたらした敵(ヴィラン)との戦いはいったん終結。小気味よいテンポで話がすすむ。 と思ったらいきなりの学園祭編!なんかジャンプっぽさ満開! もうちょっとヴィラン編で各キャラの掘り下げやってもよかった気がするけどこんなものかなぁ。 クラス最強の轟くんの掘り下げは進んできて、出来との絡みがちらほら。あと麗日お茶子のヒーローをめざす理由も。 爆豪が安定の暴れっぷりであっという間に読み切ってしまった。 中表紙のイラストが素敵です。 はやく次読みたいんですけど。
3投稿日: 2015.04.03
クラフト★ビア★マンさんのレビュー
いいね!された数603
