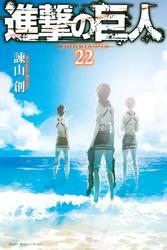
進撃の巨人(22)
諫山創
別冊少年マガジン
巨人の進撃
初めて読んだときから違和感はあった。「巨人の進撃」でなく「進撃の巨人」? 何?巨人が攻めてくるんだから巨人の進撃じゃないの?と。ん?こっちが攻めんの?と。 そういうことかいな! しかし、英語の「Attack on titan」もなんだかピンと来ていない。「Titan’s attack」とか「Attack by titan」あたりじゃないんか?ここにもカラクリがあるのか。 どこまで考えているのだ、この諌山さんという作家は。デビュー作でこれだけ破綻なく奥深い、人の期待を裏切り続けることが出来るってのは何なんですかね… 天才過ぎてゲロ吐きそうです。。 自由の意味と恐ろしさについて考えさせられた刊でした。
4投稿日: 2017.04.10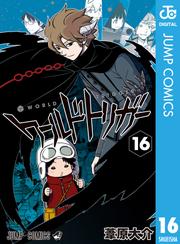
ワールドトリガー 16
葦原大介
週刊少年ジャンプ
ストーリーの本筋が少し見えてきた?
このマンガのストーリーの核はネイバーという異世界に侵攻され、拐われた人が大量にいることにある。 そして、それがどのネイバーの国がしたのかわからないことにあって、その可能性のある国のひとつアフトクラトルのお国事情が本筋のストーリーに重なりつつあって、今後どうなるやらわからなくなってきた。 アフトクラトルのヒュースを捕虜にしていることが思った以上に本筋に絡んできてるな、という印象。これだけ絡んで、全然さらったり侵攻した国と関係ないとかだったらどうしよう。どうもしないか。 もうひとつの軸としては、そもそもトリガーというテクノロジーの発見と、ボーダーという組織の成り立ちが謎なので、そこがどう絡むやら。 一方で、三雲くんの成長も見れて、模擬戦が相変わらず緻密で面白い。色んな要素をしっかり積み重ねながらのストーリー展開は見事。はよ続きよみたいです。
5投稿日: 2016.09.06
デービッド・アトキンソン 新・観光立国論―イギリス人アナリストが提言する21世紀の「所得倍増計画」
デービッドアトキンソン
東洋経済新報社
相手の立場に立って考えよう
観光産業を振興することが日本のGDP縮小への一番の対策であるとする本作。 GDPは人口の量にほぼ依存しており、避けられない少子化が既に起こっていること、そして移民政策は日本人の感情的にも経験的にも受け入れがたく(ヨーロッパ諸国を見ていると副作用も大きい)ことからGDPが下がるのは必然。そこで提唱されているのが「短期移民」、つまり観光客だ。 マクロ経済による観光産業の規模、他国との比較による日本のいかしきれていないポテンシャルを、理性的にロジカルに説明していく。観光地としての4大要素は「気候」「自然」「文化」「食事」で、日本は全て備える稀有な国なのに、安全や便利など的外れなアピールばかりしていると。 全体を通して感じたのは日本人は他者の視線になってものを考える習慣が乏しいということだ。他者にわかってもらうことが当たり前だという感覚が共通してあるような。そこをイギリス人で京都に長年住む著者が指摘してくれている。面白いのは、思いやりを大事にする日本人だからこそ、むしろ相手の立場になって考える客観性に乏しいというパラドックス。一見矛盾して見えるが、本質をついている。 その意味で、観光論というだけでなく、普段の仕事でも相手の立場に立ってものを考え、相手の欲しいものが提供できているのか、自分に置き換えて読むことができた。 参考になる点の多い良著。
14投稿日: 2016.06.01
マチネの終わりに(文庫版)
平野啓一郎
コルク
人生はわからないことばかり
おすすめに表示されるまま試し読みをして、吸い込まれるようにそのまま購入していた。「マチネ」の意味などわからないまま。 恋愛小説とあるが、トレンディドラマの様な恋愛描写ばかりの単純なエンタメではなく、芸術に見入られた人が直面する残酷な才能の差、身もだえするような嫉妬、戦争と震災という人知を越えた暴力、自由意思と運命を巡る理不尽なままならなさ、といった人生そのものがその下地に濃密にあり、まさに(渡辺淳一的なエロティックな意味ではない)大人の恋愛小説。 とりわけ主人公のギタリスト蒔野の演奏の描写は、文字でこれほど音楽に心捕まれる瞬間を描ききれるものかと作者の力量に、それこそ嫉妬しそうになる。 書誌説明だけ読むと、大人の許されない恋、凡庸な不倫でも描いたように思えるが、この本は人の魂を揺さぶる怨念のような、これぞ文学、と思える迫力がある。 出会えてよかった。
21投稿日: 2016.04.14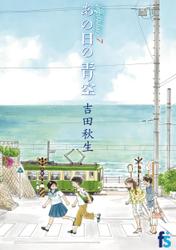
海街diary 7 あの日の青空(7)
吉田秋生
月刊flowers
相変わらず、丁寧に紡がれる良質なものがたり
昨年の映画化によって知名度が上がったことによる悪い影響など微塵も感じさせず、丁寧に、ゆっくりと紡がれるものがたりにじっくりと向き合う喜び。 吉田秋生さんの作品は女性作家による女性向けなテイストが強い(BANANA FISHはちょっと苦手)が、本作はそれを気にさせない普遍性があって、男性の自分でも人生の機微を味わせてもらってます。 4姉妹の恋愛も少しずつ前に向かっていて、形になってきた感じ。 と、思ったところで、恋愛面で一番取り上げられていなかった(一番恋愛キャラじゃないし)3女の様子が・・・。
14投稿日: 2016.02.08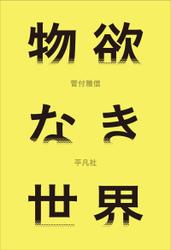
物欲なき世界
菅付雅信
平凡社
なぜ、「モノを持つことがダサい」時代になったのか?
車、時計、宝飾品、奇抜なブランドものの服、靴、高級オーディオやテレビ、家電・・・・形のあるものが売れないと言われて久しい昨今、一体何が起こっているのか。元「エスクァイア」「Cut」の編集者が自身の体験と、多くのインタビューを通して考察する一冊。 著者は学者ではないので、客観データに乏しいと感じるところはあるが、多くの体験・世界中の事象からまとめられており、説得力がある。 消費のパラダイムシフトを読み解く良著だと思う。 ・モノが売れない、欲しくない、むしろモノに縛られることがダサい ・モノ(ファッション)を通して、自分を表現し、他人より優れていることを示す必要がなくなった ・この現象は日本だけでなく、あらゆる先進国で起きている ・それはインターネット・情報化による、「作ることに金がかかり環境負荷の高いモノ・ハード・アトムの世界」ではなく、 「サービス・ソフト・バーチャルの世界」への変化が背景にある ・その変化を紐解くキーワードが「ライフスタイル」という言葉。その具体例が掲載されており、 アメリカの一田舎町だったポートランドが全米で最も住みたい街になっている理由はそこにある ・代官山ツタヤ、ツタヤ家電が生まれた文脈も同じところにある。 その代官山ツタヤで一番売れている洋雑誌は「ヴォーグ」ではなくポートランドで創刊された「キンフォーク」 ・今流行りのシェアリング・エコノミーの解く鍵も同根にある ・ライフスタイル的な生き方は、働き方の価値観にも大きく影響を与えている ・地方再生や、若者の農業への回帰、スローフードなどの動きも同じ文脈でなぜ注目されるのか見えてくる ・経済成長がなくても、文化の成長が人間の幸福度を高める。むしろ、経済成長を第一義にしていたこの数十年は特殊な時代だった 「文化の成熟」がこれからの時代のキーワード。 今起きている世の中の変化が、一体何なのか考察するのに適した良著。 社会の変化に興味がある人は是非。 ※資本主義そのものに対する考察はちょっと素人の思い込み感が強かったので個人的には「ホンマかいな」と思いながら読んでいたので★は4つ。
9投稿日: 2016.01.27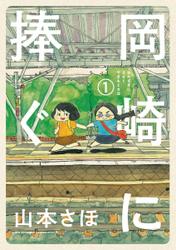
岡崎に捧ぐ(1)
山本さほ
ビッグスペリオール
糸井重里が認めた新時代の日常系マンガ
育児放棄に無職の父、いつもワインを飲んでいる母、すぐ「殺す」と言って暴れる妹と、よく考えるとなかなか悲惨な家庭環境にある「岡崎さん」と作者の友情を、全然重くないタッチで描いた日常系マンガ。 たしかに「ちびまる子ちゃん」に似ているところがあるけど、もうちょっとモチーフは深刻。なのに読み口が軽くて楽しく読めてしまう。 他にはない不思議な感覚で、古いような雰囲気なのに、独特の新しさがある。 ちびまる子ちゃんと一番違うのは世代で、作者の小学生時代の風俗が濃密にリアルに描かれている。 携帯型ゲームに夢中になったこの空気感は、それを味わった世代でないと書けないリアリティにあふれていて、思わずほくそ笑んでしまう。 もとはwebマンガで、twitterで糸井重里さんが褒めたのがきっかけで出版までこぎつけた珍しいタイプの作品。 個人的にはまだまだ売れて、長期間続くアニメとかになってほしいと思っている、良質の漫画です。 ずっしりもやっとした終わり方で、なんだか考えさせられてしまう回があるのが好きです。 たぶん、子供が読むのと、大人が読むので感想が大きく異なるでしょう。 とにかくおすすめです。
13投稿日: 2015.12.16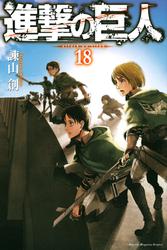
進撃の巨人(18)
諫山創
別冊少年マガジン
ハガレンの最終巻を思い出した
進撃の巨人を進撃の巨人たらしめている象徴的な1巻の壁が破壊されるシーンを巻き戻すように、丁寧に紡がれるウォール・マリア奪還戦へのプロローグ。 18巻かけて積み上げて来たものがとうとう現実になる感慨のようなものが作中からにじみ出ている。 どこかで見たようなシーンがこれでもかと挿入されて、「この漫画、そろそろ終わっちゃうんじゃないか?」と心配させられるほど。 作者の諫早さんも相当の気持ちを入れて書いているのが伝わってくる。 これまで、読者に準備させずに飛んでもない展開を異常なほどあっさり突きつけてきた本作には珍しい「タメ」のある演出だった。 なんだか、ハガレンの1巻の「オレとお前との格の違いを見せつけてやる」と 最終巻の「オレたちとお前との格の違いを見せつけてやる」の見事な対比を思い出した次第です。 さあ、次の巻はいったいどうなるやら。
6投稿日: 2015.12.11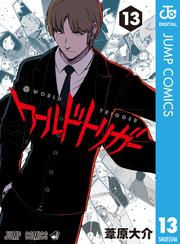
ワールドトリガー 13
葦原大介
週刊少年ジャンプ
真面目なのと型破りなのは別の話
成長する時ってまっすぐにはいかないよね、ってことを身を持って感じさせられる巻。 アニメ版がオリジナルストーリーで別物になっている今(原作のストーリーに戻ってくればまた面白くなるはず)、 やっぱり原作の練りこまれたキャラ・設定の緻密さ、淡々としているのに抑えるとこガッツリ抑えてくる展開にうならされる。 三雲君の超現実的な考え、素晴らしいです。 真面目なのにタブーがなくて、他人に縛られず自分の頭で実行できる行動力が三雲君の最大の長所だと思う。 ベンチャー企業始めるのなら投資したいレベル。 新キャラがたくさんでてきたのに、それぞれちゃんと戦いの中で立っていて、群像劇のうまさは昨今の漫画では類を見ないと言っていい。 ナルトやワンピ、ヒロアカ(僕のヒーローアカデミア)と比べても無駄がなくてきれいにパズルがハマりまくるのはお見事。 ヒロアカは取り上げるキャラが重複が多かったり、脇役の活躍を描くのがあまりうまくなかったりで、ワートリはホントにうまい。 その分、ヒロアカは勢いに乗った時の盛り上がりは半端ないけど。やっぱこの二つが個人的に2大ジャンプ漫画です、今。
4投稿日: 2015.12.07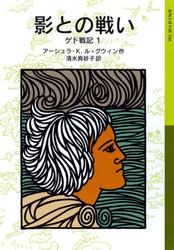
影との戦い ゲド戦記1
アーシュラ・K.ル=グウィン,清水真砂子
岩波少年文庫
世界3大ファンタジーにしてジブリ映画原作。こっちが本物です
世界3大ファンタジー「ナルニア国物語」「指輪物語」「ゲド戦記」の一角にして、ジブリの宮崎吾郎監督初監督作品「ゲド戦記」の原作。 映画版は、複数あるゲド戦記の原作の内容がなぜかごちゃまぜになっていて、本質を捕まえているとは到底思えず、原作読了者としては「?」が頭の中から取れないままだったのを覚えています。 映画の方はあんまり評判がよくない印象ですが、宮崎駿監督がずっと映像化したかったという本作は、非常にテーマが深く、10~20代前半での、個人が体験する自我が確立する過程を、ファンタジーの形を借りて克明に描いた傑作だと思います。 ユング心理学での「影」の考え方に強い影響を受けて書かれたこの「影との戦い」は心理学的な観点から見ても高い価値が認められていて、文章は低年齢層向けに平易に書かれているものの、内容は深く、暗く、重く、本質的です。 出版は1968年と古く、本作を読むと、現代の少年漫画などでよくある、自分の悪意を受け入れて主人公が強くなる(NARUTOでもあったな)描写のひな形はこれなんだと思えます。 「ナルニア国物語」「指輪物語」と比べると、登場人物は少なく、世界観も限られているので、テーマが分かりやすいかもしれません。 連作で、1作ごとテーマは大きく変化していきますが、一貫してあるのは人の心の有り様を深く掘り下げていく視点にあるように思います。 秋の夜長にはよくはまる物語ではないかと。
11投稿日: 2015.10.15
クラフト★ビア★マンさんのレビュー
いいね!された数603
