
クリスマスの文化史
若林ひとみ
白水社
クリスマスの外にいるからこそクリスマスを知りたい
毎年ロマンティックな日でもありますが、 お祭り騒ぎするためや何かを買ってもらうための理由として最高なクリスマス。 キリスト教文化圏ではない日本人にとっては、 楽しむためのきっかけとしてなくてはならない日になっています。 そんなクリスマスが、いったいどういう経緯でいまのような日になっていったのか、 サンタクロースの誕生からきよしこの夜の普及、クリスマス料理まで、 クリスマスの文化を丁寧に解説しています。 サンタクロースが聖ニコラスから来ているという話しは聞いたことがあっても、 きよしこの夜の誕生やどんやって広がっていったかなんて、まったく想像もつきません。 クリスマスを過ごす前に知っておくのも悪くない。
1投稿日: 2015.12.11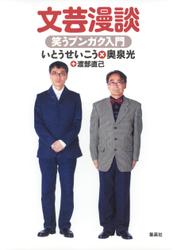
文芸漫談 笑うブンガク入門
奥泉光,いとうせいこう,渡部直己
集英社文芸単行本
小説は漫談で語れるか。
芥川賞作家で大学教授の奥泉光ともはや肩書が不明な小説家でもあるいとうせいこうが、 文学の世界を漫談形式で紹介していくのが本書。 そもそもイベントで漫談形式で行っていた文学講義を書籍化。 とぼけた奥泉のボケに芸の世界でも生きるいとうがツッコミをいれながら、 気づけば作品の奥の方へといざなわれていく。 自分と同じ種である人間のことが描かれている小説が難しいとはどういうことなのか。 それはそこに技術や思想というある体系的な構造があるときかもしれない。 こんな読み方をすればよかったのかと膝を打つ感覚を味わえるし、 何よりこんなおもしろく読めるのかとすぐ紹介されている本を手にとりたくなった。
0投稿日: 2015.12.11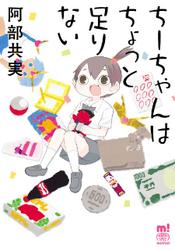
ちーちゃんはちょっと足りない
阿部共実
もっと!
不器用さは悪ではない。
この絵柄、この出だしで、結末にやってくる内容を誰が想像できただろうか。 中学2年生だけど小学生のようなちーちゃんとその友だちのナツ。 成績優秀で先輩と付き合っている旭といつも三人でいた。 タイトルの通り、ちーちゃんはどこか少し足りない。 背は小さいし、足は18cmしかないし、勉強も九九がやっとで、 テストは0点じゃなければなかなかのよかったといえるくらい。 だから、思春期を迎えてぐるぐると頭の中をいろいろな感情や考え、思惑が蠢く同級生のなかにあって、 ひとり爆発的な素直さと正直さと純粋さ、そしてバカさで動き回る。 いつも何か不安で不満な少女は、その解決の方法を子供じみたやり方でしか知らないのだ。 一方のナツは貧乏という自意識と様々なコンプレックスに圧し潰され、 誰にも本当の自分をさらけ出せず、すべては誰かのせいにしてしまう。 そして、純粋な存在はその悪意にも気づかない。 友だち、友だちじゃないという線引は、ある時期において死刑宣告と同義になる。 自分と世界の折り合いをどうつけるのか。 ヤンキーになる人も閉じこもる人も、どちらも不器用なだけ。 2015年「このマンガがすごい!」オンナ編で1位になったのが納得の作品。 確かに女性の共感度は高そうだ。
1投稿日: 2015.12.10
死にたくなるしょうもない日々が死にたくなるくらいしょうもなくて死ぬほど死にたくない日々 1
阿部共実
Championタップ!
自分てめんどくさい人間だな…と思う人にこそ読んでみて欲しい
2015年、「このマンガがすごい!」のオンナ部門で1位を獲得した阿部共実。 これまで読んだマンガの中でおそらく最長のタイトル、通称「死に日々」。 素直になれずうまくいかない人間関係もあれば、 意を決して素直になったあげくとんでもないことになることもあるのが人間関係。 素直になりなよなんて、簡単に言うけれど、 素直な自分の感情は思った以上にめんどくさかったり、 ドロドロしていたり、もしくはおどろくほどピュアだったりしていて、 そんなことをまったく気にかけず、 素直になりなよなんて行った自分と同じような人間じゃなかったら、 おまえはやっぱり気持ち悪いみたいなことになってしまうかもしれないから、 結局何も言えなくなってしまって、時間がただ過ぎる。 それを無口といえば、そうなのかもしれないけれど、 自分の好きなことが君も好きだとわかれば、 いくらだって頭のなかには言葉が渦巻いていて、どれだけだって喋ることはある。 でも言えない。 もしくは言って失敗する。 でも、もしかしたらうまくいくかもしれない。 恐いけど、それが人間関係。 そんなめんどくさいことを考えてしまう人のためのマンガ。 阿部共実、すばらしい。
1投稿日: 2015.12.10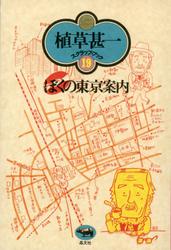
ぼくの東京案内(植草甚一スクラップ・ブック19)
植草甚一
晶文社
”散歩と雑学が好きによる私的東京のこと
1908年生まれ、映画にジャズ、ミステリー、マンガ、ファッション等々、 60年代の本格的な作家デビュー後、植草甚一=J・Jは若者サブカルチャーの象徴のような人物だった。 早稲田大学で建築を学び、映画館、東宝宣で働いた後、「キネマ旬報」同人。 そこから映画評論を書き始めるのと平行して、ミステリーの解説や編集にも携わり、 さらにはジャズの評論家としても健筆を振るった。 いつも古本屋でも持ちきれないほどの古本や雑誌を買う姿が目撃されてきた。 雑誌は必要なページだけ切ってしまっていたという。 ”散歩と雑学が好き”と本のタイトルにするほどの、いわば東京歩きのプロである。 生まれも育ちも東京のJ・Jが、昔通った馴染みの場所や店、古本屋やカフェにジャズ喫茶をネタにしながら、 明治から昭和へ、激動の時代の東京をJ・Jはどう見たのだろうか。 街は生きている。そして新陳代謝し、変化していく。 散歩の達人が、思い出とともに記した東京の記録と記憶。
1投稿日: 2015.11.18
夜のある町で
荒川洋治
みすず書房
文学は実学である。
現代詩作家である荒川洋治が98年に出した初エッセイ集。 当時書店で見た時、本書の帯には”エッセイ革命”とあった。 本書が講談社エッセイ賞を受賞し、著者は以後たくさんのエッセイ集を出している。 その出版点となった本書は、荒川洋治のエッセンスが凝縮されている。 詩人である、ということを抜きにして一介の本好き、読書好きとして、 荒川は言葉のちからを信じ、可能性を信じ、人間が人間であるために言葉が必要であると考えている。 「言葉は呪縛ではない。人間のために、目の前にあるものをいとおしむためにある」 「この国が失っているものは心である前に、まずは言葉なのだということがはっきりしている」 だから荒川は文学を実学だという。 人は、言葉で考え、言葉で行動と心象を表現し、言葉で人間をつくる。 文学は実学である、とスッパリ言われると本好きとしては、頗る気持ちがいい。 良い文章とは、知識や情報が書かれたものではない。 では、いい文章とはなんだろうか。
1投稿日: 2015.11.18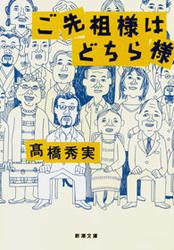
ご先祖様はどちら様(新潮文庫)
高橋秀実
新潮文庫
自分の祖先の話し、何代前まで話せますか?
自分のルーツ、先祖についてどこまで遡ることができますか? 核家族化が進む現代にあって、年配の人に話を聞く機会が減ってきているからか、 大人になって周囲に自分のルーツを調べる人が出てきだした。 ノンフィクション作家の著書も、自分のルーツを探るべく動き出す。 家族に話を聞き、戸籍を辿って、全国関係のありそうな場所へと趣き、 遠い遠い親戚だと思わる人に話しを聞き、家紋や家系図を調べる。 おもしろいのは、事実に忠実に従いながらペンを進めるノンフィクション作家にあって、 血筋を辿った時に大切にしているのが、ルーツである土地や名前等に感覚的な郷愁や念のようなものなのだ。 かといって事実を蔑ろんしているのではなく、 大昔から存在しながらどうにも信憑性の低い家系図をたどっていく時の、 個人的な縁とでも言えばいいのかもしれない。 どう信じたらいいのかわからないけれど、 どこか似ている? と思ってしまう遠くの親戚たちが話す、信じたくなる、信じてしまう先祖の話しは、 いまここにいる自分が誰なのか、ということの答えのような感覚になってくる。 実家に帰って、話しを聞いてみよう。 ちゃんと。
2投稿日: 2015.11.18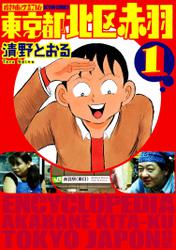
増補改訂版 東京都北区赤羽 1
清野とおる
漫画アクション
読んだ週末は、赤羽へ。
気づくと清野とおるばかり読んでいる。 そして気づくと近所の変な人やお店や場所にどんどん気づく自分がいる。 『東京都北区赤羽』は漫画家清野とおる自身が住んだ街、赤羽を描いた、 ドキュメンテーションのような作品だ。 みなさんが赤羽にどんなイメージを持っているかわからないけれど、 赤羽を知らない人で特別いいイメージを持っているという人というのも想像しにくい(失礼)。 要するにあまりに皆知らないわけだ。 駅としてはそこそこ有名で、街としてもわりと大きいのに。 日常の自分を変だと思っていない変な人を、変な人として観察する名人清野とおる。 赤羽はその観察の街として最適だった。 なぞの絵で客をおびき寄せる魔窟のような「居酒屋ちから」と そこで繰り広げられる不思議な人間関係。 ホームレスのアーティスト「ペイティ」さんとの交流。 ”(清野とおるにとっての)赤羽の二大カリスマ”の魅力は汲めども尽きない。 おそらく赤羽以外の街にも、おもしろいことはたくさん眠っている。 でも、そのポテンシャルを発揮できるかどうか、 その魅力を引き出す人を呼び寄せることができるかどうかも街のすごさだ。 週末、赤羽に行きたくなった。
0投稿日: 2015.11.18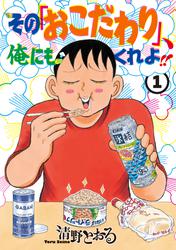
その「おこだわり」、俺にもくれよ!!(1)
清野とおる
モーニング・ツー
自分で気づいていないこだわり、ありませんか?
幸せは人それぞれである、ということをこのマンガはこれ以上ないほどにつきつけてくる。 なんでもない日常にあって、気づかない程度の些細で極個人的な日々のこと。 話しを聞いて、自分で試してみるまで、どうでもいいような、何が楽しいのかも理解できないこだわりたち。 清野とおるは、そんな他人のこだわりを収集し、 その喜びを自分も味わいたいと聞く話し、聞く話しを、 自ら繰り返して言葉に出しながら、実践していく。 ポテトサラダの食べ方、何の味も加えられていない白湯とのつきあい方、さけるチーズの裂き方などなど、 お金をかける趣味ではなく、どうしようもなくやってしまうこだわりと生きる喜び。 人に伝わる必要はないけれど、 自分が納得できる喜びは大切にしたい。 おそらくみなさんもそう意識していないだけで、 実はあたなだけのこだわりがあるかもしれませんよ。
2投稿日: 2015.11.17
エンバンメイズ(1)
田中一行
good!アフタヌーン
ダーツは投げる技術と同等の精神力が必要だ
ダーツがモチーフのマンガは珍しいのではないだろうか。 ボウリングと同じで、基本的には高得点であれば勝てるゲームであることを考えると、 熟練した人間たちが出て戦っていけばそんなに多様な戦い方はないのではと思ったら、 とんでもない。 やったことのある人はわかるかもしれないが、 ダーツは投げる技術と集中力、精神力が同じくらい大事。 闇社会のダーツは、命をかけるような特殊な状況下とルールで戦いを続ける。 主人公烏丸徨は抜群の技術はもちろん、 どこまで読んでいるのかわからないほどに深い心理戦を用いて、 相手を迷路に迷い込ませていく。 迷路に迷い込んだプレイヤーの精神力は続かず、ダーツはもはや的には届かないのだ。
0投稿日: 2015.11.13
BACH/バッハさんのレビュー
いいね!された数446
